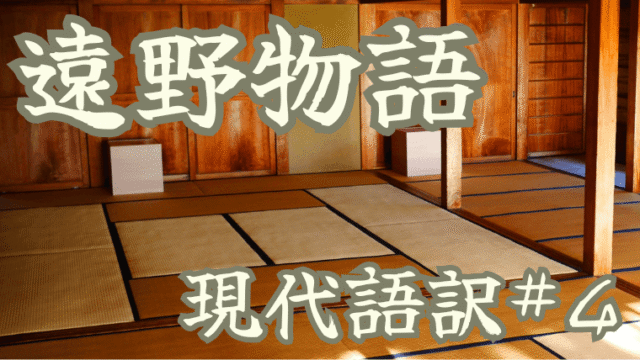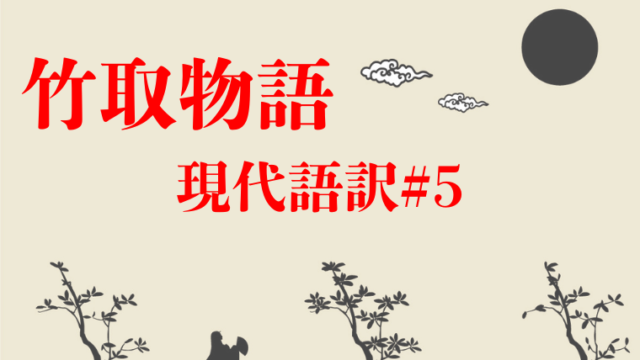現代語訳
清原氏の懐柔
同年12月の国解には次のように記されている。
『諸国から兵糧や兵士を徴発するという名目があるにも関わらず、実際には一切到着していない。また、ここ陸奥国の民は残らず他国へ逃げ出してしまい、兵役に従おうとしない。そんな状況である。さて、出羽国守の源兼長は混乱や反乱の意図を持っていないため、出羽国へ兵糧を移送するのは問題ないと判断する。手筈は済んでいるが、朝廷の許可が下りないのだ。許可を得ないで、どうして討伐を完遂することができようか。』
と。これを受けて朝廷は、出羽国守の源兼長を解任し、代わりに源斉頼を出羽国守に任命した。それと同時に安倍貞任を討伐させることも任として命じたが、斉頼は不相応なほどの恩賞を受けておきながらも、全く貞任征討に協力する意思を示さなかった。さらに、諸国からの軍兵や兵糧が一向に届かなかったため、再び攻撃を仕掛けることができなかった。
貞任らはますます諸郡を横行し、人民を脅しては略奪を働いた。賊軍の藤原経清は数百人の甲冑を着た兵を率いて衣川の関の外へ。そして、諸郡に兵を派遣しては、朝廷に納めるはずの官物を無理やり徴収させ、更に次のように命じた。
「白符を使用せよ。赤符を使用してはならない。」
と。
白符とは経清が私的に発行した徴収書であり、捺印が押されていないため白符と呼ばれました。一方、赤符とは国から発行された正式な徴収書であり、国印が押されているため赤符と呼ばれました。
頼義将軍は貞任らの行為を抑制することができなかった。そのため、常に甘い言葉を用いて出羽国山北の俘囚の主、清原光頼やその弟、武則らを説得し、官軍に協力させようとした。光頼らはなかなか決断しなかったが、頼義将軍はたびたび珍しい品々を贈り続けた。これによってようやく、光頼や武則らは官軍への協力を許諾したのだった。
康平5年(1062)春、源頼義は陸奥守の任期を終えたため、新たに高階経重が陸奥国守に任命された。そんな経重は赴任のために出発し、陸奥国に入り着任したのだが、なんと何もせずにそのまま帰京してしまったのである。これは、陸奥国内の民衆が皆、前任の国司頼義の指揮に従っていたためであった。思うように奥六郡の統治が進まず、議論が紛糾する中、頼義将軍はしきりに清原光頼と弟の武則らに派兵を求め続けていた。
国司の任期は4年ですが、頼義は5年勤めていたようです。期間は、天喜5年〜康平5年(1057-1062)。
そしてこの努力が実を結び、同年(康平5年)秋7月、ついに武則は、子弟や家臣など約1万の兵を率いて陸奥国へ渡ってきたのであった。
小松柵の戦い
頼義将軍は武則の応じに大いに喜び、約3000の兵を率いて武則のもとへ出発した。7月26日に出発、8月9日に栗原郡の営岡に到着した(営岡はかつて坂上田村麻呂将軍が蝦夷征伐の際に軍を支え整えた場所で、それ以来「営塹」と呼ばれ、今もその跡が残っている)。先にこの地に到着し布陣していた清原武則は、後からやってきた頼義将軍と合流し、互いに心中を打ち明け、共に涙をぬぐいながら悲しみと喜びが入り混じった感情を分かち合った。同年8月16日、諸陣が配置された。
第一陣:押領使、清原武貞(武則の子)
第二陣:橘貞頼(武則の甥。通称志万太郎)
第三陣:吉彦秀武(武則の甥で娘婿。通称荒川太郎)
第四陣:橘頼貞(貞頼の弟。通称新方二郎)
第五陣:源頼義。この陣はさらに三つに分かれる(頼義、清原武則、陸奥国内の官人たち)
第六陣:吉美候武忠(通称班目四郎)
第七陣:清原武道(通称貝澤三郎)
清原武則は、遠く京の都に向かって拝礼し、天地に誓いを立てて言った。
「私は子弟を率いて頼義将軍の命に応じました。節義を全うする、そう志を立てたのです。この命を顧みるつもりはありません。もし仮に死なずに命永らえるようなことになれば、必ず恥ずかしくなり、生きることができないでしょう。八幡宮の三神よ、我が忠義心を照らせ。もし私が身命を惜しみ、死力を尽くさないようなことがあれば、必ず神鏑(八幡の加護を象徴する矢)に射抜かれ、死を迎えるでしょう。」
こうして各陣が一丸となり、士気が一気に高まった。同じ日、一羽の鳩が軍勢の上を飛んだ。頼義将軍以下、全員がそれを拝んだ。そして軍勢は、松山道を経て南磐井郡の中山にある大風沢に向かって進軍を始めた。
翌日、軍は南磐井郡にある萩の馬場に到着した。宗任の叔父である僧、良昭の守る小松柵までは五町(約550メートル)余りの距離であった。この柵には宗任も籠っている。その日は計画が合わず、また時間が夕方に差し掛かっていたために攻撃する予定は無かったが、第一陣の清原武貞や第四陣の橘頼貞らがまず地勢を確認するため柵の近くまで接近した。この時突然、敵の歩兵が火を放ち、柵外の宿営地を焼き払ってきた。これにより城内の兵が奮起して鬨の声を上げ、矢や石を乱れ撃ちした。官軍もこれに応じ、先陣を争うようにして攻撃を開始した。頼義将軍は清原武則に命じて言った。
「軍議は明日の予定だったが、それに反して急に戦が始まってしまった。戦とは、戦が起こりそうな機運を待つものであって、必ずしも日時を選ぶものではない。南朝宋を建国した武帝、劉裕は危険を恐れず勝機を捉えて功績を挙げた。だからこそ、戦機というものは、その時々の状況で柔軟に判断するべきだと私は思うよ。」
武則は言った。
「不意打ちを食らった我が官軍の怒りは火に水を注ぐかのように激しいものとなっております。触れると危険なほどに。なれば、兵を動かす機会は今をおいて他にございませんぞ。」
そこで、騎兵に小松柵を包囲させ、歩兵に城柵を攻めさせた。しかしながら、東南には深い流れの川と碧い淵、西北には青い岩壁が聳えている小松柵の天然の守りに、歩兵も騎兵も行く手を阻まれてしまった。そのような状況ではあったが、兵士たちはこの深い川を渡ることを決断した。大伴員季は死を覚悟した兵20数名を率いて、剣を用いて岸を削り、鋒を使って岩をよじ登った。そして柵の基礎を切り崩し、城内に乱入して力を合わせて攻撃した。城内は大混乱に陥り、賊軍は壊滅した。城内にいた宗任は800騎を率いて城外に出て戦いを挑んできたのだが、官軍の先鋒はかなり疲弊しており、これを打ち破ることはできなかった。
そこで官軍は、五陣の兵士すなわち、平眞平、菅原行基、源眞清、刑部千富、大原信助、清原貞廉、藤原兼成、橘孝忠、源親季、藤原時経、丸子弘政、藤原光貞、佐伯元方、平経貞、紀季武、安部師方を召集し、戦力を集中させて攻めることにした。左に列挙した兵は皆、頼義将軍指揮下の関東の精鋭武士である。そして、生を忘れ死を顧みない奮闘が功を成し、ついに官軍は宗任軍を破ったのだった。また、第七陣の陣頭、清原武道が守っていた本陣には、宗任の精鋭約30騎が遊撃隊として襲撃してきたのだが、迎え撃った清原武道はこれをほぼ全滅させた。官軍の完勝である。
戦後処理
賊軍は柵を捨てて逃げ散ったため、官軍は火を放ってこれを焼いた。討ち取った賊徒は約60人、傷を受けた賊徒は数え切れないほどであった。官軍の死者は13人、負傷者は150人であった。兵を休ませ武器を整えたが、追撃は行わなかった。また、連日雨に見舞われ、ただ徒に数日を過ごすこととなった。さらには食糧が尽き、軍中は飢えに苦しんだ。磐井郡以南の各地では、宗任の命により官軍の物資輸送を妨害する者が現れ、さらには往来の人を襲う者や物を奪う者までも現れた。
このような悪党を追捕するため、頼義将軍は約1000人の兵を栗原郡へ分遣した。磐井郡仲村は陣地から四十余里の距離にある。この地は田畑が広がり、民家も非常に豊かであった。そこで約3000人の兵を派遣し、稲や穀物などを刈り取らせて軍糧とした。このようにして、陣地に留まった兵は約6500人に達した。それまでに要した日数、18日間。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |