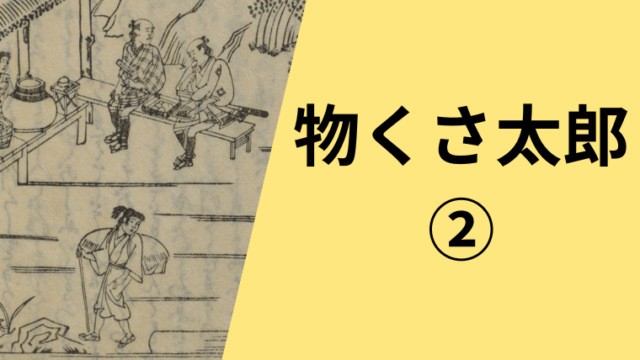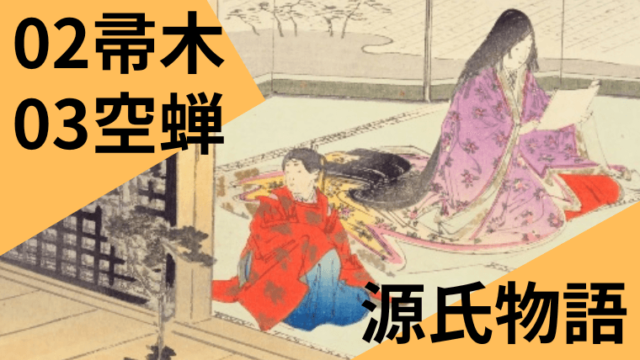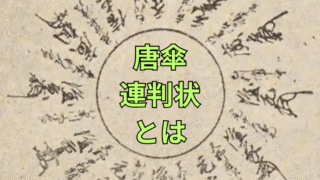現代語訳
| 一覧に戻る << | 続きを読む >> |
第六 重盛父清盛の法皇へ対し奉っての憤りのふかいことを諫められ、その謀として勢を集められた事。

右馬之允
喜一よ。もう少し続けてくれ。

喜一
それでは、夜が更けるまでですが、もう少し語りましょうーーーー。清盛は、このように多くの人々に警告しても、どうしても安心できなかったのでしょう。赤地の錦の直垂に、威を示すように黒糸の帯を腹巻きを身につけ、白金の装飾が施された着物を着て、銀の蛭巻(刀の鞘)に小長刀(こなぎなた)を携えて、常に枕元から離さずに備えました。脇に挿して中門の廊下に出てきた時の様といったら、まことに威厳があり、立派に見えました。
そこで清盛は
「貞能!」
と平貞能を呼びつけました。貞能は、木蘭地の直垂に、緋威(ひおどし)の鎧を身につけ、恭しく清盛の前に控えました。しばらくして、清盛は言いました。
「貞能、お前はこのことをどう思う? 保元・平治の乱以来、お前もよく知っている通り、帝のために命を捨てようとしたことは幾度もあった。たとえ誰が何と言おうとも、帝は、この七代(平高望ー繁盛ー維衡ー貞盛ー正盛ー忠盛ー清盛)の間、平家一門を決して見捨てることはなかった。そのはずなのに、下賤で道に外れた西光とかという坊主の言葉に乗せられた愚か者成親によって、今にもこの一門は滅ぼそうとされている。これが後白河法皇の計らいだというのだから本当に恨めしい。この先も後白河法皇に平家の讒言をする者が出続ければ、その時こそは『平家を滅ぼせ。』との院宣が下されるに違いない。朝敵となってしまえば、どれほど悔やんでも悔やみきれん。そこでだ。これから世を静めるしばらくの間、法皇には鳥羽離宮の北殿へとお移し申し上げるか、そうでなければ、こちらからお迎えして御幸(天皇の遠出)していただこうと思う。もしそうすれば、北面の武士たちも一本くらいは矢を射ることになるだろうよ。侍たちには、その覚悟をしておくように触れ回せ。後白河法皇への奉公は思い切ることにした。馬に鞍を置かせよ。甲冑を取り出せ!」
そう怒鳴りつけました。
主馬判官の平盛国は、急いで清盛の子重盛のもとへ駆けつけ、
「世の中はすでにこのような状況になっております。」
と申し上げました。重盛はそれを聞き終える前に、
「ああ、もう成親卿の首は刎ねられてしまったのだな。」
と言いました。
「そうではございません。しかし、重盛殿が甲冑を召されることになった以上、従う侍たちは皆立ち上がり、ただ今、法住寺殿(後白河法皇の御所)へと向かう準備をしております。また、法皇を鳥羽殿に押し込めてしまおうという計画があるとのことですが、内々では鎮西(西方)へ流す予定だとも聞いています。」
重盛は、『なぜ今、このようなことが起きているのだろうか。』と思いましたが、『今朝の清盛の様子から、何か物狂く思われた事が起こったのだろう。』と考え、車を飛ばして西八条(清盛の屋敷)へと向かいました。門前で車から降り、門内に入って見てみると、清盛は腹巻きを着ており、その周りには一門の人々がそれぞれ色々な直垂と思い思いの甲冑を身につけ、中門の廊下に二列に並んで座っていました。
その他各国から都に召されていた侍たちも縁側に座っており、さらには入りきらない侍たちが庭にぎっしりと並んでいました。旗竿を身に引き寄せていました。馬はというと、腹帯はしっかりと締められ、また兜の緒もきちんと結ばれており、今にも立ち上がって戦いが始まりそうな様子でした。重盛は、烏帽子と直衣も大紋のついた指貫も脱いで、ざわめきながらその場に入っていったののですが、侍たちには、その姿が場違いのように映っていました。
清盛は目を伏せて、『ああ、またいつものように重盛が世を軽んじるような振る舞いをしているのか! これは厳しく諫めなければならならんな。』と思いました。清盛は、相手が我が子であっても、内心では五戒(不殺生戒、不偸盗戒、不邪淫戒、不妄語戒、不飲酒戒)を守り、慈悲を優先し、外では五常(仁義礼智信)を乱さず、礼儀を正しく守る性格であったため、重盛のあの姿に対して腹巻きを着て向かうのはさすがに恥ずかしいと思われたのでしょうか、清盛は障子を少し引き立てて、慌てて素絹の衣を腹巻きの上に着ました。しかし、胸元の金具が少し外れて見えてしまい、それを隠そうと頻りに衣の胸元を引き違えて、整えようとしました。
重盛は、母違いの義理の弟である宗盛の上座に座ることになりました。清盛はそのことについて何も言い出すことはなく、重盛もまた、そのことについて何か言うこともありませんでした。
しばらくして、清盛は言いました。
「成親卿の謀反は、たいしたことではない。もともと法皇の計画であったのだ。だから、しばらくの間、世の中を静めるために、ここに法皇をお迎えして御幸を奉ろうと思っているのだが、どうだろうか。」
これを聞いた重盛は、言葉もなくぽろぽろと涙を流した。重盛は
「どうして。どうして。」
と呆れ、しばらくして涙をこらえながら言いました。
「このお言葉を聞くと、平家の運命はもう終わりに近づいていると感じます。人は運命が傾きかけると、どうしても悪事を思いつくものです。また、今の清盛公の様子は、現実のものとは思えません。太政大臣という地位にある者が、あんな甲冑を着るなど、礼儀に反することではござらぬか?特に、出家している身でございますのに。これは本当に、仏門に入った者とすれば既に破戒や無慚の罪、仏に帰依する世の人とすれば、仁義礼智信といった基本的な教えに背くものですぞ。何とも恐れ多いことをこれから申し上げたいのですが、これは心の底で恨みや復讐の気持ちを抱いているのではございませんので、申し上げます。四恩というものがあります。天地の恩、国王の恩、父母の恩、そして衆生の恩。その中でも最も重いのは朝廷の恩です。『天下に王のいない国は無い。』なんてことはありません。必ず天下には王の国があり、我が国ではそれが朝廷にあたります。故に、我が国に生を受けた衆生は朝廷に恩を尽くさねばならないのです。古代中国の許由は聖帝堯が自分に帝位を譲ろうというのを聞いて嘆き、汚い頴川で耳を洗ったといい伯夷・叔斉の兄弟は、帝の父から譲位の話を受けましたが、最終的には二人で首陽山に隠れ住み、蕨ひとつで死ぬまで命を繋いだといいます(いずれも、貴富権力に囚われない高潔な賢人の話。)。勅命に真っ向から背けないだけに、礼儀を示したのです。清盛公は、先祖が聞いたこともないほどの高位である太政大臣に任命され、権力を極めました。こう申しております私重盛自身も愚かな身でありながらも内大臣の位にまで昇り詰めました。それのみならず、国や郡の半分は平家一門の所領となり、その田畑は悉く平家の財産となりました。このようになったのは、前例のないほどの朝恩ゆえではございませぬか?今、これらの莫大なご恩を忘れて、みだりに法皇を倒そうとすることは、天道の御内証にも反することであります。また、法皇の考えは、道理から外れているわけでもないですぞ。特にこの平家一門は、代々朝廷に逆らう者を平定し、四海の逆浪(全国の乱れ)を鎮めるという比類なき忠義を尽くしてきました。とはいえです、これら功績を誇るような振る舞いは、傍若無人であるとも言えませぬか。このような家の運命がまだ尽きていないのです。何か起きても不思議ではありません。故に、既に謀反が露見しました。その上、法皇の側近でもある成親卿を平家が召し寄せたとなれば、たとえ法皇がどんな不義を思い立たせたとしても、何の恐れがありましょうか。法皇に相応の罪が執行されるのであれば、この場を退いて事情を説明しに行かせていただきたい。法皇のためにいっそう忠義を尽くし、民のためにはますます慈悲と慈愛を施すのです。それで平家は天命にかなうことができ、天の加護を受けることも出来ましょう。そうすれば、法皇も思い直すのでは?君主と臣下を並べた時、自分と親しいか疎遠かにこだわらず、必ず君主を立てるのが道理です。正しい道理と誤った考えを比べて、どうして道理に従わないことがありましょうか?
太政大臣とはいえ官職のひとつ。つまり清盛とて、天皇の臣下であることに変わりは無いのです。
これは君主に対する道理でございますので、たとえ私の願いが叶わなくとも、院の御所を守護し奉るつもりです。この重盛はじめ大臣から大将に至るまで、すべて君主のご恩によって今があります。その恩の重さは幾千万の宝玉にも勝り、深さは幾重にも染め重ねた紅の色よりもさらに深い。それ故、私は院の御所に参上し、籠城します。この重盛の身代わりとなり、命を捧げると誓った侍たちが少なからずおります。このような事態となった以上、彼らを召し連れて院の御所をお守り申し上げるとすれば、さすがに尋常ではない一大事となるでしょうな。なんとも迷惑なことではありませんか!法皇のために忠義を尽くそうとすれば、八万由旬(由旬は単位。1由旬=約13km)の須弥山の頂よりも高い父の恩をたちまち忘れることになり、不孝の罪を犯すことになる。かといって、不孝の罪を免れようとすれば、不忠の逆臣となってしまう。なんと、進退ここに窮まれり。。どうしても判断がつかない事態となった。。結論を申し上げよう。清盛公よ、ただただ重盛の首を召し取られよ。法皇を守護することもできないで、院参のお供などできぬ。かの蕭何(しょうか。劉邦の前漢統一の功労者)も、あまりにも大きい忠節が他人に勝っていたため、高位に上るのみならず、剣を帯び沓を履いたまま殿上の間に昇ることが許されていました。しかし、このような蕭何ですら、当時の皇帝、高祖(劉邦)の思し召しに背くことがあれば、厳しく戒めを受け、重い罪を科されていたのです。このように、先例を思い返してみても富貴や栄華、朝恩、重要な職など、あらゆるものを極めたとしても、その運が尽きることは難しくはない。『後漢書』巻十には、『富貴の家は代々禄位が重なるものが、木が再び実をつけると根が傷むように、代を重ねる毎に傾いているのだ。』とあるので、平家の今後を不安に思います。
後漢書、皇后上、明徳馬后紀のことです
いつまで生きて、いつまで乱れる世を見続けることになるのでしょうか。ただこの家の末代に生まれて、このような辛い目に遭う私の運命が情けないことです。今すぐにでも、侍一人に命じて私を御所の庭に引き出して首を刎ねるなど、容易いことでございます。皆々、我が話は聞きたな。」
直衣の袖を絞るほどの涙を流しながら口説かれたので、その座に列席していた人々は、心ある者も心ない者も、皆袖を濡らしたのでした。
清盛は、頼りにしていた重盛がこのような態度であったので肩を落としてしまい、
「いやいや重盛、それほどのことは考えていないぞ。法皇が悪党どもの言うことにつられて、誤ったことが起こるのではないかと思っているだけだ。」
と言いました。
重盛は、
「たとえ誤ったことが起ころうとも、法皇に手は出してはならぬ。」
と言い捨てて立ち上がり、中門へ出て侍たちに言い放ちました。
「今この重盛が申し上げたことを、お前たちは聞いたか? この騒ぎを静めようと朝からここにいようと思っていたが、あまりにも騒がしいから帰ることにした。院参のお供については、我が首が刎ねられるのを見届けてから参れ。」
そう言って、小松殿(堀川の西にある重盛の屋敷)へ帰っていったのです。
それから重盛は盛国を呼び、
「『重盛は天下の大事を聞き届けた。我こそ我こそ思う者たちは、皆武具を整えて馳せ参じよ。』こう触れ回れ。」
と命じ、盛国は、言葉の通り広く伝えました。
普段は騒がない者たちも、『このようなお触れがあるということは、特別な事情があるのだろう。』と言い、皆武具を整え、「我こそは。我こそは。」と重盛のもとへ馳せ参じました。
淀・羽束師(はづかし。現伏見区)・宇治・岡屋(現滋賀県蒲生郡)、その他、京周辺の各地に溢れるほどいる兵たちも慌ただしく騒ぎ立てながら集まってきました。甲冑を着ていなかまらまだ兜を被らない者、矢を背負っていながらまだ弓を持たない者、片方の鐙を踏む者など、様々です。
小松殿で騒ぎが起こったと聞くや、西八条に集まっていた数千騎の兵たちは、清盛に何も言わず、ざわめきながら小松殿へ馳せ参じました。特に、弓や矢を携えた者は、一人残らず駆けつけた。
清盛は大いに驚き、貞能を呼び寄せて言います。
「重盛は何を思って、このような者らを呼び集めたのだ? この様子を言い表せば、まるで清盛のもとへ討手を差し向けんとしているかのようではないか。」
貞能は涙をぽろぽろと流しながら、
「人にはそれぞれ心というものがございます。とはいえ、どうしてこのようなことになったのでしょうか。重盛殿がここで仰せになったことの数々、きっと後悔なさりましょうに。」
と申し上げました。
清盛は、重盛と仲違いするのは不味いと思ったのか、法皇を迎え奉ることを思いとどまり、腹巻を脱ぎ捨て素絹の衣に袈裟を羽織って、ただ意味もなく念仏を唱えたのでした。
重盛の屋敷、小松殿では、盛国が著到帳(出席簿)をつけていたのですが、それには、『馳せ参じた兵は一万余騎』と記されていました。重盛は、著到帳を確認した後、中門に出て、侍たちにこう言いました。
「日頃から約束を破ることなく参じたことは、誠に神妙なことだ。異国にもこのような例がある。周の幽王は、褒姒(ほうじ)という最愛の后を持っていた。褒姒は天下第一の美人であったにも関わらず、幽王の心に適わなかったことがある。『褒姒は笑みを含まず』といわれるように、一度も笑うことがなかったのだ。異国の慣習では、天下で乱が起こった時、各地で火を上げて太鼓を打って兵を召す仕組みがある。これを烽火(ほうか)という。ある時、兵乱が起こった。各地で火が上がったところを褒姒はご覧になって言った。『なんと不思議なことよ。火があれほど多いなんて見たことがない。』と。その時初めて笑われた。この后は、一度笑えば百もの色情が生じるほどの美人であったので、幽王はそれを嬉しく思い、それ以来常に理由もなく烽火を上げていた。その結果、人々は烽火を見て馳せ集まるのだったが、何事もないと分かるようになってから、すぐに散るようになっていった。このようなことが度重なったため、次第に兵も集まらなくなった。ある時、隣国から敵が幽王の都を攻めてきた。そのため、幽王は烽火を上げたのだが、例の后の火に慣れてしまい、兵は集まらなかった。結果、都は滅び、幽王も敵に討たれてしまった。だから、このようなことが発生し、召集が触れ回った際には、今回のように馳せ参じよ。この重盛は異変を耳にして皆を召集したが、改めて聞き直すと疑わしい点はなかった。そういうわけだ、すぐに帰るがよい。」
そうして、皆を帰らせたのでした。
実際にはそのような事(兵乱)を重盛が聞いたわけではありませんでしたが、父を諫めた自分の言葉に従い、兵を集めてみたのです。自分の勢力がどの程度あるのかを知ると共に、父子で戦をするつもりはありませんでしたが、このようにすることで、清盛の謀反の心も和らぐかもしれない、という計略であったといいます。
『古文孝経訓伝』の序文にはこう書いてあります。
「君雖不君、臣不可以不臣君(君主が君主らしくなくても、臣下は臣下としての道を欠いてはならない。父が父らしくなくても、子は子としての道を尽くさねばならない。)」
この重盛という人は、君主に対して忠義を尽くし、父に対して孝行を尽くす人であったのです。
後白河法皇もこの話をお聞きになって、
「今に始まったことではないが、重盛の心の内は本当に立派なものだ。敵に対しても恩をもって報いたのだ。」
と仰いました。当時の人々は、
「その素晴らしい果報によって重盛殿は大臣や大将にまで登りつめられたのだ。その風体は人より優れ、その上、才能才覚も世に抜きんだ人物だ。」
と言って、皆感嘆し合ったといいます。
『国に諫める臣がいればその国は安泰であり、家に諫める子がいればその家は必ず正しくなる。』という『孝経』の言葉はまことにもっともです。昔においても末代においても、このような人物は稀なことですな。
『孝経』諫諍章の要約です
(第六。終。)
| 第五に戻る << | 第七を読む >> |