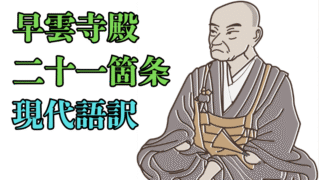現代語訳
| 一覧に戻る << | 続きを読む >> |
借金が返せない理由
69年前(寛永元年:1624)の元日朝に日食があったのだが、元禄五年(1692)の夜明け頃に再び日食を見ることになるとは、珍しい話である。持統天皇四年(690)に、元嘉暦から、日食月食をもとにした儀鳳暦に改められたことを始めとして、以来改暦は日食月食をもとに行われてきたことは、世間の人でも疑う余地のない話である。
「口(暦の初日。つまり元日)」に始まり、「末一段(暦の最終日。つまり大晦日)」となった今日、町からは浄瑠璃や小唄の音が聞こえない。今日一日は仕事が忙しいのだ。特に、小さな家が多い所では、喧嘩と洗濯と壁下地の修繕と、何もかもを一度に取り交ぜて行うものだから、新春の用意などとてもできない。餅一つすら、小鰯(ごまめ)一匹すらもない。富のある人と見比べれば、驚きあきれて声も出ない。
この相借屋(長屋の借家)に住む六、七軒の住人は、どうやって年明けを迎えるのだろうかと私は思ったのだが、どうやら皆、質種(質に入れる品物)に心当たりがあるらしく、世を嘆く様子が少しもない。彼らの普段の生活といえば、家賃はその月の月末に支払うし、その他をとってみても、全ての世帯道具、米、味噌、焼木、酢、醤油、塩、油に至るまで、後払いで売ってくれる商人などいないので、全て当座買い(現金払い)にして、取立てを恐れることのない平穏な日々を送る。借金の書かれた帳面をぶら下げた取立て人が、支払期日の節季(盆と年末)毎に、
「誰かいるか。」
と尋ねずに家に入って来るようなこともないし、誰かを恐れながら謝罪することもない。『楽しみは貧家に多し』という昔の人のことわざは、無用な言葉にはならず今でも通用する。書き出し(請求書)を渡されていながら完済しないという姿勢は、一般人に紛れて生活している盗人と同じである。
これらのことから思うに、人は皆、一年間の収支は高を括って算出しているのだろう。それでいて毎月の胸算用をしないから、つばめ(収支)が合わないのである。対して、その日暮しで生計を立てている者(その日の収入はその日に使い切る者)は、どのような生活をしているか分かりきっているから、小遣い帳一つ付けるまでもない。
皆の正月の迎え方
さて、このような者たちは、大晦日の夕方までいつも通りの様子でいるわけだが、正月を迎えるにあたってどのようにして事を片付けるのかと思うと、どうやら各々、質に入れる覚悟(破産覚悟)があるらしい。そのような心持ちで正月の華やかな準備をするのはなんとも哀れである。
とある一軒
とある一軒は、古い傘一本、綿繰り機一つ、茶釜一つと、かれこれ三品を銀一匁を質に入れて、それを正月の費用に当てた。またその隣では、身分の低い女房が、普段使っている帯を観世紙縒(かんぜごより)に替えて一筋に、そして主人の木綿頭巾一つ、蓋のない小重箱一組、七つ半の筬(おさ。機織りの道具)一丁、五合升と一合升の二つ、湊焼(現大阪府堺市)の石皿五枚、釣御前(つりおまえ。掛け軸にした絵像の持仏)にその他仏具を添えるなどして集めた二十三品で、一匁六分を借りて正月を迎えた。
その東隣の家
その東隣には舞々(幸都舞)の役者の男が住んでいたのだが、元旦から大黒舞(門付け芸能のひとつ。正月に大黒天に扮して(大黒天の面をつけて赤い頭巾を被り、打出の小槌を持つ)門口に立ち金品を受け取るといった形式の大道芸。)で稼ぎに行っているようで、五文の面と張貫(型の周りに紙を何重にも貼り、最後に型を抜くことで、型の形状を紙で表現した細工品。獅子舞の面などが代表例。)の槌一つだけで正月中は口過ぎ(生計を立てる)していた。また、舞々道具の烏帽子、直垂、大口袴などは不要な物なので二匁七分で質入れし、舞々の稼ぎとこの質入れ金で、のんびりと年越ししたのだそうだ。
東隣の家の隣
その隣は気難しい紙子牢人(いつも紙でできた服を着ているような貧乏な浪人)で、長年、武具や馬具を売り物にして食いつないでいた。少し前に流行った、馬の尾でできた鯛釣り糸の小刀細工も流行が終わってしまったので、今という今、小尻(鐺。刀の部位。鞘尻を補強するために付けられる金具)が抜けずに詰まったような、そんな窮状となってしまった。
この大晦日を越すための考えも思いつかず、偽物の梨地蒔絵が施された長刀の鞘を一つ、女房に質屋へ持って行かせたものの、質屋の亭主からは
「こんな物が何の役に立つものか。」
と、少しも手に取らず女房に投げ返されてしまった。女房はそのまま顔色を変え、
「人の大切な道具を、なぜ投げて壊したのだ。質として受け取るのが嫌なら嫌だと言えば済むことだろう。そのうえ、何の役にも立たないとの発言は、聞き捨てならないね。その長刀は、私の父親が石田治部少輔乱(石田は三成のこと。関ヶ原の戦い)の時、並々ならぬ手柄を挙げた時に使った長刀だ。まだ存命だった昔、私の嫁入り行列の対の挟箱の前に持たせたものでね、男の子がいなかったから私に譲ってくれたんだ。さて、役に立たない物と言われちゃあ先祖の恥。女に生れたとはいえ、命は惜しまぬ。相手は亭主にあり!」
と言って、質屋の亭主と取っつかみ合いになっては泣き出した。亭主も困って、色々と詫びたが女房は許してくれない。そのうち近所の者たちが集ってきて、
「あの女房の旦那の牢人はたかり屋だから、旦那がこの騒ぎを聞きつけてやって来ないうちに上手くやれよ。」
と、皆が質屋の亭主に囁いたので、亭主は銭三百文に加えて、詫びとして玄米三升を女房に差出し、ようやく話をつけた。
人は過去を捨てられない
はてさて、時代も変わるものだ。この女房は昔、千二百石の家の娘で何事においても上品な暮らしをしていた身であったが、今は貧しくなって人にたかりながら暮らしている。きっと自分でも分かっているだろうから、それが歯がゆく思う。誇りも栄華も失って心が貧相になっても、人とはそう簡単には死ねないのだ。
既に騒ぎも落ち着いて、質屋の亭主から女房は銭三百文と玄米三升を受け取ったのだが、
「この玄米はこのまま受け取って帰っても、明日の役に立たないよ。」
と言うので、亭主は
「幸いにも、ここに臼があるぞ。」
と、精米にさせてから帰した。これが世に言う『触り三百(少し関わっただけで大きな損害を受ける、の意)』であろう。
東隣の家の隣の隣
また、その牢人夫婦の隣には、37、38歳くらいの女が住んでいた。この女は親類どころか世話してくれる子供もいない独身である。5、6年前に旦那と死別したということで、髪を肩の高さで切り、紋無しの無地の着物を着てはいるが、身だしなみは目立たないようにしていて、昔のような夫人としての気概を持っていた。容姿は悪くない。
普段は、奈良苧(ならそ)を慰みのように摘んで(機織り業のこと)日々を送っているのが、この女は、はやく12月初めにはあらゆる業務を手回しよくこなして正月の準備をしていた。割木(薪のこと)も2月、3月分まで蓄え、正月に出す肴には二番(そこそこ大きめ)のブリを1本、小鯛を5枚、タラを2本、羹箸(かんばし。正月に雑煮を食べる時に使う箸)に塗箸(ぬりばし)、紀伊国五器(きのくにごき。紀伊国で産出される漆塗りの食器のうち、特に朱塗りの椀を指す)、鍋蓋まできれいさっぱり新調した。そしてやってきた家主殿(主人)へは目黒(詳細不明)を1本、その娘御(むすめご。他人の娘)へは緒が絹でできた雪駄を、お内儀様(おないぎさま。他人の妻)へはうね足袋(畝刺しを施した足袋)を一足、七軒の長屋の主人には餅とゴボウ一把を添えて、礼儀正しく新年を迎えていた。
この女は、私の知らない世渡りの方法をしているのだろう。どうやって稼いでいるのかまでは知らない。
東隣の家の隣の隣の奥の家
その奥の軒では、2人の女が一緒に住んでいる。一人は、年が若くて、耳も目も鼻も世間の人と異なるところはない普通の女である。ただ、一生独身で暮らすことを悲しく思い、鏡を見るたびに横手を打っては
「これでは妻に相応しいと誰も思わないわね。」
と、その身の程を嘆いていた。
もう一人の女は、東海道にある関の地蔵(現在の三重県亀山市にある九関山宝蔵寺地蔵院のこと。行基創建。)近くにある旅籠屋で客引きをしていた際、抜け参り(主人の許可なしに家を抜け出し、往来手形なしで伊勢参りに行くこと。江戸時代に流行、黙認されていた)で木賃泊まり(食料を煮炊きする薪代だけを支払って宿泊すること)していた旅人にきつくあたって旅人が持っていた米などを盗んだ。その罰の報いを来世を待たずにこの世で受けたのだろう、僅かな米を求めて托鉢坊主となって、もっともらしい顔をつくって、心にもない口先ばかりの念仏を唱えて過ごしている。
思えば、外見は尼でありながら心は鬼のようで、まさしく『狼に衣(表面は慈悲深そうに繕っているが、内面は善人らしく見せかけていること)』ということわざ通りである。勤行に精進することを忘れてはいるが、毎日墨染めの麻衣を着ているものだから、ここ14年、15年は仏のおかげであろうか、人々が施してくれていた。
「鰯の頭も信心から(信じてしまえば、どんなにつまらないものでも尊く思われること)」
とはよく言ったものである。毎朝托鉢に行っていると、一町ごとに2箇所ずつ手で掴めるほどの米を施してもらい、20箇所ほどまわってようやく1合となる。つまり、五十町駆け回らないと、米5合にならない。修行僧とて壮健な体でなくては勤めようにも勤められない。この尼は今年の夏に霍乱(かくらん。日射病のこと。下痢や嘔吐を伴う)を患い、どうしようもないのでこの麻衣を一匁八分で質入れしたが、その後それを取り返すだけの収入を得られず、世渡りの糧が尽きてしまった。
人は誰しも来世の安楽を願って仏教を信仰しているというのに、黒染めの衣を着た修行僧は朝は米5合を貰い、衣無しの修行僧には2合の施しもしない。特に年の暮れは、親の命日も忘れるほど誰しもが忙しい。この尼も例外なく師走坊主(年の暮れは誰もが忙しいために相手にされず困窮してしまう坊主のこと)となった。こうして誰も施しをくれないので、仕方なく、銭八文で年を越したのであった。
修行僧の身なりで人は施しの対象を選んでいます。修行僧であることには変わりないのに。
とはいえ、本当に世の中の哀れな一面が見えるのは、貧しい家の側にある小質屋である。強気でなければ成り立たない商いだからだ。このように世の一部を脇から覗き見してきたわけだが、悲しいことが色々と垣間見えた年の暮れであった。
まとめ
この話は、長屋に暮らす貧しい人々の年越しと借金事情を描いています。井原西鶴は読者に対して、「人が借金を抱え返せなくなる理由」や「町人の現実」といったことを考えたり知ったりしてもらう目的で書いたように思われます。
当時は、無理のない生計を立てながら慎ましく生き、取立ての恐怖とは無縁な人々であっても、正月だけは質入れによって一時的に凌いでいるようです。まあ、そこまで考慮して生計を立てろという話ですがね。
役者や浪人など、過去の栄光や誇りを希望に生計の足しにしようとしたり、逆に、未亡人、尼など、過去に縛られながら生きたりと、様々です。
タイトルの『長刀はむかしの鞘』とは、過去の長物は今となっては役に立たない、という意味で、そういった人たちを皮肉交じりに表現しています。いつまでも昔の価値観で何とかやり過ごせると思ってはいけませんね。
また、修行僧の身なり一つで施しの程度が変わる話は、人情の不平等さが浮かび上がってきます。
質屋というのは、人々の人生を垣間見ることのできる場所なのでしょう。
| 第一話に戻る << | 第三話を読む >> |