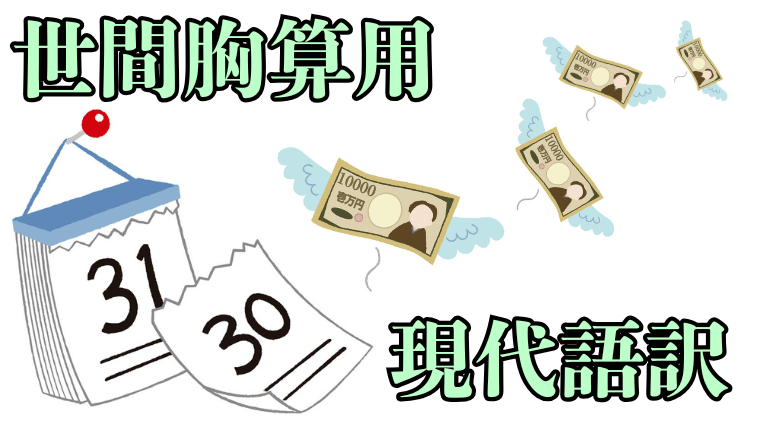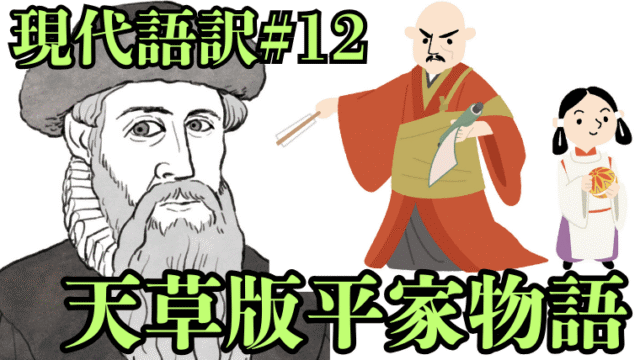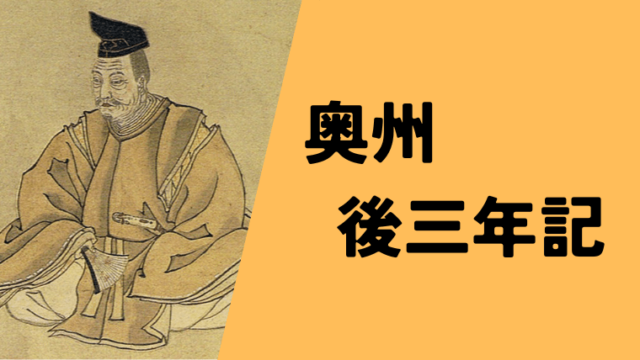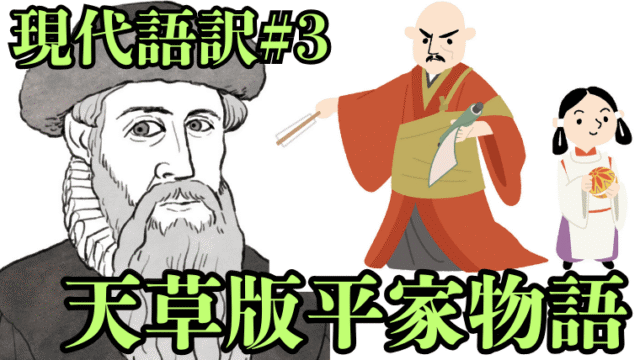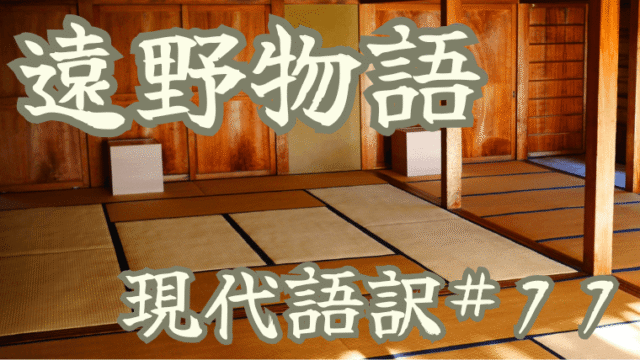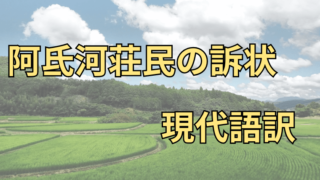解説
胸算用とは
「胸算用」とは、費用や利益といった損得などを頭の中で行う見積もりや計算のことを指します。
- 胸:心、内心
- 算用:計算、見積もり
要するに、感覚的・直感的なざっとした予測ですね。
『世間胸算用』の内容
『世間胸算用(せけんむなざんよう)』は、江戸時代中期の作家である井原西鶴によって書かれた浮世草子(うきよぞうし)で、年末の勘定や暮らしの悲喜を描いた作品です。
大坂の町人を中心に焦点が当てられた作品で、様々な職業の人々が登場します。年末年始にお金のやりくりに苦しんだり、知恵を絞ったりする姿がリアルに、そして皮肉やユーモアを交えて書かれています。
全5巻20話です。とらちゃブログでは
- 問屋の寛闊女
- 長刀はむかしの鞘
- 伊勢海老は春のもみじ
- 鼠の文づかひ
を現代語訳しています。
『問屋の寛闊(かんかつ)女』の内容
年末、特に大晦日は昔から「闇夜」であると知られているにもかかわらず、人々は油断し、支払いに追われて右往左往する。その最大の原因は借金であり、その借金の原因は子供の出費である。正月の破魔矢から雛人形、端午の節句の飾り、七夕の太鼓、年末の餅つきに至るまで、子供の年中行事には膨大な出費がかかる。それは目に見えにくいが、積もれば大きな金額となる。
さらに女房の浪費も深刻である。流行を追って高級な着物を新調するのだ。そのくせ、染め代に金一両もかける。帯やかんざしも贅沢品で、今の米価に換算すれば数俵分の値打ちがあるほど。町人の妻という身分でこれらを着こなすのは分不相応であるし、しかもそれを商売で借りた金でまかなっているというのだから、愚かというほかない。
それなのに、夫は女房の浪費を止めないのだ。なぜか?それは、配偶者の持ち物というのは差し押さえ対象外なので、仮に破産したとしてもそれを売って再起しようという算段があるからだ。だから、女というものは破産当日まで無駄遣いをやめない。ことわざの「月夜に提灯」「闇夜に錦」「湯を沸かして水にする」などは、まさにこのことである。
そんな中、夢に出てきた亡き父が、息子のだらしない経営を叱る。借金まみれでこの家も来年には売りに出される運命だ、と悲嘆しつつも、家宝の仏具だけは盆の送り火に託して極楽へ持ち帰るつもりだという。目覚めた息子は夢の父を笑い、仏具を菩提寺に納めようと決めた矢先、借金取りが大挙して押しかけてくる。
亭主は、手元の銀25貫目を両替商に預け、振手形という支払い伝票で商人たちに支払ったつもりになる。しかし振り出した手形の合計は80貫目以上で、両替商も慌てて計算を始める。手形を受け取った取り立て人たちは、その手形をまた別の支払いに使うため、次々に渡していき、金の流れは混乱を極める。
こうして年末は大混乱のうちに終わるが、元旦の朝には、何事もなかったかのように「豊かな正月」がやってくるのだ。。。
伝えたいこと
伝えたいことは以下の5つでしょう。
必要以上の子供への出費は控えよ
子供の行事や女房の贅沢など、「必要そうに見えて実は無駄な出費」が家計を圧迫している。
見栄のための借金は破滅につながる
特に女房。流行ものに便乗し、仲間や友人同士で見栄を張るために借金してまでして体裁を保つと、最終的に家そのものを失う原因になる。
金の管理は計画的に行うべき
小賢しい手形で帳尻を合わせようとするが、いずれは必ず自分に返って来る。
人間は愚か
父が死んでもなお息子の経営と見栄を嘆いているにもかかわらず、本人は反省することなく笑って受け流している。
表面的な「正月の豊かさ」は虚構である
当主だけでなく、皆が同じような手で借金を乗り越えようとしていることが読み取れる。そんな町人たちは「皆が」豊かな正月を装っているのだ。そのような姿は、なんとも皮肉で、空虚ではないか。
元禄文化
『世間胸算用』はどのような時代に書かれたのかみていきましょう。
江戸時代中期(17世紀後半〜18世紀初頭)の文化で、上方(京都・大阪)で隆盛しました。文化を形成するのはいつの時代も貴族が主でしたが、これは町人文化が花開いた期間となります。5代将軍徳川綱吉による文治政治によって経済が安定し、その担い手である町人が台頭したのが背景となります。
安定していた分、現世を「浮き世」として捉える風潮があり、それを肯定するかのような安寧的な作品が目立ちます。そして、浮世とあることから察せるように、浮世絵が隆盛したのもこの時期です。また、社会の安定は実証的、実用的な学問の発達を誘引しました。
これが元禄文化の特徴です。このことを頭に入れて代表例を見ていきましょう。
文学
- 井原西鶴
- 松尾芭蕉
- 近松門左衛門
絵画・工芸
主に尾形光琳の流れを汲む琳派が隆盛しました。そのため、名のある作品は尾形家系の作品が多くなっています。
- 菱川師宣:『見返り美人図』
- 尾形光琳:八橋蒔絵螺鈿硯箱・紅白梅図屏風・燕子花図屏風
- 尾形乾山:色絵十二ケ月歌絵皿
- 宮崎友禅:友禅染
- 円空:円空仏
ちなみに、友禅染とセットで扱われがちな「西陣織」ですが、この西陣というのは、応仁の乱の時に、西軍が陣を敷いたことから「西陣」と名付けられたと言います。
では東陣は?これは存在しません。なぜなら、東軍は花の御所に陣を敷いたからです。たったこのことから、東軍が現役将軍側であることが分かります。
建築
主に戦国期に関係する建造物が再建されています。
- 善光寺本堂:川中島の戦いの激戦地となった善光寺平に位置します
- 後楽園
- 東大寺金堂:松永弾正久秀によって焼き払われました
学問
- 儒学
- 林羅山
- 山鹿素行
- 新井白石
- 契沖
自然科学
- 貝原益軒
- 宮崎安貞
- 吉田光由
- 関孝和
- 渋川春海
洋学
- 新井白石
現代語訳
借金の原因は子供
世の中の常識として、大晦日が闇夜であることは天の岩戸が開いた神代の時代から知られていることなのに、人は皆いつも通り世渡りに油断していている。
毎年の支払い計画が外れて、大晦日の最終支払いができずに迷惑蒙るのは、各々の覚悟が弱いからである。一日千金にも替え難いほど重要な、大晦日。金がなければ、この冬と春の境である峠は越えられない。まあ、この峠、もとはといえば、己が築いた借金の山であるが。
借金は各々子供が要因である。子供というのは、人一人が持つ財産ほどに費用がかかるのだ。その出費はさしあたって目には見えないが、年間を通して見ると積もり積もって膨大になっている。
例えば、一度使えばゴミ箱行きの破魔矢や手鞠の糸屑(1月1日)。その他雛遊びの摺鉢が割れたり(3月3日)、菖蒲刀の箔が剥げたり(5月5日)、踊り太鼓が破れたり(7月7日)、八朔の数珠が切れたまま放置されたり(8月1日)。さらには、中の玄猪の日を祝うもち米を買い(10月中)、夏越しの祓い祭で供える氏神のお祓い団子を作り(6月31日)、大晦日には餅をつき(12月31日)、厄払いの包み銭も与え(3月3日)、悪夢除けのお札を買う(12月31日)。等々、宝船にも車にも積みきれないほどの出費を、子供は必要とするのだ。
女房の散財
特に近年は、どこの家でも女房が、旦那に奢って贅沢している印象である。着物に節約も何も気も使わないのだ。流行しそうな浮世模様の正月小袖を模索するべく、羽二重一反銀四十五匁の真っ白な絹の生地を買っては種々の素材を使って百色に染めあげるのだが、その染め賃は生地より高く、金一両にも及ぶ。それでいて、たいして人の目を惹くほどの出来ではないのだから、むやみやたらに金銀を捨てること捨てること。
帯にしても古くに渡来した高級な本繻子織を使う。一幅一丈二尺の一筋帯に、銀二枚を腰にまとう。さらに小判二両のかんざしは、今の米価に換算すると、本俵三石頭なわけだから、本俵三石頭を頭に挿しているわけである。
湯具(腰巻)は紅花で染めた高価な紅色の帯を二枚重ね、そして白絹の足袋を履いている。このようなこと、昔は大名の奥方でもしなかったというのに、と思えば今や町人の女房の分際でこのようなことをしているのだ。神仏のお咎めはどうなることやら、恐ろしいことありゃしない。
せめて自分で貯めた金銀が余ったうえでの贅沢であればまだ分かる。雨が降っても日が照っても昼も夜も油断できないような利息がついた金を借りて商いをする身でありながら、このような女の派手な金の使いようは、よくよく考えてみれば、我ながら恥ずかしいものである。
帯の布地の幅は二丈五寸で、当時の女性はそれを半分に切って使用していました。なお、男性は三つ切りでした。
散財の意外な目的?
これを許している旦那というのは、仮に明日、自己破産にあったとしても、女房の諸道具は差し押さえられないので、それらを売って金を生んでは再び商売に取り付くのだろう。要するに、回りまわって世帯を支えるめの糧とするつもりではないかと私は思っている。
総じて、『女の知恵は鼻の先(女は目先の利益しか考えられない、という意味。)』ということわざどおり、女は破産する日の夕方まで贅沢なことをする。
月が明るく出ているというのに、無駄に提灯持ちを2人つけて無駄に見栄を張る(ことわざ『月夜に提灯』)。
闇夜なのに錦の上着を無駄に着る(ことわざ『闇夜に錦』)。
湯を沸かしたのに冷めてから入浴するようなもので(ことわざ『湯を沸かして水にする』)、まったく、家庭に何の役にも立たない品行である。
仏壇の親父の忠告
死んだ親父が仏壇の隅からこれを見て、
「あの世とこの世は浮橋の雲で隔たれているものだから、悔やんでも悔やんでも忠告できない。お前の今の商売のやり方は、偽り問屋の総本家のようなものだ。嘘で騙して金稼ぎしているのだ。十貫目の物を買い、八貫目で売って二貫目の金を手に入れるその考えは、安直すぎて経営力の衰えがみえる。それで稼げるものか。借銭を返せるものか。来年の春には、この家の門戸に『こちら売り家!広さ十八間だよ!内には蔵三つ、戸も家具もそのまま、疊は上物中物が240畳!他には江戸舟が一艘に、五人乗りの御座船!さらには伝馬船まで付いて販売中!来たる1月19日、この町の会所で競売開始だよ!』なんて張り紙がされ、いずれ他人の所有物になることが仏である俺にははっきり見えて悲しいぞ。仏具までも人の手に渡るだろうよ。その中でも特に、唐金(青銅)の三つ具足(花立・燭台・香炉)は代々継いできて惜しいから、7月の盂蘭盆会の送り火の時、蓮の葉にそれらを包んで極楽浄土に持ち帰ってやろう。お前は『この家も来年までか』なんて心の中で思っているから、今丹波にかなりの田地を買い漁っているのだろうよ。周到に丹波に引っ込む用意をしているが、かえって分別無い行いである。俺は賢いから、お前のような人間に金を貸す人は利発な奴なのだから、隠し財産も一つ一つ調べ上げて残らず競売に出されることになろうよ。そんなしょうもない悪事に頭を使うくらいなら、何とかして今一度商売をやり直せ。こんなお前でも、やはり死んでも子供は可愛いのだ。だから夢枕に立って忠告しに行こうぞ。」
ということで、親父が現れた夢を見て、目が覚めた日は12月29日の朝であった。
大笑いしながら寝所から起きて、
「さてさて、年末の今日や明日は忙しいというのに、死んだ親父の欲心を夢で見た。あの三つ具足は菩提寺に奉納しよう。でないと後の世まで欲心しては夢枕で言い続けるぞ。」
と親父を謗っていると、あらゆる銭貸の取立て人が山のように集ってきた。さて、この亭主はどうやって始末をつけるのか。
大晦日の乗り越え方
近年、金のない商人たちは、手元に金銀があるうちに無利子で両替商へ預けておいて、金が必要な時に借りるようにしていた。金銭管理のために、小賢しい者が振手形(支払い明細書)というものを考え出したが、これは預ける側も預かる側も互いに便利なシステムである。
この亭主も、その心づもりで、11月末から銀二十五貫目を親しい両替商に預けておいた。そして大払い(大晦日の最終支払い)の時、取立てにやってきた米屋、呉服屋、味噌屋、紙屋、魚屋、観音講の出し前(負担金)、揚屋(遊郭)の支払いも、皆に対して、
「この両替商で受け取れ。」
と、彼らに振手形を一枚ずつ渡して、
「これで全部支払い終わった。」
と年籠り(年末の参詣)をしに住吉参りに出かけたが、内心ざわざわしっぱなしである。こんな人の初尾(賽銭。奉納する初穂が訛ったもの)など、受け取るのが神様であっても気をつかうだろうよ。
年籠りは要するに外出なので、借金取立てから逃げる手段として使われました。
泣きを見る人たち
さて、取立て人に渡した振手形だが、取り立て人にやった振手形の額が八十貫目余りであったのに対して、亭主が預けていた額は銀二十五貫目しかなかった。取り立て人が次々やってくるものだから、両替商は「計算して、差額分の請求書をを後で渡そう。振手形の額の方がどう見ても多いぞ。」と、色々調べる。そんな取立て人ですら、そこで得た額を支払いに当てるために別方に渡すのだ。その別方も更に別方に渡し・・・。
最終的にはどさくさに入り乱れ、誰がどこから貰い、いくら金が動いたのかも分からない、役に立たない振手形を金の代りに握って皆新年を迎えるのだ。
一夜明ければ、豊かな正月なのであった。
まとめ
この話は、年末の商人たちの借金や出費、特に子供や妻の浪費が家計を圧迫していく様子を、風刺的に描いています。年末の支払いを追跡困難な手形で乗り切ろうとする小賢しさ、それを皆がやってるから結局誰もが混乱したまま新年を迎えるという、当時の庶民生活の虚しさや愚かさを、ユーモアと皮肉を交えて表現していました。
現代でも、年末に取り立てが来ることがあるのでしょうか。経験が無いので分かりませんが、そんな年末は避けたいものです。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |