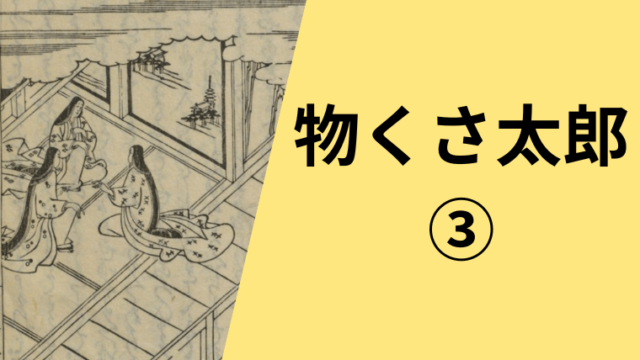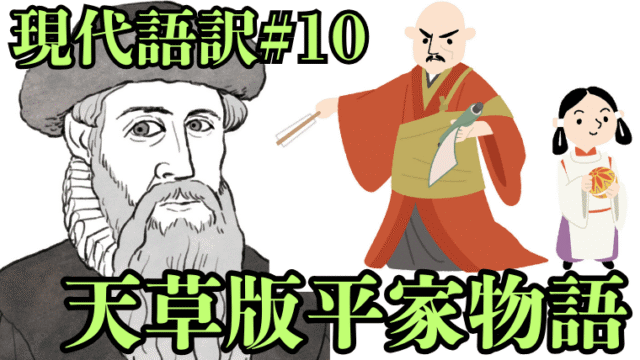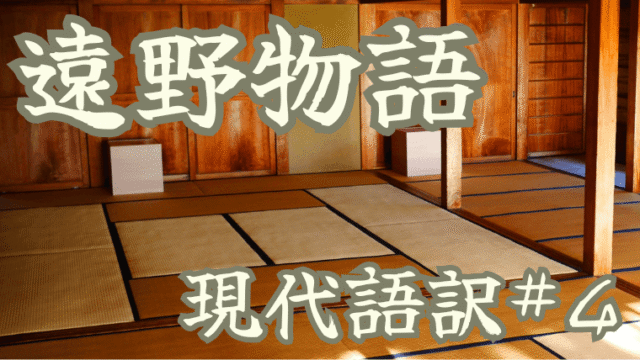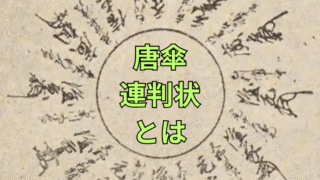1:地勢
遠野郷は今の陸中上閉伊(かみへい)郡の西の半分、山々に囲まれた平地である。
新町村(しんちょうそん)の構成は、遠野、土淵、附馬牛(つくもうし)、松崎、青笹(あおざさ)、上郷、小友(おとも)、綾織、鱒沢、宮守、達曾部(たっそべ)の一町の範囲を十の村が分布している。近代になってから西閉伊郡とも呼ばれるようになっており、また、古来よりは遠野保(とおのほ)とも呼ばれている。
今日、郡役所のある遠野町は郷唯一の町場であり、一万石の石高を持つ南部家の城下町である。この南部家の城は横田城ともいう。
遠野の町へ行くには花巻の停車場で汽車を降り、北上川を渡ってその川の支流である猿ヶ石川(さるがいしかわ)の渓谷に沿って東の方へ十三里行く必要がある。
山奥にしては珍しく栄えている。伝承によると、遠野郷の地は大昔すべて湖水で、その水が猿ヶ石川となって人界に流れ出た、その後自然に今のような人里になった、という。
谷川であるこの猿ヶ石は多くの道に通ずるためここで待ち合わせする者も非常に多く、俗に七内八崎(ななないやさき)ありと言われている。「内」は沢または谷のことで、奥州の地名に多く付いている。
※遠野郷の「トー」はもともとアイヌ語で湖という意味の単語が由来であろう、「ナイ」もアイヌ語が語源となっている
2:神の始
遠野の町は、南北を流れる川の落ち合いに位置する。以前は『七七十里(しちしちじゅうり)』といって、七つの渓谷の奥に行くこと七十里先から売買の物品を集めていたという。市の日には馬が千頭、人が千人集まり賑わったという。
四方を囲む山々の中で最も高いのを早池峯(はやちね)という。北の方、附馬牛(つくもうし)のさらに先にある。東の方には、六角牛山(ろっこうしやま)が聳える。石神山は附馬牛と達曾部(たっそべ)との間に位置し、石神山の高さは先に述べた早池峯と六角牛山よりも低い。
大昔、女神は三人の娘を引き連れて遠野に来て、今の来内村(らいないむら)の伊豆権現の社に泊まった。その夜、女神は
「今夜、いい夢を見た娘にはいい山を与えます」
と三人の娘たちに語った。寝ている間、姉の胸の上に天から霊華が降ってきた。目を覚ましていた末の姫はこれの花を盗って自分の胸の上に乗せると、ついに最も美しい早池峯という山を与えられ、姉たちは六角牛の山と石神の山をそれぞれ与えられたのだった。若い三人の女神は各々の山に今も住んでいるという話があり、遠野の女性たちはその妬みの心を畏れて今もこれらの山には遊びには行かないという。
※この一里は小道で、約550mある。
※「タッソベ」はアイヌ語であり、岩手郡玉山村にも同じ名称の土地がある。
※上郷村大字来内の「ライナイ」もアイヌ語で、「ライ」は「死」のこと、「ナイ」は「沢」のことである。水が静であることが由来か。
美しさに対する妬み(山の高さ=美しさか)でしょうか
3:山女
山の奥には山人が住んでいるという話はご存じだろうか。
和野というところに七十数歳の佐々木嘉兵衛(41・60・62に同じ)という人がいた。若いころ、狩猟のために山奥に入ったときの話である。遠くの岩の上に極めて色白な美しき女一人に出会った。その女性は長い黒髪をとかしているところであった。嘉兵衛は恐れることなくすぐに女性を銃で撃つと、弾は命中して女性は倒れた。その場に駆けつけてみると、その女は背が高く、黒髪はその背丈よりも長かったのであった。「証拠に残そう」と思ってその髪を少しだけ切り取って、これを束ねて懐に入れた嘉兵衛。帰り道の途中、彼は強烈な睡魔に襲われ、しばらく見えないところに隠れてうとうとしていた。
夢うつつにいた時のこと。背の高い男が近寄ってきて、懐の中に手を差し入れて、あの黒髪を取り出した。まるで、「取り返した」というような感じで立ち去っていったのを見ると、不思議なことにすぐに眠気が冷めたのである。この男は、妖怪山男に違いないと伝わっている。
※土淵村大字栃内の話である。
4:山女
山口村の吉兵衛という男が、笹を刈りに根子立という山に入った。刈った笹を束ねて担ぎ上げようとした時、笹っ原の上で怪しい風が吹き渡っているのに気が付いて顔を上げると、奥の林の方に幼子を背負った若い女が見えた。なんとその女は笹原っの上を歩いてこちらへ来たのだった。前の話の女(3山女)と同じく、この若い女も黒髪の長い非常に美しい女であった。
その様子はというと、藤の蔓で作った結い紐で幼子を背負い、どこにでもあるような縞模様の服を着ていた。そして裾のあたりがボロボロに破けており、いろいろな木の葉を使って修繕されていた。事もなげに近寄ってきたと思ったら、特に男に何かするということもなく、すぐ前を通ってどこかへ行ってしまった。吉兵衛はこの体験がきっかけで心身を煩い始め、長いこと闘病していたのだが、最近亡くなったという。
※土淵村大字山口の「吉兵衛」という名は代々の通称であるため、代が変わればこの主人の名もまた「吉兵衛」である。
5:山男・地勢
遠野郷から海岸にある田ノ浜や吉利吉里という土地へ行くには、昔から笛吹峠という山路を通る必要があった。また、山口村から六角牛につながる道の始点に行くにもこの山路を通った方が早い。
しかし近年、この峠を通る者は、必ず山男山女に出逢うという。みな恐ろしがり、結果その峠の往来は稀なことになっていた。ついには別の山路を境木峠という方に作った。途中にある和山を馬次場として利用して、今は基本的にこちらの峠を越えるようになっている。二里以上の遠回りである。
※「山口」は六角牛に登る山の入り口であるため、それが村の名となったのである。
6:山男
遠野郷では、豪農のことを今でも『長者』という。青笹村大字の豪農であった「糠前の長者」には娘がいたが、行方が分からなくなって長い月日が経過していた。ある日、同じ村の何某という猟師が山に入って一人の女に遭遇した。怖くなってこの女を撃とうとした時、女は「怪しい者ではない、撃つな」と言った。その女をよく見ると、驚いたことにあの糠前の長者のまな娘ではないか。
「なにゆえこんな所にいるのか」と聞くと、娘はこう答えた。
「あるモノに連れ去られて今はそのモノの妻となっている。子宝に恵まれたが子供たちは残らず夫に食い尽くされてしまった。だからこのようにひとりでいるのだ。私は逃げ出せない、この地で一生涯を送ることとなるだろう。だから誰にも言うな。あなたの身にも危険が及ぶから早く帰れ」と。
何某は言われるがままに、娘や夫のいる場所も聞かずに逃げ帰ったという。
※「糠の前」は糠の森の前にある村で、「糠の森」は諸国でみられる「糠塚」に同じである。遠野郷にも糠森・糠塚が多くある。
7:山男
上郷村の民家の娘が栗を拾いに山に入ったまま帰って来なかった。家の者は、娘は死んでしまったと思い、娘が使っていた枕を形見として葬式を執行った。それから二、三年経過した。
ある日、その村の者が狩猟のために五葉山の中腹のあたりに入った。その者は巨大な岩で覆われた岩窟のようになっているところを見つけ、中を覗くと、なんと偶然にも行方不明であった娘がいたのだった。互いに驚き、その者が娘に対して問うた。
「どうしてこのような山にいるのか」
娘は言う。
「栗を拾いに山に入ったら怖い人に攫われ、こんなところまで来ました。逃げて帰ろうと思うが、そのような隙もございません。」
「その怖い人とはどのような者か」
「私には普通の人間に見えます。違うことがあるとすれば、背丈が非常に高く、目の色が違うことです。子供を何人か生みましたが、その人は子供を見るたびに『自分に似ているようで似ていない、我が子ではない!』と言って食らい殺し、その後はどこかに持ち去ってしまいます。『本当に人間か?』とその人に聞いたところ、衣類などはいたって普通なのに、眼の色が少し違うことに気が付いたのです。また、一度か二度、同じような人が四、五人集まっていたのを見ました。五日間ほど何か話をして、どこかへ出て行くのを見ました。食べ物などは外から持ち込んでいるので、今は町に出かけているのかもしれません。こう話しているうちにもすぐそこへ帰って来るかも知れません。」
この言葉を聞いて、猟師は怖くなって帰ったという。二十年も前の話かと思われる。
8:昔の人
『女や子供が黄昏時に外に出ていると神隠しに遭遇しやすい』といった話は他の国々と同じである。
松崎村の寒戸というところの民家の話である。そこに住む若い娘が梨の樹の下で草履を脱いだまま行方知らずとなったことがあった。それから三十数年過ぎたある日、その民家に親戚や知人が集まっていたところへ、年老いてよぼよぼになった姿のあの娘が帰ってきたのだ。
「どのようにして帰って来たのか」
「皆に会いたかったから帰ってきた。また来るから、それでは。」
そう言って、あの時のように足取りも残さずまたどこかへ行ってしまった。その日は風が激しく吹き荒れていた日であった。そのため、遠野郷の人は、今でも風の吹き荒れている日には、「今日はサムトのおばばが帰って来そうな日だ。」というのだとか。
9:山男
菊池弥之助という老人は若いころは「駄賃」という馬の背中に人や物を乗せて運搬する運送業に従事していた。弥之助は笛の名人で、夜通し運送する時などは、よく笛を吹きながら仕事していた。
薄月夜のある日に、多くの仲間の者とともに、浜へ行くために境木峠を越える、ということで、その夜も笛を吹きながら道を進んでいた。その途中に大谷地という沢があった。ここは深い谷と鬱蒼としている白樺の林があり、その下は葦などが生息している湿地であった。
一行がこの大谷地を通過した時、谷底から何者かが甲高い声で笛の音に対して「風流だな~」と叫んできた。全員が顔色を真っ青にして逃げ走ったという。
※「ヤチ」はアイヌ語で湿地という意味で、内地の著名に多く見られる。「ヤツ」や「ヤト」「ヤ」ともいう。
10:昔の人
ある男がきのこを採集のために奥山に入ていった。山中の小屋に泊めてもらった時、深夜に、遠くから「きゃー」という女の叫び声が聞え、非常に驚いてしまったことがあった。里へ帰ってみると、自分の妹が妹の息子に殺されていた。山中で叫び声を聞いた日時と同じだったという。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |