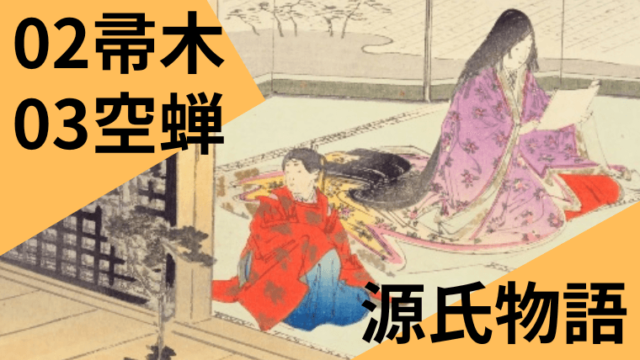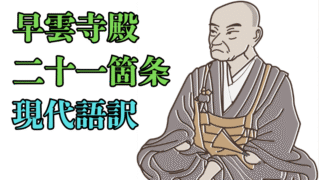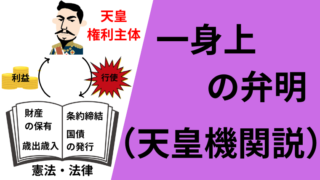現代語訳
| 一覧に戻る << | 続きを読む >> |
第九 康頼と少将とかの島で熊野詣での真似をし、また卒都婆を作つて流されたことを蘇武が雁書に引合はせて語る事。

右馬之允
鬼界ヶ島での出来事なども語っていただきたい。

喜一
かしこまりました。さて、成経と康頼はもともと熊野を信仰していたため、
「どうにかしてこの島の中で熊野に似た場所を探し出し、『熊野』と名付けてお参りしたいな。」
と話し合いました。あちこちを探ったところ、風景から木々の様子に至るまで、他のどこよりも熊野に似ていた場所を見つけました。
南を見れば、海は広々と広がり、雲は波のように立ち込め、波は煙のように立ち昇り、深々と続いている。北に振り返れば、山や峰が聳え立ち、その間からは滝が勢いよく流れ落ちている。その音は実にもの寂しく、松風が神秘的な雰囲気を醸し出していました。この様子が、熊野権現の鎮座する那智の山によく似ていたため、二人はそこを「那智の山」と名付けました。そして毎日、二人は一緒に熊野詣での真似をして、都へ帰れることができるように、と祈ったのです。
康頼入道(性照)は、あまりにもどうしようもない境遇に嘆き、千本の卒都婆(そとば)を作り、それぞれに仮名(けみょう。通称のこと)と実名(じつみょう)を書き記し、さらに二首の歌を添えました。そして、
「もし故郷き流れ着くことがあれば。」
と願いながら、卒塔婆を海へ流しました。その歌は次のようなものでございます。
薩摩潟 沖の小島に 我ありと
親には告げよ 八重の汐風
「私は今、薩摩潟の沖にある小島にいます」と、親に伝えてください、八重に重なる潮風よ。
思ひやれ しばしと思ふ 旅だにも
なほ故郷は 恋しきものを
ほんのしばらくの旅でさえも思いやられるのに、この島流しの旅は、なおさら故郷が恋しく思われるよ。
「せめて一本だけでも都のあたりへ流れ着いてほしい。」
と願いながら、千本の卒都婆を海へ流しました。そのうちの一本は安芸国の厳島の渚に打ち上げられたのです。康頼と縁のある僧がこれを得ました。
『然るべき便りがあれば、それを理由に、何とかしてあの島へ渡り、康頼の消息を確かめたい。そして、その便りが今ここに。』
そう思い、西国修行の旅に出ました。まず厳島へ立ち寄ったのですが、着いたのは日暮れで月が昇り、満潮の時間でした。その時、漂う藻屑の中から、卒都婆のようなものが波に揺られているのを見つけました。何となしにそれを手に取って見てみると、
「沖の小島に我あり。」
と書かれていました。その文字は、しっかりと彫り刻まれていたため、長い間波に洗われても消えなかったのです。おかげで、はっきりと読み取ることができました。
「なんと不思議なことだ。」
と言って、その卒都婆を持ち帰り、笈(おい)の片側に挟んで都へ上りました。そして、尼の康頼の老いた母や妻子たちがひっそりと暮らしている紫野(一条の北にある)という場所へ行って見せ、それを見た母や妻子たちは、
「それならば、どうして、この卒都婆が唐などの異国の方へ流されていかずにここまで伝えに来たのだろう。今更、辛い思いが込み上げてきます。」
と悲しむこと、計り知れないほどでございました。
しばらくして、この卒都婆は後白河法皇もご覧になりました。
「なんと痛ましいことか! まだ彼らは生きているようだな。」
そう仰せになっては涙を流されました。そして法皇は、すぐにこの卒都婆を重盛のもとへ送らせました。重盛がそれを父清盛に見せると、清盛もまた哀れに思ったと伝えられています。どれほど冷酷な人物であったとしても、さすがに心は有るものなのです。
清盛が哀れに思ったことをきっかけに、京中の老若男女を問わずあらゆる身分の人々が、鬼界ヶ島に流された人々の和歌を口ずさんだといいます。
それにしても、千本もの卒都婆を作ったとはいえ、小さなものであったはずなのに、薩摩潟からはるばる都まで伝わったとは、不思議な話でございますな。人があまりに強く思うのは、昔からこのような霊験があるためでしょうか。
昔の話をしましょう。古代中国、漢王が胡国(異民族の国)を攻めました。最初に李少卿(李陵)という者を大将軍に任命し、三十万騎の軍勢を送り込んだのですが、漢の軍勢は弱く、対して胡国は強かったため、官軍は悉く打ち滅ぼされ、それどころか、大将軍の李少卿までもが生け捕りにされてしまいました。
漢王は次に、蘇武という者を大将に任命し、五十万騎の軍勢を仕向けました。しかし、やはり漢の軍は弱く、胡国は非常に強かったため、官軍は悉く滅ぼされ、それどころか、6000人余りの兵までもが生け捕りにされてしまいました。
胡国の兵は、大将軍李少卿、蘇武をはじめとする兵630人ほどを選び出し、一人ひとりの片足を切って追放しました。それによってすぐに死ぬ者もいれば、しばらく生き延びた末に死ぬ者もいました。
そんな中、蘇武だけは死なずに、片足を失ったまま生き延びました。彼は山に登って木の実を拾い、春には沢辺で根芹(ねぜり)を摘み、秋には田んぼの落ち穂を拾うなどして、いつ消えてもおかしくない命を繋ぎ続けたのです。
田にたくさんいた雁たちは、蘇武を見慣れて恐れなくなったほど。そこで蘇武は、
『これらの雁は皆、私の故郷へわでいくのだろうな。』
と思い、懐かしさから自分の思いを一筆書き、雁の翼に結びつけて放しました。すると、不思議なことに、その雁は漢の昭帝が遊んでいた場所へ飛んでいったのです。
時は夕暮れ、空は薄く曇り、何とも物悲しい雰囲気でした。雁の一群が空を飛び渡っていった時、あの雁が飛び下りて来て、翼に結びつけた玉章をくわえて落としました。それを官人が拾い上げて、皇帝に奉りました。皇帝がその玉章を開いて見ると、こう書かれていました。
『3年間、岩の洞窟に幽閉され、悲しみと苦しみを耐え忍んできた。しかし今は、広い田の中に捨てられ、片足だけの身となってしまっている。屍をこの地に散らしたとしても、魂は再び君のもとに仕えるであろう。』
と。それから、この手の文は「雁書」または「雁札」と呼ばれるようになったと言われています。
さて、漢の昭帝はこの文を見て、
「まだ胡国に蘇武が生きているからこそ、このようなことが起こったのだろう。」
と言いました。そして、今度は李広という将軍に命じて、百万騎を胡国に仕向けました。結果、今度は漢が強く、胡国の軍は敗れたのです。味方が戦に勝ったと聞いた蘇武は、広い野原から姿這い出て、
「我こそ古に活躍せし蘇武である。」
と名乗り、十九年の春秋を経て、片足を切られた身でありながら、輿に担がれて故郷へ帰ったのでした。
蘇武は16歳で胡国に進軍したのですが、この時、帝から旗を賜っていました。蘇武はこの旗を何とか隠し持ち、放すことなく持ち続けていたのです。旗を取り出し、帝の前に差し出したところ、君主も臣下も皆並々ならぬ忠義心に感動しました。結果、蘇武には厚い賞賜が与えられ、大国も多く与えられたのだとか、と伝えられております。
唐土の蘇武が書を雁の翅に結びつけて故郷へ送ったように、日本の康頼もまた浪を便りに和歌を故郷へ伝えました。
蘇武はただの一筆、康頼は二首の和歌です。また、蘇武は古代の出来事、康頼は末代の出来事でございます。胡国と鬼界ヶ島といった、距離に隔てはありますが、時代が変わっても、その風情は同じだったです。本当に不思議な出来事でございます。
(第九。終。)
| 第八に戻る << | 第十を読む >> |