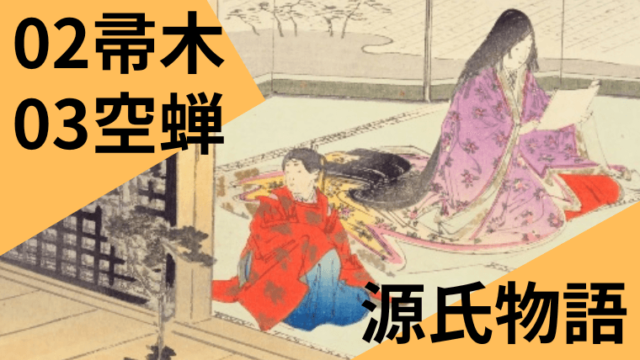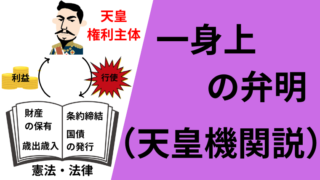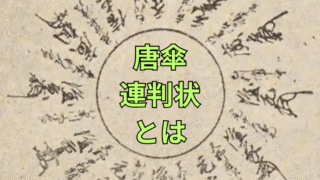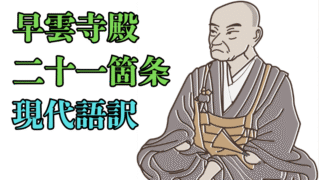現代語訳
| 一覧に戻る << | 続きを読む >> |
第十 鬼界が島の流人を許さるゝについて後に残らるゝ俊寛の悲しみ深い事。

右馬之允
その鬼界ヶ島の流人たちが清盛によって許されたらしいですが、経緯を語っていただきたい。

喜一
后となった清盛の娘、中宮様がご懐妊されたのですが、これが思いの他大きな悩みの種となり、天皇をはじめ多くの人々が中宮を気遣いました。
中宮とは平徳子のことです。高倉天皇の正妻、安徳天皇の生母で、出家後は建礼門院と名乗りました。
清盛も様々な祈祷を行ったのですがその効果は顕れませんでした。そんな折、鬼界ヶ島へ流された少将(藤原成経)の舅、宰相殿(平教盛)がこのことを耳にし、重盛に申し出ました。
「中宮様のご出産祈願には、特別に恩赦を出す以上のことはないかと存じます。とりわけ、鬼界ヶ島に流された流人たちを都へ召し還すことが最も大きな功徳、そして善行になるのではないでしょうか。」
と。そして重盛は父禅門(清盛)の御前に参上して申し上げました。
「あの成経殿が私(平家)のことを非常に嘆かれていることが気の毒です。中宮様のお悩みへの祈りとしても、成経殿は都へ召し戻されるのが良いと存じます。人々の心を安らげれば、思し召すことも叶いましょう。人の願いを叶えれば、天はこれを受け入れ、祈りも成就しましょう。そうすれば、中宮様はすぐに皇子をご出産なされ、我が家門の繁栄もますます盛んになることでしょう。」
清盛は、日頃と似ずに穏やかになり
「さてさて、では俊寛と康頼はどうなっているのか。」
と尋ねました。すると側近が
「彼らも同じように都へ召し戻されるのがよろしいでしょう。もし一人でも島に留め置くようなことをすれば、それは大きな罪業になりましょうぞ。」
と申し上げました。
「康頼はともかく、俊寛は別だ。俊寛は重盛の口添えによって高位に登った身でありながら、場所なんていくらでもあろうに、まして鹿谷を選んで城郭を築き、自ら謀反を企てたような奴だ。俊寛を許すなど、思ってもおらぬ。」
と清盛は言いました。
重盛は父清盛の兄弟(=叔父)である教盛を呼んで、
「成経殿はすでに赦免されました。ご安心ください。」
と言いました。教盛は手を合わせて喜びました。教盛は、
「成経殿は西国に下っている時も、『なぜ私がこれほどの仕打ちを申し受けているのか。』というような様子で、私の顔を見るたびに涙を流しておられました。それがあまりにも不憫でした。」
と申し上げると重盛は、
「本当にそう思います。親の不幸を聞けば子は誰でも悲しくなります(成親成経親子のことだけだなく、もし徳子に最悪の事態があった時のことも言っている)。なので、清盛公にはよくよく申し上げました。」
と言って、鬼界ヶ島の流人たちを都へ召し還す旨の許し状を清盛から受け取って使者を鬼界ヶ島へ派遣しました。
教盛はあまりの嬉しさに、使者に自分の使いを添えて共に送り出しました。使者一行は昼夜を問わず急いで下ったのですが、海の度は思うように進みません。波風と戦いながら進んだがため、都を7月下旬に出発したのに、鬼界ヶ島に到着したのは9月20日ごろとなってしまいました。
使者は丹左衛門尉基康といいます。到着した元康は船から上がると
「都から流されてきた丹波の少将殿や俊寛御坊、また平康頼などはここにおらぬか。」
と尋ね回りました。二人(成経と康頼)は、いつものように熊野詣でをしていて留守であったのですが、俊寛一人だけが島に残っていました。この話を聞いた俊寛、
「あまりに願っていたものだから夢でも見ているのではないのか。それとも、天魔破旬(人の心を乱す悪魔)が私をたぶらかそうとしているのか。現実とは思えぬ。」
と言って、慌てふためきました。転びそうに走りながら、倒そうになりながら、急いで使者のもとへ走り向かいました。
「何事ですか。我こそ京から流された俊寛にございます。」
と名乗ると、使者一行の雑色(下級の役人)が、首にかけていた文袋から清盛の許し状を取り出して俊寛に捧げました。開いて見ると、こう書いてありました。
「重罪、島流しの刑を免ず。早く帰京の準備をせよ。これは中宮様ご出産の祈願による特別な恩赦である。ここにおいて、鬼界ヶ島の流人である藤原成経と平康頼の赦免を認める。」
と。しかし、そこに俊寛の名は書かれていませんでした。俊寛は
「礼紙(添え紙)に書いてあるのだろう。」
と思い、礼紙を見ましたが、どこにも自分の名前は見当たりませぬ。
俊寛は許し状を奥から端まで、端から奥まで読み返しましたが、やはり、「二人」としか書かれておらず、「三人」とはどこにも書かれていません。そうこうしているうちに、成経と康頼が熊野詣でから帰ってきました。成経が許し状を手に取って見ても、康頼が読んでも、やはり「二人」とだけ書かれており、「三人」とは書かれていない。このようなことは夢の中でならありそうな話です。俊寛は、夢かと思えば現実であり、現実かと思えば夢のような心地がしていました。
そのうえ、成経と康頼の二人のもとには都から伝言や文がいくつも届いていたのですが、俊寛のもとには、文一通すらありませんでした。これを見た俊寛は言いました。
「さてさて、我々三人は同じ罪に問われ、同じ所に島流しされたのに、どうして赦免の時になって、二人は召し還され、一人はここに残されるのかだ?平家が私の存在を忘れたのか?それとも執筆の誤りか? これはいったいどういうことなのだ。」
俊寛は天を仰ぎ地に伏して泣き悲しみましたが、それも無駄なことでした。そこで俊寛は成経の袂にすがりついて訴えました。
「私がこのような目に遭ったのも、貴方の父大納言殿(藤原成親)が根拠もない謀反を密告したせいではないか。だから成経殿、これは他人事とはお思いにならないでくれないか。たとえ赦されず都に帰れなくとも、この船に乗せて、せめて九州の地に降ろしてくだされ。貴方がたがここにいたおかげで、春には燕が飛来し秋には田に雁が訪れるように、自然と故郷の話を伝え聞くことができた(渡り鳥の自然の摂理になぞらえている)。これからはどうやって知ることができようか。」
そう言って、俊寛は悶え苦しみました。その時、成経は俊寛に申し上げました。
「本当に、そのようにお思いになるのは尤もです。我々が召し還されることは嬉しい事ですが、あなたのご様子を目の当たりにすると、空を飛ぶような気持ちで上洛する気にはなれません。しかし、あなたを乗せて共に上洛することはできないのです。どうしようもないことなのです。都からの使いが『それは叶いませぬ。』と言っているというのに、更に赦しも出ていないというのに3人揃って島を出たなどと都に伝われば、かえって事態は悪化しましょう。故に、まずは我々が上洛します。人々と申し合わせ、清盛公の機嫌を伺いながら、迎えの人をこの島へ進めるように手配しましょうぞ。それまでの間、日頃しているように強く願いながらお待ちくだされ。命長らえることは何よりも大切です。今回は赦免から漏れていましたが、命さえあれば、最後には何かしらの理由で赦免を受け、都へ帰る日を迎えることができましょう。」
そう慰めたのですが、俊寛は人目も憚らないで泣き、悶え苦しんだのでした。
さて、
「船を出そうか。」
と人々がひしめき合っているところで、俊寛は乗っては下り、下りては乗りを繰り返すという予想通りの行動に出ました。俊寛は自身の形見として、成経には夜の衾(寝具のこと)を、康頼には法華経の大部分を与えました。そして、船の纜(ともづな)を解き、船が押し出される時が来ました。俊寛は綱にしがみつきます。水深は腰まで上がり脇まで上がり、立てる所まで身を引きずったのですが、ついに足がつかないほどの水深にまでなりました。それでも俊寛は船にしがみつきました。
「さてさて皆よ、ついに俊寛を見捨てることになさったのですか?このようになるとは思ってもいなかった。日頃吉野にかけていたお情けも、今となっては何にもならない。道理を曲げてでも私を船に乗せくだされよ。せめて、せめて九州の地まで!」
俊寛は必死に訴えましたが、都からの使いは、
「それは、どうしてもそれは叶わぬのです。」
と言い、俊寛の手を振りほどいた。そして、ついに船は都に向けて漕ぎ出されたのでした。俊寛はどうにもできず、渚に上がって倒れ伏しました。幼い子供が乳母や母親を恋しがるように足ずりをしながら、
「私を乗せて行ってくれ! 連れて行ってくれ!」
と喚き叫んだのですが、漕ぎ行く船が戻らないのは世の習い、ついに残されたのは白波ばかりなのでございました。
まだそれほど遠ざかってはいない船ではありましたが、俊寛は涙に溢れて船を見ることができませんでした。そして、高い場所へと駆け上がり、沖の方へ向かう様子はまるで沖に招かれているようで、かつて松浦小用姫が、唐へと去っていく船を恋しく思って領巾(ひれ)を振り続けた(松浦佐用姫の伝説は『肥前風土記』にもみられる)という『万葉集』の話も及ばないほど哀れに思われました。
船は見えなくなり、そして日も暮れてしまいました。しかし、俊寛は自分の粗末な家に帰らず、波に足を洗われながら露に濡れて、浜辺でその夜を明かしました。
「私を置いていったとはいえ、成経殿は情け深い人だから、良きように取り計らってくれるだろうよ。」
そう成経に願をかけて、衝動にかられて身投げ心中はしませんでしたが、後から振り返ってみれば、希望を抱いたことは愚かなことであったと言えましょう。
(第十。終。)
| 第九に戻る << | 第十一を読む >> |