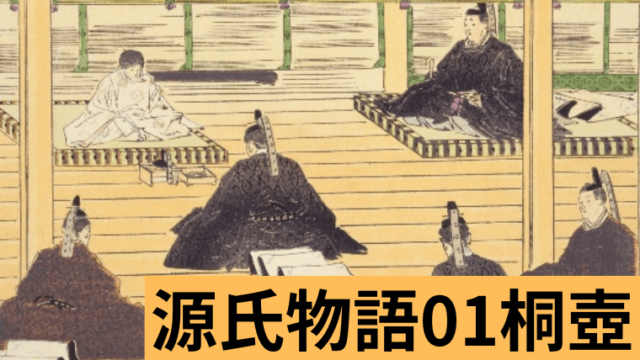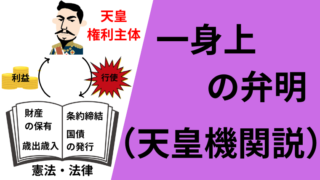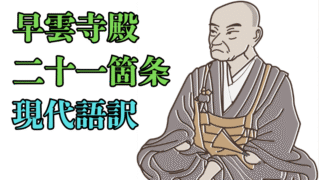現代語訳
| 一覧に戻る << | 続きを読む >> |
第十一 少将・康頼都へ帰らるゝ道すがらの事。

右馬之允
はてさて、これは本当に哀れなことだったな。ところで、成経や康頼はそのまま都へ上られたのか?

喜一
そのことについて話しましょう。成経と康頼の一行は鬼界ヶ島を出て、宰相殿(平教盛)の知行国である肥前国鹿瀬の荘に到着しました。すると、京から教盛の使いが下ってきて、
「年内は波風が激しく旅帰路も心休まらないだろうから、そこに逗留し、体を労りください。春になったら都へへお戻りあれ。」
と伝えてきました。それに従って、成経は鹿瀬の荘でその年を過ごしたのです。
年が明けて治承3年(1179)1月下旬、丹波の少将(成経)と康頼は鹿瀬の荘を出立し、都へ急いだもですが、まだ余寒が厳しく海も荒れていたため、浦伝い島伝いに歩みを進め、2月10日頃に備前国の児島に到着しました。
父成親が住んでいた所を訪ねて行ってみると、竹の柱や古びた障子に筆跡が書き残されていました。これを見て成経は
「ああ、人の形見の中で、手跡に勝るものはない。もし書き残されていなかったら、どうやって父の息遣いを見たら良かったのか。」
と言いながら、平康頼と2人、読んでは泣き、泣いては読みを繰り返しました。
そこには、
『安元3年(1177)7月20日出家。同じく7月26日信俊下向。』
と書かれていました。これによって、信俊が成親のもとへ参上していたことも分かったのでした。
さて、成親卿の墓を尋ねてそれ見ると、松林の中に頼もしいほどの壇が築かれていた、ということもなく、ただ土を少し高く盛っているだけでありました。少将は袖を合わせ、生きた人に語りかけるように涙ながらに言いました。
「ご逝去されたことは、鬼界ヶ島でかすかに伝え聞いていましたが、思うように動けない辛い身の上でしたので、急ぎ参ることもできませんでした。あの島へ流され、露のように今に消えてしまいそうな儚い命となって2年、ついに都に召し還さらることの嬉しさはもちろんでございます。しかし、長く生き延びた甲斐とは、この世で生き延びた父のお姿を拝見できてこそ、感じるものです。ここまで急いで参りましたが、これから先、急ぐものは何もありません。」
と。ただただ心の内を吐き出し、泣きました。
本当に存命であれば、大納言入道殿(成親)も
「我が子よ、どうしたのだ。」
とでも声をかけるでしょう。生と死を隔てる定めほど恨めしいものはございません。苔むす墓の下から、誰が返事をしてくるというのでしょう。ただただ、嵐に靡きざわめく松の音が、もの寂しく響くばかりでした。
その夜は、夜通し康頼入道と2人で墓の周りを行道しながら念仏を唱えました。翌朝になって、新しい壇を築き、柵などを設け、墓前に仮屋を建てました。そして、七日七夜にわたり念仏を唱え、写経を行いました。結願(供養の最終日)には、大きな卒塔婆を立て、その年号と月日を刻み、その下には、
『孝子成経』
と書きました。卑しい山人や、心のない者でさえも、
「子に勝る宝はない。」
と言い、涙を流し袖を絞らない者はいなかったといいます。
さて、成経は
「父よ、もうしばらく念仏を唱えて功徳を積みたいところではございますが、都で待つ人々も心細く思っていることかと思われます。まずは都へ上ることにします。また必ず参ります。」
と言い、亡き父に別れを告げ、涙を流しながらにその場を後にしました。亡き父も草の陰で名残惜しそうに思われて辛い気持ちになりましたが、その場に留まるわけにもいかないのでここを経ち、同じ年の3月19日、成経一行は鳥羽に到着したのでした。
この鳥羽には、父成親の山荘「洲浜殿」があったのですが、人が住まないまま月日が流れたため、築地は残っていたが屋根は崩れ、門も残ってはいましたが扉が無ありませんでした。
庭に立ち入ってみると、人の訪問が無いために苔が深く生い茂っていました。池の周りを見渡すと、「秋の山」と名付けられた築山に春の風が吹き寄せ、池の白波が頻りに打ち寄せており、水面では、鴛鴦(おしどり)や鴎(かもめ)といった鳥たちが、あちらこちらへと泳ぎ回っていました。それを見るだけでも、かつてこれを興じた人がここで楽しんでいたと思われました。その時は尽きたのに、今は涙が尽きません。
家は残ってはいるものの、連子窓は破れ、蔀(しとみ)や遣戸は無くなっていました。成経は
「ここにはかつて父が住んでいた。この妻戸から、いつも外に出て。。。あの木も、父が自分の手で植えられたもで。。。」
と、父を恋しそうに語りました。
3月半ばではありましたが、花の名残りはまだ残っていて、楊梅(やまもも)や桃、李(すもも)の梢まで、昔を知っているような顔で色とりどりに咲き乱れていました。かつての主人はもういないというのに、それでも、春の訪れを忘れずに花は咲いているのです。成経はその花のもとへ近寄り、詠みました。
桃李不言春幾暮
煙霞無跡昔誰栖
桃やスモモは何も言わないまま、幾度の春を迎えては過ぎ去る。
煙霞の立たない(人気無い)ここには、昔誰が住んでいたのだろうか。
ふるさとの 花のものいふ 世なりせば
如何に昔の 事を問はまし
故郷の花が、言葉を話せる世の中だったら、どれほど昔のことを尋ねてみようか。
この古い詩歌(『和漢朗詠集』・『後拾遺集』)を口ずさむと、康頼入道もこの時物悲しさに襲われ、墨染めの袖を涙で濡らしました。日暮れに帰ろうと考えていたのですが、あまりにも名残惜しく思われて、夜が更けるまでそこに留まることにしました。
夜が更けていくにつれ、古い軒の板間から差し込む月光は、影も作らず辺りを照らします。荒れ果てた宿の常でございます。やがて鶏籠山(『和漢朗詠集』哀愁を誘うことを言っている)もその姿をはっきりと見せる頃になりましたが、成経は家路へと急ぐことができませんでした。
とはいえ、何時までもそうしている訳にもいかないので
「都から迎えの乗り物を派遣してくれているというのに、彼らを待たせるのは心無い振る舞いだな。」
と言って、泣く泣く洲浜殿を出て、都へ帰ったのでした。その心の内は、さぞかし嬉しくもあり、また哀れでもあったことでございましょう。
康頼入道にも迎えの乗り物が用意されていたのですが、康頼は乗らず、
「今さらながら名残惜しい。」
と言って、成経と同じ車に乗って後ろに座り、七条河原まで同行しました。そこで別れることとなっているのですが、康頼はなかなか別道への足が進みませんでした。
花のもとで半日を共に過ごす客や、月を眺める一夜の友、旅人が通り雨が止むの待つのに一本の木陰に立ち寄る。そのような一瞬の仲であっても、別れる時は名残り惜しく思われるものなのに、あの恨めしい島での暮らしや、船の中、波の上で寝起きを共にした仲です。名残惜しくないわけがありません。前世からの浅くない縁を感じずにはいられないのは、自然のことです。
成経が舅である平教盛の屋敷へ立ち入ると、普段は霊山(りょうぜん。東山三十六峰のひとつ。)にいる成経の母が、昨日から教盛の屋敷にやって来て、息子の帰りを待っていました。入ってきた成経の姿をひと目見て、
「命があれば。。。(『古今和歌集』を踏まえる)」
と言ったきり、布物を被って伏せたのでした。
『古今和歌集』巻八・哀傷歌「命あれば 今年の秋も 月は見つ 別れし人に 逢ふよなきかな(命があれば、今年の秋の十五夜の月を見ることはできるでしょう。しかし、別れたあの人に再び会うことはこの世では叶わないのですね。)」
の和歌のことでしょう。
教盛の屋敷の女房や侍たちが集まってきては皆喜び泣きました。ましてや成経の北の方(妻)や乳母の六条の心の中は、さぞかし嬉しかったことだろうと思われます。六条は尽きることのない物思いのせいで、黒かった髪もすっかり白くなり、北の方はかつて華やかで美しく見えた人だったのですが、いつの間にか痩せ衰えてしまい、もはや同じ人とは思えないほどになっていました。
流罪で別れた3歳幼い子も、すっかり成長して落ち着いた様子となり、すでに髪を結う年頃になっていました。その傍には3歳ほどの幼い子がいたので、少将が
「あの子は誰だ。」
と尋ねると、六条は
「この子こそが。。。」
とだけ言って、袖を顔に押し当て、涙を流しました。成経は
『そうか、あの時は心苦しそうな様子を見て都を下ったが、無事に育ったのだな。』
と思い出し、さらに悲しくお思いになったとのことでございます。
成経は以前のように後白河院に召され、『宰相の中将』に昇進されました。康頼入道は東山の雙林寺にあった自分の山荘に落ち着き、まずは、長く思い続けていた心情を一首の歌にしました。
故郷の 軒の板間に 苔むして
思ひしほどは 洩らぬ月かな
故郷の家の軒の板間が苔むしている。月の光が苔に遮られて洩れ入ってこないのを見ると、喜界島で過ごした年月の長さが思われるよ。
やがて、康頼入道はその山荘に籠り、疎ましかった過去を思い続けながら、『宝物集』という物語を書き記した(編纂の意も含むか)と伝えられています。
(第十一。終。)
| 第十に戻る << | 第十二を読む >> |