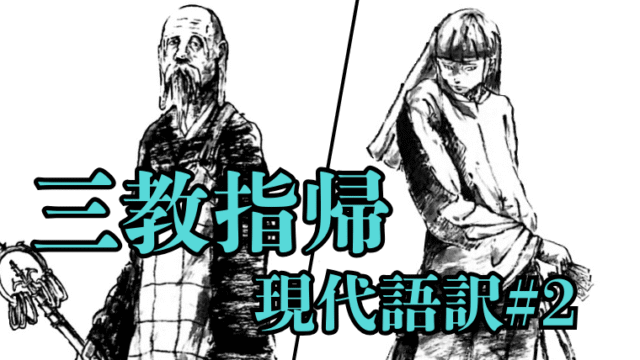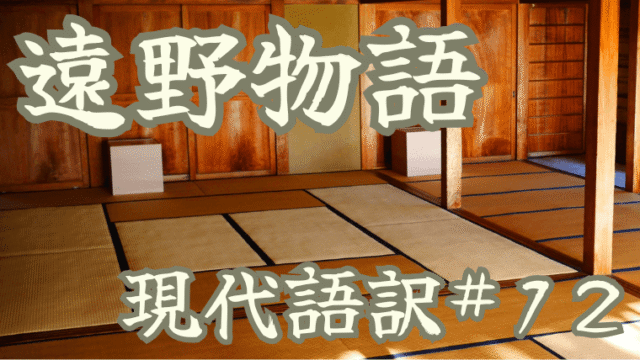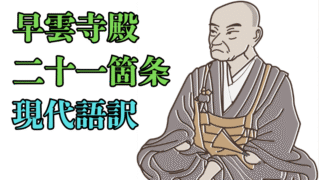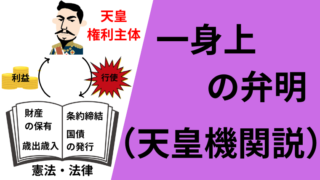在原業平平安
特に有名な2話をご紹介します
芥川
登場人物
- 男
- 二条の后
- 国経の大納言
現代語訳
その昔、男がいた。妻にしたかった女がいたのだが、結婚を受け入れてくれなかったので何年もの間求婚していた。そうしているうちに、やっとのことで女を盗み出すことに成功して、非常に暗いところまで逃げ来たのだった。芥川という川まで連れて行くと、女は露が乗っている草を見つけ、
「あれは何ですか。」
と男に尋ねた。しかし、男は無視した。まだ目的地までの道のりは遠いが、既に夜は深くなっていた。男はこの地に留まることにした。今いるこの地が鬼が出る所だとは知らずに。雷はたいそう鳴り、雨もひどく降っていた。男は荒れ果てた蔵の奥に女を押し入れて弓や胡簶を背負い戸口で見張りをしていた。早く夜が明けてくれ、と思っていたところ、なんと鬼が女を一口で喰っていたのだった。
「あれれー」
女はそう言うが、激しい雷のせいで男は聞こえなかった。
さて、だんだんと夜も明けてきたので蔵の中を見るも、連れてきた女がいない。男は地団駄を踏んで泣くも、どうしようもなかった。。。
男は詠む。
白玉か 何ぞと人の 問ひし時
露と答へて 消えなましものを
「あれは白玉か何か宝石ですか。」とあの人が聞いた時に「露ですね。」と答えておけばよかったなあ。今は、はかないあの露のように私も消えてしまいたいと思うよ。そうすれば失った悲しみを感じずに済んだかもしれなかっただろうに
さて、この話の真実を話そう。二条の后が、いとこの女御の側にお仕えしていらっしゃった時に、容姿がたいそう優れていた二条の后を心にかけた男が、そのまま后を盗み出したことがあった。その後、地位の低い者として内裏に参上なさった、二条の后の兄で堀河の大臣のご長男である国経の大納言はたいそう泣く人の声がするのを聞きつけ、男を捕らえて二条の后を取り返しなさったのだった。
つまり男は、国経の大納言を鬼と勘違いしたのであった。
まだ国経の大納言がたいそう若くて、そして后が普通の身分でいらっしゃった頃の話だとか。
東下り
登場人物
- 男
- 友人1
- 友人2
- ある人
- 修行者
- 船頭
現代語訳
その昔、男がいた。その男は、自分を必要とする者はいないと思い込み、
「今日にはいまい。東の方に進もう。住むにふさわしい国を求めて。」
と思い立って東へ足を進めた。昔からの友人一、二人と共に行動した。しかし道を知っている者もおらず、三人は迷ってしまった。三人は、三河国の八橋というところにいた。八橋というのは、河がクモの手のような形状をしているため、橋を八つ架けたことが由来だそうだ。三人はその河の沢のほとりの木の陰に下りて乾飯を食べた。カキツバタが趣深く咲いていた。それを見てある人が
「カキツバタの五文字を句の頭に使って旅の心境を詠め。」
と言ったので男は詠んだ。
唐衣 きつつなれにし つましあれば
はるばるきぬる 旅をしぞ思ふ
唐衣をしばらく着ていると慣れてくる褄の部分が着物のように、馴れ初めからずいぶん経った恋しい妻がいる。遥々遠くまで来たこの旅も悲しく思うことだよ。
皆、乾飯の上に涙を落すので、乾飯がふやけてしまった。
さらに進んで駿河国に着いた。宇津の山に来たのだが、通ろうとする道は非常に暗く、細い道であった。それに蔦や楓の木が茂っている。心細く、思いがけず辛い目に遭うだろうと思っていたところ、修行者の一行に出会った。
「このような荒れた道にどうしていらっしゃるのですか。」と、修行者の中にそう言う人がいた。その人を見ると、なんと知った顔ではないか。この機会に男は京の恋しい人に向けて手紙を書いた。
駿河なる 宇津の山べの うつつにも
夢にも人に あはぬなりけり
駿河にある宇津の山べまで来た。その名には「うつ」が入っているなあ。ああ、現実(うつつ)でも夢でも恋しい人に会いたいものだ。
富士山を見ると、五月の末にもかかわらず、雪がたいそう積もっていた。
時知らぬ 山は富士の嶺 いつとてか
鹿の子まだらに 雪の降るらむ
季節を知らない山だな、富士山は。今をいつだと思って鹿の子の模様のようにまだらに雪を降らせているのだ。
富士山を京で例えるとするならば、比叡山を二十ほど積み重ねたくらいの高さだろう。山の形は塩尻のようである。
ちなみに、宇津の山は鎌倉時代の紀行文『東関紀行』でも登場します。
さらに進んで、武蔵国と下総国との間にある、すみだ川というたいへん大きな川のほとりに来た。
「思い返すと、ほんとうに遠くに来たものだな。」
と嘆き合っていたところ、船頭が
「はやく船に乗れ、日が暮れる。」
と言うので、船に乗ってすみだ川を渡ろうとしたのだが、皆なんとなく辛くなってしまった。京に恋しく思う人がいないわけでもないのだ。その時、嘴と足が赤い、シギほどの大きさの白い鳥を見つけた。水の上で遊びながら魚を食べている。京では見ない鳥なので誰もこの鳥を知らない。船頭に聞くと、
「都鳥って名だよ。」
と言ったのを聞いて、詠む。
名にし負はば いざこと問はむ 都鳥
わが思ふ人は ありやなしやと
「都」という名を背負っているのならば、さあ、尋ねようではないか、都鳥よ。私の恋しく思う人は無事でいるか、いないのか。
船に乗っていた人皆涙を流したのだった。
解説
文中からも、これら和歌からも、京にいる恋しい人を想って嘆いている様子が読み取れます。そのように辛い思いをしてまで東国に行きたかった理由は本当に「安住の地を探すため」だけでしょうか。
『伊勢物語』は平安時代初期に成立した歌物語です。一般に「東下り」というと、幕府が置かれた鎌倉に向かうことを指しますが、平安時代にはまだ鎌倉は幕府は存在しませんので、解釈が一致しません。
結論から言うと、これは「左遷」を意味します。作者である在原業平がモデルであるとすると、これは桓武天皇の時勢の話といえます。
桓武天皇の時代には「按察使」や「征夷大将軍」、「勘解由使」といった地方行政のために設けられた官職(令外官)がすでに存在していました。在原業平は非常に高貴な身分であったため、国司として派遣されてもおかしくありません。そう考えると、
「命令なので、泣く泣く東国に行く、京に引き返したくても引き返せない。」といった状況が思い浮かばれるのではないでしょうか。思い嘆く様子が自然に読み取れます。
また、冒頭の「京では必要とされてない」という部分からは、中央政府から必要とされなかった立ち位置であったとも取れます。「こんな京出て行ってやる。」と出立当初はやけくそになっていたとも取れるでしょう。とはいえ、京を離れれば離れるほど寂しく思う気持ちには高級貴族とはいえ勝てなかったようですね。