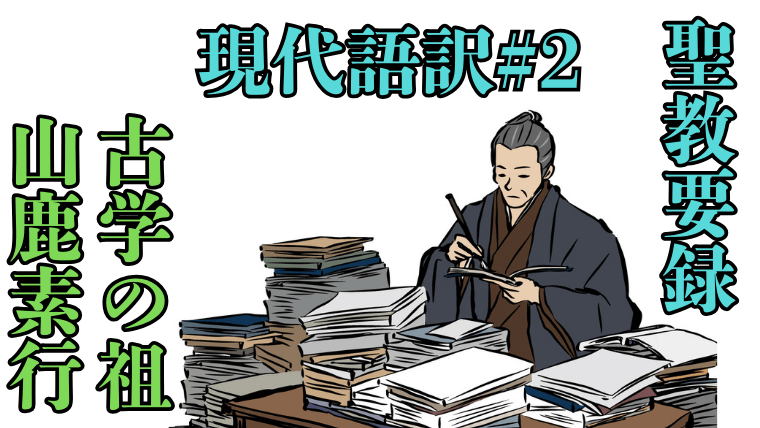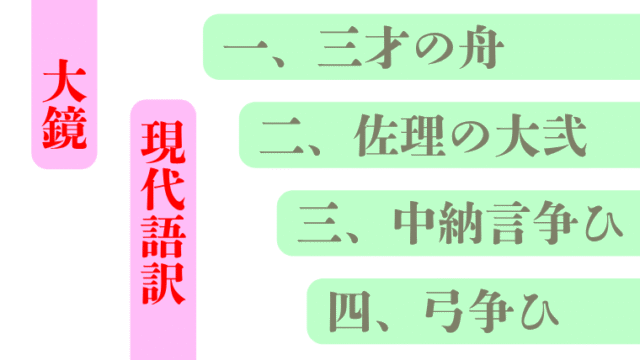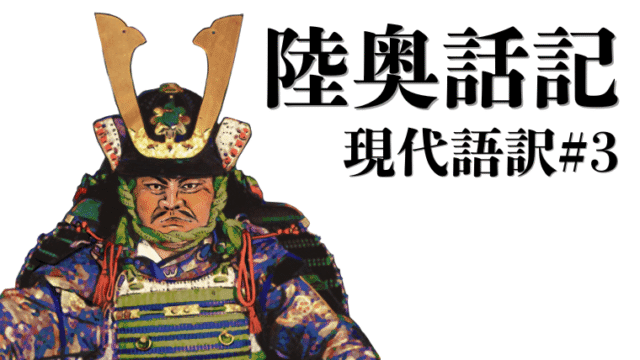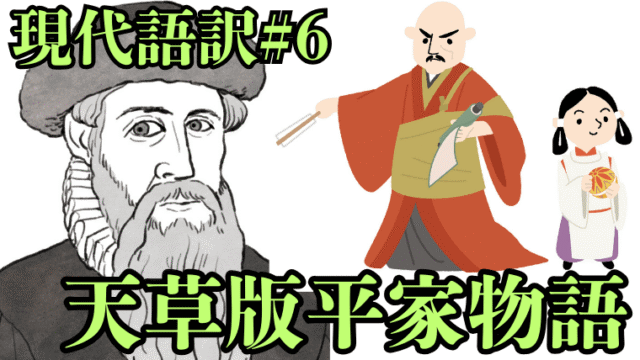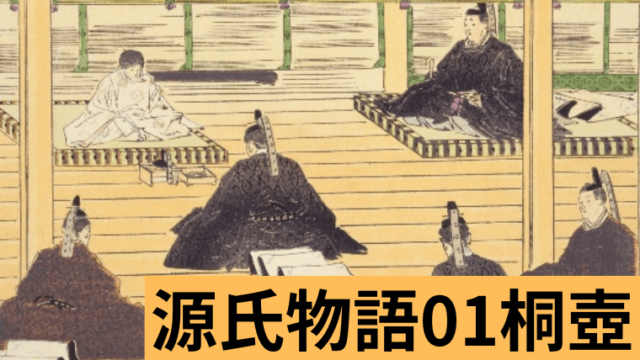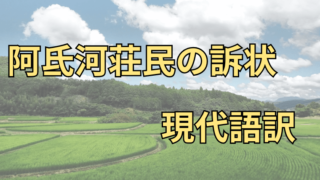聖教要録を読む前に
儒学に関する予備知識はこちらで解説しています。

『聖教要録』の概要や構成についてはこちらで解説しています。
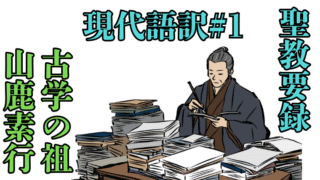
現代語訳
⑤文教
人不教不知道不知道乃害於禽獣民人陥異端信邪説祟鬼魅竟無君無父者教化不行也
古昔王者建国君民教学為先君長之御下以教人之道則臣僕敦化教之久也自為風俗人人自安家有家教国有国教天下有天下之教一道徳以同俗
人は教えなければ道を知らない生き物である。道を知らない人は獰猛な獣よりも害のある存在である。異端の教えに陥り、邪説を信じ、化け物を尊び、君主も父も蔑ろにする。そのような人は教導しなければならない。
古の王は国をつくり民を導く存在として、教導を専ら優先した。君主や上長が下の者を尊重する。これは人を教導する道理である。そうすれば、下の者は上の者を篤く敬うような習慣ができるだろう。
長く教導されないと、勝手に賤しい風俗が生まれ、人々はそれで心を安らかにしてしまう。家には家の教えがあり、国には国の教えがあり、天下には天下の教えがある。道徳を第一の教えとし、道徳を風俗とするのだ。
⑥読書
書者載古今之事蹟器也読書者余力之所為也措急務読書立課以学為在読書也学与日用扞格是唯読書不致其道也読書以学之志則大益也以読書為学則玩物喪志之徒也読書在聖人之書聖教甚平易也毎読書而味之玩而繹之推而行之足以証之他皆渉利口便知事其一言半句一事一行有可執用焉推其始終乃不全唯広才博識之一助也又不可釈之読書之法専記誦博識乃小人之学也忌多走作詳味訓詁本聖人之言可直解後儒之意見無所取材
書は古今に起きた事実を載せた器である。読書は余力の許す限りするべきである。徳のある人が日常生活での急務を一旦後回しにしてでも書を読む(余力のある状態)のは、「書から日常生活において学ぶことがある。」ということを意味している。
学問と日常生活とを相容れないものとして捉えるのは、ただただ、書を読まないで道を極めていないからそう思うのである。
書を読んで学を志せば、それだけで読書に大きな効果があったといえる。「書をただ読むことが学ぶことである。」とするのは、不用な物を弄び、本心を失った者と同じである。
とらちゃ 読書は、ただ本を読むだけではいけません。学んだことを生活に活かすことで初めて読書といえるのです。
読むべきなのは、聖人の書である。聖人の教えは非常に簡潔であり、理解しやすい。常にこれを読んで聖人の教えを学べ。
ひたすら読んでは気になる点を尋ね、それを実践するのだ。それだけで聖人の教えが本当に正しいか証明するに十分である。他の書の場合、読むには頭の良さが必要であり、物事を多く知っていることが前提となっている。
それらの書から、日常生活で採用したい、ちょっとした言葉やちょっとした行動が出てきた場合に関しては、採用したいそれを全部実践する必要はない。
それは聖人の教えではないため、ただただ広く浅い知識の助けになるだけならば全部実践する必要はないということだ。また、聖人の教えを学ばない言い訳に、これを用いてはならない。
とらちゃ 聖人の教え以外のものだけど、実践して徳を積んでいる最中だから、聖人の教えは学ばなくていいよね!というのはダメだということです。山鹿素行に言わせてみれば、そもそも聖人の教え以外は邪説なので、聖人の教え以外を実践しても、徳を積むことはできていません
書を読む時、暗記で知識を深めることを専らにしている人は、徳の浅い人の学び方である。そのような人は、実践し多く試行錯誤することを嫌う。詳しく古の教訓を学べ。聖人の言うことを基本とし、そのままの意味で解釈するのだ。
後の時代の人の見解は実践に取り入れる必要はない。
⑦道統
伏羲神農黄帝尭舜禹湯文武周公之十聖人其徳其知施天下而万世被其澤及周衰天生仲尼自生民以来未有盛於孔子也孔子没而聖人之統殆尽曽子子思孟子亦不可企望
漢唐之間有欲当其任之徒又於曽子子思孟子不可同口而談之及宋周程張邵相続而起聖人之学至此大変学者陽儒陰異端也道統之伝至宋竟泯没況陸王之徒不足算唯朱元晦大功聖経然不得超出余流噫道之託人行世皆在天其孰強与於此乎孟子没而後儒士之学至宋三変戦国法家縦横家漢唐文学訓詁専門名家宋理心学也自夫子没至今既向二千余歳三変来周公之道陥意見誣世惑民口唱聖教其所志顔子之楽処曽点之気象也
習来世久嗚呼命哉
「伏羲・神農・黄帝・尭・舜・禹・湯・文・武・周公」の十聖人は、万世、徳を天下に施した聖人である。
周の衰えに及んで、天下は孔子を生んだ。があって以来、いまだに孔子の教えは盛んとなっており、それを超えるものは無い。孔子が没して、聖人の意志を継ぐ者はほとんどい無くなってしまった。孔子の弟子である曽子、孔子の孫である子思、孔子の教えを発展させた孟子といった者らも、孔子を超えようなど企み、それを望むことはなかった。
漢、唐代の間、孔子の座に及ぼうと望んだ輩がいた。漢の董仲舒、唐の韓退之である。彼らは、曽子・子思・孟子に関して論じてはならないとした。
宗代となり、周・程・張・邵が相次いで誕生した。聖人の教えはこの頃に大きく変化し、学者は、儒学が正当な学問であり、それ以外は異端であるとしたのである。聖人の道はこれによって、宋代で滅んだ。
陽明学の陸象山や王陽明のような輩は、聖人の列に加えるには及ばない。ただ、朱子学の朱元晦は聖人に相応しい功績があるといえる。しかし、そこから様々な流派が生まれ、朱子学が隆盛したわけではない。
ああ、思想家に治世を任せたのは、皆天の思し召しだったのだろう。今の世、誰がこれを授ることができようか。
孟子が没して後、儒学者は宋代に至るまでに三度変わった。①戦国時代の韓非子や張儀などの縦横家。②漢・③唐の時代の文学・訓詁・専門・名家・心学(王陽明らが主張した、儒教の中でも唯心論的側面が強い論)・理学(朱子学、陽明学の総称。宇宙の原「理」を追求した論)である。
孔子が没して今に至るまでに二千年余りが経過している。つまり孔子は二千歳余りということだ。この二千年余りで孔子は三つに姿を変化させた。
周公・孔子の示した儒学は批判の対象となり、世の中を混乱させては民を惑わした。聖教を唱えて志す先は子淵の言う「楽処」や、曾晢の風流を重んじ自然に身を任せる性格である。
聖人の教えを習い予行する世の中が来なくなって久しい。ああ、おしまいだ。
⑧詩文
詩者志之所之内有志則言必動古詩自然之韻叶也其志或存諷諫或評事義或述好風景或自警或称時政君臣徳如此則六義自然相具後之学作詩巧言奇趣其所言皆虚誕也故詩人者天下之閑人佚楽游宴之媒也作詩必事経書文学言道徳仁義欲渉世教亦詩之一病也学教何借詩宋明之儒多有此蔽不知聖人之道也文者言辞之著於書也聖賢之言不得已而発自然之文章也後之作文皆巧言令色也無事之処求奇趣向造作求尤可汗韓柳欧蘇文章之達人而其学皆乖戻文過質史也
詩には志(=目的)が現れる。内に志があれば、必ず言が動く(詩に反映される)。
古の詩は自然の様子を捉えている。例えば、遠回しに諫めたり、物事を評価したり、単純に好きな風景を感じたままに述べたり、自分に言い聞かせたり、その時代の君子や臣下の徳を讃えたり。
このような志を持っている古の詩は、自然と詩の規則である六義が伴っている。後代の詩を学んだとしても、それは巧みな表現に重きを置いたものであり、本来の詩ではない。言えば、そのような詩は皆偽物なのである。
とらちゃ 六義に関しては、古今和歌集の序文にて言及されています。こちらをご覧ください
故に、詩人は世俗を脱した閑人だと言える、詩は、気の向くままに遊んだり、宴を楽しんだりするための手段のひとつなのである。
作詩には必ず経書(聖人の記した典籍)の文を基本とし、道徳や仁義を意識して、儒学の道を求めて欲しい。また、作詩は詩において頭を悩ませることの一つである。学問と教がどうして詩から引用しようか。
聖人の教えが廃れた宗代、明代の儒学にはこのことが障害として多く見られる。聖人の教えを知らないからこうなるのである。
とらちゃ 道統で、宗代に聖人の教えは途絶えたと説明されています。
文は言辞の書に書いてある。聖人や賢人の言葉とは、やむを得ず発された自然の文章である。後代に作られた文章は、皆巧言令色である。何も感じないところから奇抜な趣や技巧表現を求め詩を作る。なんと冷や汗をかくことか。
韓退之・柳宗元・欧陽修・蘇軾は文章の達人で、詩の道を正しく戻した。文章表現とその内容に勝るのは公的文書だけである。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |