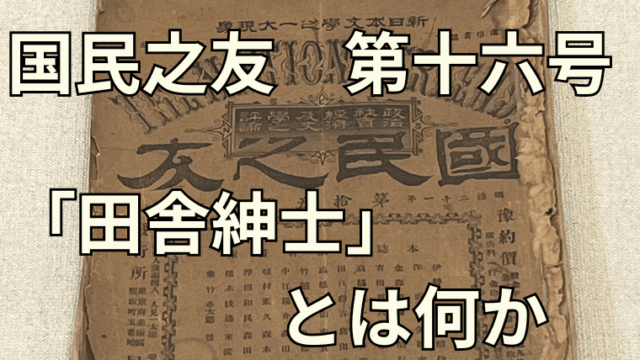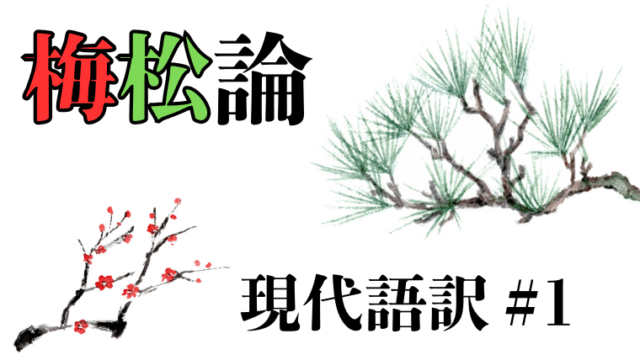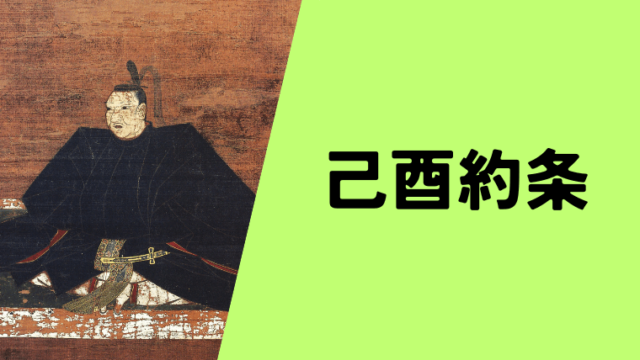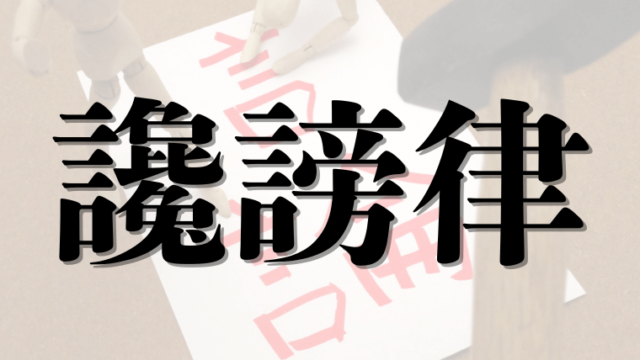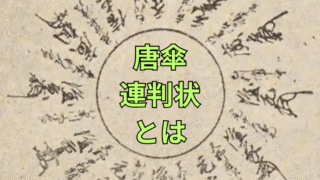改新の詔と大化の改新
改新の詔は、孝徳天皇によって発布された詔で、「大化の改新」という中央集権事業の方針の柱になりました。主導したのは中大兄皇子で、彼はナショナリズムを唱える蘇我氏を倒し、外国勢力に負けない国家の建築を急ぎました。
ナショナリズムは、国内の現状維持と考えてください。中大兄皇子らは、大陸の国力の強大さに危機感を感じ、積極的に外国の産物を取り入れようとしました。
その一つが、中央集権体制だったのです。
改新の詔の内容
改新の詔は全4条で構成された詔で、中央集権化の根幹を担う部分の整備を進めました。
646年(大化2年)に発布された全4条の詔。
孝徳天皇の詔だが、主導したのは中大兄皇子で、中央集権化の第一歩となった
大化の改新の政策は主に4つです。
| 第1条 | 公地公民制 |
|---|---|
| 第2条 | 地方行政、軍事整備、交通の整備 |
| 第3条 | 班田収授法 |
| 第4条 | 税制 |
中央集権化の第一段階は、旧勢力の徹底的な圧迫です。蘇我氏になびいていた皇族、豪族を解体し、それらが所有していた人と土地という財産を国有にしました。
第1条:公地公民制の導入
天皇や地方豪族の私有地である「屯倉」と私有民である「子代・部曲」を廃止し、全ての土地と人民は国家(天皇)のものであると宣言しました。いきなり彼らの財産を没収すると全国的な反乱になりかねないため、地方豪族には食封(給与)が与えられました。
第2条:地方行政、軍事整備、交通の整備
都を京に定め、国・郡・里という3つの行政区分に基づいて土地を分割しました。各国の独立化阻止を目的として、国司や郡司などを中央から派遣、中央集権化の逆進を防ぎました。また、駅伝制や防人など配置によって交通、警備体制を確立しました。
第3条:班田収授法
よく耳にする班田収授法はここで定められたものになります。人口やその土地を把握する戸籍と税収を確保する計帳の作成を指示しました。その後、確定した国有の土地を、班田収授法によって、6歳以上の公民に対して口分田を均等に配布、死後にその土地を国へ返還させる仕組みを制定しました。
第4条:税制
複雑化していた私的な税収や賦役を廃止し、唐の制度に倣った租、調、庸を導入。全国的に統一化された税収によって、財政安定と私的な税収による特定の組織の巨大化を防ぎました。
現代語訳(改新の詔)
大化2年1月(改新の詔発布)
二年春正月甲子朔。賀正禮畢。即宣改新之詔。曰
大化2年(646)正月一日(甲子)。賀正の礼が終わり、改新の詔が下された。
第1条
其一曰。罷昔在天皇等所立子代之民。處々屯倉。及別臣連伴造國造村首所有部曲之民。處處田庄。
仍賜食封大夫以上。各有差。降以布帛賜官人百姓有差。又曰。大夫所使治民也。能盡其治則民賴之。故重其祿。所以爲民也。
その一。天皇や豪族は、子代(私有民)と屯倉(私有地)を持つことを廃止する。また、臣・連・伴造・国造・村首の所有する部曲(私有民)と田荘(私有地)も廃止する。
それらを廃止する代償として、大夫以上の者には、各々食封(給料として与えられる戸)が与える。官人には布帛(織物)が与えられる。また、大夫は政治に参加することとする。民の為に政治を執り行うこと。ゆえに、大夫や官人に多くの給与が与えられるということは、それだけ民の為に尽くすというべきだということを心得よ。
第2条
其二曰。初修京師。置畿内國司郡司。關塞斥候防人。驛馬傳馬。及造鈴契。定山河。
凡京每坊置長一人。四坊置令一人。掌按檢戸口。督察奸非。其坊令取坊内明廉強直堪時務者宛。
里坊長並取里坊百姓淸正強幹者宛。若當里坊無人。聽於比里坊簡用。凡畿内。東自名墾橫河以來。南自紀伊兄山以來。[兄。此云制。]西自赤石櫛淵以來。北自近江狹々波合坂山以來。爲畿内國。
凡郡以四十里爲大郡。三十里以下四里以上爲中郡。三里爲小郡。其郡司並取國造性識淸廉堪時務者爲大領少領。
強幹聰敏工書算者爲主政主帳。凡給驛馬傅馬。皆依鈴傅苻剋數。凡諸國及關給鈴契。並長官執。無次官執。
その二。京師(都)を造ることとする。畿内に国造を、その他郡司、關塞、斥候、防人、驛馬、傳馬を置くこととする。駅には鈴と木契(割符)を設置し、山河によって行政区画を定めよ。
京において条坊制をとるにあたり、坊ごとに坊長を1人置く。また、四坊ごとに四坊長を一人置く。両長の職務は、民を治め、心のねじけた輩を矯正し、反抗するのを諦めさせることである。両長には、坊内の民のうち、素直で屈強で、真っすぐな心を持ち、その時々の政治に詳しい者を取り立てよ。
里坊長には、里坊内の民のうち、素直で屈強で、勇ましいものを取り立てよ。もし里坊に人がいなかった場合、隣の里坊から人を取り立てることを認める。畿内の範囲について。東は「名墾の横川」まで、南は「紀国の兄山」まで、西は「明石の櫛淵」まで、北は「近江の狭々波の合坂山」までとする。
郡の規模と名称について。郡は四十里を大郡とし、四里以上、三十里以下を中郡とし、三里を小郡とせよ。郡司は、国造がその為人をみて判断し、取り立てよ。具体的には、性格が素直で、その時々の政治に詳しい者である。取り立てた者は大領(律令制でいう郡司の長官)、少領(律令制でいう郡司の次官)に任命する。
また、大領、少領に続き、屈強で聡明で、文字書きと算術に長けた者を主政・主帳(いずれも書記官)に任命せよ。駅馬、伝馬は、鈴や印が刻んであるだけの数とする。関所に鈴と木契を所持した馬が来たら、長官がその手続きを、いなければ次官がその手続きを行うこと。
第3条
其三曰。初造戸籍。計帳。班田收授之法。凡五十戸爲里。每里置長一人。掌按檢戸口。課殖農桑。禁察非違。催駈賦役。凡田長卅步。廣十二步爲段。
十段爲町。段租稻二束二把。町租稻廿二束。若山谷阻險。地遠人稀之處。隨便量置。
その三。戸籍・計帳・班田収授法を制定する。五十戸で一里とする。一里ごとに里長を一人置く。里長の職務は、民を治め、桑農を生業とし、法を犯すものを矯正することである。また、賦役が滞りなく遂行されるよう監視せよ。田の単位は段とする。一段の面積は、縦三十歩、横十二歩とする。
十段で一町とする。段ごとの租は稲二束二把、町ごとの租は二十二束とする。もし、山や谷が険阻なせいで都から遠く、そして人がほとんど住んでいない、というような所であれば、通達に従い租を設定すること。
第4条
其四曰。罷舊賦役而行田之調。凡絹絁絲綿・並隨鄕土所出。田一町絹一丈。四町成疋。長四丈。廣二尺半。
絁二丈。二町成疋。長廣同絹。
布四丈。長廣同絹絁。一町成端。
[綿絲絇屯。諸處不見。]別收戸別之調。
一戸貲布一丈二尺。凡調副物鹽贄。亦随鄕土所出。凡官馬者。中馬每一百戸輸一疋。若細馬每二百戸輸一疋。其買馬直者。一戸布一丈二尺。
凡兵者。人身輸刀甲弓矢幡鼓。凡仕丁者。改舊每卅戸一人[以一人充●也。]而每五十戸一人[以一人充厠。]以宛諸司。
以五十戸宛仕丁一人之粮。一戸庸布一丈二尺。庸米五斗。
凡釆女者貢郡少領以上姉妹及子女形容端正者[從丁一人。從女二人。]以一百戸宛釆女一人之粮。庸布庸米。皆准仕丁。
その四。旧制の賦役を廃止する。その代わり、新たな賦役として田に調を課す。調の対象品目は、平絹、絁(あしぎぬ)、糸や綿、その土地の特産品である。平絹について。田一町で平絹一丈を課す。四町では平絹一匹となる。つまり、平絹一匹=平絹四丈である。幅は二尺半。
絁について。田一町で絁二丈を課す。二町で絁一匹となる。つまり、絁一匹=絁四丈である。長さ、幅ともに平絹に同じ。
布について。田一町で布四丈を課す。一町で布一端(たん)とする。つまり、布一端=布四丈である。長さ、幅ともに平絹、絁に同じ。
(糸や綿の重さに関する記述はみられない。)これらと別に家ごとに調を課す。
一戸につき、あら布一丈二尺、そして副産物として塩と特産品である。塩と特産品に関しては、各国が示したものにせよ。献上馬について。中級馬の場合、百戸につき1匹、上等馬の場合、二百戸につき一匹とする。馬を買う場合、一戸につき布一丈二尺とする。つまり、中級馬の場合百戸分の布を、上等馬の場合二百戸分の布を用意する必要がある。
武器について。一人につき刀、よろい、弓矢、幡(布製の、目印などに使われる旗のようなもの)、鼓をそれぞれ一つずつ課す。仕丁(力役)について。これまで、三十戸ごとに二人を徴収し、うち一人を厨房に充てていたが、以降は五十戸(=一里)ごとに二人徴収することとする。うち一人は厨房に変わらず。もう一人は諸役所に配置する。
なお、出自の里が彼らの食費を負担すること。内訳は、一戸につき庸布一丈二尺、庸米五斗である。
釆女は、各郡の少領以上の者の姉妹及び子女を献上すること。ただし、容姿端麗の者で。それに加え、従者一人と童二人も付けること。なお、釆女の食費は百戸(=二里)で負担すること。庸布、庸米の内訳は、仕丁と同じとする。
まとめ
改新の詔は明治時代の西洋化政策に似たものを感じさせます。税制度の明確化や人口把握、土地制度の統一化などです。今(といっても100年以上前ですが)も昔も、対外勢力は国家規模での脅威であったとよく分かります。歴史は繰り返しますね。
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |