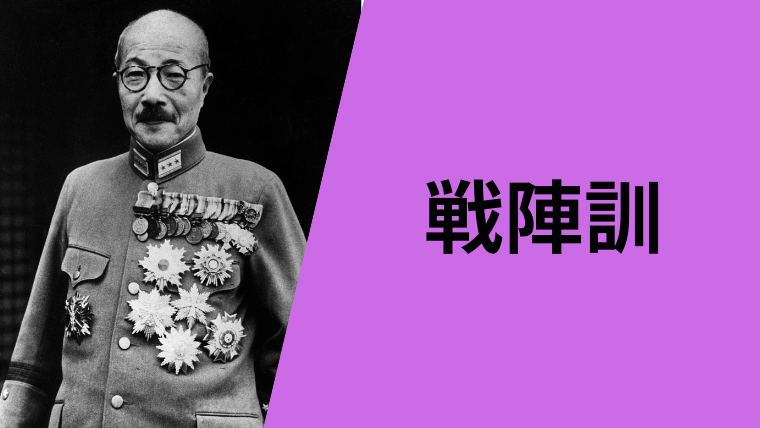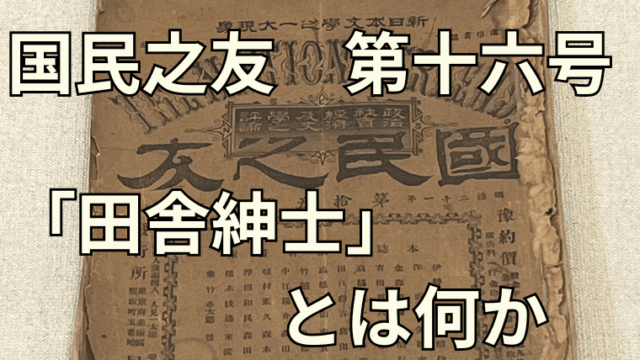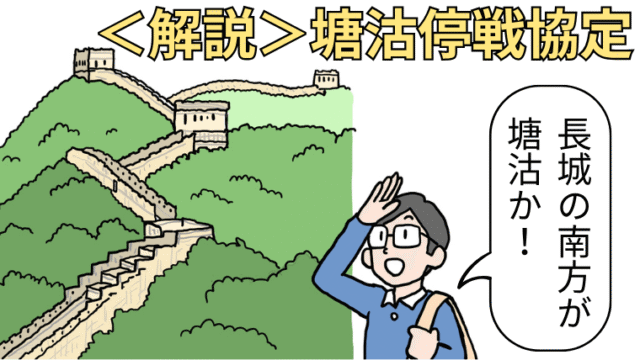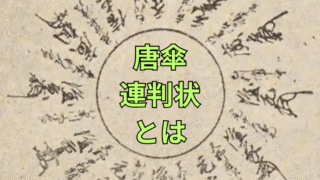「生きて虜囚の辱を受けず」のフレーズはあまりにも有名です。「捕虜となるなら死を選択しろ。」という意味ですが、いったいなぜ、このような悲しい歴史が生まれてしまったのでしょうか。『戦陣訓』が生まれた時代背景と、集団自決との関係を学んだうえで、全文を読んでみましょう。
『戦陣訓』と時代背景
どのような経緯でフレーズが生まれたか
まず、東条英機内閣の時期に出された『戦陣訓』。「生きて虜囚の辱を受けず」という部分が生まれた理由として、個人的な意見としては、
- 日中戦争における清軍の残虐非道な振る舞いに対して皇軍が人道的な対応を取ることで、戦争世論を高めようとしたため
- 捕虜の自白による情報漏洩を防ぐため
の2点が可能性が高いと思います。
国内の情勢
ソ連の南下を防ぎ、同時にアメリカの参戦を防止して東洋を救済する。そのために日本は中国における領土が必要でした。これを目的としてはじまった日中戦争は泥沼化し、1938年に施行された『国家総動員法』をはじめ、軍事が国体の最優先となったことで国内経済は疲弊、戦争反対の世論も次第に増加していました。
国外の情勢
さらにこの時期、日本は国際的な立ち位置も怪しくなっていた時期でもありました。
当時締結していた日独伊三国同盟は、日本の意図では、ソ連の南下を抑止し、アメリカの参戦を阻止するために結ばれたものでしたが、そのうちドイツが、敵対していたソ連と1939年に『独ソ不可侵条約』を結び、あっけらかんと同盟を破ってしまいます。
平沼騏一郎の「欧州情勢は複雑怪奇」という言葉は有名です。
と思いきや、1941年にはソ連に対してドイツは宣戦布告、日独伊三国同盟は解消します。さらにアメリカのルーズベルト大統領が日独伊三国同盟を批判したこともあり、日本はアメリカを敵に回した状況で、第二次世界大戦に参戦することとなりました。こうして、計算が外れた日本は国際的にさらに孤立することとなったのです。
このような状況下で『戦陣訓』は出されました。国内外で悪手を打ち続け、じわじわと劣勢に立たされつつあった日本陸軍は、戦争に関して人道的な振る舞いをすることによって、皇軍の存在意義を高め、好戦的な士気をもたらそうと考えていたのではないか、と内容から読み取れます。
『戦陣訓』と集団自決
『戦陣訓』と集団自決との関係は様々な論が展開されており、以下のように要約することができます。
『戦陣訓』が出された対象は、専ら軍人であったが、この軍人が、非戦闘員である民間人にも指導しはじめた。
この際、民間人に誤った解釈が伝わってしまったのは、『戦陣訓』の表現が言葉足らずであったという見方が強い。
結果、非戦闘員は集団自決という最悪の手段を選択せざるを得ない状況に陥った。
また、生き延びようとしても、それを認めない軍人による自決強要といった圧力もあったという。軍人を崇敬する政治的洗脳も集団自決の常習化を招いた可能性が高い。
戦争をする以上、軍人と民間人の接触は常です。国としては、軍人だけでなく、民間人の意識も戦争に向ける必要がありました。
この『戦陣訓』はポケットサイズのものもあり、戦闘服に携帯していたという事実があります。そのため、民間人の教育材料としても扱いやすかったのは間違いないでしょう。その上、文章のまま捉えられ、結果、集団自決をもたらしました。
そう考えると、集団自決は政府や軍の方針というよりは、意図せず引き起こされた負の事象であったように感じられます。