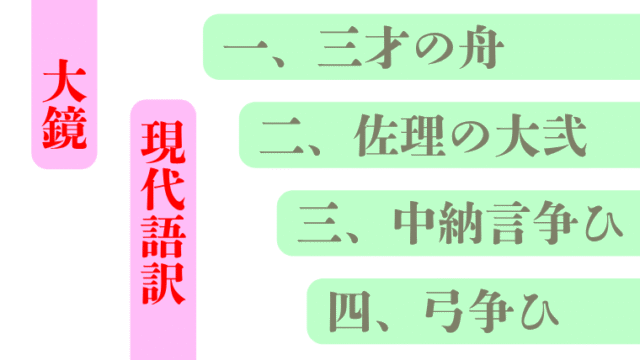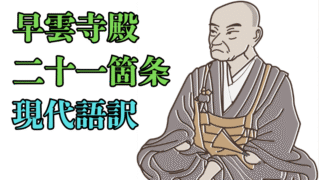東関紀行とは?
『東関紀行』とは、作者不詳の紀行文です。
京都に住まう作者。用事が出来て鎌倉に下ることになり、長い旅路を進みます。
その間に見たこと聞いたことを漢文の深い知識と繊細な和歌で感想を述べます。最後は、鎌倉で数か月を過ごした後、逆に京都に用事が出来て帰ることになりました。
特に有名な紀行文は3つあり、これは中世三大紀行文と呼ばれています。
- 東関紀行 :作者不詳
- 海道記 :白河辺りに住む侘びの者
- 十六夜日記:阿仏尼
どこを通ったの?
道中、様々な名所に立ち寄ったり、通過したりします。
逢坂の関がスタート、鎌倉大仏がゴールです。
- 逢坂の関
- 石山寺
- 打出浜
- 粟津
- 近江大津宮
- 瀬田の長橋
- 野路
- 篠原
- 鏡宿
- 鏡山
- 長光寺
- 笠原
- 奥石神社
- 醒井
- 柏原
- 不破の関
- 杭瀬川
- 今宿
- 熱田神宮
- 鳴海
- 二村山
- 八橋
- 矢作
- 宮路山
- 赤坂宿
- 本野ケ原
- 豊川
- 渡津
- 高師山
- 浜名
- 橋本宿
- 天竜川
- 今の浦
- 事任神社
- 小夜の中山
- 菊川宿
- 岡部
- 宇津山
- 峠
- 梶原景時供養塔
- 清美関
- 興津
- 蒲原宿
- 田子の浦
- 浮島ヶ原
- 千本の松原
- 伊豆国府
- 三嶋神社
- 箱根神社
- 箱根湯本
- 大磯
- 江の島
- 唐が原
- 和賀江
- 三浦岬
- 鶴岡八幡宮
- 永福寺
- 勝長寿院
- 由比ヶ浜
- 鎌倉大仏
番号と対応した地図です。基本的に東海道を歩いていたことが分かります。
所々寄り道してますね!
序文
年は50歳に近づき、霜が一面に降って冷たく感じるように、白髪は増えて老いを感じるようになった。しかし、何かを成し遂げようと思うこともなくただ日々を過ごしていたわけではない。どこか臨終の地となる住む場所を求めたい。と常々心の中で決めていたのだ。
かの白楽天は『身は浮雲に似たり、首(こうべ)は霜に似たり』という詩を残していて、私はこれが趣深いと感銘を受けた。元々私は金帳七葉と言われるような地位や名声を好まない人である。ただただ陶潜五柳、つまり隠棲の地を求めたいと思っている。
とは言いながら、私は昔、山奥に建てた柴造りの庵でしばらく休んだので、なまじ都に近いほとりに住みつつ、人の住む世で生活している。
つまり、身は俗世に、心は隠世にあるという感じか。このように思っていたところ、思いがけないことが起きた。仁治三年(1242)の秋、八月十日ごろ、都を出て東へ赴く用事ができたのである。
知らない道の空。山を越え沢を越え。遥々遠い旅ではあるが、何とか雲を凌ぎ霧を分けながら、しばらく当てのない旅路を進んでいた。
ついに10日ほどの旅程を経て鎌倉に下ったのだが、その間に過ごした、山中にある館や野にある粗末な家での夜、人知れない海辺の水際など、目に留まった所々で、沸き起こった思いを歌に書き置いた。これを忘れず、私の事を思う人がいれば、後世の形見となれば嬉しく思う。
滋賀県の旅路
| ①逢坂の関 | ⑨鏡宿 |
| ②石山寺 | ⑩鏡山 |
| ③打出浜 | ⑪長光寺 |
| ④粟津 | ⑫笠原 |
| ⑤近江大津宮 | ⑬奥石神社 |
| ⑥瀬田の長橋 | ⑭醒井 |
| ⑦野路 | ⑮柏原 |
| ⑧篠原 |
①逢坂の関
東山のほとりにあった住処を出て、逢坂の関を過ぎたころは駒迎えが行われる望月、つまり八月十五日ごろに近い日であった。秋霧が立ち込め、深い夜に昇る月もぼんやりとしている。
木綿を付けた鶏が人知れず訪れているのを見ると、秦から逃れる孟嘗君一行が残月の光を頼りに幽谷関まで来た様子が思い浮かばれる。というのも、孟嘗君は幽谷関の門を鶏の鳴き真似で開けさせたという話があるからだ。
昔、蝉丸という世捨て人が逢坂の関あたりに藁屋の床を敷き、いつも琵琶を弾いて心を澄まし、大和歌(※1)を詠んではその心情を詠っていた。
そんな彼は、激しく吹き荒れる嵐の風に誰も近寄らないのと同じように、寂しく日々を過ごしていた。ある人が言う。「蝉丸は延喜帝こと醍醐天皇の第四皇子であった(平家物語に既出)ため、この関のあたりを『四宮河原』と名付けられたのだ。」と。
古への わらやの床の あたりまで 心をとむる 相坂の関
今目に映る光景だけでなく、今は存在しない古への藁屋の床まで思い起こされる。逢坂の関は魅力的な場所であったなあ。
※1
[古今雑下]
あふ坂の あらしの風の さむけれと ゆくへしらねは わびつゝそぬる
古今和歌集、雑歌下。逢坂の関で吹き荒れる嵐の風が寒い。けれどもこのような風がどこへ行くのか、その行方は誰にも分からない。哀れなことだよ。
②石山寺
東三条院(※2)こと藤原詮子は近江国石山寺に参詣し、都にお帰りになる際、逢坂の関で清水が湧き出る名所があった。そこを通り過ぎようとした時にお詠みになった歌がある。
『幾度となく参詣した石山寺。その度に逢坂の関を往来しましたが、この清水を見るのも今日が最後と思うと、水面に映る影が物悲しそうに見えます。』いったいどのようなお気持ちであったのだろうか。何とも哀れで寂しく思われた。
※2
東三条院は、円融院の女御一条院母后、法興院殿の二女である。
③打出浜④粟津⑤近江大津宮
関山を越えると、近江国の枕詞でもある、打出の浜や粟津の原を通過したが、夜が明けていなかったため、果たして耳にしたような場所であったかは定かではなかった。
昔、天智天皇の御代、大和国飛鳥の岡本宮から近江国滋賀郡の大津宮に遷都した。ここはその造られた場所だ、と聞いた。かつては栄華を極めた煌びやかな皇居であっただろう。しかし今はただの古い時代の皇居跡に思われて、しみじみと感じられた。
さゝ波や 大津の宮の あれしより 名のみ残れる しかのふる郷
ここ大津宮(さざ波が導く)は、かつての栄華は失われ、荒れてしまっている。当時の面影はなく、今の滋賀の里にはかつて皇居があったという名だけが残っているだけだ。
⑥瀬田の長橋
夜が明けた。瀬田の長橋を渡ると、琵琶湖が壮大に姿を現した。かの奈良時代の歌人、満誓沙弥こと笠朝臣麻呂は比叡山でこの海を望みつつ歌を詠んだという(※3)。それが思い出されて、漕ぎ行く舟の後ろに立つ白波が本当に儚く思われ、物悲しく思われた。
世の中を 漕ぎ行く舟に よそへつゝ 詠めし跡を 又ぞ詠むる
人生を漕ぎ行く舟になぞらえて詠もう。「漕ぎ行く舟の後に立つ白波の行方は誰も知らない。まるで人生であるなあ。」と詠まれるのだが、詠み終えた頃には、その白波は無くなってしまっている。これを見ると先ほどのように人生の儚さが感じられて、続けてまた同じように詠んでしまうよ。
※3
[拾遺集]
世の中を なににたとへむ あさぼらけ こぎ行く舟の あとのしらなみ
世の中を何に例えたらよいだろうか。朝ぼらけに漕ぎ進む舟、その後に立つ白波は一体どこへ行くのだ。これに例えられようか。
⑦野路
この場所も通り過ぎ、野路という所に着いた。広がる草原では草露が非常に多く、いつの間にか袖も濡れてしまった。
東路の 野ぢの朝露 けふやさは袂に かゝる始めなるらむ
東山道の野路にて。ここの朝露が袂にかかったが、このことは旅で最初の出来事だろう。今日が旅愁で涙を流す最初の日となったのだろうか。
⑧篠原
篠原という所についた。東西方向に遥かに長い堤がある。北側では里人の住まいが一帯を占め、南側では遠くに池の水面が見られた。
向こう岸の水際では、緑深い松が繁っていた。『白氏文集』「昆明春」には、終南山の影が昆明池に映されていたが、ここでは終南山の影を映さずとも、波の色と一体となって水は青々とみなぎっていた。
洲崎が所々で入り組んでおり、葦や真菰(まこも)といった植物が生い茂っている。その中に、おしどりの群れが飛び交わる様子は、葦手(鳥や水などを文字のように描いた画法)のように思われた。
都を立った旅人はこの篠原宿に泊まるのが常であったが、今は通り過ぎる者が多く、一帯は衰退してしまった。「この辺の家屋はまばらになってしまった。」そう聞くと、世の中は不変である、という世の習いが感じられる場所が飛鳥川の淵瀬だけではないと思われるのであった(古今和歌集『世の中は 何か常なる 飛鳥川 昨日の淵ぞ 今日は瀬になる』)。
行く人も 泊らぬ里と なりしより 荒れのみ増る のぢの篠原
旅人が泊まらない里となってしまい、ただ荒廃が進むだけだよ、この野路の篠原は。世の中に不変なことなどないと思うと、しみじみと思われる。
⑨鏡宿
鏡宿に着いた。昔々、この宿で七人の老人が集まり、老いを嘆いて詠まれた歌がある。
鏡山 いざ立ち寄りて 見てゆかむ 年へぬる身は 老いやしぬる
さあ、名所である鏡山に立ち寄って見てこようではないか。「鏡」山なのだから、我が身が老いてしまったかどうかを知れるだろうよ。
「ここがこの歌の山か。」と思いだされて、自分の境遇と重なった。宿を借りたいと思われたがさらに山奥に訪れたい所があったので、通り過ぎた。
たちよらで けふは過なむ 鏡山 しらぬ翁の 影はみずとも
立ち寄らないで今日通り過ぎた鏡山よ。見ず知らずの老人の姿を映さなくても、年老いたと自分が分かっているのだからね。
⑩鏡山⑪長光寺
日が暮れたので、武佐寺こと長光寺という山寺の辺りに宿をとった。鏡宿からそう遠くない所である。鳥籠(とこ)の山から吹く秋の風は夜が深くなるにつれて身に染みて、ふと都にいた時と同じような心地がした。
枕近くで鳴り響く鐘の音に導かれ、空は暁色に染まっていく。白居易は、香炉峰の北にある遺愛寺のほとりにある草庵で枕近くで鳴り響く鐘の音に寝を覚まし、心安らかに過ごしたという。遺愛寺に築かれた草庵での寝覚めも、このような感じだったのかと思われてしみじみとした感情に襲われた。同時に、まだまだ行く末の遠い旅のことが思われて、非常に辛くなった。
都出でて いくかもあらぬ こよひだに 片しきわびぬ 床の秋風
都を出てそんなに月日も経っていない。そう思われた今宵。鳥籠の山から吹く秋風が身に染みるせいで、寝床で一人寂しく過ごす今が物悲しく思われたよ。
⑫笠原⑬奥石神社
この宿を出て笠原という野原を通り過ぎたあたりで、杉が多い老蘇という森に出た。ここには奥石神社がある。下草に夥しい量の朝露が付いていたが、この朝露が霜に変わる時はそう遠くはないだろう。月日は儚くも自然と移ろうものである。これを見て、私のこの旅の行く末もそう遠くないと思われた。
変らじな 我がもとゆひに 置く霜も 名にしおいその 杜の下草
同じことではないか。私の元結が白髪に移り変わっていくのも、下草の露が霜に変わっていくのも。なんたって、ここはその名の通り、「老」蘇の森なのだから。
⑭醒井
噂に聞く醒が井を見た。木の影で暗くなった下の方にある岩根から流れ出る清らかな水が非常に涼しく澄みわたっており、実に身に染みるところであった。
暑さが続く秋であったため、東山道を往来する旅人の多くがここに立ち寄って涼み合っていた。
古代中国、前漢時代の女官、斑婕妤(はんせふよ)は寵愛を失い、自身の身を月のように円く、真っ白な雪のように例えた。斑婕妤のように寵愛を失った女性を秋になって使われなくなった扇になぞらえて秋扇と言うのだが、吹いては通り過ぎていく秋風にそのような思いを馳せしばらく暑さを忘れた。まだまだ先の長い旅なのにここから去ることが辛く思われたため、もうしばらく休むことにした。
かの西行法師が
道のべに 清水ながるゝ 柳かげ しばしとてこそ たちどまりつれ
道の脇に清らかな水が流れている。傍にある柳の木陰で「少しだけ休もう」と思い休んだら、ずいぶん長居してしまった。
と詠んだのも、このような場所であったのだろうか。
道のべの 木陰の清水 むすぶとて しばし涼まぬ 旅人ぞなき
道の脇の木の木陰で清らかな水が流れており、私を引き留めた。「しばらく涼もう。」と足を止めない旅人はいないのであった。
⑮柏原
先に進み、柏原という所へ着き、さらに進んで美濃国関ケ原に差し掛かった。谷川では霧が立ち込め、その下から水が流れる音が聞こえてくる。また、山風は松の梢を吹き通っては、鬱蒼とした音を奏でる。日の光が見えないほどの木陰道は物寂しく、そして心細く思われた。
| 前の記事へ << | 続きを読む >> |