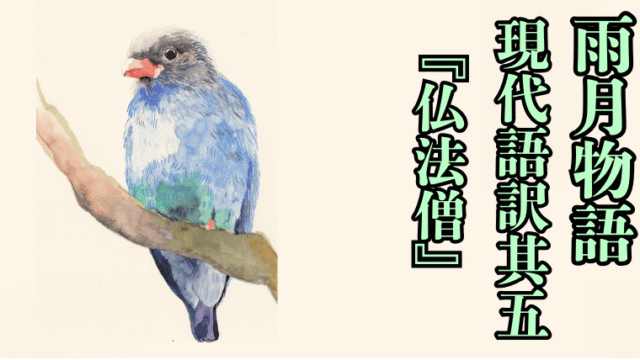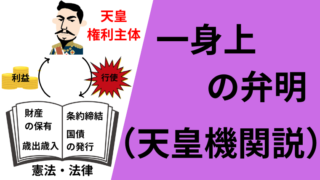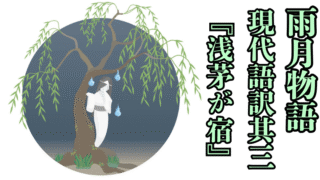解説
『色絵十二ケ月歌絵皿』は尾形乾山の作品で、元禄文化を代表する作品となっています。
乾山の号名は、開窯した京都の鳴滝が乾(いぬい)の方角(=北西)にあったことが由来となっています。
さて『色絵十二ケ月歌絵皿』ですが、文字通り、各月になぞらえた和歌を皿に描いています。ひと月に2首描かれていますので、計24首ですね。
皿の表に和歌の情景の絵を、皿の裏に2首記しています。この2首は、「花」と「鳥」を題しています。つまり、皿の表には花と鳥が描かれている風流な作品となっているわけですね。
この和歌は尾形乾山が自ら詠んだものではなく、平安時代を代表する歌人、藤原定家の『詠花鳥倭歌各十二首』という作品を視覚的に落とし込んだものです。
著作権の問題で本サイトには載せることができませんが、繊細な筆のタッチとぼかしの技法により、奥行きを作っていますね。また、皿によっては、内壁まで絵の領域が広がっており、重層的な見せ方をしています。
では、実際に和歌の現代語訳を見てみましょう。そのうえで、絵皿を見ると、感じ方も変わってくるかもしれません。
(追記)※余談です
偶然にも美術館で本物を拝見する機会があったのですが、思っていたよりも小さかった印象を受けました。あと、厚みや染料の質感、筆運びなど、二次元では分からない部分をこの目で見ることが出来たので、非常に有意義な時間になりましたね。皿という小さい空間を最大限に活かして、2首の和歌の情景を落とし込むその表現力は見事なものでした。
皆さんも是非、機会があれば足を運んでみてください。
現代語訳
正月
鶯
春来ては いくかもあらぬ 朝戸出に
うぐひすきゐる 里のむら竹
春になってまだ幾夜も経っていない。そんなある日の朝、外に出てみると、窓に近いところにある生い茂った竹にウグイスが来ていたのだ。春だなあ。
柳
うちなびき 春くる風の いろなれや
日をへて染むる 青柳のいと
柳が風に靡いている。この風は春の到来を告げる風だろうか。日に日に柳の垂らす糸が染まりつつあるのだから。
二月
雉
狩人の 霞にたどる はるの日を
つまどふきじの こゑに立つらむ
立ち込める霞は狩人に春を告げる。そんな狩人は雉の鳴き声に足を止めるのだ。雉も春を報せてくれた。
霞は春の季語
雉の異名は妻恋鳥
桜
かざしをる 道行き人の 袂まで
さくらににほふ きさらぎのそら
挿頭(かざし)にするために桜を手折る道行く人々。彼らの袂にまで桜の美しさが見いだせる。そんな二月の陽気な空。
三月
雲雀(ひばり)
すみれ咲く 雲雀の床に 宿かりて
野をなつかしみ くらす春かな
すみれが咲いている雲雀の巣。その巣に泊めてください。野に心惹かれながら春を過ごしたいのです。
藤
行春の 形見とや咲く ふぢの花
そをだにのちの 色のゆかりに
過ぎ去ろうとしている春の形見ともいえる藤の花が咲いている。咲くならせめて夏の気を含んでください。春の終わりを報せるだけに咲くなんて、悲しく思われます。
藤の花は晩春の季語
四月
卯花
白妙の ころもほすてふ 夏のきて
垣根もたわに さけるうのはな
真っ白な衣を干す季節(夏)がやってきた。垣根に、しなやかに曲がり咲く卯花を見ると、改めて夏だと思わされるよ。
白妙 :衣を呼ぶ枕詞
たわ(撓):しなやかに曲がるの
卯花 :垣根に、家の仕切りとして用いられた
郭公
時鳥 しのぶの里に さとなれよ
まだ卯のはなの さつき待つころ
ほととぎすよ。卯の花が咲く皐月になる前に早く陸奥にある信夫郡の里に慣れるんだよ。
郭公と題がありますが、これはホトトギスです。古くは、郭公はホトトギスのことを指していました。
五月
盧橘(ろきつ)
時鳥 鳴くやさつきの 宿がほに
かならずにほふ のきのたちばな
自分の宿のような顔つきで鳴くホトトギス。それを見れば必ず花橘の香りがするものだ。もう夏だなあ。
盧橘(ろきつ):キンカンの異名
橘:季語に注意。「橘の花→夏」「橘の果実→秋」
水鶏(くいな)
槙の戸をたゝく水鶏のあけぼのに人やあやめの軒のうつり香
マキの戸を叩く音がするということはもう夜明けだ。誰か訪れたのだろうか。人とあやめの移り香がする。
水鶏:くいな。鳴き声が戸を叩く音に似ている。
軒のあやめ:端午の節句に魔除けとしてあやめを軒端に掛けていた
六月
常夏
大方の 日かげにいとふ みな月の
空さへをしき とこなつのはな
長く黒い日影を残さない水無月の空。鮮やかな撫子の花はそんな空さえも愛おしく感じているよ。
日陰の黒と撫子の花の鮮やかさとの対比です。
鵜
みじか夜の 鵜川に上る かゞり火の
はやく過ぎ行く 水無月の空
夏の短い夜。鵜飼をしている川に昇る篝火は夜が明ける前に昇りきろうと速く行ってしまう。そんな水無月の空だよ。
七月
鵲
長き夜に 羽をならぶる ちぎりとて
秋まちわたる かさゝぎの橋
長い夜。天の川にかかる橋はカササギが羽を並べているようだ。逢瀬の秋を待たずして織姫と彦星が渡っているよ。
女郎花
秋ならで 誰もあひ見ぬ をみなへし
ちぎりやおきし 星合のそら
秋なのに誰にも逢うことができない「女」郎花(=私)。そんな女郎花のように、七夕の空では織姫と彦星が逢えずにいるよ。
女郎花は自分を指しています。歌い手は女性でしょうか。
八月
初雁
ながめつゝ秋の半もすぎの戸にまつほどしるき初かりのこゑ
秋の半ばに外を眺めると、杉の戸の上に雁の声が聞こえてきた。秋も半ばなのに初めて聞いたよ。待ちわびたぞ。
鹿鳴草
秋たけぬ いかなる色と 吹く風に
やがてうつろふ もとあらの萩
秋が深まった。風が遠くへ吹き去っていくように、美しい色であった萩はやがて色褪せるのだよ。
鹿鳴草:萩の別名
九月
薄
花すゝき 草の袂の つゆけさを
すてて暮れ行く あきのつれなさ
秋に咲くススキ。秋だからかススキの袂に露が乗っている。これを掃っていたら日が暮れてしまっていたよ。こんな私をよそ目に、秋は知らぬ風だ。
鶉
ひと目さへ いとゞふかくさ かれぬとや
冬まつ霜に 鶉なくらむ
冬を待つ霜の中でウズラが鳴いている。一目さえでも地上を見ることができず枯れてしまう雪深くに生える草があるのだから、お前は死ぬんじゃないよ。
十月
残菊
神無月 霜夜の菊の にほはずは
あきのかたみに なにをおかまし
神無月の寒い夜。そんな夜に菊が咲いているというのに香りがしない。まるで秋の終わりを告げているようではないか。呆れてものも言えないよ。
鶴
夕日かげ むれたるたづは さしながら
時雨の雲ぞ 山めぐりする
夕日の影が空飛ぶ鶴の群れに差し掛かる中、時雨の雲が山を巡っているよ。
十一月
枇杷
冬のひは 木草のこさぬ 霜の色を
はがへぬえだの 花ぞまがふる
冬を越えられない草木は枯れて霜色に染まる。枯れて落ちない枝についている鮮やかな花の色が霜色と入り乱れて区別できないよ。
千鳥
千鳥なく かもの河瀬の 夜半の月
ひとつにみがく 山あゐのそで
千鳥もいない夜の賀茂川の河瀬。月が照らす賀茂川が山の袖を磨いているように見えるよ。
十二月
早梅
いろうづむ 垣根の雪の 花ながら
年のこなたに にほふうめがえ
色が埋もれた垣根に雪が積もっている。それでも、年内には梅の匂いがしてくるのだ
水鳥
ながめする 池の氷に ふる雪の
かさなる年を をしの毛ごろも
池の氷に降る雪をぼーっと眺めている。雪がおしどりの羽に降っているのを見ると、降る雪が年を重ねることのように思われて惜しく思われるよ。
裏
元禄十五のとし 十二月朔日 乾山陶隠深省画
元禄十五年(1702)十二月一日。尾形深省(乾山)、号は陶隠。画。(花押)
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |