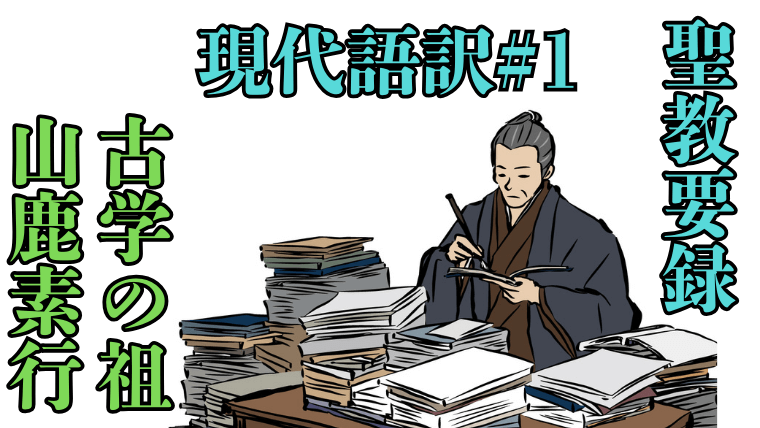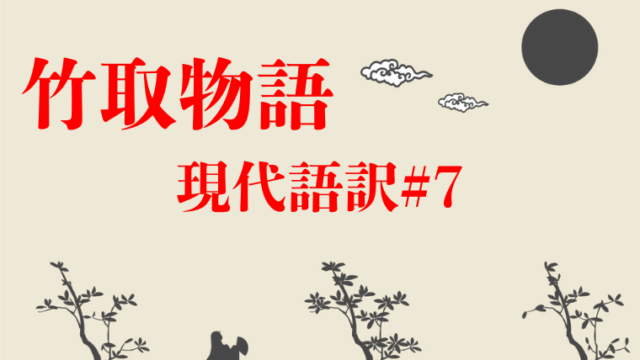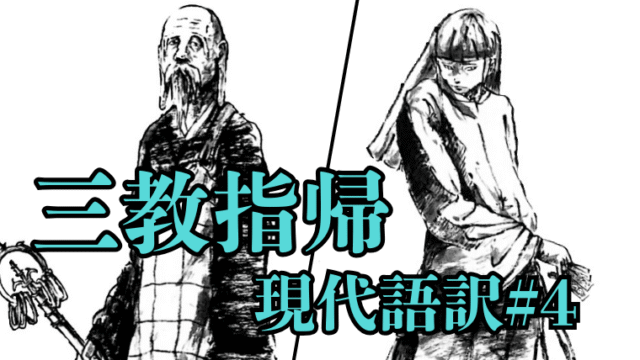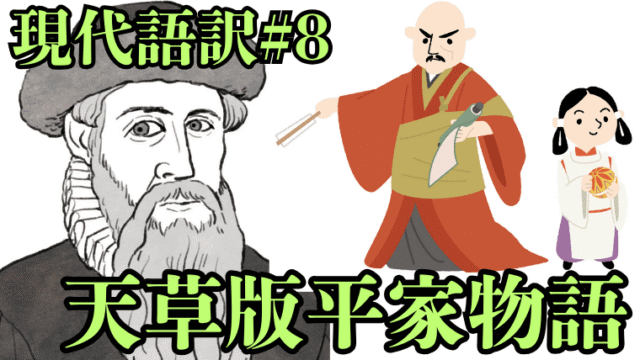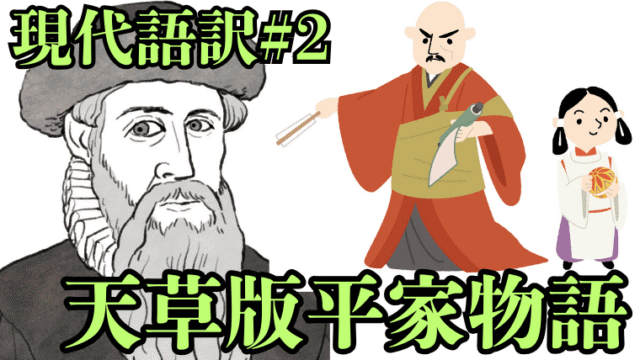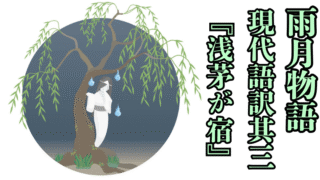聖教要録を読む前に
儒学の色々
『聖教要録』を著した山鹿素行は、儒学の一派である古学の祖です。そもそも儒学とは何か、古学の思想や、その他朱子学や陽明学との違いについて理解したうえで読まなければ理解できません。
江戸時代の儒学に関する全てをまとめた記事を作ったので、先に読むことをオススメします!

聖教要録とは
まず、古学を簡単に説明すると、古学とは、古代中国文献について知見を深め、実生活に応用しようとする学問です。直接当時の著作にアプローチしているため、古学≒儒学といえます。完全にイコールで結べないのは、古学に朱子学批判色が含まれているためです。
それから考えると、「聖教」とは、古代中国から現在まで読み継がれる聖人らが残した教えのことだと分かります。「要録」は文字通り、重要な部分だけを抜粋したもの、の意です。
この「聖教」は、山鹿素行本人を示すとも言われています。どちらも筋は通っています。
『聖教要録』は、山鹿素行自身が著した作品ではなく、弟子が山鹿素行の教えを集めた『山鹿語録』から、さらに根本理念に関わる超重要講義の部分だけを抽出した作品です。そのため、古学入門として相応しい著作であり、同時に儒学の基本を学ぶことのできるものとなっています。
全体の構成
3巻構成で、全28の題が掲載されています。
| 前巻 | ①聖人 | ②知至 | ③聖学 | ④師道 |
| ⑤文教 | ⑥読書 | ⑦道統 | ⑧詩文 | |
| 中巻 | ⑨中 | ⑩道 | ⑪理 | ⑫徳 |
| ⑬仁 | ⑭礼 | ⑮誠 | ⑯忠恕 | |
| ⑰敬恭 | ⑱鬼神 | ⑲陰陽 | ⑳五行 | |
| ㉑天地 | ||||
| 下巻 | ㉒性 | ㉓心 | ㉔意情 | |
| ㉕志気思慮 | ㉖人物之生 | ㉗易有太極 | ㉘道原 |
現代語訳
①聖人
聖人者知至而心正天地之間無不通也其行也篤而有条理其応接也従容而中礼其治国平天下也物事各得其処矣別無所謂聖人之形無可見聖人之道無可知聖人唯日用之間知至而礼備無過不及之差上古君皆教之導之後世不然別立師既衰世之政也天下所由乃聖人之道而知者過愚者不及人有一行一善之可称一曲之士也千鍾之禄可辞北斗之金可抛忠孝愿慤不為非義之士及隠士逸人名節雄知有聞当世者不乏世一行一善而於聖人之道無繊毫之相似聖人者中庸而已無得而可称焉
聖人は物事の本質を深く追求して知に至り心を備えてきた(格物致知)。これは宇宙の真理なのである。聖人はその行いを徹底しており、筋道がみられる。その対応の仕方や何時でも冷静さを保つ振る舞いは「礼」に該当するといえる。天下を平和に治める際に生じた事象はその聖人によって処理される。
あなたがもし聖人を目指すというなら、別に聖人の振る舞いを見る必要はなく、聖人が示す道を見る必要もなく、聖人のもたらす効果を知る必要もない。ただただ日ごろから格物致知を徹底すれば自然と「礼」は備わるのだ。備えた「礼」に多い足りないの差はない。
古い昔は、君主や上長が「礼」が備わっていない者を教導していた。後世は君主ではなく、師匠がその立場に立った。それも既に衰えた世の中にはなってしまったが。治国とはつまり聖人の道でありる。教導すれば、知者には十分理解されるが、愚者にはいくら説明しても理解されないものなのである。
一行一善というのがある。一度の行いに一つの善を積むことができる者がいれば、その者は一廉の人物である。多くの俸禄を辞退するために、北斗星のごとく不動の精神で蓄えた金を放出できる財力を持つような人物である。
真心に基づいた忠孝の心を持ち正義に背くことをしない者。出世争いを避けて世俗を逃れた者。名誉と節操のある雄士。
こういった者は世間の評判がある者であり、世の中の道理に乏しいことはない。一行一善と聖人の道は似て非なるものである。聖人は中庸の心のみを体得するべきものであり、これといって称される名はない。
一日一善という言葉と似たようなものです。行動により徳を積むという考え方は道教が由来となっています。道教と朱子学は深い関わりがあるため、山鹿素行はこの行いも批判しました。
②知至
人者万物之霊長也有血気之続者莫知於人聖賢也知之至也愚不肖也知之習也知之至在格物天生蒸民有物有則能至其物無不尽則其知至而無不尽無不通者聖人也思曰叡叡作聖人知多故欲亦多欲不可充君子以義為利小人知利不知義君子之利能亨小人之利不全義利不支離利者義之和也義之所有利随之人皆有睎聖之志其知不至動陥異端異端之教也矯人情直情径行戎狄之道也聖教異端聖学俗学之辮唯在義利之間知而不力行則不可謂至力行而不省察則知鑿又不可謂至力行省察而後知之至也
人は知ろうとする好奇心が強い。故にそれに伴って欲もまた強い。欲(後に述べる「利」)というのは意図的に満たしてはならない。君子は「義」を示し、結果としてそれを「利」に変える。心が乏し人は「利」を求めることばかり知って「義」を知らない。君子の示す「利」はよく人の心に響くが、心が乏しい人の「利」は全くそういうことがない。「義」と「利」は常に離れることはない。
儒学の祖、孔子の『春秋左氏伝』において「利は義の和なり」とある。人としての正しい行いである「義」と己の利益「利」は公私の相反する存在であるが、己の利益「利」とは「義」の積み重ねによって生まれるものである。このことからも、「義」と「利」が離れてはならないといえる。
「欲=利」を満たそうとすると、「義」の心を忘れてしまい、結果として「利」も落としてしまいます。「義」は公的な感情、「利」は私的な感情ですが、この相反する性格をどちらもちょうどいい具合(中庸)で持たなければならないのです。
人は皆聖人を目指そうとする志を持っている。ただ、格物致知に通達することをしないでいると、聖人の道から外れた朱子学の思想などに陥ることになりかねない。他の思想やその思想に基づいた人情に矯正させて直ちに行動に移す。これは辺境の地に住む卑しい民族のように心を卑しくする道である。とはいえ、私が主張する聖人の道に関わらず、聖教・異端・聖学・俗学といった言葉は全て、ただただ「義」と「利」の中間に存在する、いわば「義」と「利」を備えるための手段なのである。
「義」と「利」のバランスをどうするかは自分次第であり、その補助として様々な思想があるという意味です。当然、山鹿素行が主張する聖人の道も、批判する朱子学も補助手段の一つでしかありません。「義」を重視したい場合は○○学、「利」を重視したい場合は△△学を、といったように己の意思で選択できるのです。山鹿素行の場合は、「義」と「利」のバランスを取る(中庸)のために古学(=聖人の道)が必要だと述べているのです。
知ったとしてもそれを行動に移さなければ(力行)、格物致知に通達したとはいえない。また、行動に移したとしても、きちんと物事を追求しなければ(省察)、ただ憶測に振り回されて正しい道を見失ってしまう。これも格物致知に通達したとはいえない。力行と省察をどちらも行い、その後で「知った」時、初めて格物致知に通達するのである。
力行の段階の「知」はただ知った、あるいは知ったつもりでいる段階です。書いてあるとおり、力行と省察をどちらも行うことで初めて格物致知に通達するのです。
③聖学
聖学何為乎学為人之道也聖教何為乎教為人之道也人不学則不知道生質之美知識之敏不知道其蔽多学唯学于古訓致其知而施日用也知之至遂変気質学在立志志不立則為人也学有法小学大学下学上達中人以上中人以下各有法学必在問問必在審不問則不新学必在習学而時習也学必在思不思其知不至学必有蔽心学理学甘心嗜性其蔽過読書泥事其蔽不及共学之蔽也学必有標準其所志不正乃読書知日昏覔道理日惑其行過於倹其称君子亦事物不通言必信行必果硜硜然小人也
「学」は「志」を立てることで生じる。「志」がなければ、やることなすこと自分のためでなく、人のためにしてしまうだろう。「学」には必ず「法(=規律)」がある。「小学と大学」「下学と上達」「中人以上と中人以下」、いずれも「法」が存在する。それぞれの状態に合わせて必要な「学」があるのだ。
「学」を実行していると必ず「問い」が生じる。「問い」は、必ずその「学」を明らかにする力がある。格物致知に通達するまでの通過点なのだ。「問い」が生まれてこなければ、新しい自分にはなれない。
「学」には必ず「習う」ことが含まれる。対象の「学」から習っているという意味である。
「学」には必ず「思う(=考える)」ことが生じる。考えなければ格物致知に通達することはない。必ず弊害が生じてしまう。心学(王陽明らが主張した、儒教の中でも唯心論的側面が強い論)や理学(朱子学、陽明学の総称。宇宙の原「理」を追求した論)は心に甘んじた側面があるため、堕落してしまうだろう。その弊害は過ぎたものとなる。それらの書を読むだけで、行動に移さなければ、弊害はそこまで及ばない。とはいえ、共に「学」の弊害であることには変わりない。
「学」には必ず基準がある。志した先が正しくなければ、書を読んでもいつまで経っても「知」に暗く、道を求めてもいつまで経っても「理」に迷う。そして、可能な行いが狭くなってしまう。そうなれば、君子と称しても物事の道理が分からず、発言には信頼がおけるが、行動をすれば必ず器量の小ささが露呈する。まさに小人である。
④師道
人非生而知之者随師稟業学必在師於聖人世世聖教之師唯文字記問之助耳然道在天地之間而人物有自然之儀則其言行賢於己者可以師何有常師乎天地是師也物事是師也立師以厳重師事之所以修身也師道不重則所学不固師有軽重一技之術亦師也如聖教其深重同君子古人以君父同相称之師示其端倪朋友輔其私師友之益也
生まれてすぐにこれ(人の道=人倫)を知っている人はいない。師に従い、学ぶことで自身の体に身につけるのだ。「学」を行うには、必ず聖人を師とせよ。どの時代も聖教における師とは存在せず、ただ文字を暗記することだけが「学」を習得する助けとなっている。
しかしながら、人倫とは、宇宙の真理の中に存在するものであるため、それを身につけようとする人や物には必ず自然の法則というものが作用する。言動が自分よりも勝っている人がいれば、その者を師とせよ。人は学び成長する。段階に応じて必要な「学」が違うのだから、どうして生涯同じ師を仰ぐ必要があろうか。宇宙が師であり、事物が師でもあるのだ。
師には厳しい者を立てよ。師を仰いで付き従えば、より良い修業となろう。良い修業のために厳しい師が必要なのだ。軽い師を立てれば、学ぶことは難しいだろう。
師には必ず軽重がある。一つのことを学びたいのであっても、学ぶ以上それは師である。聖教の師の場合、より一層重いものとなるだろう。主君や父に同じである。そのため、古では、君主も父も同じ「君父」という呼ばれ方をしていた。
師は事の始終を示し、学友は道を誤りそうになった時、助けてくれる。これは、師と友を持つことのメリットである。
| 解説を読む << | 続きを読む >> |