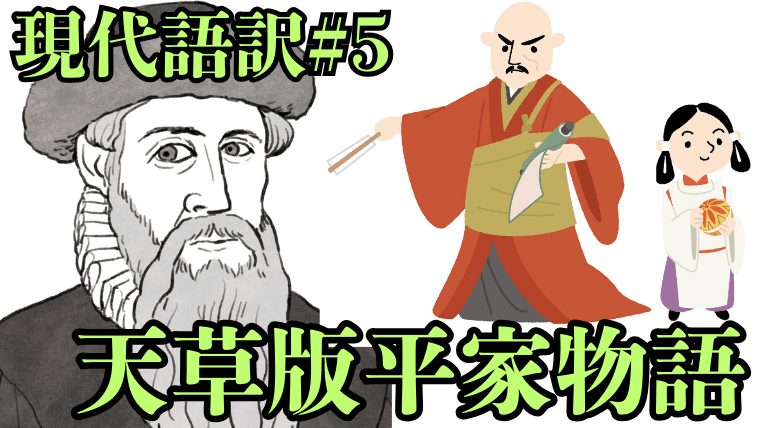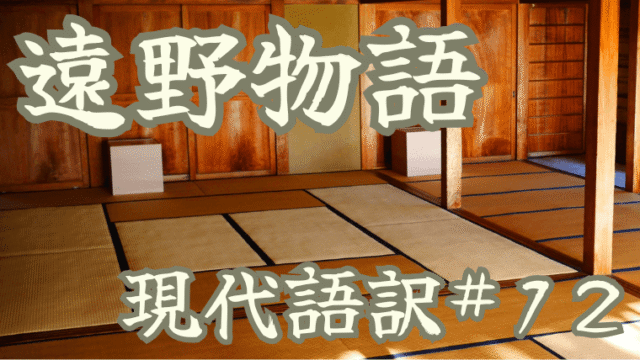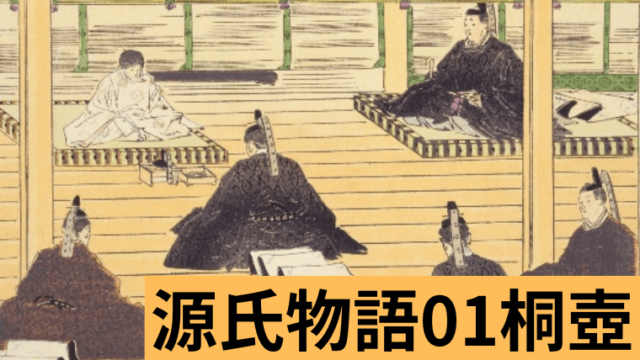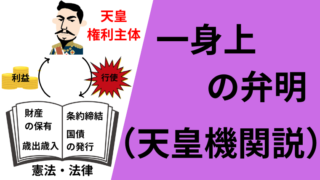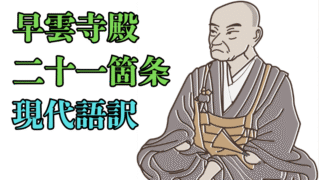現代語訳
| 一覧に戻る << | 続きを読む >> |
第五 成親卿の子息少将についての事。

右馬之允
少将殿(藤原成経)は、その後どうなったのだ?

喜一
少将殿はその夜ちょうど院の御所に宿直していて、まだ退勤していませんでした。そこへ成親卿の家臣たちが急いで御所へ駆けつけ、少将殿を呼び出してこのことを申し上げました。
「なぜ宰相殿(平教盛)から今まで知らせがなかったのだ。」
最後まで言い終わらないところで、ちょうど宰相殿の使者がやって来ました。ちなみに、宰相とは、清盛の弟教盛です。
教盛の宿所が六波羅の総門内にあったため門脇の宰相殿と呼ばれておりました。そしてこの教盛は成経の舅(妻の父)です。
「成経、何事かは知らないが、清盛公が『必ず成経を西八条へ連れてこい。』ときつく仰せになっているぞ。」
そう伝えられて成経は事の重大さを悟り、近習の女房たちを呼び出して言いました。
「昨夜、何やら外が騒がしかったから、いつものように山法師(比叡山の僧兵)が強訴しに下ってきたのかと、他人事のように思っていた。それがまさか自分の身に関わることであったとは。昨夜、父を斬るよう命が下っているようだな。私も同じ罪に問われるであろうと覚悟している。今一度、帝の御前に参上して、お顔を拝したいとは思うが、すでにこのような身となってしまった以上、それは憚られる。」
そう申したので、女房たちが成経の代わりに帝の御前に参り、このことを奏上しました。
法皇は大いに驚かれて、
「やはりそうか。今朝、清盛の使いが来ていたのはこのことだったのだな。とにかく、こちらへ。」
と仰せになったので、それを聞いた成経は御前へ参上しました。法皇は涙を流され、何と仰せになることもできず、少将も涙にむせび、申し上げる言葉もありませんでした。
このまま時間を過ごしてもどうにもならないことなので、しばらくしてから成経は袖で顔を押さえ、涙を流しながら退出したのでした。法皇はその後ろ姿を遠くまで見送りながら、
「ただただ、これからの時代を思うと嘆かわしい。これが最後と、再び会えなくなる者も出てくるのだろうな。」
と言って涙を流されたといいます。これは本当に、少将にとって恐れ多くもありがたい出来事でございました。
院の御所の人々は、少将の袖を引き止めたり、袂にすがりついて名残を惜しんだりと、涙を流さない者はいませんでした。成経は舅である教盛のもとへ向います。さて、成経の北の方(妻)は間もなく出産を迎える頃でありましたが、北の方は朝から嘆きに嘆き、死んでしまうのではないかと疑われるほどの様子となっていたのです。
成経が御前を退出されてからも、流れる涙は尽きません。そのような状態であったので、北の方(妻)の様子を成経が見に行くと、北の方はいよいよどうしようもないほどに悲しく思われた、とのことです。そこへ、成経の乳母の六条という者がやって来て、こう成経に申し上げました。
「お生まれになってすぐから、成経殿を抱き上げてお世話をしておりました。月日が経っても自身の加齢は嘆かず、ただ成経殿が大人になられるのを嬉しく思っておりました。お生まれになってから僅かしか経っておりませんのに、今年で二十一年間になります。一度も離れることなくお仕えしてまいりました。院の御所に伺候してからというもの、少しでもお帰りが遅くなるだけでも気がかりでございましたのに、今さらどのような辛い目にお遭いになるのでしょうか。」
そう言って泣いていたので、成経は
「そんなに泣くな。教盛殿がいるのだから、命だけはきっと助けていただけるだろう。」
と六条を慰めましたが、それでも、六条は人目も憚らずに泣き悶えたのでした。
そうしているところへ、西八条(清盛の屋敷)からの使いが次々とやって来たので、教盛は
「屋敷へ行けば、何とかなるだろう。」
と言い、成経は教盛の車の後ろに乗って出発しました。保元・平治の乱以来、平家の人々は楽しみや栄華ばかりで、辛さや嘆きを感じる出来事とは無縁でありましたが、この教盛だけは、縁あって迎えた婿(少将)なだけあって、このような嘆きを味わうことになったのです。
西八条が近くなったところで車は止まり、使者が清盛に成経の到着を知らせました。清盛が
「成経は屋敷の中へ入れるな。」
と命じたために、成経は屋敷近くの侍の家に降ろされました。一方の教盛は門の中へ入っていきました。
成経は、いつの間にか兵たちに囲まれ、監視されることになりました。頼りにしていた教盛とも離された成経の心の中は、どれほど心細かったことだろうと、哀れに思われます。一方の教盛は中門まで入ったものの、清盛は教盛と対面しようとしませんでした。
教盛と清盛の間に入った平季貞に教盛はこう伝えました。
「思いがけず、このような事態に深く関わってしまったことを悔しく思いますが、今さらどうしようもありません。それに、成経殿の北の方は、最近体調が優れておりませんでした。そこへ今朝からのこの嘆きが加わり、すでに命も絶えてしまうのではないかと思われるほどです。なぜ北の方は苦しんでおられるのか?。。。しばらくの間、成経殿は教盛殿にお預けになりませぬか。教盛殿ほどのお方であれば、決して誤ったことはなさらないでしょう。」
季貞が清盛のもとへ参上し、この旨を申し上げると、清盛は
「そうか、いつものように教盛が愚かなことを言っているようだな。」
と言い、すぐには返事をしませんでした。しかし、しばらくして清盛はこう言いました。
「成経の父、成親卿は、我が一門を滅ぼして天下を乱そうと企てたのだ。成経は成親卿の嫡男なのだから、父とどれだけ疎かろうが親しかろうが、決して許すことはできない。もしこの謀反が成功していれば、お前とても無事では済まなかったかもしれないのだぞ。」
季貞が戻って教盛殿にこのことを申し上げると、本当に無念そうな様子で、さらにこう言いました。
「私は、保元・平治の乱以来、戦が起きるたびに、まず第一にあなた(清盛)のお命に代わろうと思ってきました。これからも、吹き荒れる風(平家の危機)を防いでいこうと考えております。たとえ私が年老いたとしても、若い子供たちが大勢おりますので、きっとあなたの周囲を固める助けとなることでしょう。それなのに、成経をしばらく預かりたいとお願いしても許されないということは、結局、私が二心を持つ者(裏切り者)だとお思いなのですか?このような後ろめたい感情を抱かれては、生きていたところで何の意味がありましょうか。こうなっては、ただただ出家の許しをいただき、高野山や粉河寺(こかわでら。現和歌山県にある粉河観音宗の総本山)にこもって、ひたすら来世は安楽の身で生まれ変わることを願って修行するしかありません。つまらぬ俗世の交わりです。俗世にいるからこそ望みは生まれ、その望みが叶わぬからこそ恨みも生まれます。そういうことですので、この憂き世を捨てて、真の道(仏道)に入ろうと思います。」
こう嘆いたのでした。季貞が清盛のもとへ参上し、
「教盛殿は、もはや覚悟を決めたご様子。どうか、良きように取り計らってくだされよ。」
と申し上げると、清盛は大いに驚き、
「保護を認めないからといって、出家までするのは、あまりにもとんでもない。それならば、『成経はしばらく教盛のもとに預けることとする。』と伝えよ。」
と命じたのでした。季貞が戻ってこのことを申し上げると、
「ああ、子どもなど持つものではないな。我が子と関係の無い者の申し出であれば、これほどまでに心を悩ませることもなかっただろうに。」
そう言って、その場を立ち去ったのでした。
成経は教盛を待っていました。
「さて、どうなりましたか」
「清盛公はあまりにも腹を立てていたから、ついに私とは対面もしなかった。『許すわけにはいかない。』と何度も言っていたが、私が出家するとまで申し出たら、そのためか、『しばらく成経は教盛のもとに置いてもよい。』と言ってくれた。ただ、これも長く続くとは思えん。」
「そうということであれば、この命は清盛公のご恩のおかげで、しばらく間延びたことになります。命長らえるといえば、教盛殿は、我が父成親についてどのように申し上げましたか。」
教盛が
「そこまで頭が回ってなかった。」
と返すと、成経は涙をぽろぽろと流しながら言いました。
「確かに、ご恩のおかげで、しばらくの間でも生き長らえることができました。ありがたいことです。しかし、私が命を惜しむのは、ただもう一度、父上に会いたいと思うからなのです。もし父上が斬られることになれば、少将の身とはいえ、この世に生き続けて何の意味がありましょうか。『成親卿を斬首するのであれば、どうか私も父上と共に最期を迎えられるよう取り計らってほしい。』そう、お願い申し上げていただけませぬか。」と。
教盛は心苦しそうに言いました。
「いやはや。お前のことについては、あれこれとお願いしたが、そこまでは考えもしていなかった。しかしだ。成親卿の処遇については今朝、重盛様が様々に申し上げたことで、しばらく安心できるようにとは聞いているぞ。」
成経は涙を流しながら手を合わせ、喜びました。その様子を見て、教盛は
「実の子でなければ、いったい誰が、自分のことを後回しにして、これほどまでに喜んでくれるだろうか。本当の絆というものは、親子の間にこそあるのだな。人はやはり、子を持つべきものかもしれぬな。」
と考えを改めたのでした。さて、今朝のように成経と教盛が一緒に車に乗って帰ると、宿所に女房たちが一斉に集まり、喜びの涙を流したのだった。まるで死んだ人が生き返ったような気持ちであったに違いないことでしょう。
(第五。終。)
| 第四に戻る << | 第六を読む >> |