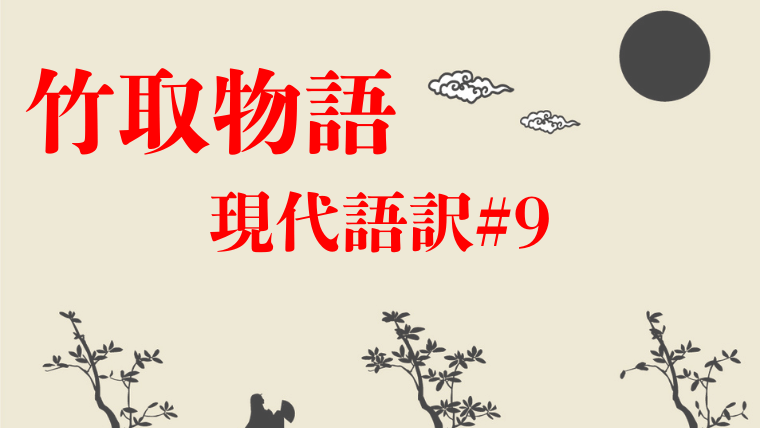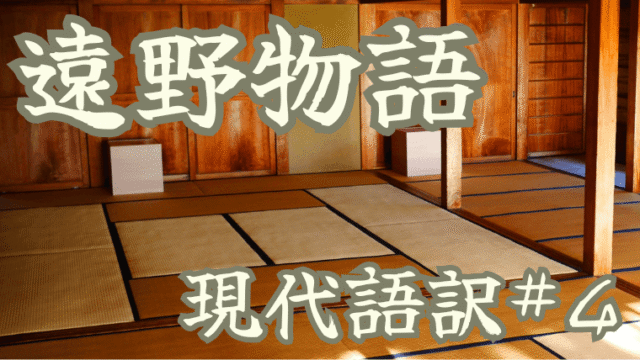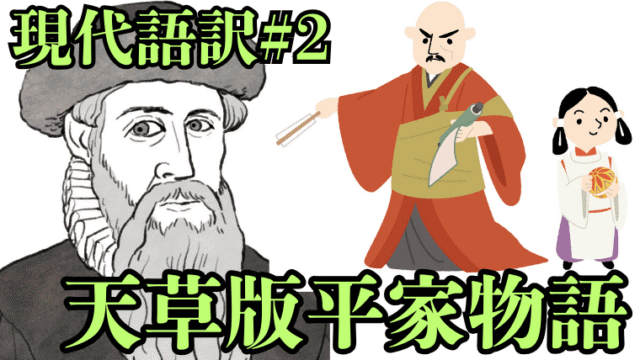一覧は下記サイトをご確認ください。
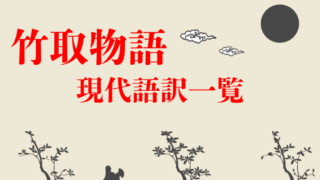
⑨かぐや姫の物思い
このように、互いの心をお慰め合っているうちに3年ほどが経過した。かぐや姫は、春の初め頃から、月が趣深く出ているのを見て、普段以上に物思いに耽っている様子であった。ある人が
「月の顔を眺め続けるのは良くないことなのですよ。」
と言ってかぐや姫を制止するも、少し放っておくと、人がいない間にまた月を眺めては、ひどく涙を流した。そして今日、かぐや姫は縁側に出てきて、この7月15日の月に激しく物思いしている様子である。側近の人々が翁に告げる。
「かぐや姫は、普段から月をしみじみと眺めておいでですが、この頃のかぐや姫はただ事ではないように思えます。たいそう嘆かわしいことがあったのでしょう。よくよく、かぐや姫を見守ってあげてくだされ。」
翁はかぐや姫に言った。
「どのような気持ちが思い起こされれば、そのように物思いに沈んだ様子で月を眺めることになるのですか。上手くいっている世の中ですぞ。」
「月を見ると、この世の中が心細くて哀れに思うのです。どうして我が身の上を嘆きましょうか。」
かぐや姫の所まで行ってその様子を見ると、やはり物思いしている様子であった。これを見て翁が
「我が仏(のように可愛い子)よ、何を思ってているのですか。考えているのはどのようなことですか。」
と言うと、
「何も考えていませんよ。何となく心細く思うのです。」
「では月をご覧になりますな。月を見ると物思いしているご様子です。」
「どうして月を見ずにいられるでしょうか。」
そう言って、やはり月が出ていると、縁に出てきては心を沈めていた。ただ夕闇の時(曇天や新月)には、物思いに耽っていないようである。やはり、月が出ている時々は嘆き泣くなどするようである。この様子を見た召使い共は
「やはり何かお思いになることがあるのであろう。」
と囁きあったが、親である翁や嫗をはじめ、どういうことなのか分からなかった。八月十五日頃の月に向かって縁側に出てきたかぐや姫は、たいそうひどくお泣きになった。この時は人目も憚らずに泣いた。これを見た翁と嫗は
「どうしたのだ。」
と聞いては騒ぎ立てた。かぐや姫が泣く泣く言う。
「前々から申し上げようと思っていましたが、『絶対にお二人の心を乱してしまう。』と思って、今まで言えずに過ごしてきました。ですが『そうばかりしてはいられませんね。』と思ったので打ち明けます。私はこの国の人ではなく、月の都の人なのです。それが前世からの因縁によってこの国にやってきたのです。今、帰るべき時が来てしまいました。この月の十五日に、あの月の国から迎えの人々が参上します。来る以上ここを去らなければなりません。こう申し上げて皆がお嘆きなさるのが悲しくて、そのことで春から思い嘆いておりました。」
そう言ってかぐや姫はひどく泣いた。翁が言う。
「これは何ということを仰るのか。わしが竹の中から貴方を見つけた時はまだ菜種ほどの大きさでいらっしゃったが、こうして今はわしの背丈に並ぶまで成長なさった。ここまで育てた可愛い我が子は誰にも連れていかせぬ。それは絶対に許さぬぞ。」
「わしこそが死のうでは。」
と言って嘆き、泣き喚いた。このことを本当に耐えられない様子である。
「私を産んだ父母は月の都の人です。少しの間ということであの国からやって参りましたが、このようにこの国で多くの年を過してしまいました。私はあの国の父母のことを覚えていません。ここではこんなに長い間楽しませていただきましたから、お二人のことを慕っております。月に帰っても嬉しく思いません。ただ悲しく思うだけです。けれど逆らえませんから、この心に反してお別れとなりましょう。」
その場にいた皆がひどく泣いたのであった。仕える人々も、かぐや姫と数年来親しくしていたため、この別れを悲しんだ。かぐや姫の人となりが上品で美しかったことを知っているからこそ、いなくなれば恋いこと耐え難く湯水も飲めないような気持ちになるであろう、皆が同じく嘆かわしい気持ちになるであろうと思うのであった。このことを帝がお聞きになって、帝は屋敷に使者を派遣した。使者とは翁が取り合った。顔を出した翁はこの上なく泣いていた。このことを嘆き続けるものだから、髪は白くなり、腰も曲がり、目もただれてしまっていた。翁は今年は50歳ほどであった(序盤の「70歳過ぎ」と矛盾している)が、
『心配事が片時も頭から離れなかったからこのように急に老けてしまったのだな。』
と思われた。使者は翁に向けての帝の仰せ言を伝えた。
『かぐや姫がたいへん心苦しく物思いしているというのは本当か。』
と。翁は使者に泣く泣く申し上げた。
「今月の十五日に月の都から、かぐや姫の迎えがやって来るそうです。畏れ多くもお尋ね申します。この十五日、朝廷より警護の人々を派遣していただけないでしょうか。月の都の人がやって来たら、捕えさせるのです。」
と。宮中に帰参した使者は、翁の様子を申して、翁が奏上したことなどを申し上げた。帝はお聞きになって仰った。
「一目見たあの時の感情でさえ忘れられないのに、明けから暮れまで常にかぐや姫を見慣れた翁からすれば、月に遣ることになってどのように思っているだろうか。」
そして十五日、各役所にお命じになり、勅使には近衛少将高野大国という人を指名し、六衛(左右近衛府、左右衛門府、左右兵衛府)から合わせて2000人の兵を翁の屋敷に派遣した。屋敷に到着した兵は築地の上に1000人、屋根の上に1000人配置した。加えて屋敷に仕える多くの人々も動員したため、空く隙間も無く守らせた。屋敷の警護にあたる人々も兵同様に弓矢を身につけており、また、屋敷内では女房らを番として守らせた。嫗は塗籠の中にかぐや姫を入れて籠を抱いている。翁も塗館の戸を閉鎖して戸口に立った。翁は
「これほど人が守っているのだ、天人に負けるはずがない。」
と言って屋根の上にいる人々に言う。
「少しでも空を飛んでいる物があれば、速やかに射殺してください。」
守る人々が返す。
「これほどにまで守っているのです、そのような所にコウモリ一匹でもいたら、まずは射殺して、息の根を止めてから外に追い出そうと思います。」
翁はこれを聞いて頼もしがった。これを聞いてかぐや姫は、
「私を籠らせて守り戦う準備をしたとしても、あの国の人とは戦えません。弓矢を中てることはできないでしょう、このように籠らせてもあの国の人が来たら皆開いてしまうでしょう。戦おうとしても、あの国の人の前では、勇み奮い立たせることができる人はよもやおりますまい。」
翁は、
「お迎えに来る人の眼球を、この長い爪で掴んで潰そうではありませんか。髪を取ってひきずり落とそうではありませんか。尻を掻き出し、ここらにいる多くの役人に見せて恥をかかせようではありませんか。」
と言って腹を立てている。かぐや姫が言う。
「大声でおっしゃいますな。屋根の上にいる人々が聞いたらと思うと、本当にみっともないです。ただ、これまで私に注いでくれたお心遣いに応えないで、ここを去ることは悔しく思います。『長い縁がなければ、程なくしてここを去ろう。』そう思っておりましたが、長い年月を過ごした今、去ることが悲しく思います。そして、親のお世話を全くせずにおりましたから、帰り道にそのことが心残りになろうと思いました。ですので、月の出ている夜に縁側に出て、『親孝行したいのです、どうか今年限りの猶予を。』と申し上げていたのです。しかし決して許されませんでした。あのように思い嘆いていたのはそういう故にございます。お心を乱させたまま去ることが、悲しく堪え難いのです。あの月の都の人はたいへん美しく、そして年を取りません。思い悩むことのない世界なのです。そのような所へ帰りましても、私は嬉しく思いません。老い衰える親をお世話したかった、月に帰ってから、そう恋しく思うでしょう。」
そう言って泣いた。 翁は
「胸が痛くなることを仰いますな。麗しい姿をしたお迎えの遣いにも、決して触れさせませぬ。」
と言って奴らを忌々しく思った。こうしているうちに宵も過ぎて子の刻(0時頃)を迎えた。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |