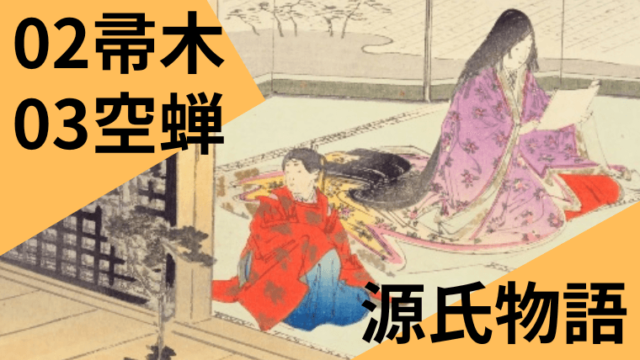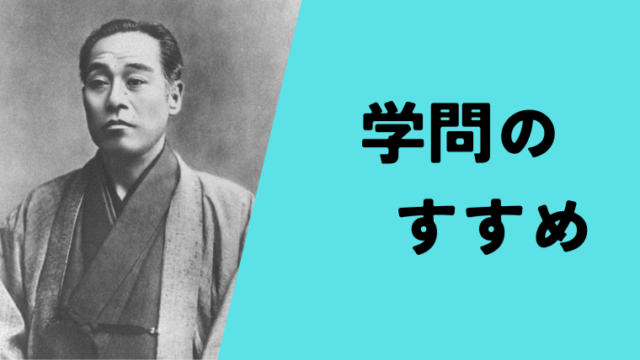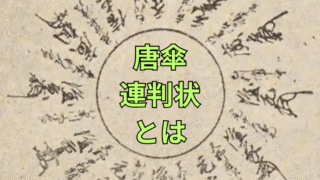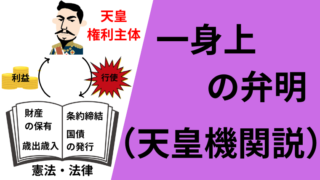現代語訳
| 一覧に戻る << | 続きを読む >> |
第一 平家の先祖の系図、また忠盛の上の誉れと、清盛の威勢栄華の事。

右馬之允
検校僧侶よ、平家の由来について聞きたい。簡潔に語っていただけないか。

喜一
お安い御用です。大まかにお話しましょう。まず『平家物語』の冒頭では、『奢り高ぶっては他人を人とも思はないような振る舞いをする者は、最終的に滅びる』という道理の根拠として、唐や日本で驕りを極めた人々の末路が語られています。本文には、六波羅の入道こと太政大臣平清盛公という人の、不法な振る舞いが記されているのです。
さて、その清盛公の先祖は桓武天皇で、その九代目の子孫です。讚岐守正盛の孫、刑部卿忠盛の嫡男にございます。この忠盛の時代までは、先祖の人々は平氏を名乗っておりました。先祖、高望王は平氏の姓を賜り武士になられたのですが、殿上人としての地位は許させられなかったのです。
誤りがあるといえます。高望王は平氏を賜ったのではなく、自ら名乗り始めたというのが定説です。そのため、高望王の子孫が代々平氏を名乗ったと言えます。高望王以前から既に平氏を名乗っていたとは言えません。
そこで忠盛に対して、鳥羽院はこう宣いました。
「得長寿院という寺を建て、また三十三間堂を造って1001体の仏像を安置せよ。その功績への報酬として、どこでも良い、希望する国を与えよう。」
と。そして忠盛は宣旨の通り、三十三間堂と得長寿院を造営、程なくして完成させました。その時、ちょうど但馬国が空いていたため、忠盛に但馬国を下賜されたのです。
鳥羽院は感激のあまり、特別に内裏への昇殿を許しました。忠盛は36歳の時(1135年)に初めて昇殿したのですが、公卿たちは忠盛を妬み、そして憤りました。同年のある時、公卿たちは忠盛を暗殺しようと談合します。しかし、この計画は忠盛の耳に入ってしまいました。
これを聞いた忠盛はこう思いました。
「俺は長袖を着る貴族の身ではない。武士の家に生まれた者だ。思いもよらないことで恥辱を受けるようなことがあれば、それは家にとっても自分とっても不愉快な事態だ。つまるところ、俺は武士だから、身を呈して君主に仕えるというのが本分であろうな。」
と。そう考えた忠盛は事前に暗殺を迎え撃つ準備を整えました。
どのような準備か。それは、参内の始めから大きな鞘卷を用意して、束帯の下に自然なふうに隠したというものです。ほの暗い火の方に向かい、静かに刀を抜いては鬢に引き当てたのでした。この様子が自然であったために、周囲の人々には忠盛が刀が氷か何かで冷やしているように見えており、このために、多くの人が目を見張っていました。
刀を堂々と出すことで、その覚悟と対抗心を敵に見せつけました。と同時に、自然な様子を振る舞うことで、無警戒どころか、いつでも戦える状態というのを悟られないようにもしたのです。
その上、殿上の小庭には忠盛の郎党である平家貞という者が控えていました。家貞は、薄淺黄色の狩衣の下に萠黄威(もえぎおどし)の鎧を着て、弓矢の入った袋を携え、太刀を脇に挟んでいたので、番衆どもはこれを見て怪しく思い、
「そこの布衣(ほい)を着ている者、何者だ。無礼者め。出ていけ、出ていけ。」
と責め立てました。
「そのことです。我が一族にして主の忠盛様を、恐らく今宵、闇に乗じて討ち取ろうしている者がいると伝え聞きました。その様子を見届けようと思いまして、このように参上したわけでございます。ですので、ここを出ましょう、とは申し上げることはできません。」
そう言って家貞は少しも動じずにそこに居座り続けました。敵は、これでは討ち入っても意味が無い、と考えたようで、その夜の闇討ちはなかったのでした。
そのような事があった後、忠盛は御前で舞を披露することになりました。公卿達は忠盛を嘲り笑います。囃し立てながら、「伊勢瓶子(いせへいし)は酢瓶だぞ。」と言ったのですが、これには理由があります。忠盛は以前、都にある屋敷にはあまり住まず、伊勢国に住みがちなことがありました。
そのため、伊勢国の器物になぞらえたのです。さらに、忠盛は眇目(すがめ)であったため、このように公家達は申したのでした。
眇目とは、目が細いことを言います。酢瓶(すがめ)と掛けてますね。
そのようなことがあったわけですが、忠盛とて御前での出来事ゆえ、どうしようもできませんでした。まだその遊びの途中でしたが、忠盛は恥ずかしさのあまりこっそり退出しようとして、横たえて置かれてあったあの刀を、紫宸殿の裏手で、ある人に預けてから退出されたのでした。皆が見ている前での、堂々とした行動でした。
忠盛を待っていた家貞は
「お早いですね、さて、どうなさいましたか。」
と申し上げました。忠盛は、遊びの場での様子を話したい、と思いましたが、もし話せば、内裏にまでも討ち入りに入りそうな性格であったので、
「特別何も無いぞ。」
と答えたのでした。

右馬之允
それにしても、公卿達はつまらないことをしたということですよね?

喜一
その通りです。公卿達がこのような事をするのは、今に始まったことではありません。それで思い出したのですが、昔、權帥(藤原季仲)という人はあまりにも肌が黒かったため、これを見た者どもは、彼を黒帥とあだ名をつけたといいます。
そして、藤原季仲が、忠盛と同じように御前で舞ったところ、公卿たちもまた調子を変えて、「ああ黒い黒い、黒い頭だなあ。誰が漆を塗ったのか」と言って、はやし立てたのです。
また、藤原忠雅公というお方は、10歳ほどの時に父を亡くし、孤児となっていましたが、播磨守という方が娘の婿として迎え、たいそう華やかにもてなされました。この忠雅も、先ほどのように内裏で舞を披露されたところ、公卿たちのいたずらで、
「播磨の米は木賊(とくさ)か、椋の葉か。人の綺羅衣を研ぐのはどっちだ。」
と、からかわれては、はやし立てられたのです。
米を研ぐ様子になぞらえてからかわれています。播磨の米は忠盛を指します。木賊は表面の粗い研ぎ道具。対して椋の葉は滑らかな表面の研ぎ道具でした。人というのは播磨守のことで、粗雑な素材で磨いて、守の着ている衣が美しいとはたまげた。という意味です。要するに、相応しくない身分でありながら、守の庇護を受けている忠雅をからかっているのです。

右馬之允
そのような悪口や無礼を受けても、みな我慢していたのだろう?

喜一
その通りです。昔はそのようなことがあっても、表立った問題にはなりませんでした。しかし当時は、将来これが原因でどうなってしまわないかと、みなが、忠盛が面目を失った時には気を遣ったと聞いております。

右馬之允
して、その後はどうなったのだ?

喜一
さて、話を続けましょう。忠盛の退出劇をそのまま放っておくこともできず、殿上人一同、忠盛のことを天皇に訴え申し上げました。
その内容はというと、
「忠盛は、数いる武士のなかでもとりわけ帯刀して内裏に出入りし、武具を持ち込んでおりました。これは特別な事情がない限りあり得ないことです。この忠盛は、一族郎党だと称して武士を内裏の庭に呼び寄せたり、腰に帯刀したまま節会の席に列席したりするなどしました。この二つはいずれも、前代未聞の狼藉でございます。罰を科すべきでございましょう。官位を剥奪するのが相応です。」
というものでした。このように、真っ黒な訴えを申し上げたのです。
天皇も非常に驚かれ、すぐに忠盛を召してお尋ねになりました。
「これは何だ。」
「まず、郎党を庭まで伺候させたことについては、全く私が承知していたことではございません。ただ、最近、御前の方々が私に対して何かと侮辱されている子細ありとの話を聞きました。私を助けようと、長年仕えてきた家臣が私に知らせず、ひそかに参ったものでございます。私の力では止めるに及びませんでした。もし、それでもなお罪があるとお考えならば、その者を召し出しましょうか?次に、刀の件ですが、それはすぐにその場で身内に預けておりました。この刀をお召し出しすよう命を下し、実物をご覧になった上で、罪の有無を判断なさいませぬか。」
天皇はこれを聞いて、
「なるほど、それはもっともなことだ。では、その刀を取り寄せよ。」
と仰せになりました。そして実際にご覧になると、黒塗りの鞘巻、中は表面に銀箔が貼られているだけの木刀でした。これは、忠盛があの場での恥辱を免れるために、刀を携えているかのように見せかけたのです。
公卿からの召し出されることを考えて、本物の刀ではなく木刀を帯びていました。
これを見た天皇は
「この策は弓箭を携える者(武士)の心得として非常に見事なものだ。」
と仰せになり、さらに
「郎党が庭に伺候したことに関してだが、これは武士の郎党にとっては習慣であり、これは忠盛の罪ではない。」
と仰せになりました。つまり、大いに感心なさったのです。天皇は、忠盛に罪を科すことなど夢にも思っていませんでした。

右馬之允
さてさて、忠盛という人は賢い人であったのか?

喜一
無論よ。忠盛の利口話はこれだけだとお思いか?実は忠盛という人は、文武両道の人でした。あるとき、忠盛が備前国から都へ上った際、天皇から
「明石の様子はどうだ?」
とお尋ねになりました。それに対し、忠盛はこう答えたのです。
「有明の月も明石の浦風に揺られて、波ばかりが寄ってくるように見えるよ。」
この返答に、天皇は大いに感心されたのでした。

右馬之允
それで、忠盛は何歳まで生きたのだ?

喜一
58歳で亡くなられました。清盛は忠盛の嫡男でしたので、清盛はその跡を継ぎ、次第に官位も昇進、ついには天下を一人でほしいままにするほどの権勢を持つようになったのです。

右馬之允
なあ喜一。次は清盛の話も聞きたいよ。

喜一
私が疲れない限り、いくらでも語りますよ。

右馬之允
いやはや、このような話であれば、七日七夜聞いても飽きることはありませんぞ。

喜一
それでは話しましょう。清盛は家督を継いで以来、先ほど申し上げたように、その極めた権勢や位に、肩を並べることができる者は一人もいませんでした。さて、清盛が51歳の頃、病を患い、命も定まらない状況に陥りました。病気平癒を祈るためでしょうか、出家して入道となり、法名を淨海と名乗るようになりました。
天がこの行いを受け入れた証なのでしょうか、病はたちまち癒えました。人々が清盛に付き従う様は、まさに吹く風が草木をなびかせるようであり、また世の人々が清盛を広く仰ぎ敬う様は、まるで降る雨が国土を潤すようでした。
そのため、清盛のご一族と言えば、公家でも武家でも、誰一人として、顔を合わせたり横に並び立とうとしたりしませんでした。清盛の義理の弟である時忠卿に人物に至っては、
「我が一門に属していない者は、皆、人のように見えるだけで人ではない」
とまで申したほどです。
そのため、あらゆる人が清盛一門との縁を結ぼうと努めました。平家の時勢があまりにも大きかったため、衣紋や烏帽子の被り方までも、
「六波羅様(清盛の家)がされている。」
と言えば、天下の人全てがこれに倣うほどでした。
まことに、なんという時勢でしょう。たとえ高位の人であっても、従者から陰口をたたかれることは避けられません。しかし、この清盛の栄華が極まった時代には、清盛のちょっとした油断や怠慢に対してさえ、批判を口にする者はいませんでした。
その理由は、清盛の策略にありました。14歳から16歳の少年たちを300人集め、頭髪を禿髪にして赤い直垂を着せて使い走りとしたのです(少年で構成された偵察団、禿(かむろ)のこと)。禿は都中に溢れかえり、あちこちを往来しました。
もし平家について悪く言う者がいれば、その言葉は誰かが必ず耳にしました。300人いる禿のうち誰か一人がその噂を聞きつけると、すぐに仲間に触れ回り、その家に乱入しました。そして財宝や生活道具を悉く奪い取り、さらには平家を非難したとして、捕らえては六波羅へ引き渡しました。
このような状況であったため、たとえ平家の悪事を目にしたり心で知っていたりしても、それを言葉で表現することはできませんでした。清盛に仕える禿といえば、それだけで道行く馬や車までも避けて通るほどで、また、内裏の御門を出入りする際にも、何者だ、と咎める者もいないほどでした。都でどれほど威勢のある人物であっても、清盛と禿たちには目を背け、何事も見なかったかのように振る舞ったといいます。
この清盛は、己自身の栄華を極めたことはもちろんのこと、一門も繁栄を遂げたため、世の中は、もはや平家以外の人はいないようにも見えたといいます。清盛には8人の姫君がいらっしゃいましたが、各々、良き縁談に恵まれました。その中の1人は后にまでなりました。皇子をお産みになった後は建礼門院と呼ばれました。このように、平家の威光と人々の崇敬は、言葉では言い尽くせないほどであったのです。

右馬之允
それで、清盛の嫡男はなんと言うのか。

喜一
長男は重盛と申します。次男は宗盛、三男は知盛です。この3人の威勢は、誰がどれほど優れているとも言えないほどだったといいます。
(第一。終。)
| 一覧に戻る << | 第二を読む >> |