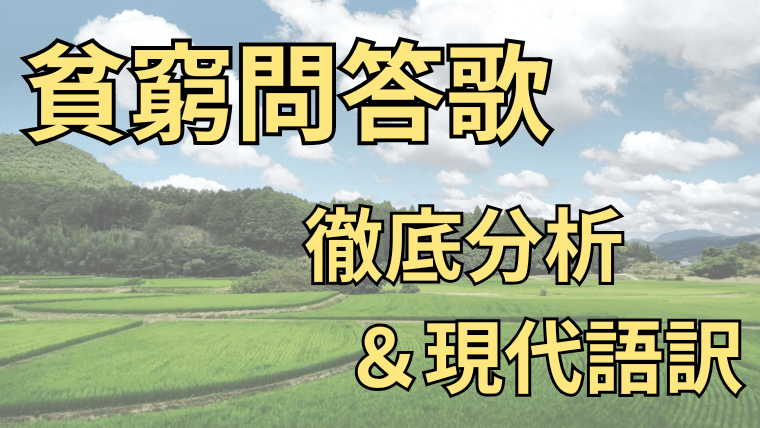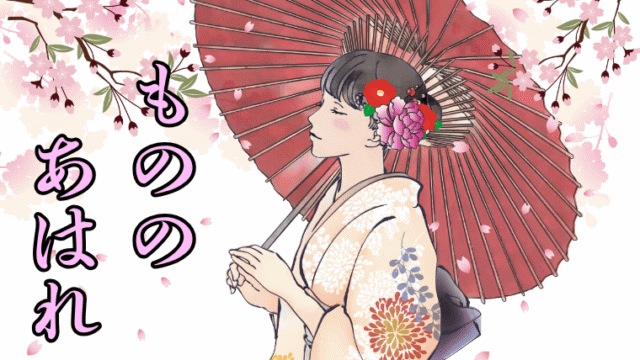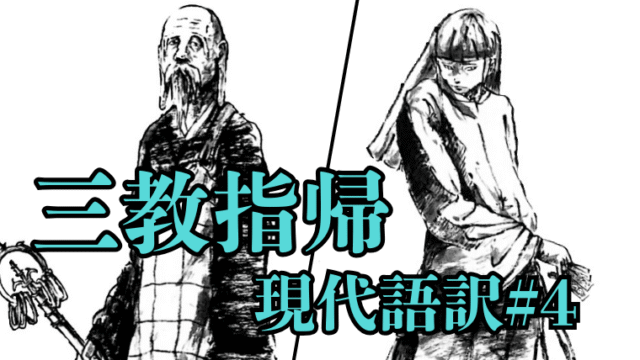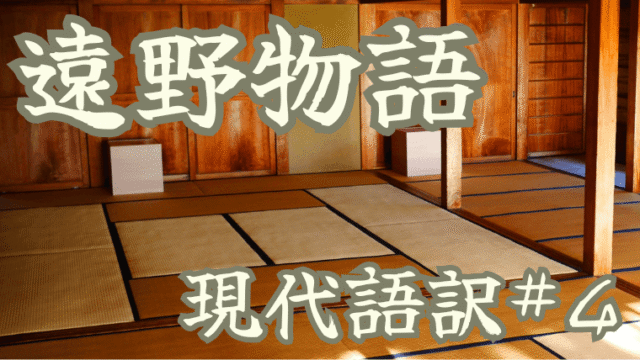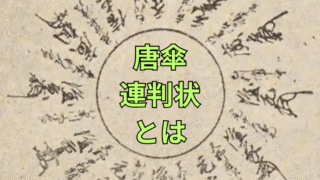貧窮問答歌の解説
長歌について
「貧窮問答歌」とは、『万葉集』の五巻に収録されている長歌です。長歌にも規則があります。
- (5・7)音を3回以上続ける
- 最後を(7)音で締める
- その反歌として最後に1首を添える場合がある
『万葉集』には全部で1400首の和歌が収録されていますが、そのうち長歌が約250首収録されており、全体の17.9%を占めています。
「貧窮問答歌」も上に挙げた規則に従いますが、中盤で字足らずと字余りが何度か発生しています。
なぜ詠まれたのか?
皆さんは、そもそもなぜ「貧窮問答歌」は詠まれたのか、考えたことはあるでしょうか。実は不可解な点が一つあります。それは、
自分が治める国の窮状を詠むなんて、自身に不利益ではないのか?という疑問
です。
作者の山上憶良(~733)は筑前国を治める国司として晩年に派遣されました。当然、その国民(筑前国)が貧しい暮らしをしているという事実が明らかになれば、管理職としての資質が問われるのは想像に難くありません。自国民の窮状が公になることは自身に不都合なことであるにも関わらず、これを題材にした歌をなぜわざわざ歌集に書き留めたのか?その理由が分からないのです。
というわけで、「貧窮問答歌」を分析していきましょう。
歌の分析
よく、農民の苦しみを問答形式で詠んだと言われますが、多くの人が誤解している点が2つあると私は思っています。
- 最初から最後まで山上憶良の自作である
- 民衆視点の歌ではない!!!!←超重要
の2点です。
①山上憶良の作である理由
農民の惨状を、と言いながら、歌詞の一部の言い回しや暗喩表現から、農民が歌った歌ではないことが分かります。
- 竈の煙は立つことがなく(仁徳天皇の逸話)
- 短いものを端切るように
- 天地は広いというが、私から見れば狭いものだ。太陽や月は世界を明るく照らし、草木に英気を与えてくれるというが、私にも照らしてほしいものだ。
- 海松(みる)のように
- ぬえ鳥が物悲しそう鳴くように
漁師でなければ、まず海松なんて見たことないでしょう。『貧窮問答歌』は漁師にクローズアップして詠まれた歌ではないため、そうでない暮らしをしている人が海松を使うと情景の想起が薄れてしまい、歌のバランスが崩れてします。
また、「天が、地が、万物を支配している、我々に秩序をもたらしてくれる」という部分ですが、この考えは、天道思想といい、知識人に広まっていた思想になります。これの影響により官吏などの間では、天災を「為政者の責任である」と捉えるようになりました。
そのため、「天が、地が、万物を支配している、我々に秩序をもたらしてくれる」という一文は、官吏視点の思考だといえるのです。
民衆視点であれば、天災が起きれば農耕儀礼に思考が向き、「国司のせいだ!」とはなりません。
②民衆視点の歌ではない
民衆視点の歌ではないことは上で述べた天道思想から十分に理解できますが、これ以外にも根拠となる部分はあります。
まずはこの歌詞。
我を除(お)きて、人は有らじと、誇ろへど、
「自分を除いて、優れた人はいないだろう」と誇らしく思う(そんな自分は貧者)
という部分です。搾取される側である民衆がこれを思うのはかなり傲慢だと思います。
となると、家の様子や暮らしを述べているこの「貧窮問答歌」は、ある程度地位のある者の窮状を表していると考えることができるのではないでしょうか。
であれば、身分に関わらず国全体が窮状に立たされていた状況といえましょう。
歌詞には具体的に生活苦が挙げられています。
- 潰れたような、傾いたみすぼらしい家に住んでいる
- 土の上に直に藁を敷いて
- 飯を炊くことすら忘れてしまった
- あるだけの布肩衣を全部重ね着しても寒い
見るに堪えない窮状です。
最後に補足ですが、私は「貧窮問答歌」についてこれまで、「”民衆”の窮状を~」というふうに解説してきました。ここで解説したように、農民視点の歌ではないという意味を含めてそうしています。
時代背景
「貧窮問答歌」が作られた時代は天平3年~天平5年(731~733)と推測されています。これまで見てきたような窮状になったのは何故でしょうか。
その謎の手がかり、723年「三世一身の法」から、当時の民衆の生活を逆算してみましょう。
そもそも、「三世一身の法」が制定された理由は、田畑を誰も開墾しようとしなかったからです。その原因は、口分田の仕組みにあります。
6歳以上民衆に対して、国から貸し与えられる田のこと。所有者は国のため、借主が死んだ場合、国に田を返還する必要がある。
民衆からすれば、「頑張って開墾したところで、最終的に手放すことになるなら、耕す意味など無い。」と思うわけです。
当時、稲を基準にした租という税金が主流でした。口分田が減れば稲作の作付面積は減り、収穫量も減り、結果的に、税収も減る。
国としても、民衆に田畑を積極的に開墾してもらう必要がありました。そこで打ち出された政策が722年の百万町歩開墾計画です。農具や食料を支給する代わりに良田を開墾させる計画でしたが、誰も従わないことが即発覚。そして翌年723年に「三世一身の法」が出されました。孫世代までは所有権は借主にあるという施策です。農具や食料支給といった一時的な恩恵では民衆の心はつかめなかったようです。
- 722:百万町歩開墾計画農具や食料を支給する代わりに良田を開墾させる施策。即失敗に終わる。
- 723:三世一身の法孫世代まで口分田の所有権を借主に与える施策。大きな効果はなかった。
さて、次々と土地改革を行う中央政府ですが結果的に失敗に終わります。主な要因は
税負担が重すぎて、浮浪・逃亡が大量発生したため。
でした。
浮浪と逃亡の違いについては説が2つありますが、とにかく「逃げた者」と覚えておいてください。
| 説① | 逃亡 | 民衆視点での「逃げた者」 |
| 浮浪 | 管理者視点での「逃げた者」 | |
| 説② | 逃亡 | 賦役(調・庸・雑徭)を欠いた者 |
| 浮浪 | 賦役を欠かない者 |
この事実は実際に、史料『山背国愛宕郡出雲郷雲上里計帳』からも読み取れます。この史料は神亀三年(726)のもので、「三世一身の法」施行の3年後の史料となります。つまり、この史料は、一連の土地政策の失敗を裏付けているのです。
結論、民衆の苦しみはこのような国家事業の失敗に起因しているといえます。
筑前国というところ
筑前国とは、現在の福岡県に位置します。厳密には、秋月~博多~北九州西部の領域となります。秋月は、明治時代に秋月の乱があった場所ですね。神風連の乱と並んで、士族の反乱として扱われています。博多、北九州は現在でも大都市なので説明するまでもないでしょう。
さて、この筑前国ですが、超重要な施設と歴史を持っています。それは、「大宰府政庁」と「水城・大野城(白村江の戦いの対策)」です。
博多には白村江の戦いや新羅滅亡から逃れた大陸の貴人、民衆が多く流れ込みました。朝鮮半島では「鬼」という名がよく使われていました。福岡県では「鬼」がつく名字(「鬼塚」や「鬼瓦」)が集中しているのは、これが遠因となっているとも言われています。
防人が置かれたり、水城や大野城を築いて侵攻対策したり。。
そのような国難まみれの国、すごく辛いわけです。国家をひとつの家と捉える考えも当時ありましたから、そのような国の政庁が「大宰府」という名になったというのはしっくりくるのではないでしょうか。これは俗説とも本当とも言われて、定かではありません。
さて、当時この大宰府長官は大友旅人という人物でした。西国を司る官庁なので、筑前国司の山上憶良は大伴旅人の部下という関係にあたります。そしてこの二人、かなり仲が良かったと言われています。
山上憶良からすれば、大伴旅人は上司にあたるので、国の現状は訴状や公文書として報告しないといけません。しかし、山上憶良は、あえて『万葉集』を選んでいます。その理由は、これまで説明してきた内容から推測することができます。これまでの話を全てまとめましょう。
結論
これまで説明してきたことを踏まえると、自身の任国の窮状をわざわざ歌にした理由は以下の通りであるといえます。
国内の窮状を、為政者に婉曲的に訴えるため。
訴状ではなく歌にしたのは、歌集であれば、役人に広く伝えることができるため。
700年代初頭、重税や土地制度の揺らぎによって、国内の窮状がより深刻化しました。これは何も筑前国に限った話ではありません。だからこそ、任国の窮状を詠んでも特別不思議ではなかったのでしょう。
そして、この窮状の解決は、国司という中間管理職にはどうすることもできない問題であるため、国司はより国家運営に発言力のある上級官吏に訴える他ありませんでした。
訴状や意見封事ではなく歌にその実態を込めたのは、上司にあたる大伴旅人と、役人として以上に文化人としてのつながりがあった可能性が考えられます。仮にそうでなくても、歌集を手段として訴えることは、情景を誘いつつ、国内の窮状を広く伝えることができ、方法としては非常に有効です。それに、歌詞中に天道思想を持ち出しているのも、これの意味が理解できる役人に向けて歌ったものだといえましょう。
また、大陸の影響を良くも悪くも受けてきた「とても辛い」こと大宰府のある筑前国だからこそ、歌にするだけの価値が、説得力があったかもしれません。必ずしも関係ないとは言えないはずです。
さて、これらを踏まえた上で「貧窮問答歌」に触れてみましょう。きっと、見方が変わっているはずです。