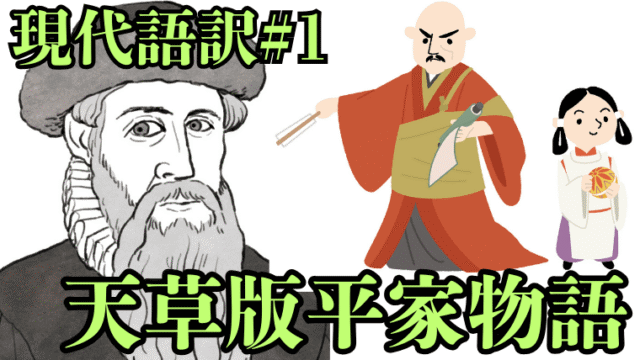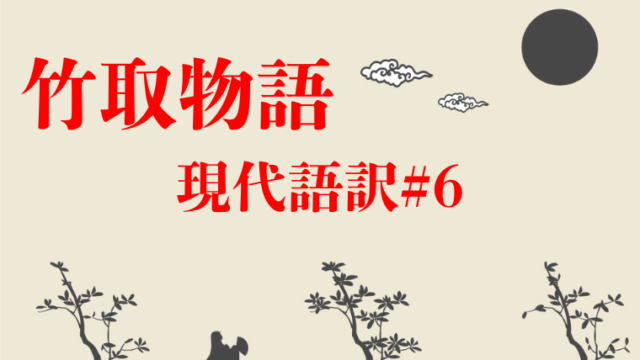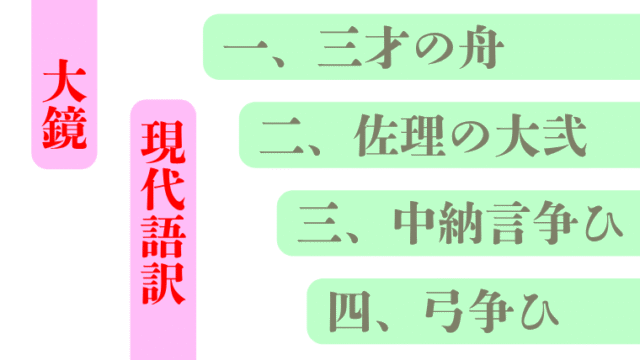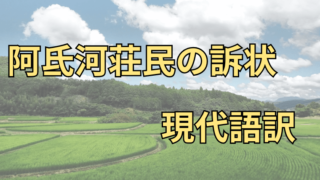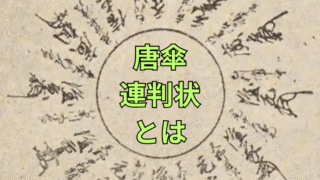本文(続き)
③小さな家での暮らし
この小さな家でも必要最低限のものがあれば快適に過ごすことが出来る。春は藤の花が一面に咲き誇り、西方浄土の様子が浮かばれる。夏はホトトギスが冥途の案内役のような鳴き声をし、秋はひぐらしが、はかない世の中を悲しんでいるように鳴く。冬は雪が積もっては消えゆくさまが人間の罪が生まれては消えるの如く感じられる。念仏を怠けるときもあるが、咎める者は誰もいないし、戒律を破るような誘惑もない。朝には船を眺めながら満沙弥の風情を感じ、夕方には白居易の「琵琶行」を演奏する。自分で演奏し、自分で詠い、自分で心を穏やかにする、そんな日々を過ごす。また、友となった子供と共に伏見や鳥羽を歩き、蝉丸や猿丸太夫のといった歌人の墓を見に行ったりした。夜は庵の外から月を眺め、今は亡き旧友を偲び、夜に光る蛍は宇治の夜漁の明かりを思い出させた。
災害が起きれば人は移動し、新たな住まいを設ける、再び災害が起きればさらに人は移動し、新たな住まいを設け・・・。というふうに無常なのは人の心だけでなく、生活に必要なもの、身の回りのもの全てが無常であるといっているのです。
本文では、春夏秋冬、朝夕といった定めない環境に宗教的な感性と文学的な教養をもって、田舎暮らしを五感で感じ取っています。晩年に至り、極楽浄土を思う気持ちが以前に比べ大きくなっていったのかもしれません。また、亡き旧友や、かつて住んでいた宇治を思い返すなど、人生を振り返っていることからも、山の情緒と共に晩節を全うせんとする様子が感じ取れます。
原文では、「潯陽の江」という表現があるのですが、これは白居易を意味しています。白居易は潯陽の揚子江のほとりで「琵琶行」を作ったそうです(下記参考)。
竹村則行1981「呉偉業「琵琶行」における白居易「琵琶行」の受容」『九州大学中国文学会』10 146-177頁
④人生とは何か
最後の章には、特に人の移動と住まいを中心として人生論が展開されています。
5年が経過した。この仮住まいにも枯れ葉や苔が生えている。都からの便りを聞くに、身分の高い人も随分と亡くなられたという。この住まいは手狭だが、寝床はあるし昼は座るに足る広さもある。自分の生き方をわきまえたからこそ、穏やかに生きる方法を見つけることができたのだ。
人は必ずしも自分のために家を建てているとは限らない。親族や主君、財宝、牛馬のためなどよくある。しかし、私は自分のために家を建てた。妻子もおらず、従者もいないからだ。家を広くしたところで誰を泊まらせ、誰が住まそうか。友と言える人間だって、結局は金持ちや見た目といった外面で選ぶものが多い。召使いにしても、報酬が多い主人を選ぼうとするし、情けや愛で繋がっているわけではない。
ならば、自分で事を済ませてしまえばよい。自分の足で歩けば、馬や牛に気を使う必要はない。歩きたい時に歩き、休みたい時に休む。人に苦役を強いるなどどうしてできようか。衣食も同じことで、粗末な素材であっても、それで十分生きながらえることは出来る。みすぼらしい姿で生活しても、誰ともすれ違うことはない。
勘違いしてほしくないのだが、私自身の今昔の経験が、この生活に満足感を与えているのであって、無理にこの生活を強いているわけではないということを断っておく。仏教の教えに「三界唯一心」というのがある心の持ちようで何事も決まるという教えである。何も臨まなければ、最小限の生活品で満足できるということである。もし私の考えを疑うのならば魚や鳥の生き様を見ろ。魚でなければ水の良さは分からないし、鳥は都ではなく林を求めて飛んでいく。私の閑居も同じことなのだ。すまない人にこの気持ちはわかるはずもない。
今月を見ると、山の端まで下りてきている。私の人生も終わりに近く、三途の闇を思う頃か。仏教の教えには、執着を持つなというものがある。私はそのつもりでいたが、この閑居を好んでいる以上、これもまた執着ではなかろうか。今までのことを振り返ってきたが、そもそもこの住まいに移り住んだのは出家したためである。しかし、私は煩悩に染まった聖人となっている。なぜこうなってしまったのか、自分に問うても答えはでない。なので、ただただ、「阿弥陀仏」と両三篇唱え終わりにした。1212年、三月の終わりごろ、蓮胤、外山の庵にてこれを記す。
全体を通して無常観をテーマとして話が進んでいることを考えると、様々な災害を経験する前の時代は、物事は変わらないものである、といった考えが当時の常識であった可能性が考えられます。貴族が栄華を極めた平安時代は約300年続いていました。永遠に同じ世界が続くと捉えても不思議ではありません。実際、戦後たった80年しか経過していない時代を生きる我々ですら、この生活が死ぬまで続く、何だかんだ大丈夫だと思っているのですから。
そんな平安時代は、貴族から武士の時代へ移り変わる時代の転換期でもありました。いち個人の力ではどうしようもない時代の流れ、自然の力、これらが短期間に降りかかれば、無常観を抱かずにはいられません。
まとめ
よく、「『方丈記』は災害をテーマにした最初の文学作品だ。」といわれますが、確かにそれは間違ってないとは思います。実際、災害に関する話題を全体の50%占めています。しかし、序文と最終章の内容を考えると、鴨長明は災害を文学にしようとしたわけではなく、無常観に至るきっかけであった災害の話をしただけと考えるほうが適当ではないでしょうか。災害の悲惨さについてではなく、災害から見出した人生論の話をしているからです。
結論、人間の力ではどうしようもない自然の力に対して、人間の力では逆らうことのできない時代の流れに対して、人はどう考え、どう人生を切り開くか、その根底に無常観があり、そこから何かを見出す。これが、今の私たちに活かせるメッセージだと私は思います。
- 鴨長明の人生論は、「周りの視線は気にせず、自分が満足する生活をするといい。」というもの
- 無常観の原因は、永遠の栄華と思われた都が不安定になったため
- 見栄を張ったり無理に広い家にしたりしないで、自分の人生観に合った住まいを見つけることが大切である
その他参考
須藤敬1985「『保元物語』形成の一側面:多近久と仁和寺」慶応義塾大学国文学研究室
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |