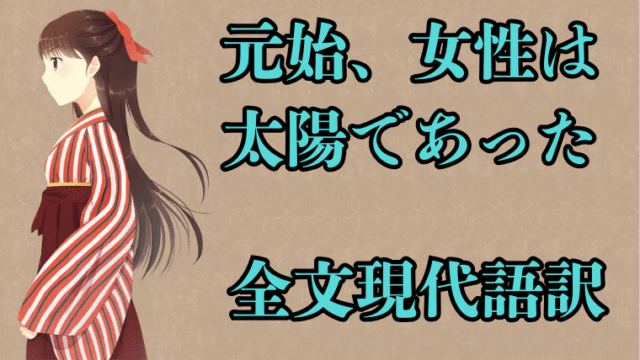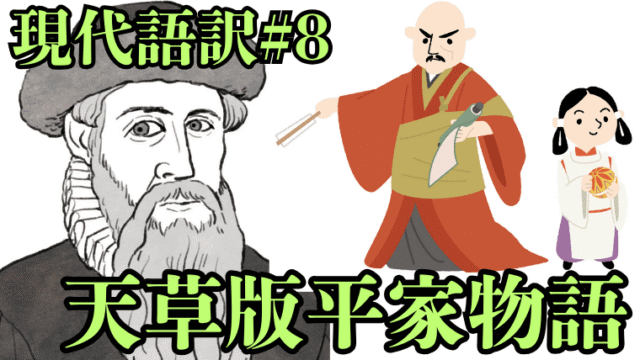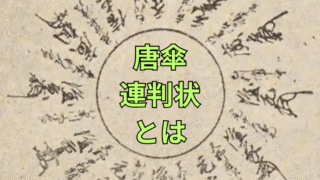現代語訳
厨川柵の戦い(天然の要害)
14日、官軍は厨川柵へ進軍した。15日の酉の刻(18時ごろ)に到達し、この柵と隣接する嫗戸(おうど)柵の2柵を包囲した。2柵の距離は約7~8町(約770~880m)ほどである。官軍は陣形を整えて鶴翼の陣をとり、一晩中これを維持した。
厨川柵は、北西側に広大な沢があり、北東に流れる北上川と北西に流れる木賊川によって遮られている。川岸の高さは三丈(約9メートル)以上で、壁のように立っており、通れる道は無い。その内部には柵が築かれ、防衛に特化していた。柵の上には櫓が設けられ、精鋭の兵が警護に当たっていた。さらに、川と柵の間には濠が掘られ、底では刃物を逆さまにして設置していた。地上には鉄片が撒かれていた。また、遠くの敵には弩が、近くの敵には石が放たれるようになっていた。
官軍が柵の下まで攻め行けば、賊軍は熱湯を浴びせたり、鋭利な刃物を振って殺したりした。官軍が到着した時、櫓の上の兵が官軍を招いて言った。
「戦いたい者は来い!」
と。更に数十人の女が櫓に登っては歌を歌って官軍を煽った。これを見た頼義将軍は不愉快に思ったのであった。16日卯の刻(6時頃)に官軍は攻撃を開始した。一日中、積弩を乱れ打ちした。飛び交う矢や石は雨のようであった。城内の賊軍は官軍の猛攻を堅く守り抜き、ついに官軍は柵を攻略できなかった。官軍の死者は数百人に上った。
厨川柵の戦い(天啓)
17日未の刻(14時頃)、頼義将軍は土木兵に命じた。
「分かれて周辺の村落に入り、民家を壊して木材を運び出し、これを使って城の堀を埋め立てよ。また、各自で萱草を刈り取って、それを河岸に積み上げよ。」
と。兵は周辺の村の民家を壊して木材を運び、萱草を刈り集めて積み上げた。その量はまるで山のようであった。頼義将軍は馬を降りて朝廷の方向を仰ぎ見、深く誓いを立てた。
「徳がまだ衰えてない漢の時代には、泉が校尉(宮城の防衛や西域鎮撫などに当たった武官)の節義に応じて湧き出したという。今、天の威厳は新たに輝いている。必ずやこの大風が我が老臣の忠義を助けてくれるだろう。伏して願う。八幡三所の神々よ、風を起こし、火を吹き、あの柵を焼き尽くしてくれ。」
と。頼義将軍は自ら松明を持っては、これは神の火である、と称して、柵へ向けて投げつけたのだった。このとき、一羽の鳩が現れ、軍陣の上を飛び過ぎて行った。頼義将軍はこれを吉兆と捉え、再び深く拝礼した。すると突如、暴風が吹き起こり、松明の火は、まるで煙と炎が飛び交うように広がったではないか。これまで官軍が放った無数の矢が、柵正面の櫓に蓑毛のように刺さっていたのだが、飛び散る火炎がこれら矢の羽に燃え移ったことで、櫓や周囲の建物に急速に燃え広がったのだ。
城内の男女数千人は一斉に悲しみの涙を流し、潰乱した。ある者は青い川に身を投じ、ある者は白刃で己の首を刎ねた。官軍は川を渡り攻めた。決死の賊軍数百人は甲冑を着て刀を振るい、包囲網を突破してきた。死を覚悟し、生還しようとする心意気はない。屍兵と化した賊軍から傷を受けたり、死したりした官軍は多かった。武則は兵に命じた。
「包囲網を解き、全ての賊徒を柵から出させよ。」
と。包囲網を解いたところ、たちまち賊徒は、外に出ることができるかもしれない、と心付き、戦うことなくまっすぐに外を目指した。ここを官軍は横から射撃して残らず殺したのである。官軍の勝利であった。
厨川柵の戦い(戦後処理)
この策の中で、経清を捕らえることに成功した。頼義将軍は経清を召して尋問した。
「お前の先祖は代々我の家来として仕えてきた。そうでありながら近年、朝廷の威厳を軽んじ、本来の主人である我を蔑ろにした。大逆非道である。今ここで正式にお前を裁く。覚悟は良いな?」
と。経清は頭を垂れて何も言わなかった。頼義将軍はこれを不快に重い、意図的に錆び付いた刀で経清の首を斬った。経清に少しでも苦痛を味わせるためである。この時、経清は少しでも抵抗せんと、貞任の刀を抜いて官軍を斬った。官軍は鋒で経清を刺して瀕死に追い込み、その体を大楯に乗せて6人で担いで頼義将軍の前に置いた。身長は六尺(約180cm)を超え、腰回りは七尺四寸(約220cm)。堂々として立派な体躯で、皮膚は白く肥えていた。頼義将軍は貞任の罪を責め、その場で処刑。また、弟の重任(通称北浦六郎)も処刑した。
ただし、宗任だけは混乱に乗じて深い泥の中に身を投じ、逃げられてしまった。貞任の子である千世童子は13歳である。美しい容姿で、柵の外に出ては甲冑を身に付け奮戦した。その戦ぶりは祖父頼時や父貞任に通じる勇敢さを見せた。頼義将軍は哀れに思い、千世童子を宥めて助けようとした。武則は進言した。
「小さな情に囚われ、大きな害を見逃すべきではありません。」
と。将軍はその言葉に頷き、結局千世童子を斬首した(貞任は34歳で命を落としている)。城内の美女数十人は皆絹織物をまとい、金の装飾で着飾っていた。彼女たちは煙の中で悲しみに泣き叫んだ。捕虜として連れ出され、それぞれ兵に与えられた。後のことは言うまでもない。ただし、則任の妻だけは違った。柵が破られた際、則任の妻は3歳の息子を抱えながら夫に向かって言った。
「あなたが死ぬというのに、私一人だけ生き残るわけにはいきません。どうかあなたの前で先に死なせてください」
と。そして、子どもを抱いて深い淵へと身を投じた。まさしく、烈女(信念を貫き通す女性)と言うにふさわしい女性であった。その後すぐに、貞任の伯父安倍為元(字は赤村介)と貞任の弟家任が降参した。また、数日後に宗任ら9人が投降した。
首級
12月17日の国解にはこう書いてある。
『討ち取った賊徒は、安倍貞任、安倍重任、藤原経清、散位平孝忠、藤原重久、散位物部惟正、藤原経光、藤原正綱、藤原正元である。投降した賊徒は、安倍宗任、安倍家任、安倍則任(出家投降)、散位安倍為元、金為行、金則行、金経永、藤原業親、藤原頼久、藤原遠久である。』
と。貞任の家族や遺族については詳細不明である。ただし、正任はこの時点ではまだ投降していなかった。宗任の伯父で僧侶の良昭はすでに出羽国にて国守源斎頼によって捕えられた。正任については、出羽国の清原光頼の息子で、「大鳥山太郎」と呼ばれる清原頼遠のもとに隠れていたが、その後、宗任が降伏したという知らせを聞き、姿を現して投降した。合戦のことである。義家は矢を放てば必ず、敵兵を討ち取った。後日、武則は義家にこう言った。
「私はあなたの弓の威力を試してみたい。」
と。
「よろしい。」
義家はこれに応えた。そこで、武則は頑丈な甲冑を三つ重ね、樹の枝に吊るした。義家が矢を一本放つと、三重の甲冑はたった一度で貫通したのだった。武則は
「これは神の力による奇跡だ。とても人間技とは思えない。このような力があるからこそ、武士たちはあなたに帰伏しているのだ。」
と、大いに驚いた。また、義家の弟義綱も非常に勇敢で馬術や弓術に優れており、その才能は兄に次ぐほどである。康平6年(1063)2月16日、安倍貞任、安倍重任、藤原経清の首級3つが京都に送られた。その光景は壮観で、都の通りは車の車輪がぶつかり、人が肩をすり合うほどの混雑ぶりであった(詳細については別の書に記している)。首級を献上する使者には、貞任に仕えていた降伏者が選ばれたのだが、彼らは『首級の髪を整える櫛がないではないか。』といったことを理由に、首級の差し出しを遅らそうとしていたようである。首級を催促しに来た使者が言った。
「お前たちは私用の櫛を持っているではないか。それを使って髪を整えよ」
と。そこで担夫(荷物運び担当の従者)が櫛を取り出し渡して、元家臣らは主君の髪を梳き始めた。涙を流し、声を詰まらせながら言う。
「我が主君が生きておられた時、その御威光は天高き空のように崇高なものでありました。どうして汚れた櫛で主君の御髪を梳くなどという畏れ多いことができましょうか。この悲しみは耐えがたいものです。」
と。その場に居合わせた人々は皆、この光景に涙を流した。担夫のような立場の者でさえも、元家臣らの忠義心を知るには充分な出来事であった。
論功行賞
2月25日、除目(官職の任命儀式)の際に論功行賞も行われた。
源頼義は正四位下に叙され、並びに伊予守に任命された。源義家は従五位下に叙され、並びに出羽守に任命された。
源義綱は左衛門尉に任命された。
武則は従五位下に叙され、鎮守府将軍に任命された。
首を京に献上した使者、藤原秀俊は右馬允に任命され、物部長頼は陸奥国大目に任命された。
これらの論功行賞によって、一同は目に見えるかたちで天下の誉れとなったのである。
古代中国は強大な存在であった戎狄(異民族の総称)を制することができなかった。それ故に、漢の時代には、平城で包囲された劉邦を救うため、呂后は屈辱的な態度を取らされたという事件が起きている。我が国では古の時代にしばしば大軍を出して国内の様々な異民族討伐を行ったが、中国と違って大敗したことは一度もない。かつて、坂面伝母礼麿(阿倍比羅夫)は蝦夷、粛慎に降伏を促し、奥六郡全ての異民族を服従させた。ただ一人、永久に讃えられるべき名声を残した。彼はまさに東北地方に君臨した神の化身、希代の名将といえよう。
それから200年以上が過ぎ、ある者は猛将として一戦の功績を立て、ある者は謀臣として優れた計略を振るい、その名を残した。しかし、ただ一つの一族、ただ一つの城を服従させただけで諸異民族を討伐するという威光を示した者はいまだいなかった。源頼義は、自ら矢や石が飛び交う戦場に身を投じ、異民族の勢力を挫いたのだ。どうして世に名を残す特別な功績ではないと言えようか、いやそんなことはない。郢支(異民族長の総称)の単干(異民族指導者の総称)を討ち取ったり、南越王を討ち取ったりした漢の兵の功績に、どうして源頼義の功績が劣るだろうか。
今、国解の内容を、人々の語り伝えに基づいて抄録、一巻にまとめて注釈を加えた。とはいえ、私は奥六郡から遠く千里の地にいるため、この記録には必ず多くの誤りがあろう。真実を知る者が訂正してくれることを願うのみである。
(『陸奥話記』終)
| 前に戻る << | 最初に戻る >> |