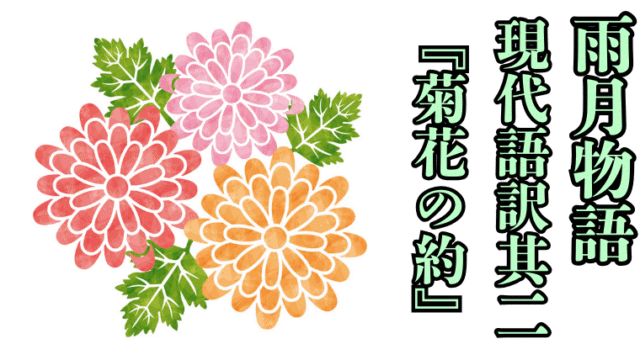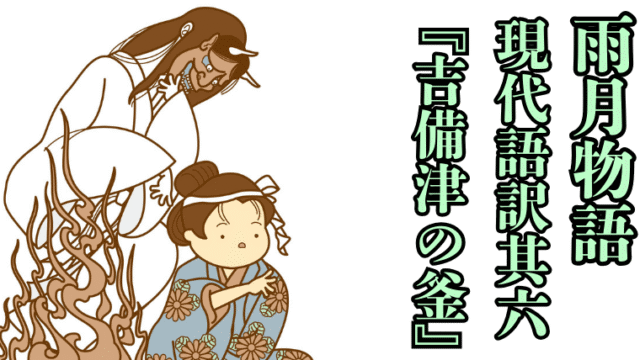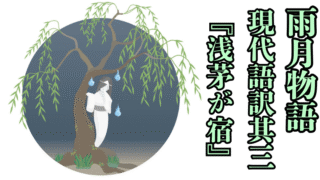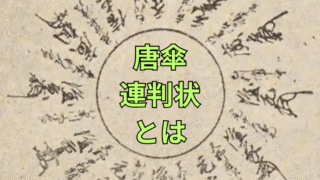現代語訳
1句目
雪なから山もとかすむ夕かな(宗祇)
行水遠く梅にほふ里(肖柏)
夕方に雪が残る水無瀬山の麓を見ると、春霞でかすんで見えるよ。春に移り変わっているのだなあ。
雪解け水で咲いた梅の香りが遠くから漂うよ。遠い昔のことが思い起こされる。
2句目
河風に一むら柳春見えて(宗長)
舟さすおともしるきあけかた(祇)
河を吹き渡る風が一叢の柳を揺らして過ぎ去っていく。春らしさを感じるよ。
明け方に舟を漕ぐ音がはっきりと聞こえた。やはり春が来たのだな。
3句目
月やなおきり渡る夜に殘るらん(柏)
霜おく野はら秋は暮れけり(長)
霧がなお立ち込めていて月が見えない。夜空に隠れているのだろうか。
その翌朝野原を見ると、草葉に霜が降りている。秋は暮れてしまっているな。
4句目
鳴くむしの心ともなく草かれて(祇)
かきねをとへはあらはなる道(柏)
鳴いている虫の気持ちなど知らずに草木は枯れてしまった。垣根に沿って虫の音を尋ね歩くも、草木は枯れて地面が露わになっているだけだ。
5句目
やまふかき里や嵐にをくるらん(長)
なれぬすまゐそ寂しさもうき(祇)
この山奥にある里では、嵐は季節に遅れて吹くのだろうか。
慣れない住まいに住んでいる今、これまで慣れ親しんだ季節が感じられず寂しく思うよ。
6句目
今さらに獨有身を思ふなよ(柏)
うつろはんとはかねてしらすや(長)
今更老いた独り身のことを嘆かわしく思うなよ。
花が散るように、人生もいずれ終わることなど、予てから知っていたではないか。
7句目
おき侘る露こそ花に哀れなれ(祇)
また殘る日の打ちかすむ影(柏)
露が花に乗ろうとしているが、乗り損ねている。そんな様子の露は哀れなものだ。
まだ夕日が沈まず、霞が出ているこの時。宙を舞う霞の影で起きていること。
8句目
暮ぬとやなきつゝ鳥の歸るらん(長)
み山を行はわくそらもなし(祇)
夕暮れだと知った鳥は、鳴きながら家に帰ってゆくのだろうか。
深山を歩くと空が見えないと知っている。鳥よ。迷子になるぞ。
9句目
はるゝまも袖は時雨の旅衣(柏)
わか艸まくら月ややつさん(長)
晴れているのに降る時雨に、旅衣の袖は濡れる。
若草を枕にして寝る私を月が優しく照らしているよ。
前向きな心の奥底には不安な気持ちが表れていて、涙している様子を、晴れと時雨と袖で表現しています。
そんな自分を月は優しく見守っているのです。
10句目
徒にあかす夜おほく秋ふけて(祇)
夢にうらむる荻のうは風(柏)
特にすることも無く夜を明かすことが多い秋。今日も夜が更けてしまった。
夢の中でさえ、萩の上を吹く風に恨みを抱いているよ。
心の中にある不安や悲しみが深まっています。
11句目
みしはみな故郷人のあともなし(長)
老のゆくへよなにゝかゝらむ(祇)
かつて見た故郷の人々は皆いなくなってしまった。老いていく自分の行く末はどうなるのだろうか。
12句目
色もなきことの葉をたに哀しれ(柏)
それもともなる夕くれのそら(祇)
哀しい夕暮れの空。
それとは関係ないはずのに、あなたの情緒のない言葉にさえ哀しみを感じるよ。
13句目
雲にけふ花ちりはつるみねこえて(長)
きけは今はの春のかりかね(柏)
今日、ついに雲の中で花が散り終わった。そんな峰を越えると、
春の終わりを告げる雨燕(あまつばめ)の鳴き声が聞こえてくるよ。
花とは、雨のことです。
アマツバメは夏の季語で、海岸や絶壁に巣を作る渡り鳥です。
14句目
おほろけの月かは人もまてしはし(祇)
かりねの露の秋のあけほの(長)
ぼんやりとした月が見えるこの夜、人を少し待っている。
ああ、秋の夜明けというのは、露が仮寝しているのがよく感じられるよ。
露は気温が上がる朝までの短い間を仮の宿としています。そんな露をよそ目に、自分は宿らない人を待っています。対照的ですね。
15句目
末野なる里ははるかに霧立て(柏)
吹くる風はころもうつこゑ(祇)
野の果てにある里には、遥かに霧が立ち込めている。
吹き行く風は衣を打つような音を立てているよ。
16句目
さゆる日も身はそてうすき暮毎に(長)
たのむもはかな爪木とる山(柏)
寒さが身に染みる日々だが、薄袖の衣で過ごしている。毎日頼りにしている薪は使えば儚く消えてしまう。
今の自分は、そんな爪木(薪)を取った山のようだ。
薪を取ればとるほど山は禿げていきます。自分の薄袖の衣を、薄くなった山肌になぞらえているのです。当然、衣も着れば着るほど消耗するので、この点が山と同じだと言っています。
17句目
さりともの此世の道はつき果て(祇)
こゝろほそしやいつちゆかまし(長)
命永らえたいと思っても、この世の道が尽き果てるその時はやって来る。
心細い。いったいどこへ行けばいいのだろうか。
18句目
命のみ待ことにするきぬゝゝに(柏)
猶何なれや人の戀しき(祇)
今着ている衣を頼って命が尽きることだけを待つことにしよう。
それでもなお、どうしてこんなにも人恋しく思うのだろうか。
「きぬきぬ(衣々)」は、男女の共寝のことを言います。これになぞらえ、衣を見て人恋しいと言ったのです。
長くない命に対する不安や覚悟の気持ちを示す中でも、人を恋しく思う人間性溢れる歌となっています。
19句目
君をおきてあかすも誰を思ふらん(長)
その面影に似たるたになし(柏)
あなたを置いて夜を明かす時、私は誰を思うだろうか。
あなたの面影に似た人は他にいない(=あなたしかいない)。
20句目
草木さへふるき都のうらみにて(祇)
身のうきやとも名殘こそあれ(長)
草木さえもかつては栄えた古の都の寂しさを感じている。
そんな中、我が身の浮き沈みも名残として残っている。
浮き沈みとは、人生のことでしょうか、栄華のことでしょうか、名声のことでしょうか。
21句目
たらちねの遠からぬ跡になくさめよ(柏)
月日のすゑや夢にめくらん(祇)
親の跡がそう遠くないことに泣き悲しんでいる私。父よ母よ、幼い頃のように慰めてくれないか。
月日の終わり(死ぬ日)は、夢の中で父と母に見守られながら日めくりしたいよ。
22句目
この岸を唐舟のかきりにて(長)
又生れ来ぬ法を聞かはや(柏)
この岸から唐船が漕ぎ出していく。
この唐船のように、再び生まれ変わる方法を聞きたいものだ。
23句目
あふまてと思の露のきえかへり(祇)
身をあき風も人たのめなり(長)
「また会う日まで。」と言っていたが、その思いは露のように消えてしまった。
秋風に身を任せることが儚いように、人を頼りにすることも儚いものだ。
24句目
松むしのなく音かひなき蓬生に(柏)
しめゆふ山は月のみそすむ(祇)
松虫の鳴く声が虚しく蓬生(よもぎう)に響く。
湿った夕暮れの山では、月だけが澄んで見える。
蓬生は、蓬などが生い茂って荒れ果てた土地のことです。
25句目
鐘に我たゝあらましのね覺して(長)
いたゝきけりな夜なゝゝの霜(柏)
鐘の音で目が覚めてしまった。
でも、そのおかげで、夜の霜の美しさを知ることができたよ。
26句目
ふゆかれの芦零侘て立る江に(祇)
夕しほかせを沖つ舟人(柏)
冬枯れの日、鶴が寂しく立っている川辺に、
夕潮に流されて沖に向かう舟人がいる。
「芦零」は「あしたづ」と読みます。鶴の異名です。文字に鶴を用いるのではなく、芦をつけることで、より寂しさを表現しています。
動かない鶴と、動く舟人が対照的に描かれています。
27句目
ゆくゑなき霞やいつく果てならん(長)
くるかた見えぬ山里の春(祇)
行く先のない霞(かすみ)は、いったいどこまでいくのだろうか。
来た方角も見えない山里の春。
夏になった時、春はいったいどこへ行っているのでしょうか。
28句目
茂みよりたえゝゝ殘る花おちて(柏)
木のもと分るみちの露けさ(長)
絶え絶えに残っている花が茂みから落ちてきて、
木の下で分かれている道が露で湿っている。残り少ない友との別れ道を前に、私の目も涙で湿っているよ。
「露けさ」とは、涙にぬれている意を表すことが多いです。木の下での別れ道に悲しんでいることが伝わってきます。
29句目
秋はなともらぬ岩屋もしくるらん(祇)
苔の袂も月はふけけり(柏)
秋花が咲かない岩屋も寂しく感じられる。
そんな苔むした岩の袂にも、月の光は差し込んでくるのだ。
30句目
心あるかきりそしるき世捨人(長)
おさまるなみに舟いつるみゆ(祇)
世捨て人というのは、心を持ち続ける限り、世間から批判される。
収まっている波の中、舟に乗っている貴方が見える。
収まっているというのは、雑念を捨て、悟りの境地に至った様子を表しているのでしょうか。
31句目
朝なきの空にあとなき夜の雲(柏)
ゆきにさやけき四方の遠やま(長)
夜明け頃の空に飲まれ、跡形もなく消えていく夜の雲。
そして、日に照らされた雪に反射して、四方の遠い山々は清らかな姿を見せてくる。
32句目
嶺のいほ木のはの後も住みあかて(祇)
さひしさそふる松風の聲(柏)
嶺の庵で日々を住み明かしていると、木の葉がサッと通った後に寂しさが募る。
松風の音がその寂しさをさらに誘ってくるよ。
33句目
誰かこの暁おきをかさねまし(長)
月はしるやの旅そかなしき(祇)
誰が夜明け前に起きる日々を重ねて習慣にしようか。
月は知っているだろうか、この旅の哀しみを。知らないだろうから、夜明け前に起きてやるものか。月に会ってしまうからね。
暁起きとは、夜明け前に起きて勤行する場合も指します。
34句目
露ふかみ霜さへしほる秋の袖(柏)
うすはなすゝきちらまくもをし(長)
露が深く付き、霜さえも湿りを帯びている秋の袖。
花薄(はなすすき)が色落ちていくのも惜しいよ。
はなすすき色というのがあります。表は白色、裏は薄縹(うすはなだ)色です。
35句目
鶉なくかた山くれて寒き日に(祇)
野となる里もわひつゝそすむ(柏)
鶉(うずら)が鳴く片山の寒い日の夕方。
これから野原となるであろう人のいない里を惜しみながら、今日もこの里で日々を送っている。
片山は片田舎の「かた」と同じです。
36句目
帰りこは待し思ひを人やみん(長)
うときも誰か心なるへき(祇)
帰りを待つ私の思いを、他の人はどう思うだろうか。
親しくない人でも、誰かが心にかけてくれるだろうか。
37句目
昔よりたゝあやにくの戀のみち(柏)
忘られかたき世さへうらめし(長)
恋の道がただただ無慈悲というのは、昔からの習いである。
昔の恋を忘れられないのもなかなか質が悪い。この世の中さえも恨めしく思ってしまうよ。
38句目
山かつになと春秋のしらるらん(祇)
うへぬ草葉のしけき柴の戸(柏)
山蔓(やまかずら)などは春や秋などの季節を知っているのだろうな。
植えてもいないのに、年中柴の戸に山蔓の草葉が生い茂っているのだから。
蔓は年中生えているから、卑しい存在であるくせに春秋といった季節の風流を知っているのだろうと、皮肉ってます。
39句目
かたはらに垣ほのあら田かへしすて(長)
行人かすむあめのくれかた(祇)
すぐ傍らのには高貴な人が住んでいるであろう垣根がある。
その横で荒れた田んぼを耕し捨てて行く人が雨で霞んで見えるよ。そんな夕暮れ。
貧富の差と定まらない貧しい農民の行く末を雨と夕暮れで見事に表現しています。
40句目
やとりせん野を鶯やいとふらん(長)
小夜もしつかにさくらさくかけ(柏)
この野で宿を取ろうとしているが、ウグイスは嫌がるだろうか。
静かな夜に桜が咲くような所だから。
美しい景色に、老いぼれた自分という対照的な表現です。
41句目
灯をそむくる花にあけそめて(祇)
たか手まくらに夢はみえけん(長)
ともしびに背を向けて咲く花(朝顔)が朝日に染まる頃、
貴方は高い手枕の上でどんな夢を見ているのですか。
高い手枕は恋人の腕枕のことです。
朝に咲くだけあって朝顔は起きています。そんな朝顔の後ろでは、恋人たちが寝ているのです。
42句目
ちきらはやおもひ絶えつゝ年もへぬ(柏)
今はのよはひ山もたつねし(祇)
遥か幽谷のさらに奥にある里で暮らす私。生きる活力が絶えてからというもの、幾年も過ぎてしまった。その代わり、死期の近い年齢だけに、黄泉の国へと続く死出の山を訪ねるばかりだよ。
「千吉良(ちきら)」と書きます。三河地方に多くみられる地名です。
「今際の齢(いまわのよわい)」と書きます。
43句目
かくす身を人はなきにもなしつらん(長)
さてもうき世にかゝる玉の緒(柏)
隠棲した私「もういない人」と思っているだろう。
それでもまだ、私の命の糸はこの辛い世の中にかかっている。
玉の緒とは、つながれている命の糸のことです。
44句目
松の葉をたゝ朝夕のけふりにて(祇)
うらはの里よいかにすむらん(長)
松の葉を焚いて、朝夕に煙る中で生活している私。
松の葉のない浦の里の人々はどのように暮らしているのだろうか。
45句目
秋風のあら磯枕ふしわひぬ(柏)
鴈なくやまの月ふくるそら(祇)
秋風が荒々しく磯吹き付けている。私はこんな磯を枕にして寝ている。
横になって見上げると、雁が鳴き、山の月が満ちる空が広がっていた。
46句目
小萩はら移ろふつゆも明日やみん(長)
あたの大野をこゝろなる人(柏)
野に咲く小萩の葉の上の露が移り変わるように、私も明日には消えるだろうか。この風景を見ることはできるのだろうか。
そう思いながら、阿多の大野にいるあの人を心にかける。
阿多の大野は詳細不明です。現在は鹿児島県に阿多という地名があり、また、「あの人」のという思いをかけている表現から、「諸国を巡礼していた飯尾宗祇が鹿児島県を訪れた時に会った人」という可能性を考えましたが、『筑紫道記』では飯尾宗祇が鹿児島まで足を運んだ記録は見られなかったため、答えは出ませんでした。
現在の地名に残っていない土地なのかもしれません。
47句目
わするなよかりにやかはる夢うつゝ(祇)
おもへはいつをいにしへにせん(長)
忘れるなよ。仮に夢が現実に変わったとしても。
この思いはいつも昔のままです。
48句目
佛たちかくれては又いつる世に(柏)
かれし林もはるかせそふく(祇)
仏たちは身を隠れた(死んだ)としても、またいつかこの世に戻ってこられるだろう。
枯れた林にも、春風は吹くのだから(春が来れば再び芽吹くのだから)。
49句目
山はけさいく霜よにかかすむらん(長)
けふりのとかにみゆるかりいほ(柏)
今朝の山はすっかり霜に覆われているというのに、なぜ霞んで見えるのだろう。
仮の住まいから立ち上る煙のせいだろうか。
50句目
いやしきも身をおさむるは有つへし(祇)
人におしなへ道そたゝしき(長)
卑しい身分であっても、己を律することはできるはずだ。
人に教える道というのは、ただただ正しいものであるべきだから。
卑しい身分とは、己のことを指します。飯尾宗祇は連歌師であり、僧でもありました。
| 前の記事へ << | 第一話を読む >> |