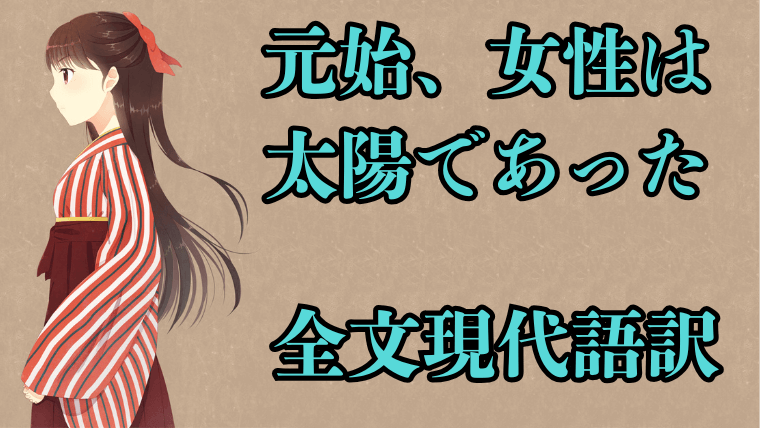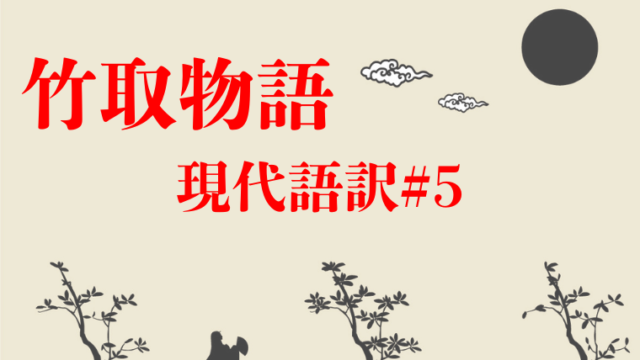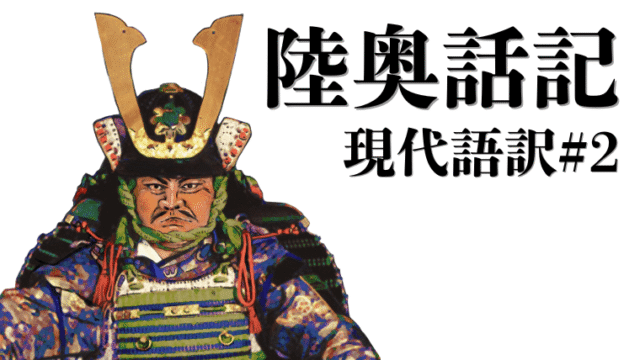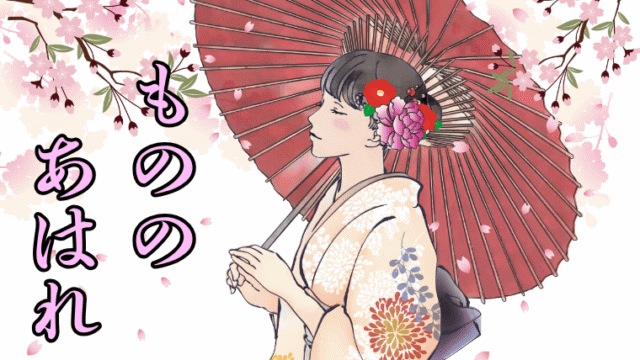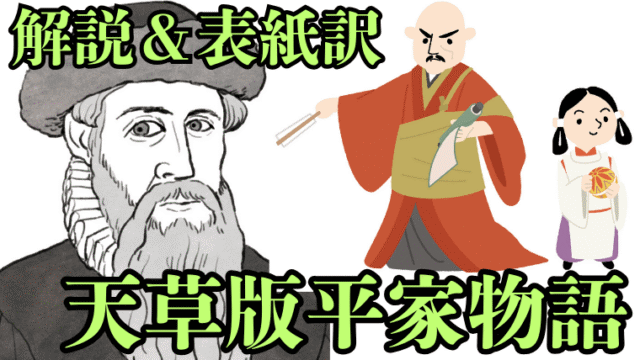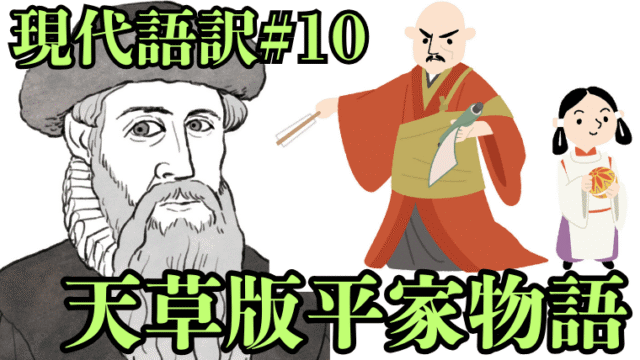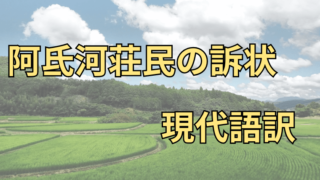解説
「女性は太陽」の意味
そもそも太陽とは光をもたらす存在(能動)であり、影や月は太陽の光が無いと存在できないもの(受動)です。
本来は女性は自分の意思で能動的に行動をすることができましたが、明治時代ではそれが出来なくなっている、ということです。平塚雷鳥は、「明治時代の女性は、性差や世間体という外部的抑圧によって、女性自身の内には潜在能力があるのに、それを自覚できずにただその外部抑圧の奴隷となっている。目を覚ませ!」と訴えたのです。
それを哲学的表現を用いて訴えました。雑誌『青鞜』は女性のそのような潜在能力を引き出すための手段として発足されたのです。
青鞜とは
『青鞜』は平塚雷鳥が創刊した女性中心の文芸雑誌です。
明治44年(1911)~大正5年(1916)の6年間という僅かな期間での出版でしたが、日本におけるフェミニズム運動の先駆けとして、世間に多くの影響を与えました。
『青鞜』の由来は、イギリスで「教養ある女性」を指す、「ブルーストッキング(blue stocking)」です。この言葉は、イギリスの文芸結社「ブルーストッキング・ソサイエティ」のもと広まりました。結社発足時、メンバーの1人が正装ではなく青い靴下を履いてきたことにユーモアを感じて、そのまま社名命名に用いたといいます。この結社は、女性の地位向上に広く貢献したことが高く評価され、その名が知られるようになりました。
世界でのフェミニズム運動の先駆けとなった「ブルーストッキング・ソサイエティ」。平塚雷鳥がリスペクトするのは、日本での女性の地位向上の成功を願ってでしょう。
潜める天才とは
平塚雷鳥は文中、何度も「潜める天才」という表現を使用します。平塚雷鳥は、「潜める天才」は女性の真の自由と解放のために必須のツールであると主張しました。真の自由、開放とは、具体的には、心身が、外部的抑圧(社会常識・世間体など)も内部的抑圧(外部的抑圧によって引き起こされる恐怖・不安)も感じてない状態を言います。
ではそこに至るためには何をしたらよいのか。それは、「精神集中」です。「精神集中」の発動条件は、
- 「どん底の状態で、」→自信を顧みることが出来る場
- 「ただ強く祈ること」→神力や意思力(これが難しい)
です。
人間とは、男女関わらず、己の力で困難な状況や運命から、悟りや未来を得ることができる生き物なのですが、当時、女性はそれが出来ていないという社会風潮になっていました。
その理由は、女性には許された時間が無いから。女性は男性を支える立場として社会的に確立しています。その代表例が子育てと家事です。現代でも同じですが、本当に自分の時間が取れません。
これは「家のことをしているから仕方がない。」と思うかもしれませんが、視点を変えれば、社会という外部的抑圧が「精神集中」の時間を奪っている、女性が「潜める天才」を発揮できない状況を作っているとも言えるのではないでしょうか。これが平塚雷鳥が鳴らした警鐘です。
ならば女性にその時間を提供すれば良い。つまり、「潜める天才」を発揮できる環境を作ることが、女性の真の自由と解放という最終目標には必要である、その場(ツール)が『青鞜』であるということなのです。
現代語訳
原始、女性は太陽であった
人類が誕生してからというのは、女性は太陽のように自ら光り輝く存在であった。真正の人(己の意志に基づいて能動的な行動ができる人)であった。しかし今の時代、女性は月となっている。太陽の光を受けて輝く、受動的な存在。そんな月は病人のように青白い。
さて、ここにおいて雑誌『青鞜』は刊行された。現代の日本の女性が持つ頭脳と手腕によって完成された。今の時代、女性の成すことは嘲笑を招くばかりである。 私はよく知っているとも。その嘲笑の下に隠れた『あるモノ』を。
そして私は少しも恐れない。
しかし、女性が自らの意志で『青鞜』を刊行したということは、女性自らが自らの上に、新しく、痛ましい羞恥と汚辱を生むということである。女性とは、こうも嘔吐するに値する存在なのだろうか。 いやいや、当然、女性も真正の人なのだ。それなのに、今の世の中は。。。
うん、私は少しも恐れない。
私たちは今日の女性としてできるだけのことをした。心の全てを尽くして、産んだのがこの『青鞜』なのだ。それが低能児だろうが奇形児だろうが早生児だろうが仕方ない。
「しばらくは、これで満足すべきだ。」と言い聞かせる。
果たして私たちは心の全てを尽くしたのだろうか。ああ、誰が、誰がこの結果に満足しているか。 私たちはここにおいて、女性が持つより多くの不満足に一石を投じた。今の世の中では、これほどのことしかできない。女性はこうも力なき存在なのだろうか。 いいや、当然、女性も真正の人なのだ。それなのに、今の世の中は。。。
平等たる精神集中の世界
そうは言いながら、日が照り付けるこの真夏に生まれた『青鞜』が、極熱すらも熱殺するほどの猛烈な熱誠(熱のこもった誠意)をもっているということは私とて見逃してはいない。
「熱誠!熱誠!」
私たちはただこれに突き動かされたのだ。熱誠とは、祈禱力であり、意志の力であり、禅定力であり、神道力である。総じて言い換えれば、精神集中力である。神秘に通じる唯一の門を『精神集中』という。 今、私は『神秘』と言った。これは、はるか現実の上あるいは現実を超越して、手の先や頭の先で神経によって描き出されたものを指しているのではない。そして夢でもない。
『神秘』とは、『我々人間の主観のどん底において、深い瞑想の奥でのみ見ることのできる現実そのもの』ということをここに断言しておく。私は精神集中の真っ只中に『天才』を求めようと思う。天才とは、神秘そのものである。真正の人である。天才に性別は関係ない。男性限定ではないし女性限定でもない。男性や女性といった性的差別は精神集中世界における『中層あるいは下層の自己』『死ぬべき、滅ぶべき仮の自己に属するもの』『最上階の自己』『不死不滅の本来の自己』といった領域には存在しない。
雷鳥の精神崩壊
私はかつてこの世に男性、女性の違いがあることを知らなかった。 私の心は常に多くの「男女(=人)」からの影響を受けていた。彼らの本質や人間性を見ていたのである。男性や女性といった性別で「男女」を見ていなかった。そして私の過剰な精神力は性的差別などの社会規範に耐えきれず、理性を超えてしまった。そのような数々の無法な行為を治すことは難しい。
私は救いがたい疲労に陥った。人格の衰弱!実に私は、これによって自分が女性であると初めて気が付いた。それと同時に、男性というものを認識するようになった。こうして私は「死」という言葉を学んだ。
死!死の恐怖!
かつて天地に自己を重ね、生死の岸頭(迷いや苦しみの世界と悟りの世界の境界)に生きた者、女性。
死を感じたこの時、足がよろめいた(=生死の岸頭からの離脱)。それは滅ぶべき者である。つまり女性。
かつて統一界(経験や知識が統一された秩序ある世界。統一されて初めて、対象を認識することができる。)に住んでいた者、女性。
死を感じたこの時、雑多界(統一される前の多様で混沌とした経験の世界。直感的に感じる多様な現象や出来事の集合体を指す)に落ちて途切れ途切れに息をする存在となった。雑多界に落ちた不純な者、つまり女性。
人間とは、蓮が泥の中から美しい花を咲かせるように自身の力で困難な状況や運命から悟りや未来を得ることができる生き物である。しかし私は、自己の運命を自ら切り開くことを知らない宿命論者に同調しそうになった。ああ、思い出すと、自分の無力さに冷や汗が流れる。私は泣いた。苦しくも泣いた。日夜奏でてきた私の琴の糸が緩んでしまったことを。音の調和が低くなったことを。そう、私の過剰な精神力は衰えたのだ。
「性格」というものを自覚した時、私は「天才」に見捨てられた。個性を認めてしまったのである。天翔ける羽衣を奪われた天女のように、陸に揚げられた人魚のように。私は「神秘」に至るための精神の揺れ動きを、そして最後の希望を失った。嘆いた。痛々しく嘆いた。自身の力で運命を切り開くべきだと考えていのに、その最後の手段「精神集中」から離脱してしまったのだった。
雷鳥の再起への道
とはいえ、苦悶、損失、困憊、乱心、破滅。総じてこれを支配する主もまた常に自分自身であった。 私はこれらを常に支配する権利を行使することができる。それに気づき、私は自分自身を支配する自主自由な人であることに満足し、自滅に陥れる自分自身を悔いることなく、どれほど悪い出来事が起きようと、自分が自分であるための道を休みなく進んだ。
ああ、我が故郷の暗黒(抑圧された過去)よ、そして絶対なる光明(抑圧から解放された未来)よ。自ら輝き、その温かなる光で全世界を照らし、万物を育む存在、太陽。
ああ、太陽は天才だ。真正の人だ。
人類が誕生してからというのは、女性は太陽のように自ら光り輝く存在であった。真正の人(己の意志に基づいて能動的な行動ができる人)であった。しかし今の時代、女性は月となっている。太陽の光を受けて輝く、受動的な存在。そんな月は病人のように青白い。私たちは隠されてしまった「自分たちの」太陽を今取り戻さねばならない。
「隠れた我が太陽よ、内なる才能を発現せよ!」
自身の内に向けられた絶えることのない叫び声、抑えられない消せない渇望。これらのような雑多な精神(本能や欲望)全てを統一し、最終的に全人格的な唯一の本能を発現させるのだ。この叫び声、この渇望、この全人格的な唯一の本能こそ、熱烈な精神集中のきっかけとなるのだ。