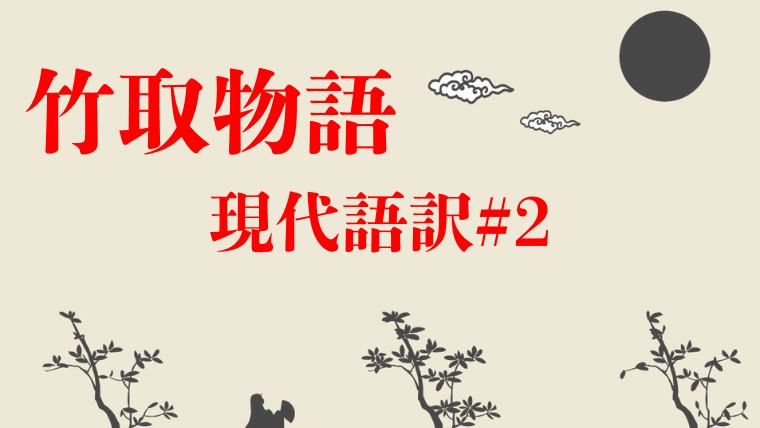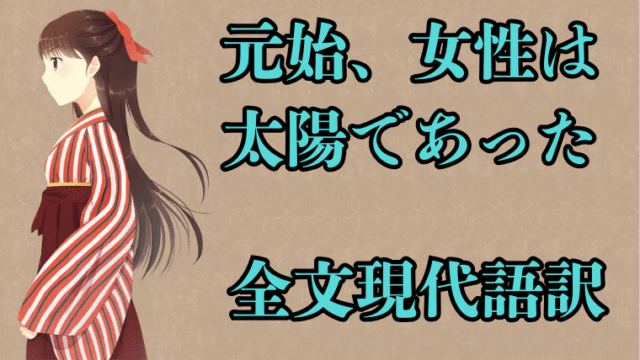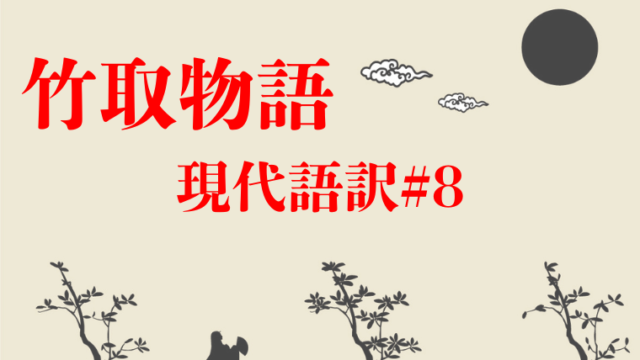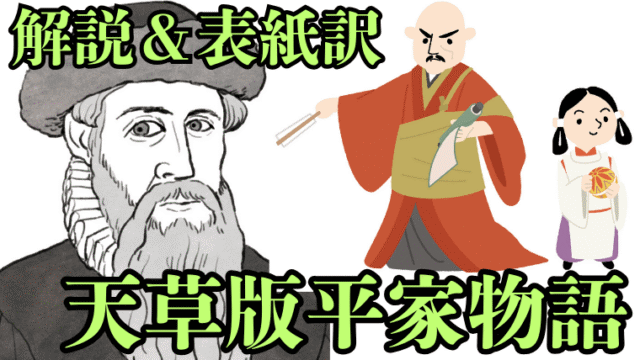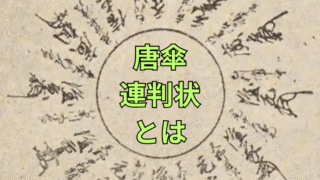一覧は下記サイトをご確認ください。
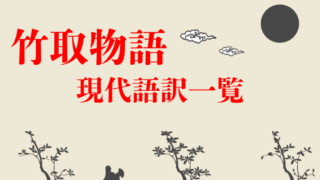
②五人の貴公子と結婚の条件
世の男は、かぐや姫の噂を聞き、身分の高い者も低い者も、『どうにかして、このかぐや姫を妻にしたい手に入れたい。妻にしたい!』と心を乱した。遂には、翁の屋敷を囲む垣根や家の外では、夜に安眠もせず、闇夜に出てきては穴を開け、どこかしこから覗き見をするほどになり、男たちは心を乱していた。家の者でさえ容易に見ることができないというのに。
その頃から、いわゆる夜這い人(求婚を望む人)という人たちであろうか、普通は誰も行かない場所に行っては心を乱しながら歩き回っていようたが、その行動に何の効果もありそうには見えない。家の人たちに何か言おうとして話しかけるも、彼らは相手にされなかった。
翁の屋敷を離れない貴公子たちとには、夜を明かし日を暮らす者(一日中恋を求めて日々を過ごす者)が多い。あまり本気でない貴公子は「このまま無意味な外出を続けてはつまらない。」と言って、来なくなってしまった。それでもやはり言い寄ってきたのは、生粋の色好みと言われている五人であった。思い止める時もなく、夜も昼もやって来ていたのであった。
彼らの名は、石作皇子(いしつくりのみこ)、車持皇子(くらもちのみこ)、右大臣阿倍御主人(あべのみうし)、大納言大伴御行(おおとものみゆき)、中納言石上麻呂足(いそのかみまろ)。彼らは、少しでも容姿が美しいと噂に聞いては、結婚したがる人たちであった。当然かぐや姫も例外ではなく、かぐや姫を自分のものにしたくて、何も食べずにかぐや姫のことを思い続け、屋敷に行っては立ち止ったり、歩き回ったりしていた。しかし、それも無駄なことであった。
文を書いてかぐや姫に送るも、返事はこないし、かと言って、恋に苦しむわび歌などを書いて送っても、同様に返事はなかった。『これも無駄なことか。』と思いつつも、十一月や十二月の雪が降る寒い日にも、六月の日が照り雷が轟く日にも、関係なしにやって来た。彼らは、時に翁を呼び出して
「娘を私に賜ってくださらぬか。」
と伏して拝み、手をすり合わせるが、
「私が生んだ子ではないので、なかなか自分の思うことに従ってくれないこともあるのです。」
と言って、取り合わずに月日を過ごした。
このような状態なので、貴公子たちは、家に帰り物思いをしては、神仏に祈ったり願を立てたりしたが、かぐや姫を思う心は消えそうにない。むしろ、『そうはいっても、いずれは男と結婚させるはずだ。いつまでも独身にさせるはずはない。』と思って期待していた。
並々ならぬ志を持って今日も歩き回っていた。これを見て、翁はかぐや姫に言った。
「私の大切な子よ、貴方は変化(へんげ)の人ですが、この大きさまで養ったこの愛情は、並々ではござらぬ。わしが申すことを聞いてくださらぬか。」
と。かぐや姫は、
「私は貴方の仰ることを聞かなかったことがありましょうか。それに、私が変化の者であると自覚した覚えはありません。貴方を親だとずっと思っております。」
と返した。
「嬉しいことを仰いますな。」
そう言って翁は続けた。
「わしは七十歳を過ぎ、この命が尽きるのが今日か明日かも分からない歳になりました。この世の人というこは、男は女と結婚し、女は男と結婚します。その後で子孫が繁栄し、一門は何門にもなるのです。どうして結婚せずに過ごすことができましょうか。」
「では、どのようなことを私はすれば良いでしょうか。」
「変化の人といっても、お姿は女性です。わしが生きている間は、このまま独身で過ごされよ。彼らが年月を経てもこのように通い続ければ、色々と仰ってくるでしょう。それから考えて、一人ひとり顔合わせしなされ。」
「美しくもない容姿なのに、相手の深い心も知らないで結婚すれば、『もし旦那に浮気心がついてしまったら、きっと後悔するでしょうね。』と思い続けてしまいます。世の中でも特に立派な人であっても、深い志を知らないでは、結婚に踏み込むのは難しい。そう思っております。」
「思っていた通りのことを仰いましたな。では、どのような志を持つ人なら結婚しようと思いますか。志が並々ならぬ人でしょうか。」
「深い愛情がどれ程かを見たい、とは言いません。ほんの僅かなことなのです。人々の持つ愛情というのは同等なのです。どうして、愛情の優劣が分かりましょうか。人それぞれがそれぞれの愛情を持っているのです。家の周りにいらっしゃるという方々にこう申し上げてください。『貴方がたの中で、私が見たいと思う物を見せてくれた方が、他より志が勝っているとし、結婚を受け入れましょう。』と。」
翁は「良いことだ。」と承知した。
日暮れ頃、いつものように彼らは屋敷の周りに集まってきた。ある者は笛を吹き、ある者は和歌を詠み、ある者は歌を歌い、ある者は口笛を吹き、ある者は扇を鳴らすなどしていた。そこへ翁が出てきて
「高貴な貴公子殿には似つかわしくない寂れた所に長い年月に渡っておいでになりましたこと、極まりのないほど有難いことでございます。」
とまずは申し上げて続けた。
「『私の命が尽きるのは今日か明日かも分からないから、このように色々と仰ってくれる貴公子から、よく考えてから結婚相手を決めなされ。』と姫に申しましたところ、『しかし、私にどれ程深い志があるのか知らなければ。。。』と申しました。その通りだと思います。そこで姫はこう決めたのです。『どの貴公子も優劣付け難い。ですので、貴方がたの志の深さは、私が見たいと思うものを見せてくれた時に分かることでしょう。結婚相手はそれで決めます。』と。これは良いことです。方々も恨みっこ無しでしょう。」
五人も「それは良いことだ。」と承諾したので、翁は屋敷の中に戻って、その見たいという物が何かを尋ねた。かぐや姫は各々に要求するものを言った。
石作皇子には、「天竺には、仏の御石の鉢という物があります。それを取って来てください」と。
車持皇子には、「東の海には蓬莱山という山があるそうです。そこには、銀を根とし金を茎とし白玉を実として立っている木があります。それを一枝、折ってきてください。」と。
もう一人(阿倍御主人)には、「唐土にある火鼠の皮衣をください。」と。
大伴大納言には、「竜の頭には五色に光る玉が付いています。それを取ってきてください。」と。
石上中納言には、「子安貝というのがありますが、その中でも燕が産んだ子安貝を取ってきてください。」と。
翁は
「どれも難しいことではありませぬか。この国にある物でもない。このような難しい要求、どうやって申し上げよう。」
と漏らしたが、かぐや姫は
「何が難しいことでしょうか。」
と言うので、
「とにもかくにも、申し上げてみよう。」
と言って、外へ出た。
「こういうことにございます。姫が申すよう、それらをお見せください。」
これを聞いた貴公子たちは、
「穏便に、『周囲を歩き回らないでいただけませんか。』と言えば良いのに。」
と言って、嫌になって皆帰った。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |