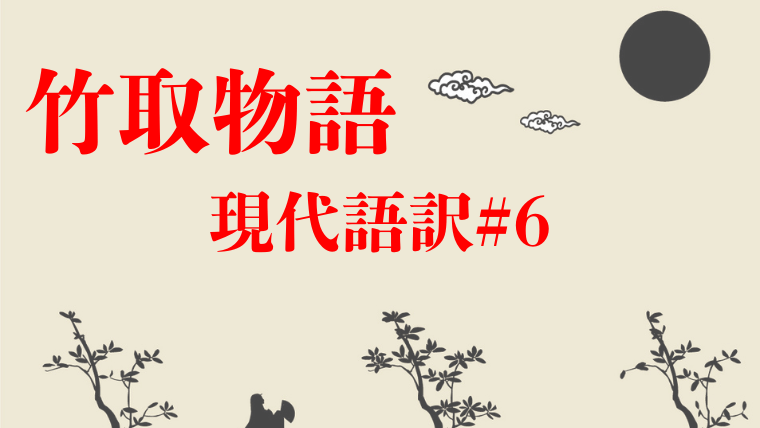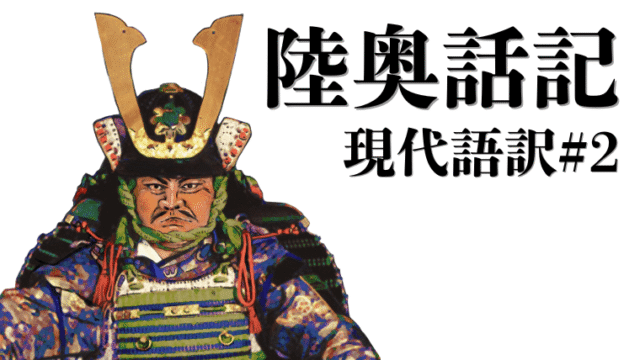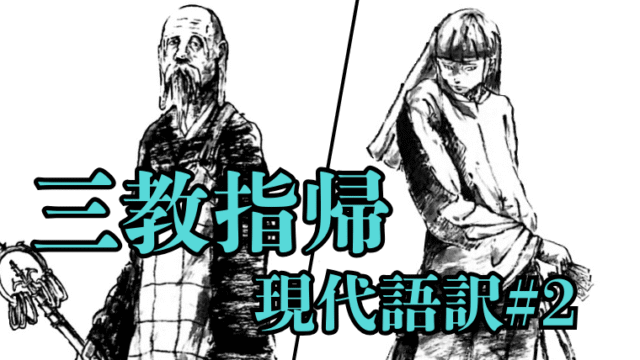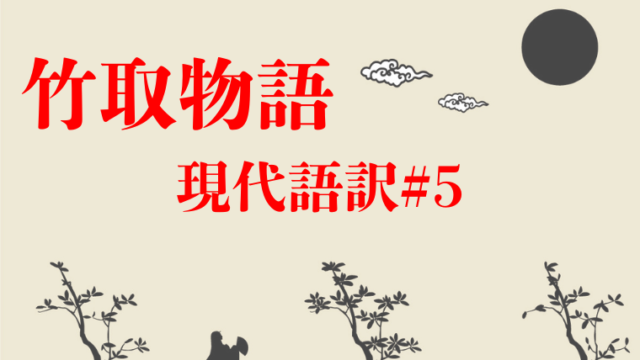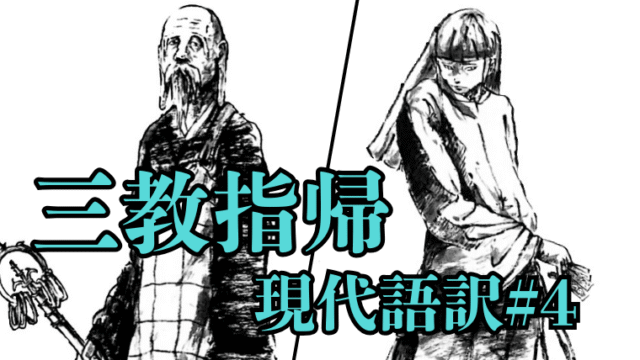一覧は下記サイトをご確認ください。
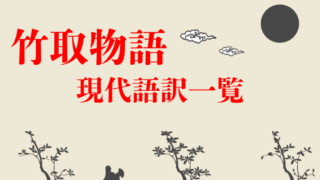
⑥四人目:右大臣阿倍御主人
大納言大伴御行は、屋敷にいるありとあらゆる人を集めて仰った。
「竜の頭には五色の光を放つ玉があるそうだ。それを取ってきた者には、願いを叶えてやろう。」
と。男共が申す。
「仰せのことは、我々としてもたいへん嬉しい話です。ただ、この玉は簡単には取れないでしょう。まして、仮に見つけたとしても、竜の頭にある玉はどうやって取りましょうか。」
「君と称されるほどの高位の者に使える者らというのは、『命を捨ててでも、我が主君の仰せ事を叶えよう。』と思うはずだ。竜の玉とは、この国になければ天竺の物でも唐土の物でもない。ただ、竜はこの国の海や山を昇り降りしているらしあ。何を思ってお前たちは難しいことだと言っているのか」
「それならば、難色を示してもどうしようもございません。困難な道のりであっても、ご命令に従い、求めて参りましょう。」
大納言はその様子を見ながら笑って、
「お前たちは大納言の君の使いとして、名が知られている。主君の命令にどうして背くことができようか。」
と仰り、竜の頭の玉を取るために、ということで出発させた。この人々が道中に必要な、穀物、その他食料に加え、屋敷にあった絹や綿、銭など、あるだけ取り出して、彼らに渡して遣った。
「私はここにいる。玉を取ってくるまで家に帰って来るなよ。」
と仰った。
「各々、君のご命令を承り、退出いたしました。竜の頭の玉を取るまで帰って来ません。」
そう答えた後、
「どっちがどっちでも良い、足が向いた方へ行ってしまおう。」
「このような物好きなことを。」
と、大納言を非難し合った。賜った食料金品は、各々で分配した。ある者は自分の家に籠り、ある者は自分の行きたい所へ行った。
「自分を親なり君なりと言うが、このように不案内かことをお命じになるとは、主君としてみっともない。」
と、納得行かず大納言を非難し続けていた。大納言は、かぐや姫を隣に置くには、普段のままでは見苦しい、などとおっしゃって、屋敷を壮麗な建物に造り替えた。壁には漆を塗り、蒔絵を施し、ひたすら屋敷をいじった。屋根の上には糸を染めて様々な色で葺き、屋敷内の調度品には、もの言う必要も無いもないそど素晴らしい綾織物に絵を描き、それを間ごとに貼った。それまでいた妻たちは大納言のもとを去った。「かぐや姫は必ず妻にする。」と準備として、大納言は今は一人で生活している。
取りに行かせた者たちを昼夜待ち続けたが、年を越すまで音沙汰がない。待ち遠しくなった大納言は、非常にこっそりと、たった2人の舎人を従者としてて、粗末な格好で難波辺りまでやってきた。人々に尋ねる。
「大伴大納言の家来が船に乗って竜を殺しに行き、その頭の玉を取ったとは聞いていないか。」
船人が
「おかしな事を言う人だな。」
「そのような仕事を受ける船もない。」
と笑って答えるので、
『意気地のないことを言う船人だな。知らないからこのようなことを言うのだな。』
と思った。
「私の弓の力をもってすれば、竜を見つければ簡単に射殺して、頭の玉を取ってしまうだろう。遅れて来る奴らなどもう待てん。」
と仰って、船に乗って色々な海を漕ぎ回っていると、たいへん遠くにある、筑紫の方に向かって漕いで向かったのであった。どうしたのであろうか、強風が吹いて、目の前の世界が暗くなり、船も風に吹かれるがままとなり、漂流した。どちらの方角とも分からず、船を海に沈めてしまいそうなほど吹き荒れた。波が当たっては船を巻き込み、雷は落ちるような閃光を放つので、大納言は困惑して、
「人生、このような辛い目に遭ったことはない。どうなってしまうのだ」
と仰る。船頭が答えて申し上げる。
「幾度となく船に乗っ漕ぎき回っておりますが、このような辛い目に遭ったことはまだございません。お船が海の底に沈まなければ、雷が落ちてくるかもしれません。もし、幸いにも神の助けがあったとしても、南の大海に吹かれて行ってしまうでしょう。情けない主のお傍に仕えたせいで、思いがけない死に方をしそうです。」
船頭は泣いた。
「人は船に乗った以上、船頭の申すことを高い山のように頼りにするものだ。どうしてこのように頼りなさそうなことを申すのだ。」
と大納言は激しく吐き散らした。船頭は答える。
「私は神ではないから、何をして差し上げられましょうか。風は吹き、波は激しいけれども、特に雷が頭上に落ちてくるようなの状況となっているのは、竜を殺そうと探し求めているからでしょう。この疾風も竜が吹いたものなのです。早く、神にお祈りなさい。」
大納言は
「それは良いことだ。」
と言って、
「舵取りの神よ、お聞きください。私は劣った身でありながら、考えが幼稚でありながら、竜を殺そうと思いました。今後は、竜の毛一本すら動かすようなことはしませぬ。」
と祝詞を言い放って、立っては座り、泣く泣く呼びかけること、千度ほどであった。このためだろうか、だんだんと雷は収まったのであった。それでもまだ少しは稲光りは見られ、風ははおも速く吹いていた。船頭は、
「これは竜の仕業でしょう。吹く風は、良い方角です。悪い方角の風ではありません。よい方角に向かって吹いているのです。」
と繰り返し大納言に言うが、大納言は聞き入れなかった。三日、四日ほどは風が吹き返し、波が押し寄せた。浜を見るとそこは播磨国の明石の浜であった。ただ、大納言はそのことに気づいていない。
『南の海の浜に吹き寄せられたのだろうか。』
と思い、ため息をついてうなだれた。同乗していた男共が国府に難破の旨を報告したため国司が参上したのだが、大納言は起き上がることができずに船底で体を横にしていた。松原に筵を敷いて、船から下ろした。その時、
『ここは南の海ではないな。』
と思った大納言、辛うじて起き上がったが、それ見ると、どうやら重篤な風邪であったらしく、腹は非常に膨れ、右と左の目は李を2つ付けたようになっていた。これを見た国司は微笑んでいた。国司は国府に命令して輦(たごし)作らせて、大納言はうめきにうめきながら担がれて、屋敷にお帰りになった。どうやって耳にしたのだろうか、派遣されていた男共が参上して申しあげてきた。
「竜の頭の玉は取ることができませんでしたので、御前に参上できませんでした。『玉の入手が難しいことは身をもって理解されたと思うので、お咎めはないだろう。』と、思ってこうして帰って参りました。」
と。大納言は体を起こして
「お前たち、よくぞ玉を持って来なかった。竜は鳴神の仲間であったのだ。竜の玉を取ろうとして、大勢の人々を殺そうとしたのだ。まして、もし竜を捕えたりしようものなら、問答無用に私は人を殺されていただろう。結果捕まえないことになって良かった。かぐや姫とかという大怪盗が人を殺そうとしているのだ。あの屋敷の周辺すら今は通るまい。男共、お前たちも歩くな。」
と言って、家に少し残っている金品等を、竜の玉を取りに行かせた者たちにお与えになったのであった。これを聞いて、大納言のもとを離れた元妻たちは腹をよじって笑った。あらゆるものを失った妻たちが造った、糸葺き屋根の家は、トビやカラスが巣作りのために咥えて持って行ってしまったのだった。世間の人々は言い合った。
「大伴大納言は、竜の玉を取ってきたのか。」
「いやそうではない。眼に2つの李のような玉を付けていたぞ。」
「なんと、耐え難いほどの恐ろしい体験をしたのだな。」
こうして、身に合わないことを「あな、たへがた。」と言うようになったのである。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |