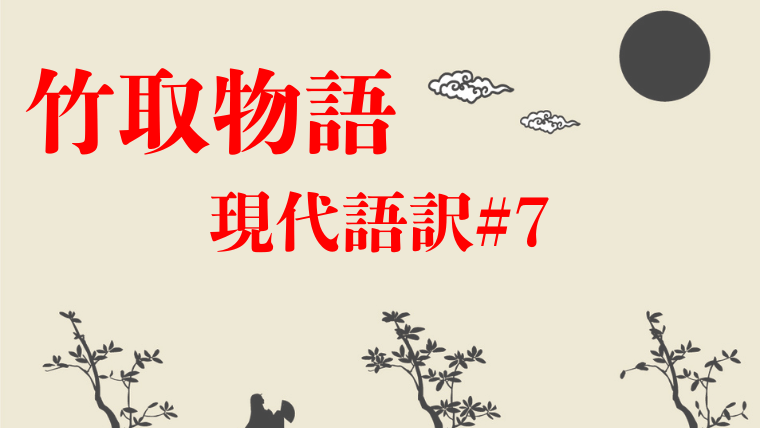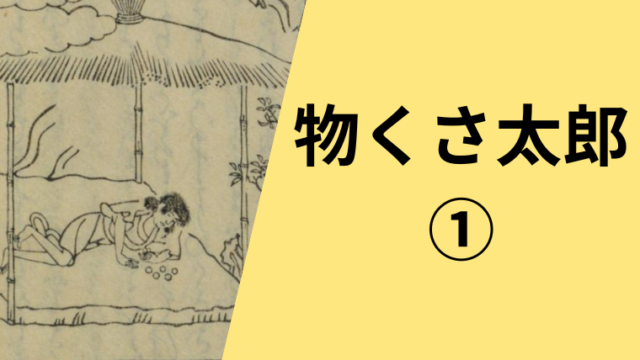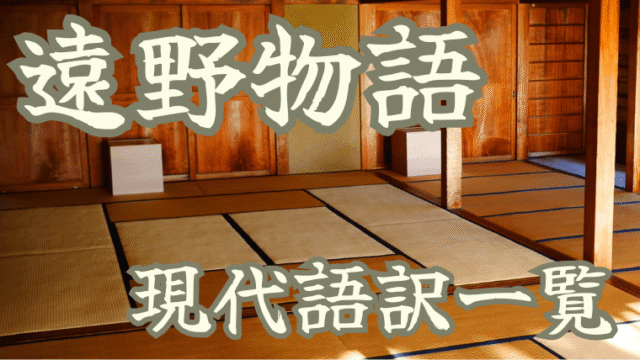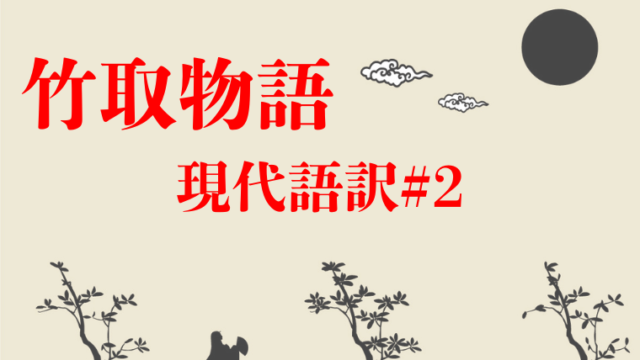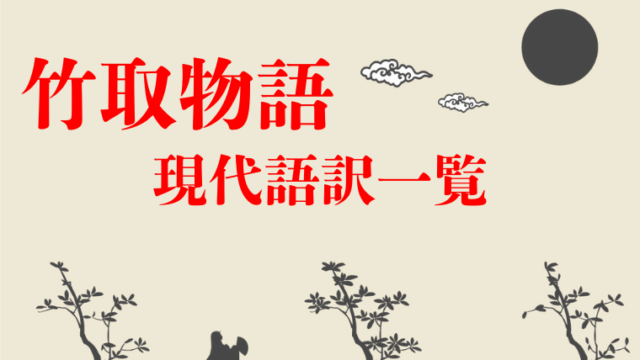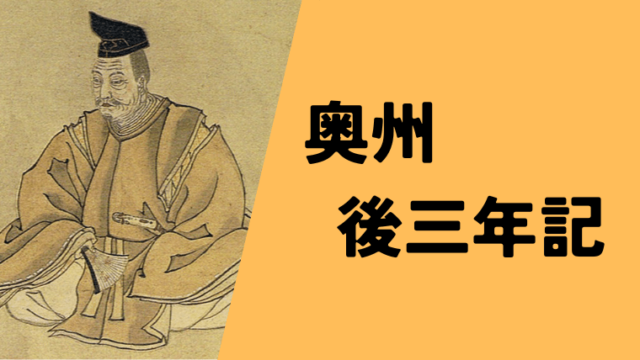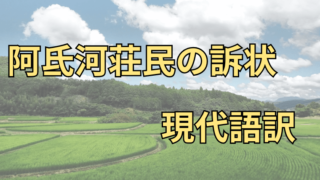一覧は下記サイトをご確認ください。
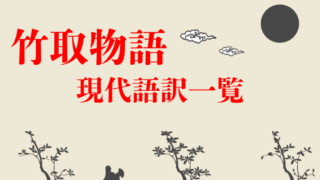
⑦五人目:中納言石上麻呂
中納言石上麻呂が、一族に仕えている男共のもとに行き、
「燕が巣を作ったら知らせよ。」
と仰った。男共はこれを承知し、
「それに何の用でしょうか。」
と申した。大納言は
「燕が産んだ子安貝を取るためだ。」
と答えた。ある男が言う。
「燕を数多く殺して見てもお腹に子安貝はありません。そもそも、子を産む時どのようにして出すのでしょうか。それに、一人一人が燕を見に行くと、逃げてしまいます。」
別の男が言う。
「大炊寮の炊事の建物の屋根にある穴ごとに、燕は巣を作っております。そこに、慎重な性格の男共を連れていき、足場を組み上げて巣を覗かせましょう。燕はそこらじゅうにいるわけですか、1羽も産まないということは無いでしょう。そう取りに行かせましょう。」
中納言は喜び、
「素晴らしいことを言うではないか。全く知らなかった。面白いことをよく言ったぞ。」
と仰って、穴々を確認させにいかせるべく足場に上がらせた。屋敷からは中納言の使者がくまなくやって来て、
「子安貝は取れたか。」
と聞く。
「大勢の人が登ってくるから、怖気づいて巣にも戻ってこないぞ。」
使者が中納言にこのように返事したところ、中納言は
『どうしたら良いだろうか。』
と思い悩んだ。すると、大炊寮の役人の倉津麻呂という者が中納言の御前までやってきて申し上げた。
「子安貝を取ろうとお考えならば、策を申し上げましょう。」
そう言うので、中納言は額を付き合わせて面と向かった。倉津麻呂は続ける。
「それは燕の子安貝の取り方として、悪うございます。それでは取れませぬ。穴々に仰々しく20人の人がいるわけですから、燕は近寄ってきません。男共にやらせる方法とは、まずこの足場を壊して、人は皆その場から退きます。そして慎重な性格の者を一人、荒籠に乗せて座らせ、網を用意して待つのです。燕が子を産もうとする時を。その時に網をつり上げさせれば、すぐに子安貝を取ることができましょう」
と申した。中納言が言う。非常に良い案だ、ということで、足場を壊し、その場にいた人を皆帰らせた。中納言が倉津麻呂に言う。
「さて、再び取りに行かせるつもりだが、燕が子を産もうとする時というのは、どのように判断するのだ。いつ人に引き上げさせたら良い。」
「燕が子を産み落とす時は、尾を高く広げて七度ほど回転するらしいです。なので、七度回る時に引き上げさせます。子安貝はその時にお取りください。」
中納言は喜び、このことを誰にも話さないで密かに大炊寮にやってきては、男共に混じって昼も夜も取ったのであった。倉津麻呂が申したことを、たいへん喜んでいた。
「うちに仕えている人でもないのに、願いを叶えてくれることが嬉しい。」
と言って、着ていた着物を脱いで倉津麻呂に褒美として与えた。更に、
「今夜、大炊寮に参上しなさい。」
と伝えて帰らせた。倉津麻呂は、日が暮れて大炊寮に行ってみると、本当に燕が巣を作っていた。倉津麻呂が言ったように、燕が尾を浮かせて回っていたので、荒籠に人を上らせて罠をつり上げさせた。燕の巣に手を差し入れさせて探らせるも、
「何もありません。」
と言う。中納言は、
「探し方が悪いから見つからないのだ。」
と腹を立て、
「誰にやらせるのが良いか分からん。」
「私が上がって探そう。」
と言って、自ら籠に乗って罠をつり上げて巣の様子を窺っていると、燕が尾を浮かせて忙しく回るのに合わせて手を入れて探ってみると、何か平たい物に触った。
「何か握ったぞ。すぐ下ろしてくれ。翁よ、してやったぞ。」
と仰ると男共が集まっきた。男共は、中納言をはやく下ろそうとしたため綱を引き過ぎてしまった。綱が切れる瞬間、八島の鼎(大炊寮にあった八個の鼎(かなえ)。鼎とは、中国鍋のこと。)の上に仰向けに落ちてしまった。人々は驚き呆れ、近寄って中納言をだき抱えあげると、中納言は白目になって倒れている。人々は水をすくって中納言の口にお入れしたところ、なんとか息を吹き返したので、鼎の上から手取り足取りして地面に下ろした。恐る恐る
「ご気分はいかがですか。」
と質問すると、息も絶え絶えのかすかな声で
「少しぼーっとするが大丈夫だ、ただ腰が動かない。それでも、子安貝はさっと握り持つことができたから、嬉しく思うぞ。まずは脂燭(しそく。油を染み込ませたロウソク)を持ってこい。この貝の姿を見よう。」
と髪を持ち上げて手を広げると、燕がした古糞を握っていたのだった。それを御覧になった中納言が、
「ああ、『貝が無い』ではないか。」
と言ったことから、思ったことと違うことを、「甲斐なし」と言うようになったのである。貝でないと分かった中納言は気分が沈み、唐櫃に入れて蓋が閉まりそうなほど、というわけではないが、それくらい腰が折れ曲がってしまっていた。中納言は、
『子供っぽいことを企んでは失敗に終わったことは誰にも聞かせまい。』
としたけれど、むしろそれが原因でたいそう衰弱してしまったのであった。腰を痛めて貝を取ることができなくなったことよりも、これを聞いた人が笑うことの方が、日が経つにつれて、ますます気がかりになっていた。病んで死に向かっていることよりも、世間の評判の方が恥ずかしいとお思いになったのである。これを聞いたかぐや姫が慰め歌を送ってきた。
年を経て浪立ちよらぬすみのえのまつかひなしと聞くはまことか
年が経っても波すら寄せてこない住之江。ここで人を待つのは無駄だと聞いてますが、それは本当ですか。
→何年経っても、住之江の松には波が立ち寄らないと言います。この松のように、子安貝を待つのは無駄だと聞いていますが、それは本当ですか。
これを中納言に読んで聞かた。中納言は、非常に弱った心でありながらも頭を持ち上げた。そして、苦しい気分でなんとか返歌を作り、人に紙を持たせて書き留めさせた。
かひはかくありけるものをわびはてゝ死ぬる命をすくひやはせぬ
確かに子安貝のことは甲斐有りませんでしたが、こうして貴方からの手紙をいただいただけでも、やった甲斐があったと言えます。ただ、心労で衰えてしまいました。かぐや姫よ、我が命を救ってはいただけませぬか。
そう書き留めさせるの、すぐに息が絶えてしまった。これを聞いて、かぐや姫は、少し気の毒にお思いになったのであった。それ以降、少し感しいことを、「かいあり」と言ったのである。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |