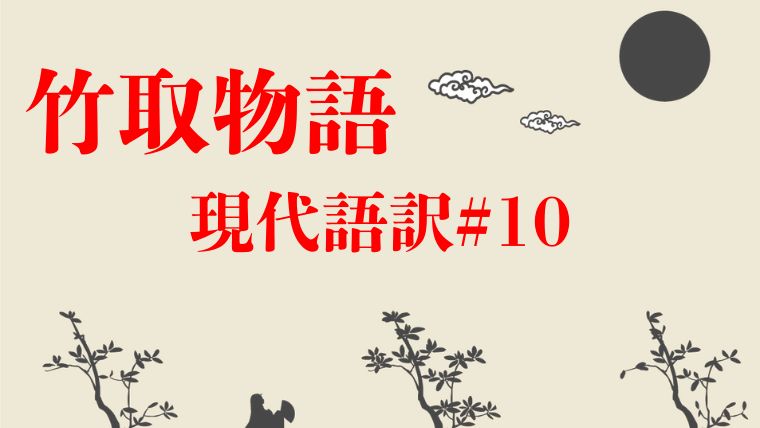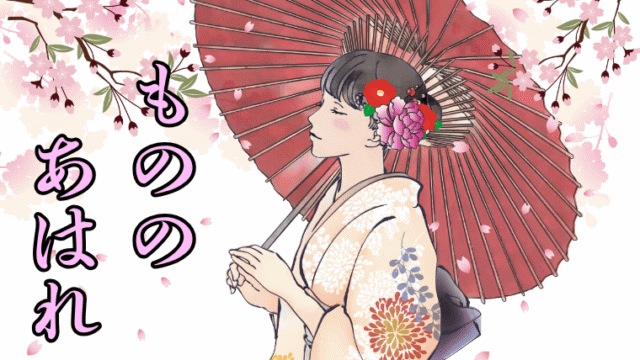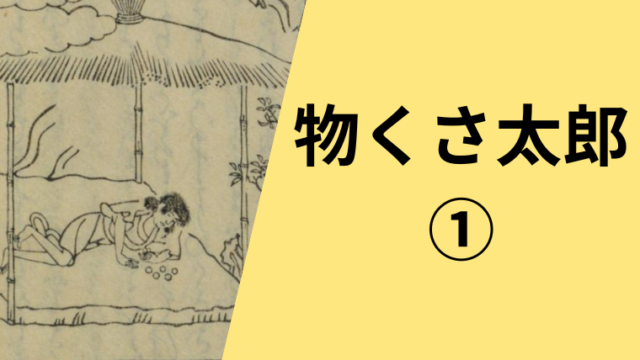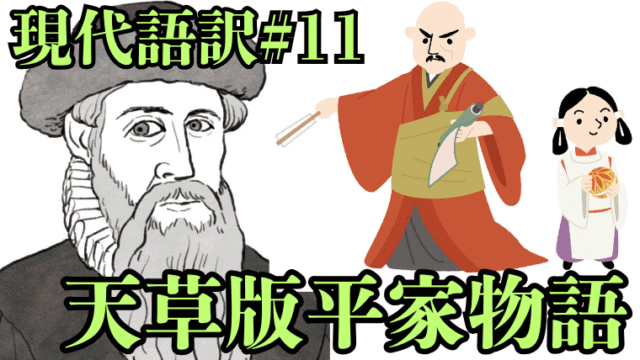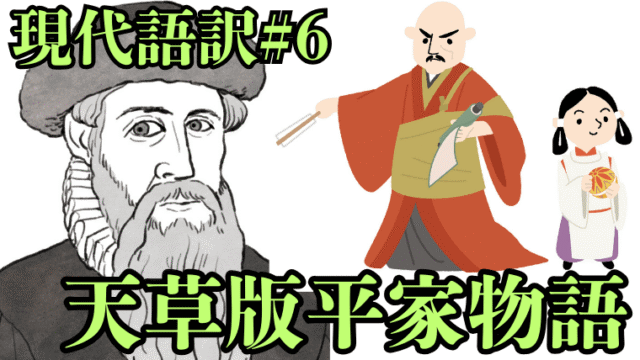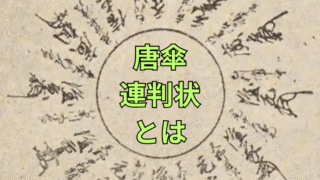一覧は下記サイトをご確認ください。
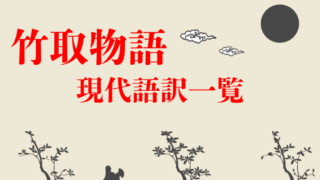
⑩月人の迎え
すると屋敷周辺が昼の明るさ以上に光った。満月の明るさを十倍したほどで、そこにいる人の毛穴さえ見えるほどである。大空から人が雲に乗って降りてきて、地面から五尺(約170cm)ぐらい上がった所に立ち並んだ。
これを見た屋敷の内外にいる人の心は、物の怪に取り憑かれたようになり、戦意を失っていた。皆辛うじて心奮い立たせて弓矢を取ろうとした。しかし手に力が入らずぐったりと物に寄りかかっている。そんな中、勇ましい心を持った者が不自由な身体に逆らって矢を射ようとした。しかし、矢はあらぬ方向へ飛んで行ったのでこれ以上戦う気も起きず、ぼんやりとした気持ちで守護にあたっていた。
宙に立っている人たちの衣装の美しいことは、この世にある物には似ていなかった。飛ぶ車を一つ持ってきており、それには羅蓋(らがい。絹製のきぬがさ。現代で言う日傘。)が挿してあった。その中にいた王と思われる人が
「造麻呂よ、屋敷にいるであろう。出て来い。」
と言った。猛々しく士気をあげていた造麻呂も、何かに酔ったような心地がしてうつ伏せになっている。王が言う。
「お主よ、未熟者よ。お主が少しばかりの功徳を作っていたから、お主を助けてやろうと思い、少しの間ということでかぐや姫をこの世に降ろしたわけだが、長年の間、帝からそこらの金を賜り続け、別人のように富貴になったな。かぐや姫は月の都で罪を犯したから、罰として賤しい身分のお主のもとにしばらくいさせたのだ。その期限が終わったからこのように迎えに来たというのに、お主は泣き嘆くではないか。かぐや姫を渡さないのは不可能だ。早くお返しいただこう。」
と。翁は答える。
「かぐや姫を養い申し上げること20年余りとなりました。それを少しの間と仰ることを怪しく思います。また別にかぐや姫と申す人がおいでになるのではないでしょうか。」
「ここにおわすかぐや姫は、重い病気をなさっているので、とても出て来られる状況では。」
と続けて申し上げるも、それに対して返事は無く、部屋の上部に飛ぶ車を寄せて
「さあ、かぐや姫。このように穢れた所に、どうして長くいらっしゃるのですか。」
と言う。籠らせていた所の戸が、直ぐに開いてしまった。格子戸なども人がいないのに開いてしまった。嫗が抱いていたかぐや姫は外に出ていった。引き止めることができないので、嫗はただただ宙に浮くかぐや姫を仰ぎ見て泣いた。かぐや姫は、心を乱し泣き伏している翁に近寄って
「貴方と同じように、私も意に反してこうして退出するのですから、天に昇るところだけでも見送ってください。」
と言うが、
「どうして、受け入れられず悲しい気持ちですのに、見送ることができましょうか。わしを残して、どうしろと言うのですか。わしを捨てて月にお昇りになるのですか。共に連れて行ってください。」
と翁が泣き伏せるので、さすがのかぐや姫も心乱れた。
「手紙を書き置いてから帰りましょう。恋しく思った時に、取り出してご覧くださいね。」
そう言って泣きながら言葉を綴った。
『私がこの国に生まれた身であれば、親が嘆かなくなるまで傍で侍るものですが、私は月の人、最後まで侍ることができずに親元を離れるのは返す返すも不本意に思われましょう。脱ぎ置くこの着物を形見としてください。月の出ている夜は月をご覧になってください。私は今、親を見捨てて去って行くこの空から落ちてしまいそうな気持ちがしています。』
天人の中に箱を持っている者がいた。ひとつの箱には天の羽衣が、また一つの箱には不死の薬が入っている。一人の天人が
「かぐや姫、壺にあるお薬をお召し上がりください。汚い世界の物を召し上がっていたので、ご気分が優れないはずです。」
と言って箱を手に近寄ってきたので、かぐや姫は少しだけ舐めて、僅かな形見として残すべく、脱ぎ置く着物に不死の薬を包もうとしたが、ある天人がこれを阻止し、そのままもう一方の箱から天の羽衣を取り出して着せようとした。その時、かぐや姫は
「しばらく待て。」
「天の羽衣を着た人は、心が普通ではなくなってしまいます。その前に、一言言っておくことがあります。」
と言って文を書いた。天人は
「遅いぞ。」
と、じれったく思っていたが、かぐや姫は
「人情の分からないことを言わないでください。」
と言い返し、たいそう物静かに帝への使者に文を差し上げた。焦っていないようである。
『このように大勢の人を派遣し私を引き留ようとなさいますが、それを許さない迎えがやって来て、私を捕えて連れて行こうとしておりますので、残念で悲しく思います。宮仕えしなかったのも、このように面倒な事情のある身でございましたので、何も知らない帝は私が宮仕えしないことを煩わしくお思いだったでしょう。頑なに承知しないから、無礼な者という印象で終わることが気がかりでこざいます。』
そう書いて、
今はとて 天のはごろも きるをりぞ
君をあはれと おもひいでぬる
この世界にいるのも最後と思いながら天の羽衣を着る時がきました。帝のことをしみじみと思い出しております。
と歌を詠んで、帝に献上させるべく頭中将を呼び寄せた。この時、あの壺に入っていた不死の薬もこっそり添えていた。天人が間に入って中将に渡し、受け取るのを確認すると、天人はかぐや姫にさっと天の羽衣をお着せした。
羽衣を着たかぐや姫は、翁を『気の毒だ、不憫だ。』と思っていた気持ちが消えてしまった。
この羽衣を着た人は、物思いが無くなってしまうのだ。そして、かぐや姫は車に乗って100人ほどの天人を連れて天に昇ったのであった。その後、翁と嫗は血の涙を流して心惑わしたが、無駄なことである。かぐや姫が書き残したあの手紙を読んで聞かせるが、
「何かをしようとするから命惜しく思うのだ。かぐや姫を失った今、誰のために命惜しく思うのか。何も要らぬ。」
と言って、薬も飲まず、そのまま起き上がりもせずに病に罹って伏している。
さて、中将は、人々を引き連れて宮中に帰った。そして、戦ってかぐや姫を引き止めることに失敗したことを、商才に奏上した。薬の入った壺に文を添えて献上した。広げてご覧になった帝はひどく悲しみ、食べ物も召し上がらず、そして管絃などの遊びなどもしなくなった。帝は大臣や上達部を呼んで、
「どの山が最も天に近いか。」
と問うと、ある人が奏上した。
「駿河国のある山が、この都も近く、そして天にも近い山でございます。」
と。帝はこれをお聞きになって、
あふことも 涙にうかぶ わが身には
しなぬくすりも 何にかはせむ
かぐや姫に逢うことができないと聞いて目に涙を浮かばせる我が身には、不死の薬であっても何の役にも立たないよ。
帝は、かぐや姫が献上したあの壺に文を添えて使者に渡し、調岩笠(つきのいわかさ)という人を勅使に選んだ。そして、
「駿河国にあるという山の頂上に持って行くように。」
と仰せになった。また、山頂でするべきこともお教えになった。
「文と不死の薬の壺を並べ、火をつけて燃やすように。」
と。それを承って、多くの兵士共を引き連れて駿河国の山へ登った。それ以降、その山は「ふし(富士)の山」と名付けられたのである。その煙は、未だに雲の中へ立ち昇っていると言い伝えられている。
(『竹取物語』終)
| 前に戻る << | 次の記事へ >> |