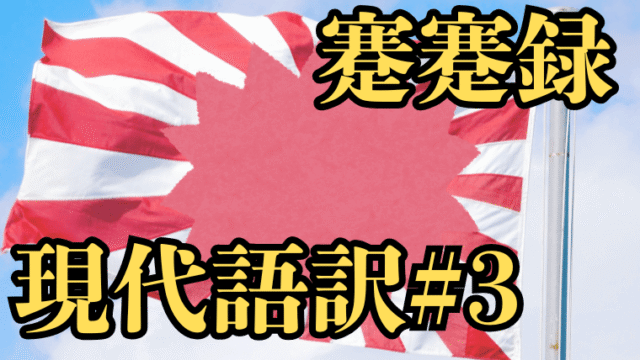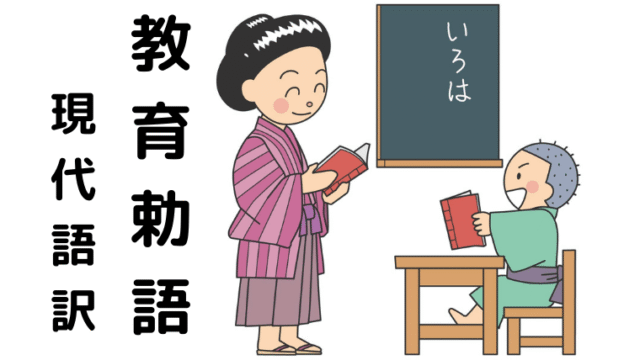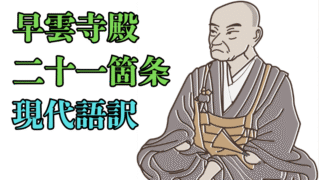9:隠岐配流
こうして、旅程十数日を経て、後醍醐院の乗る御座船は出雲国三尾(美保)津に着き、この港にあった古い御堂を一夜の皇居とした。後醍醐院がまだ六波羅探題に幽閉されていた時、板屋に時雨が降り滴る音を聞いて
住なれぬ 板やの軒の むらしぐれ 聞につけても ぬるゝ袖かな
住み慣れない板屋の軒に聞こえる降っては止みを繰返す叢時雨。この音を聞くと一層、涙が時雨のように流れて袖を濡らしてしまうよ。
と詠んだ。
御製であるだけでも恐れ多いというのに、ましてや、とても皇居とは思えない場所(六波羅南方)でお詠みになったわけである。心中を察して、同情しない者はいなかった。
この三尾(美保)津は田舎なので、下賎な言葉が常に耳に入る。また、風雅とは程遠い荒々しい空気が充満している。後醍醐院が都を忘れるほどの時は経過していなかった。そうでなくても、後醍醐院は目が覚めがちで、夜中に枕をそばだてて、浦に打ち寄せる波がこの近くで騒ぎ立てるのを聞くのである。すると、波の音だけでなく、行き交う人馬の忙しげな音も聞こえてくるのであった。
これを聞いて、昔に詠まれた須磨の寝覚め(源兼昌『淡路島 かよふ千鳥の 鳴く声に 幾夜ねざめぬ 須磨の関守』)、王昭君が匈奴に赴く時の馬上の悲しみ(李白『昭君払玉鞍 上馬啼紅頬 今日漢宮人 明朝胡地妾』)と境遇が同じに思われた。
その夜は少し寝ることができたが、都に帰る夢を見ることは無かった。そうしているうちに夜も明け、後醍醐院は供奉の者に
「ここから出雲大社へはどれほどかかるのだ」と尋ねた。
「その道、遥か遠くでございます。」と申し上げると、武士共に勅命を発した。
「お前たち知っているか。出雲大社の神をスサノヲという。その昔、スサノヲはクシナダヒメを妻とするために、命をかけて斐伊(ひい)川に住む大蛇ヤマタノオロチに挑んだ。これを倒したスサノヲは、その尾から現れた剣、草薙剣を得、クシナダヒメを妻とすることができたのだ。そして、姫を共に宮作りをして、『八雲立つ(八雲立つ 出雲八重垣 妻込みに 八重垣作る その八重垣を)』という31字の歌を残して今に伝わる(31字の和歌を作ったのはこれが始まりだと言われている。和歌の歴史は『古今和歌集序』参照)。朝廷に納められている三種の神器の第一の神器はこの神が得られたものなのだ。」
と涙を止めることができず、そのお顔は、愁いに心預けているようであった。次の日になって後醍醐院はすぐに御座船に乗ったため、送迎した輩は暇をいただき、この三尾(美保)津に留まった。昨年の冬に上洛した関東の使いも下向することとなった。その後というもの、何かと落ち着かない世の中であった。
10:護良親王と楠木正成の挙兵
そのような所に、幼くして比叡山に入山し、天台座主となっていた先帝後醍醐院の第三皇子、大塔宮が還俗されたのだ。還俗し、兵部卿護良親王と名乗る。昨年(1331)に後醍醐院が笠置山に入った時には、大和国の西側にいたとのことは聞いていたが、詳しい所在は不明であった。
しかし、大和国にある多武峰(とうのみね)の吉野の僧都らと護良親王が話し合い、会稽の恥をそそがんとの噂が耳に入った。畿内がまだ落ち着いてない頃、元弘2年(1332)の冬、楠木正成という勇士が護良親王のご意向を受け、河内国の金剛山にある千波屋(千早)城という天然の要害を拠点に、官軍を意味する錦の御旗を掲げた。
昨年笠置山に向かった東国の兵士共が再び上洛して、年明けた春、大将軍阿曽治時は奈良路を経て吉野へ向かっては吉野城を攻め落とした。護良親王の身代わりとなった村上彦四郎義暉(よしてる)を討ち取って、すぐに金剛山の千早城を囲んだ。幕府側は数万の兵を投入、軍略を尽くしたが、最強の要害なだけでなく強弓使いの精兵が多く籠っていたため、寄せ手の兵は多くが命を落とし、傷を負った者は膨大な数に上った。
幕府軍が劣勢に立たされたころ、不思議なことが起こった。
11:隠岐脱出
隠岐国でのことである。後醍醐院の監視役、守護人の佐々木清高は昨年の春(1332)から一族らで後醍醐院を警固していた。その警固人のひとり、佐々木富士名三郎左衛門尉こと富士名雅清という者は常に後醍醐院の傍で仕えて後醍醐院のお言葉に応じていたが、天皇のお心に同情したのだろうか、後醍醐院を隠岐から脱出させたのだった。
隠岐に随行した後醍醐院の側近、千種忠顕(ちくさただあき)が言う。
「私も同じく船に乗り、隠岐を出ましたが、船を運ぶ波がありません。行方も分からない潮の流れに任せて漂いましょう。」
天皇のお気持ちを考えると、この状況がどれほど痛ましいことか。申し上げる言葉もなかった。水は船を浮かべることができるし、逆に船を覆すこともできるという。後醍醐院は今こそそう思われたのだろう。天運は院を味方するのだろうか。この状況で敵が院を襲えば、その身は危うくなっていたに違いない。
そう思っていた所に、後から守護人佐々木清高の兵船数千艘が、矢を射るような速さで御座船を目掛けて追いかけてきた。みな顔色を失ったその時、院は操舵手に言った。
「敵船を恐れることは無い。急いで敵船まで漕ぎ寄せて釣り糸を垂らせ。異国の軍師太公望は釣りをしていたところ、文王が車に乗せて帰ったという話がある(天下取りを釣りに見立てた軍師呂尚(=太公望)の話と、文王がその彼を軍師に登用したという話。)。決して恐れることは無いぞ」こう仰せになった。
操舵手の男はこの命ここまでかと思ったが、勅命に身を任せて釣り糸を垂らした。敵船がこちらに進み寄る。
「怪しい船を見てないか。」
「そのような船は朝に出雲の方へ帆をあげて進んでいましたよ。順風だったので、もう渡海し終えたことでしょう。」
敵はこの船の中を見回ったが、院はイカという海の幸でお体を埋めつくし隠したので、敵はそうとも気付かず、怪しいものは無い、と言って過ぎ去っていった。いやはやめでたし。
後醍醐院は日頃からあらゆる仏や神に祈念していた。特に、伊勢、石清水、加茂、平野、春日大社を初めとする二十二社に祈念を行い、様々な願を立てていたので、此度、思し召しのままに渡海できたのである。
12:船上山御座
さて、佐々木清高の船は出雲国三尾(美保)津に着いた。一族の佐々木孫四郎左衛門高久こと塩冶高貞が出雲国の守護人であったので、「国中の軍勢を招集して与力せよ」と清高は命じたのだが、高貞は返事をしなかった。これは既に後醍醐院より綸旨を承っていたからである。
清高らがそうしているうちに、後醍醐院は伯耆国奈和庄野津郷という所に着いた。この船で働いていた男が
「ここには奈和又太郎という者がおりまして、院をお助けいたします。討死してでも仕えます親類は百、二百もおります。どうぞ、頼って頂きたく申し上げます。是非ともご覧下さい。」
と申し上げた。
「すぐに案内せよ。」
と仰せになったので、その男を先頭に千種忠顕を勅使として遣った。院御一行がちょうど与力が欲しいと願っていてのことであった。この奈和又太郎という者は後に出てくる伯耆守、名和長年のことである。
勅使が名和長年の屋敷の門外でこの旨を仰せになると、院を宿所へ通し、長年が
「院はどちらに向かわれるのですか。」と問うた。
「まだ船にいらっしゃる。」と答えた。
長年は、しばらく待てと言って、馬を連れてきて勅使の千種忠顕を乗せた。己は鎧を着て兄弟子供約50人は歩きで院の元へ参じた。長年の私邸を皇居にするのかと思われたが、
「堅固な要害にはならない」
と言って家に火をかけ、出雲にある船上山という所へ馬にて移動した。険しい山である。
柴などを敷いて食事を取った。その間に面々が着ていた服を引き裂いて縄を作り、輿に献上し、山の頂上を仮の御所を作り臨時の皇居とした。夜も明け、錦の御旗を揚げると、近くに住まう国人らが馳せ参じた。
翌日、追ってきた佐々木清高の軍勢約300が船上山の麓に押し寄せたが、長年の親類らが命をかけて終日交戦、佐々木軍の寄せ手は多く討ち取ら、また、負傷兵が多かったため撤退した。
出雲国、伯耆国の者は一人残らず後醍醐院側についたため、清高軍は力尽きて出雲国に帰った後船に乗り、援軍を求めて若狭国、越前国を目指した。このことが噂として広まりつつある中、山陽、山陰の16ヶ国(山陽:長門、周防、安芸、備後、備中、備前、美作、播磨。山陰:石見、出雲、隠岐、伯耆、因幡、但馬、丹後、丹波)の兵はみな後醍醐院のもとに集った。天が院のお見方をしたのである。
13:後醍醐天皇の天運
昔の話をしよう。中国春秋時代、会稽山において、越王の勾践が呉王夫差に敗れ、夫差の臣下とされたことがあった。そこで勾践の臣下范蠡が策をめぐらし、勾践を奪取することに成功、その後再び矛を交えた時についに呉国を滅ぼした。ただただ范蠡の冷静な行動による結果であり、「会稽の恥を雪ぐ」という故事の由来となった。呉王夫差が滅んだのは、文武を兼ね備えた賢才、伍子胥(ごししょ)の智謀を用いなかったためなのであった。
しかし今回、後醍醐院の隠岐脱出に優秀な臣下の智謀すらなかった。繰り返すが、これは天が院を味方したのである。昨年の春隠岐配流となった時、身分の高い者も、低い者も、関東幕府の恩恵を受けている者も、後醍醐院の遠行の列を見て心ある者が思う事は言うまでもない。心無い卑しい身分である山男、賤女に至るまでも涙で袖を濡らし、悲しまない者はいなかった。人々は、天皇位が安寧であることを祈念したのである。
14:足利尊氏、幕府を裏切る
さて話は戻って播磨国。赤松円心こと赤松則村、以下畿内とその近隣諸国の勢力も残らず後醍醐院側についた。これはただ事ではない。天は後醍醐院を偏重にお味方している。
船上山を本拠とした後醍醐院はついに倒幕の綸旨を出し、元弘3年(1333)3月12日、護良親王や赤松則村らは鳥羽、竹田方面より洛中に侵攻した。鎌倉幕府出張機関の六波羅探題と合戦において勝利、京都より早馬が関東に馳せる間、後醍醐院討伐のために派遣された将軍、足利尊氏が上洛した。4月下旬のことである。尊氏は、元弘元年、かつて笠置山の戦いの際に関東側の大将として派遣された過去がある。
今回の上洛には問題があった。鎌倉五山のひとつ浄妙寺の中興開基、尊氏の父足利貞氏の逝去が2ヶ月前で、四十九日法要が済んでいなかった。悲しみに暮れている最中、大将として都に軍を発するべき、と第14代執権北条高時が申し上げ、もはや異議申し立てるまでもないとして上洛した。
大将として黙ってはいられない事態ではあったが今回の騒動はあってはならない。
「喪中であるが進発せよ。」と関東殿。足利尊氏は関東将軍を深く恨んだとか。
もう1人の大将は尾張守名越高家こと北条高家である。承久の乱の際、北陸道より上洛した北条義時の次男、式部丞朝時(ともとき)の子孫である。前にも述べた通り、4月下旬に両大将が同時に上洛。そしてまた4月27日に同時に都を後にし、西へ向かった。尊氏は山陰の丹波、丹後を経て伯耆へ、高家は山陽の播磨、備前を経て伯耆へ向かった。船上山を攻めることが決定し下向していたわけだが、高家はその道中、伏見にある久我縄手で赤松則村、千種忠顕らの軍勢と激突、高家は討ち取られた。将軍を失った高家軍は戦にならないとして悉く帰京。そしてなんと同日、尊氏将軍は御料所である丹波国篠村にて反旗を翻し挙兵、陣を敷いたのだった。将軍尊氏は倒幕について代々心の奥底にあった上阿波守細川和氏、尊氏の従兄弟である伊豆守上杉重能(しげよし)は密かに事前に倒幕の綸旨を賜っていた。此度の上洛の際、2人は近江にある中山道の宿駅、鏡の宿で天下に公表した。
「既に勅命を承った。時節相応にして天命を授かったのである。」
と、早々に思い立った旨を再三申し上げた。尊氏は篠村八幡宮の御宝前において、柳の大木の先に錦の御旗を掲げた。
「春の陽気の兆しは東からやってくる。柳は「卯の木」と書くように、東方を司る王として春の気を西へもたらす。そして関東武将は東方より進軍している。西からやってくる夏の気と共に朝敵を滅ぼそうぞ。夏の気をもって春には退場してもらう。」
そうして夏の気は京中に充満し、京の軍勢はみな後醍醐院側についたのであった。まさに雲霞のごとし。尊氏は陣を篠村から嵯峨へ移し、近日洛中へ攻め入るとの噂が広がった。3月12日から十数度に及ぶ合戦に敗北した関東勢。その結果、六波羅探題に城郭を構え、ここを北朝初代天皇の光厳天皇(=持明院統)の皇居とし、数万(『太平記』には6万)の軍勢が籠ったのだった。この急ごしらえの皇居には、第93代後伏見院(=持明院統)、第95代花園院(=持明院統)も同じく籠っている。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |