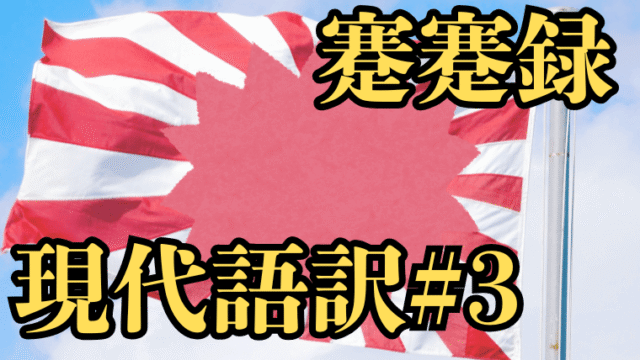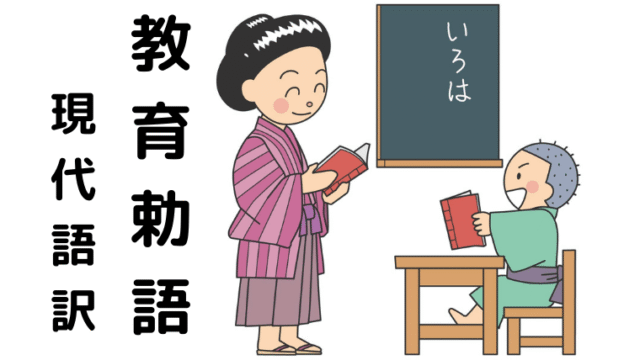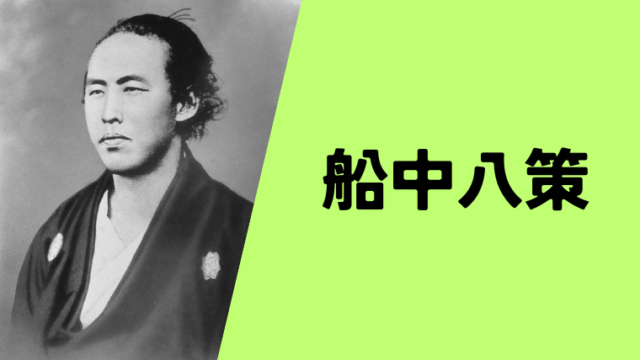現代語訳(後半)
国家を人とみるというのは、もちろん憲法上の明文には掲げられていないのでありますが、これは憲法が法律学の教科書ではないということから生じているため当然の事柄であるといえます。ただ、憲法の条文の中には、国家を法人としてみなければ説明することができない規定が少なからずあるのです。
憲法は表題において、すでに『大日本帝国憲法』と書いてあります。これはつまり国家の憲法であることを明示しているだけではく、第55条・第56条には「国務」という言葉が用いられておりまして、統治の全ての作用は国家の事務であるということが示されているのです。
第62条第3項には「国債」「国庫」と書いてありますし、第64条・第72条には「国家の歳出歳入」という言葉がみられます。また、第66条には「国庫から皇室の経費を支出する義務がある」ということを認めております。
全て、これらの字句は国家「自身」が行っていることでありまして、国家が公債を発行する主体、国家が歳出歳入を行う主体、国家が自己の財産を保有する主体、国家が皇室の経費を支出する主体、であることを明示しているということなのです。
すなわち、国家自身が法人であると解釈しなければ、到底明確に説明できないところもあるのです。その他、「国税」といい「国有財産」といい、「国際条約」というような言葉は、法律上広く公認されておりますが、それは国家自身が租税を課し、財産を所有し、条約を結ぶものであることを明示しているということは申すまでもありません。すなわち、『国家自身がひとつの法人であり、権利主体である。それを我が国の憲法及び法律が公認するのである。』そう私は言わねばならないのです。

国家が国家の利益・国家の目的(=権利の主体)のために、歳出歳入を行ったり、国債を発行したり、条約を結んだりします。これは法人が成すことと変わらないわけですね。
しかし、「法人」と申しますと、ひとつの国体であり、無形人でありますから、その権利を行使するためには必ず法人を代表する人がおり、その者の行為が法律上、法人の行為として効力を有する者でなければならないのでありまして、このような、法人を代表して法人の権利を行使する者を法律学上の観念として「法律の機関」と申すのであります。
突然、「天皇は国家の機関である地位に存在するのである。」というようなことを申し上げますと、法律学の知識の無い者の中には不穏な言葉を吐きたいと感じる者がいるかもやしれません。この「天皇は国家の機関である地位に存在するのである。」というのは、『天皇は、御身御一族の権利として統治権を保有されるのではなく、国家の公事であり、国家のための行為として効力を生じる。』と言い表していることと同じです。
例えば、『大日本帝国憲法』は明治天皇の命令により制定されたものでありますが、明治天皇一個、一人の著作物ではなく、その名称によっても示されております通り、『大日本帝国』の憲法であり、国家の憲法として永久に効力を有するものであります。
条約に関して言うと、『大日本帝国憲法』第13条に明言しております通り、条約は天皇が締結するものでありますが、しかし、それは国際条約、つまり国家と国家との条約として効力を有するものであります。
『大日本帝国憲法』第13条「条約締結」は、天皇が結ぶもの(国家統治の一環)ですが、国家間の条約として効力が発揮されます。つまり『大日本帝国憲法』自身が、統治権は天皇御身の利益、目的のために存在するのではないと証明しているのです。
もし、いわゆる『機関説』を否定し、『統治権は天皇御身に属する権利である』とするならば、その統治権に基づいて賦課されている租税は国税ではなく天皇御身に対して入って来る収入とならなければなりませんし、天皇が締結する条約は国際条約ではなく天皇御身の契約として成らなければなりません。
その他国債といい、国有財産といい、国家の歳出歳入といい、もし統治権が国家に属する権利であることを否定するならば、どうしてこれを説明することができましょうか。もちろん、統治権が国家に属する権利であると申しましても、それは決して天皇が統治の大権を有していることを否定する趣旨ではないことは申すまでもありません。国家の全ての統治権は天皇が総覧される。そう憲法に明言してあるところであります。

私が主張しますところは、天皇の大権が天皇御身に属する私的権利ではなく、天皇が国家元首として行使する権能であり、国家の統治権を活動するか、すなわち、統治権の全ての権能が天皇に最高の効力を発するものであるということなのであります。
私は、それが我が国の国体に反するものではないことはもちろん、最も良く我が国の国体に通ずる所以であろうと固く信じて疑わないのです。
②に申し上げました、『我が国の憲法上、天皇の統治の大権は万能無制限の権力であるか否か』という点につきましても、我が国の国体を論じます者の中に、『我が国の国体が存在するのは、天皇に絶対無制限なる万能の権利が属しているためである。』と言う者が存在するのでありますが、私は、これまでの主張を根拠として、その者らが我が国の国体の認識を大きく誤解していると信じているのです。
君主が万能の権力を有するというようなことがあれば、これは純粋に西洋の思想です。ローマ法王や17世紀、18世紀のフランスなどの思想なのです。我が国の歴史上、いかなる時代においても、天皇が無制限で万能な権力を行使して臣民に命令していた、というようなことは一度もありませんでした。
「天下をしろしめす(=統治する)」ということは、決して無限の権力を行使することができるという意味ではありません。『大日本帝国憲法』の上論において天皇は、「朕が親愛する臣民は、すなわち朕の祖宗が慈しんでくれてはじめて臣民となるのです。。。云々。」と仰せになっているのです。すなわち、明治天皇は、歴代天皇と臣民に対する関係を「恵撫慈養」という言葉によってお示しになったのです。
このような論を出すまでもなく、憲法第4条には『天皇は国家元首であり、統治権を総攬し、この憲法の条規に従ってこれを行使する』と明言されております。
また、『大日本帝国憲法』の上諭の中にも、「朕及び朕の子孫は将来この憲法の条・章に従い、これを行使すること。誤ってはならない。」と仰せになっておりまして、「天皇の統治の大権は、憲法の規定に従って行使されなければならないもの。」として提出されているということを意味するのです。これは明白なことであり、疑う余地などないのであります。
天皇の帝国議会との関係におきましても、同様に『大日本帝国憲法』の条規に従って行使されることは言うまでもありません。菊池武夫男爵は、あたかも私が著書において、『帝国議会が天皇の命令に全く服従しないものとして存在している。』と述べているかのような論を展開しております。もしそうであれば、「解散命令があっても、それに関わらず議会を開くことができる」ということになる趣旨の議論をされているということになります。この点に関しても、男爵が私の著書を通読していないか、又は読んでも理解されていないことの明白な証拠となっているのです。
議会が天皇の大命によって招集され、また、天皇が開会・閉会・停会・衆議院の解散を命じられることは、憲法第7条に明記されている規定であります。これは私の著作の中にもしばしば説明されております。
私が申しておりますのは、「これら憲法や法律に定まっている事柄を除いて、天皇が憲法の条規に基づかずに議会に命令することはない。」ということなのです。
『議会が原則として天皇の命令に服従するのもではない。』と言っていますのは、そういう意味であります。「原則として」と申しますのは、特定のある事柄を除いてという意味であることは言うまでもありません。

議会の法案提出などの行為は、議会「自ら」の意志で行われるものです。天皇に絶対服従していませんね。していたらそんなことできません。
詳しく申しあげますと、議会が立法または予算に協賛し、緊急命令やその他を承諾し、上奏や建議を成し、質問によって政府の弁明を求めるのは、いずれも議会が独立して行使している事象であり、勅命に従って起きた事象ではないということです。
一例として、立法権の協賛を取り上げるとしましょう。立法の協賛とは、法律案あるいは政府や議会から提出されるものであります。しかし、そのうちの議会の提出案につきましては、もとより勅命を奉じて協賛するものではありません。これは言うまでもないことであります。
もう一方の、政府の提出案につきましても、議会が独立して発する意見によって、これを可決するか否決するかの自由を持っていることは、誰も疑わないことであろうと思います。
もし議会が、天皇陛下の勅命のままに可決しなければならない機関として存在し、修正したり否決したりする自由がないとすれば、それは協賛とは言えません。また、こうなってしまえば、議会制度設置の目的が全くもって失われてしまう他ないのであります。
そうであるからこそ、憲法第66条には、『皇室経費については特に議会の協賛を要しない。』と明言されているのです。
第66条には「協賛」という言葉が書いてあります。これはつまり、議会は天皇に「協賛」するものとして機能しているということを裏付けています。
ちなみに、憲法第66条が『皇室経費については特に議会の協賛を要しない。』となっているのは、例えば、皇室経費について議会の協賛を求めれば、下手したら0円で可決される可能性があります。なので、皇室経費に関しては議会の協賛を仰がないわけです。
それとも、菊池武夫男爵は議会において政府提出の法律案を否決し、その協賛を拒んだ場合は、議会が違勅の責任を負わなければならないものとお考えでありましょうか。上奏、建議、質問等、これらが天皇の命に従って起こる事象ではないことはもとより言うまでもありません。
菊池武夫男爵は演説の中で、天皇陛下の信任によって輔弼の重責を背負っておられる国務大臣に対して、「『現内閣は模範として取るに足らない内閣だ。』と判決を下すより他はない。」と言われますし、また、天皇の「至高顧問の府」である枢密院の議長に対しても極端な悪言を放たれています。
それは恐れ多くも、天皇陛下の判断が不適切であると言っていることに他ならないのです。もし議会の独立性を否定し、「議会は何よりも勅命を優先し、これに従ってその機能を行うもの」としますならば、陛下の信任あそばせております輔弼の重責を負った各大臣に対し、どうしてこのような非難を吐くことが許されるでしょうか。それは、議会の独立性を前提としてのみ説明できるところであります。
「この国の議会は国民代表の機関であって、天皇から権限を与えられたものではない」という発言に対しても、菊池武夫男爵は大いに非難を加えるところでありましょう。しかし、議会が天皇の任命によって機能する官府ではなく、国民代表の機関として設けれられていることは一般に疑われないことであります。これが、議会が旧制度の元老院や今日の枢密院と、法律上地位が異なっている理由でもあります。
元老院や枢密院は天皇の官吏から成立しているものであり、その職員は「元老院議官」「枢密院顧問官」と言うのでありまして、「官」という文字は天皇の機関であることを示している文字であります。
天皇がこれを任命あそばせますのはすなわち、官吏に対し権限を与えている、という行為であります。議会はこれに反して「議員」と申し、「議官」とは申しません。これは、議会が天皇の機関として設けられているものではないという証拠です。
もう一度『憲法義解』を引用いたします。第33条の注には、『貴族院は身分の高い人を集め、衆議院は庶民に選ばれた人を集めている。両院があってこそ帝国議会が成立するのである。両院議員は全国の公議を代表して行う存在である。』とあります。すなわち、両院が全国の公議を代表するために設けられているのもであることは『憲法義解』においても明確に認められているのです。両院と、元老院や枢密院のような天皇の機関とを区別せねばならないことは明白であろうと私は思うのです。

元老院と枢密院は天皇の「諮問」機関。国会は天皇の「協賛」機関です。
以上、これまで述べましたことは、憲法学において極めて一般的な真理であり、学者が一般に認めていることであります。また、これらは近頃になって私が唱え始めたような論ではなく、30年前から既に主張されてきたものなのです。今に至って憲法学に対する非難が議場に現れるというようなことは私は思ってもおりませんでした。
今日、この席において、このような憲法の講釈めいたことを申し上げましたことは非常に恐縮なことではありますが、これもやむを得ないことであったと、皆さま、そう了解していただけることをお願い申し上げます。
私は切に願います。もし、私の学説を批評されるというのなら、所々から拾い集めた断片的な片言隻句を捉えて徒に誹謗中傷するのではなく、私の著書全体を通読して、前後の文脈を明らかにし、真の意味を理解して、然る後に批評していただきたい。
これをもって、弁明の辞と致します。
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |