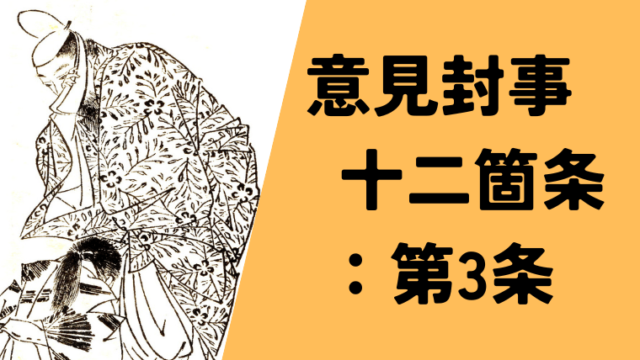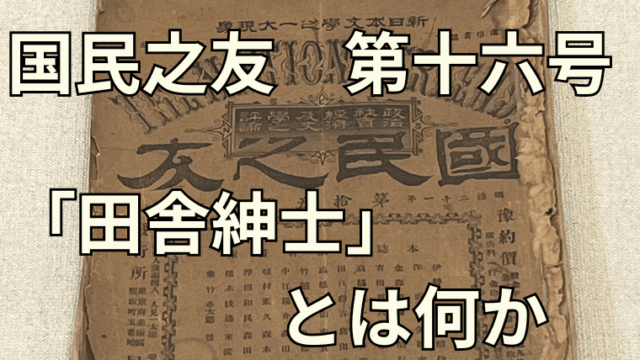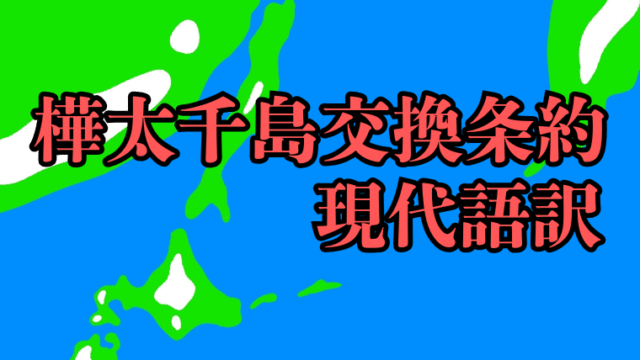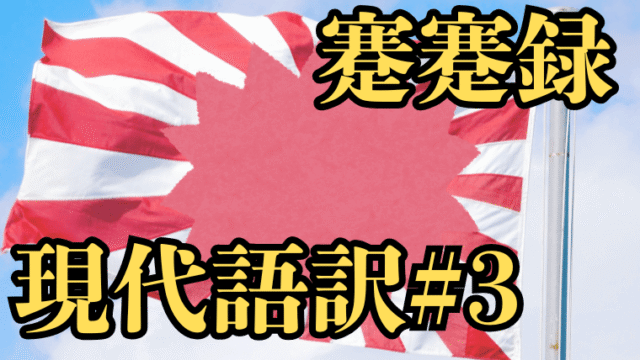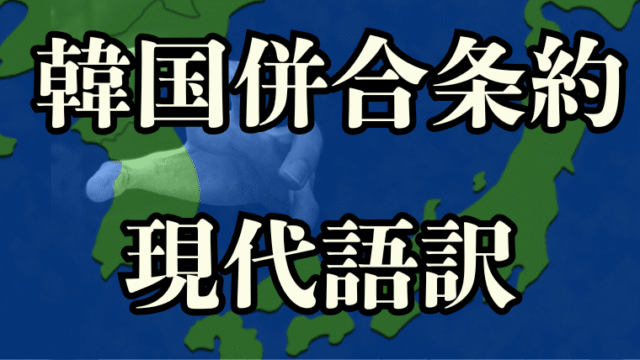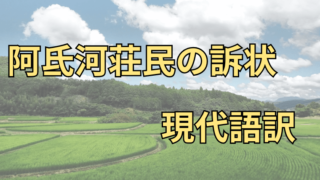現代語訳
第二章:朝鮮に向て日清両国軍隊の派遣
その後、政府は6月4日に京城を発った杉村濬臨時代理公使からの電報から、
『杉村公使が清国軍人の袁世凱と面会し、朝鮮政府はついに清国に援兵を要請し、清国政府がその要請を受け入れて、少数の軍隊を朝鮮に送ることが確実になった』
との情報を得た。そして、6月5日頃から電報で、天津一等領事の荒川巳次領事は外務省に、北京にある公使館付武官の神尾光臣陸軍少佐は参謀本部に、それぞれ清国政府が天津で軍を出動させる準備を進めている様子を伝えてきた。
ある電報では、清国軍隊の一部が某日を目指して大沽から仁川へ直接向かう予定だと報告され、別の電報では、山海関を経由して陸路で進軍する予定だと報告されていた。また、清国の運送船が若干の軍需品を積載して大沽を出航しつつあるとの情報も伝わった。この類の電報が一日に何度も届く状況であった。
特に、北京臨時代理公使の小村寿太郎から、『清国政府がついに朝鮮に兵を送ることを正式に決定した』との確かな報告が届いたことで、朝鮮政府が内乱を鎮圧できず、外部の援助を清国に求め、清国政府がすぐに軍を動かす準備をしている、あるいは、一部が既に派遣された可能性があるという事実について、もはや疑いの余地がなくなった。
したがって、これに対して日本政府は外交および軍事的な対応を一時も怠らないように努め、まず最初に、清国政府が天津条約に基づいて朝鮮への派兵を日本に正式に通知するのか、あるいは『今回の出兵が完全に朝鮮国王の要請によるものである。』という口実をもとに条約を守らないで勝手に出兵を行うのかを確かめることとした。
もちろん、天津条約の規定に関わらず、清国が確実に朝鮮に軍隊を送るというのであれば、日本もまた朝鮮における日清の勢力均衡を保つため、適切な規模の軍隊を派遣することが当然の方針であった。しかしそれだと日本は常に受動的な立場に立つことになる。それを避けるためには、清国政府が天津条約に対してどのような方針を取るのかを確実に把握することが非常に重要だったのである。日本政府は日夜、清国の動きを注視していた。ここで、なぜ清国政府が朝鮮へ軍隊を派遣する際に天津条約を実行するか否かが疑われたのかというと、日清両国の朝鮮における関係は、従来より、氷と炭のようにほとんど相容れない主義に基づいていたからである。
明治6年(1873)頃、当時の外務卿であった副島種臣が特派全権大使として清国に派遣された。副島が北京に滞在していた際、清国の総理衙門王大臣らと、清国と朝鮮の宗属関係について数回の会談を交わしたと私には伝わっている。しかし、公に表明している条約というものは特別存在しておらず、日清両国政府の間に法的な効力を持つようなものは一切なかった。
また、明治9年(1876)には、黒田清隆全権弁理大臣と井上副大臣が朝鮮に派遣され、江華島事件の後始末である日韓修好条規(江華島条約)を締結するに至った。日本は朝鮮を独立国として確認し、朝鮮もこれに応じて自国を独立国として条約を結んだ。とはいえ、日本政府は、清国と朝鮮との間に存在する曖昧な宗属関係を明確にさせる必要性を感じた。故に条約締結の前に森有礼特命全権公使を北京に派遣、彼に訓令を出して、この問題について総理衙門と交渉するよう命じた。そこで両国間で交わされた公文書は積み上がり巻構成となったほどだ。
結果、『清国政府は、一方では朝鮮が自立して内政や外交を行っているため朝鮮で起こった事件に対して清国は直接責任を負わないとしながらも、他方では朝鮮が依然、清国の属邦であり、決して独立した国家とは認めない。』と主張するという、矛盾した態度を取り続けたのである。このような清国の主張が、天津条約に基づくかどうかの疑念を生じさせた背景である。
時は戻して東学党の乱に関する日清の出兵が議論されていた当時、日本政府は天津条約による清国との対立を避けるため、国際法に基づく一般的な見解を引き合いに出して、宗主国と属国との関係というものを説明した。清国は、朝鮮を自国の属国と言いながら、その内政や外交には干渉することはできないと言う。これはつまり、属国という名前だけを使って、宗主国としての責任から逃れようとしていることを意味する。
そのため、日本は朝鮮を独立した一つの国家として認め、内政や外交など、全ての責任は朝鮮政府に負わせるべきだと主張したわけである。しかし、元来より、清国政府との交渉というのは、いつまでも終わらないものであった。かつてイギリスの公使サー・ハリー・パークスが、「底のないバケツで井戸水を汲むようなもの」だと、例えたのも分かる。この件に関する議論も結局、何の結論も得られず、言い争いが続くだけで、問題は未解決のままとなった。公文書にはただ清国の一方的な主張が記録されただけである。
明治17年(1884)の甲申事変の翌年(1885)、当時の参議兼宮内卿であった伊藤博文が特派全権大使として清国に派遣され、いわゆる天津条約が結ばれるまで、日清両国の間で朝鮮に関する正式な一度も合意はなかった。私は、明治9年(1876)に締結した日韓修好条規に基づき、朝鮮は独立国家であると主張したが、一方の清国は依然として朝鮮は中国の属国であるという主張に固執しており、両国が互いに譲り合わない状態であった。
天津条約は、甲申事変において朝鮮で軍事衝突した日清両国の軍隊の後処理を目的としたものであるため、この条約には、清国と朝鮮の宗属関係について定義はされていない。しかし、この条約で日清両国は、朝鮮国内に駐留している軍隊の同時撤退に合意し、さらに今後、朝鮮で事件が起こり、どちらかの国が朝鮮に軍隊を派遣する際には、互いに事前通知することを定めた。とにかく、この天津条約は日清両国が朝鮮に対して均等な権限を持っていることを示す唯一の明文となったのである。
ただし、この点以外に、日清両国の朝鮮に対する権力均衡を保障するものは何も存在しない。もちろん、日本国内でこの天津条約に関して多少の批判を試みた論者がいなかったわけではない。事実、清国政府にとってこの天津条約は大きな打撃となっていた。清国政府が自ら属邦と称する朝鮮に駐在する軍隊を条約に基づいて撤退させざるを得なくなっただけでなく、さらに今後どのような場合においても、朝鮮に軍隊を派遣する際には、必ず日本政府に通知しなければならなくなったわけである。結果として、これまで清国が主張してきた属邦論の論理が大きく力を失ったことは疑う余地はない。
朝鮮問題が進展する中で、英国政府は最初中立的な立場で調停を試みた。また英国は、後に日清両国政府間で一度破談となった共同委員会設置案を再び提案してきたが、日本政府はこれに対して将来のことはさておき、現時点で既に日本が独力で朝鮮政府に勧告して朝鮮政府が同意した改革事項については、もはや清国と協議する必要はないと答えていた。しかし、英国政府はまるで天津条約の意義を、朝鮮における日清両国間の平衡を保つことだと認識しているかのようであったがために、この日本政府の回答に対し「天津条約の精神を無視している」と非難した。その後も英国は、日清両国の軍隊が朝鮮の南北を共同で占拠する度に、徐々に日清両国の調和を図るべきだ、と勧告してきたが、これも同様に誤った解釈である。天津条約の効力が朝鮮における日清両国の権力均衡にどのように影響を与えるのか、という点に関して諸外国からどれほど重要視されていたか、このことから十分理解できるものがある。
本題の問題(東学党の乱に対する出兵の通知)に関して、天津条約が直接関係しているのは『両国が軍を派遣する際には互いに事前通知する』という規定のみである。しかし私が天津条約の解釈をここまで詳しく述べたのは、日清両国政府が朝鮮に軍を派遣するに至ったのがこの条約締結後初めてであり、清国政府が果たしてこの天津条約に従って日本政府に通知するかどうかを確認する必要があったからである。これは今後の日本と清国の外交において最も重要な項目であると私は考えている。このように、日本政府は一方でいつでも朝鮮に軍隊を派遣できるように出兵の準備を急ぎ、他方では清国政府が天津条約をどのように実行するかを見守っていた。
そんな中、東京に駐在していた清国の特命全権公使汪鳳藻は、明治27年(1894)6月7日付の公文書において、自国政府の命令により、
『朝鮮国王の要請に応じて東学党の鎮圧のために若干の軍隊を朝鮮に派遣する』
という旨を通知を日本政府にしてきた。この通知には出兵に関する内容としては無駄な議論が含まれており、やや傲慢な言葉も見受けられたが、その中にあった
「朝鮮は属邦である」
という一句を除いては、今は言葉遣いについて論争をする時ではないため、日本政府はすぐに
『清国政府が天津条約の第三条に基づいて朝鮮に軍隊を派遣する旨の通告を行ったことを日本政府は承認した。』
と返答した。ただし、その通知の中にあった「属邦の保護」という言葉に関しては、日本政府はこれまで朝鮮を清国の属邦と認めたことは一度もないと抗議を付け加えた。一部容認できない部分はあったものの、日本政府は清国政府が天津条約を遵守したのを確認した。もはや一刻も待つ必要はない。私はその夜すぐに北京に駐在している小村寿太郎臨時代理公使に指示を伝えた。
朝鮮国内で重大な変乱が発生しているため、日本からも若干の軍隊を派遣することこれを受けて私は、以下の旨を日本政府に伝えるよう小村臨時代理公使に伝え、小村はこれに従った。
『日本政府が軍を派遣する理由というのは、公使館や領事館、そして商人を保護するためであるため、多数の軍隊を派遣する必要は必ずしもない。それに加えて朝鮮政府の要請に基づく派兵ではないため、日本軍が朝鮮国内に入り、人民を驚かせることはしてらならない。また、万が一清国軍と遭遇した際に、言語の違いなどから何らかの問題が生じることを恐れている。』
と。日本政府は天津条約の規定に従い、朝鮮に出兵することを清国に通告しただけであり、清国から何らかの要求を受け入れる理由は全くないため、私は小村に対してさらに総理衙門に次のような趣旨の回答を伝えるよう指示した。
『第一に、清国が朝鮮に軍隊を派遣するのは「属邦を保護するため」と言うが、日本政府はこれまで一度も朝鮮を清国の属邦と認めたことはない。第二に、今回日本政府が朝鮮に軍隊を派遣するのは、済物浦条約に基づく権利(在韓の役人や一般人を保護するために日本軍隊の駐在を認める権利)によるものであり、またその派遣に際しては天津条約に基づき事前に通知した。日本政府はあくまで自らの意思で行動しており、その軍隊の規模や動きに関して清国政府から干渉を受ける理由は全くない。さらに、仮に日清両国の軍隊が朝鮮国内で遭遇したとして、言葉が通じなくても、日本軍は常に規律と統制に基づいて行動するので、不意の衝突を起こす心配は全くないと日本政府は確信している。従って、清国政府も自国の軍隊に適切な指示を与え、問題が起きないように注意を払ってほしい』
と。これは単に日清両国が既存の条約に基づいた、朝鮮に軍隊を派遣する際の通知に過ぎない。しかし、清国からの通告に含まれていた「保護属邦」という言葉に対しては、日本としては黙って受け入れることができず、これには抗議した。清国もまた、日本の通告に対して多くの質問を試みた。平和はまだ破られておらず、武力衝突もまだ起こっていないが、わずか一通の文書だけで、すでに両国の見解が一致していないことが分かり、互いに争う状態になることが明らかになりつつあった。
異なる電気を帯びた雲が接触し雷となるようにすでに両国は対立しており、これが一瞬で雷鳴と共に激しい衝突となるのは非常に明らかであった。しかし、日本政府はこの危機的な状況においても、可能な限り現在の平和を破壊せずに、国家の名誉を保つ方法を見出そうと懸命に努力した。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |