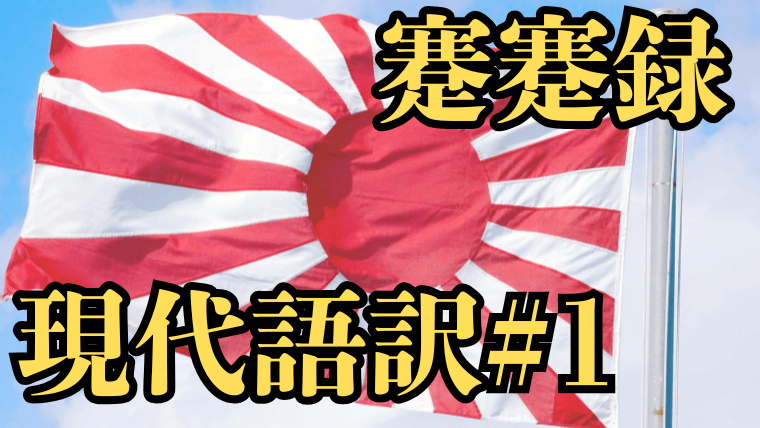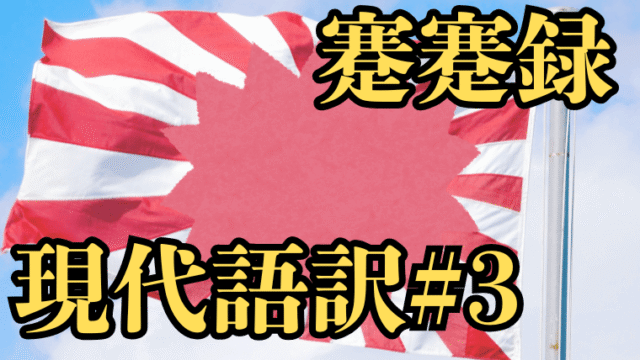蹇蹇録とは?
蹇蹇録とは、陸奥宗光が自身の体験をもとに外交に関してその経緯や所感を示した日記みたいなものです。日清戦争の原因となった「東学党の乱」から戦後の「三国干渉」までが記されています。
構成
全1巻、21章で構成されています。
内訳は以下の通りです。
| 第一章 | 東学党の乱 |
| 第二章 | 朝鮮に向て日清両国軍隊の派遣 |
| 第三章 | 大島特命全権公使の帰任及其就任後に於ける朝鮮の形勢 |
| 第四章 | 朝鮮国の内政を改革する為め日清両国共同委員を派出すへしとの提案 |
| 第五章 | 朝鮮の改革と清韓宗属との問題に関する概説 |
| 第六章 | 朝鮮内政改革の第一期 |
| 第七章 | 欧米各国の干渉 |
| 第八章 | 六月二十二日以後開戦に至る間の李鴻章の位置 |
| 第九章 | 朝鮮事件と日英条約改正 |
| 第十章 | 牙山及豊島の戦闘 |
| 第十一章 | 朝鮮内政改革の第二期 |
| 第十二章 | 平壌及黄海海戦勝の結果 |
| 第十三章 | 領事裁判制度と戦争との関係 |
| 第十四章 | 講和談判開始前に於ける清国及欧州諸列国の挙動 |
| 第十五章 | 日清講和の発端 |
| 第十六章 | 広東談判 |
| 第十七章 | 下の関談判(上) |
| 第十八章 | 下の関談判(下) |
| 第十九章 | 露、独、仏三国の干渉(上) |
| 第二十章 | 露、独、仏三国の干渉(中) |
| 第二十一章 | 露、独、仏三国の干渉(下) |
現代語訳
第一章:東学党の乱
朝鮮の『東学党』という集団に対する国内外の人々からの評価を列挙すると、ある者は
「儒学と朱子学を混同した一種の宗教団体。」
と言い、ある者は
「朝鮮国内における政治改革を目指す一派。」
と言い、ある者は
「単に反乱好きの暴徒の集団。」
と言う。
東学党がなぜこのような性質を有しているか、本書において追究する必要はないが、簡単に事実を記しておこう。東学党なる名称を有する一種の反乱民は、明治27年(1894)4月から5月にかけて全羅道と忠清道(いずれも自治体名。朝鮮半島中部〜南西部あたり。)の各所で蜂起し、点在する官舎を強奪し、地方官を殺害し尽くした。また、本部を京畿道に進め、全羅道の首府である全州府も一時は彼らが手中に収めた。このように、彼らは勢いが盛んで荒れ狂っている。
こうして、日清両国は各々主張する権利と持論をもって朝鮮に出兵、日清戦争が始まった。いくつかの形勢の変転を経て、ついに海上戦陸上戦となったが我が軍が連戦連勝、その後清国政府は使者を私(陸奥宗光)に送っては和睦を乞うてきた。
下関条約を結び、従来の日清両国の外交関係は一変(清韓の朝貢関係消滅、日本の近代化の成功による優位性の確固など)、世界は日本を東洋の優等国として認識するに至った。この近因は清韓両国の政府が東学党の乱への対応と我が国との外交を誤ったからである。もし、日清両国の間の当時の外交について書き綴る者がいるのするならば、必ず最初の一巻一章は東学党の乱を置くだろう。
東学党の勢いは日に日に強大となり、朝鮮の官軍は至るところで敗走、東学党はつい全羅道の首府、全州府をも陥落させるまでとなった。このことが我が国に報告されるや否や、新聞各社は競ってこれを紙面に起こし、物議を醸しては騒然となり、
「朝鮮政府に東学党を鎮圧する力は到底ない。我が国から派兵しこれを平定するべきだ。」
とか、
「東学党は韓国政府の暴政に苦しむ人民を救済しようとする真の革命党である。故に、東学党に加勢して、彼らの目的である韓国政治の改革を成功させるべきだ。」
と言う。
特に普段から政府に反対していた政党の者らは、この機に乗じて、我が党員を困らせるための一時的な政略だ、とも考えた。そう言ってしきりに世論を扇動する姿は、戦争の気勢を高めようとする者らのようであった。
当時の朝鮮駐在公使、大島圭介は休暇を賜り日本へ帰国していたため、臨時の代理公使を立て、これを杉村濬が務めた。杉村は朝鮮で数年勤務しており朝鮮の国情に精通していたため、日本政府はもちろん杉村の報告に信頼を置いていた。
こうして届いた杉村君からの5月頃の諸報告から考えるに、東学党の乱は近年において朝鮮で稀な事件であるが、東学党ら今の韓国政府を転覆させるほどの勢力を有しているとは認められない。また、東学党の進行方向によっては、我が国の公使館や領事館、居留民を保護するために多少の軍隊を派遣する必要があるべきかもしれないが、これを測るのは難しい。目下において言うと、京城はもちろん、釜山や仁川も、そこまで懸念することでもないと言えよう。故に、日本政府はこの時においては出兵するか否か議論するのはやや早いと思われた。
しかし、そうは言っても朝鮮の治国は常に乱雑。ややもすれば、想定外のことに奔走する清国の展開する外交に対しては、予め政略を用意しておくべきだと考え、私は杉村君に
①東学党の動きに十分注視
②韓国政府の東学党に対する処分はどのようなものか視察
③韓国政府と清国使者との関係がどのようなものか視察
以上を内密に命じた。
この時日本の議会は開会中で、衆議院はいつも通り政府の反対意見を持つこと多数、あらゆる項目において紛議が繰り広げられたが、政府はなるべく寛容な姿勢をとり、衝突を避けようと試みた。しかし6月1日、衆議院は内閣の行為を非難する上奏案を議決、政府はやむを得ず最後の手段として議会解散の詔勅を発令奉るよう天皇に奏請した。
これは容易に進まない事案である。もし東学党の乱を目視する時はすでに、異常に朝鮮に固執する日清両国の朝鮮での権力争いはなお一層激化するだろう。日本は将来朝鮮に対してただただ清国のなすがままに任せる他なく、日韓条約を結んだ意義も、踏み潰される恐れがあった。
そのため私は同日の会議に赴いては開会時にまず閣僚に杉村君の報告を示し、なおかつ私と意見交換をした。
「もしも清国が何の口実もなく朝鮮に軍隊を派出するといった不測の事態が起きたならば、日清両国の朝鮮に対する権力の均衡を維持するべく、日本も軍隊を派出すべきであります。」
と述べた。
全閣僚がこの議題に賛同、伊藤博文内閣総理大臣(第2次)は直々に人を派遣し、参謀総長有栖川宮熾仁(たるひと)親王殿下、参謀本部次長川上操六陸軍中将の臨席を求めた。2人が来会するとすぐに、今後における朝鮮への軍隊派遣の評定を協議、決定した。伊藤博文内閣総理大臣はこの件と議会解散の閣議決定を携えて直接明治天皇のもとへ参内、規則に則りご聖断賜り、これを執行したのであった。
こうして朝鮮国へ軍隊を派遣することが決定した。私は直々に、大島浩特命全権公使にいつ赴任しても問題ないよう準備することを命じ、また、西郷従道海軍大臣と内議し、大島公使を軍艦八重山に搭乗させ、海兵を若干増載した。そして、軍艦八重山が全て大島公使の指揮下に置かれる旨の訓令が発布された。参謀本部は第五師団長に内密に命じ、師団から若干の軍隊をいつでも派遣できるよう準備を命じた。
また、郵船会社等に対しては秘密裏に運輸と軍需の徴発を命令。急な出来事ゆえ、極めて敏捷に種々の事が進められた。以上の政略は外交上、軍事上の機密に属するため、一般人がこのような動向を知る由もない。
こうして政府の行動に反対する者は、政府の評議がこのように進行していることも知らずに、頻りに各々の新聞や遊説委員を使って
「朝鮮に軍隊を派遣することは急務である!」
と厳しく主張し、激しく政府の怠慢を責めたてた。彼らは暗に、議会解散に対する憤りを洩らそうとしていた。
政府の方針はすでにこのように決定したが、これを朝鮮で実際に執行する際には、国家の大誤算がないようにしなければならない。そのため政府は慎重に議論を重ね、更に方針を追加、確定した。
日清両国が各々軍隊を派遣する以上、衝突、開戦するかもしれないのだが、これが本当に起きるのか否かは予測し難いことであった。もしこのような事変が発生すれば、我が国は全力を尽くして当初の目的を貫くために、議論を待たず軍隊を派遣する。しかし、なるべく平和を破らず、国際的に日本国の栄誉を維持し、日清両国の朝鮮における権力の均衡を保つべきである。私はなるべくこの軍事行動に被動する立ち位置を執りながら、清国においては平和的解決を主動することにした。
また、この一大事件が発生すれば必ず第三者的立ち位置の欧米諸国との関係に変化が生じる可能性があった。外交の慣習として、欧米諸国が二国間の問題に仲介に入っていたからである。これに関してはどうしようも無いだろうと思う。外交問題は日清間に限るよう努力し、第三国との関係に問題が生じることを避ける。これが重要な点であった。
この政略は伊藤博文内閣総理大臣と私との念入りの議論によって出された結論であり、多くは伊藤総理の意見であった。当時の閣僚は全会一致で賛成、天皇の勅を賜った。日清戦争が起きれば、日本政府は始終この方針を一貫させることに努める。
日本政府の決定は述べた通りであるが、敵国である清国政府が果たして日本と同様の決定をしたのかは非常に疑わしい。そもそも、日清両国の朝鮮における権力争いの始まりは非常に古い。これに関しては本書で詳述する必要もなかろう。
現在の日清両国は、朝鮮における権力をいかにして維持するか、という点に関して、各々の考えのほとんどが氷と炭のように相容れないものであった。というのも、日本は最初より、朝鮮を一個の独立国として認め、従来から続く清韓間の朝貢関係を断絶しようとしていたが、これに対して清は、昔から続く朝貢関係を理由に朝鮮が我が国の属国であることを国際的に表明しようとしていた。
実際はというと、清は、国際的な公法上、朝貢との朝貢関係を認められるのに必要な要素を欠いている現状である。そのため清国は、せめて名義上だけでも、と意気込んで、朝貢関係を認めてもらおうと努めている。
特に明治十七年(1884)に勃発した京城事変(甲申事変)。親日派金玉均と日本軍が手を結び、親清派の閔氏を倒そうとクーデターを起こしたが、清国の介入によって鎮圧された。それ以後は、清国の朝鮮における勢力が著しく大きくなるに相応しい状況となったわけである。
一個人にせよ一国家にせよ、権力を得るとそ段階では満足できず、いよいよ権力を強めようと欲するのは世の常である。清国もこれに例外ではない。
しかしながら、清国は「清国と朝鮮は朝貢関係にある」と称するも、朝鮮は、清国の完全無欠の属国であることに甘心していない様子がみられるし、それだけでなく、常に朝貢関係の維持に妨害を加えようと、東隣にいち強国が存在しているのだから、清国政府がどうしてもこれを除去しようと考えることは自然である。今京城に駐在している清国軍の袁世凱のような気鋭のある壮年が日本との交戦を熱望していることは想像に難くない。
袁世凱は、明治17年(1884)の甲申事変以来、日本の朝鮮における勢力が微弱なものになったと理解した。また、明治23年(1889)に『大日本帝国憲法』を公布して以後、政府と議会とが常に軋轢している状況を見て、日本政府には、他国に向かって軍隊を派遣するか否か、といった大決断をする力は無いと判断し、この機に乗じて清国の朝鮮における勢力拡大を志した。
こうして日本に駐在していた清国公使、汪鳳藻も「日本は到底他国に対して何か事を起こす余力はない。」と思い込み、様々な所見を祖国政府に通告したのであった。両国が意図せず開戦に投合したのである。清国政府は最初から日本の形勢を見誤っていた。これが清国敗北の一因であろう。
日清戦争開戦直前の韓国政府の情勢を思い返そう。世は大院君の妻、閔妃の一族、いわゆる閔族が専制政治を敷いていた。そのような状況でありながらもなお閔族同胞で争っていた事実があったことは隠蔽することはできない。
当時、閔泳駿は王室の外戚として時勢ある職に就き、その職権を苛烈に行使していたのだが、それとは関係なく東学党の乱が起こった。東学党の官軍を次々に破る勢い、そして身内同士の争い。内外からの攻撃が閔泳駿の一身に集中し、彼は困苦艱難を極めたのである。日本か清国か、結果閔泳駿は清国使臣の袁世凱と結託して清国軍隊の派出を要請、彼らは一時しのぎの策を尽くした。
聞くところによると、当時の朝鮮政府大臣、そして国王までもが、
「東学党の鎮圧に、よその国である清国の助けを求めることは極めて危険な選択だ。」
として、閔泳駿の行動を非難したという。清国軍隊が朝鮮に入れば、これに対して日本もまた出兵することになるからだ。だからといって、閔泳駿の他に自ら進んで責務を受け、あえて難局に挑もうとするほどの勇者もいなかった。そして閔泳駿はついに清国に対して朝鮮国王を臣と称させ、清国軍隊の出兵を乞うたのである。
以上に述べた事実は、東学党の乱に関して清朝両国が外交を誤ったことを示している。そしてこれは、朝鮮政府のとった不適切な内政の第一段階目である。簡単に言うと、日本政府は当初から受動的な立場をとっており、やむを得ない状況になるまでは最後の手段を取らないよう決めていた。
しかし清国は、まず言葉で、次に行動で威嚇すれば十分と考えたわけである。日本との問題が解決しなかった場合、最終的に武力行使する覚悟がなかったようだ。清国が既にそのような状態であったため、朝鮮政府は、強国に依存する事大主義に基づき、どのようなことが起こっても、日本が清国に勝つなどとは全く考えず、 大船に乗った気持ちで清国だけを頼っていたのだろう。
このような認識の誤りに陥ったまま日清戦争は開戦、清韓両政府が平壌の戦い(大損害を与えた本格的な陸戦)や黄海の戦い(制海権を奪った海戦)が終わるまで、その誤りに全く気づかなかったのは、やむを得ないことであった。
| 一覧に戻る << | 続きを読む >> |