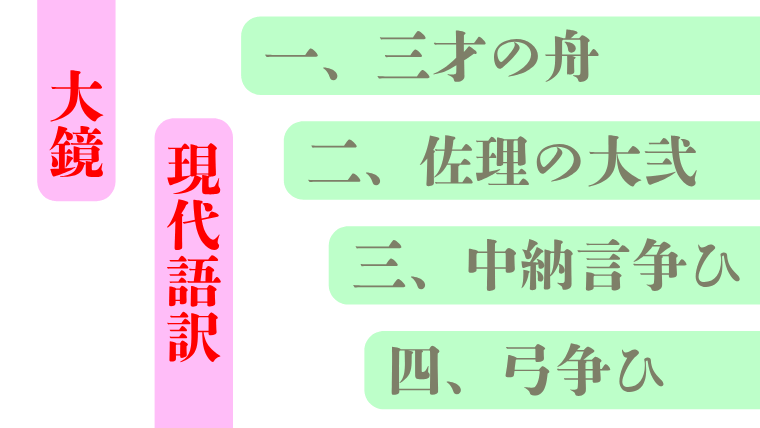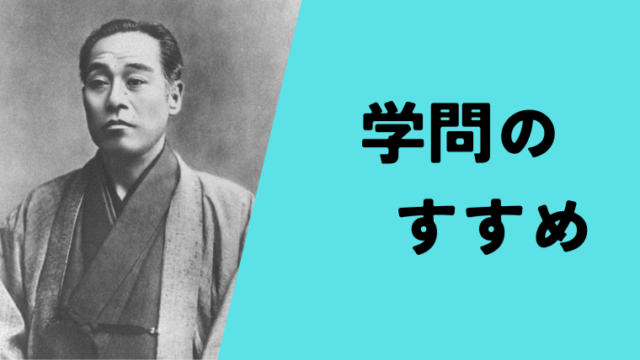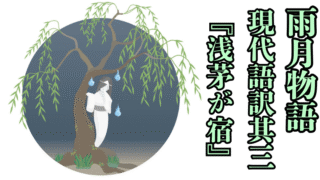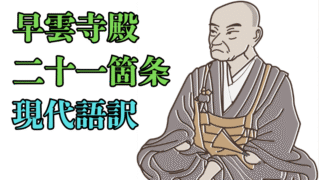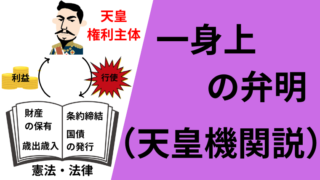『三舟の才』
登場人物
- 入道殿(藤原道長)
- 大納言(藤原公任)
単語
- 逍遥 :自由気ままに過ごす
- さても:それにしても
現代語訳
ある年、藤原道長が大井川(現代の静岡県を流れる河川)で自由気ままにお遊びになり、舟遊びをした。出した三艘の舟を、漢詩を作る舟、音楽をする舟、和歌を詠む舟とお分けになった。
その道に優れている人達をお乗せになった時、藤原公任がいらっしゃったので、道長は
「公任はどの舟に乗るでしょうか。」
とおっしゃった。
「和歌の舟に乗りましょう。」
と公任は返して続けて詠んだ。
小倉山 嵐の風の 寒ければ
紅葉の錦 着ぬ人ぞなき
小倉山や嵐山から吹いてくる風が寒く、その風で紅葉が散っていく。散った紅葉が降りかかって皆錦の着物を着ているようだ
ご自身で乗る舟を申し上げた甲斐があって上手な和歌をお詠みになったのだった。
公任が自ら仰るには、
「漢詩の舟に乗れば良かったなあ。この和歌と同じくらい立派な漢詩をお作りしたら、名声が上がったことだろうに。残念である。それにしても道長殿の『どの舟に乗るだろうか。』と仰ったのは、私も期待されたものです。我ながら得意げになってしまいました。」
と。一つのことに優れているだけでもまれであるのに、いずれの道にも抜きん出た才能をお持ちなのは昔にも例のないことであります。
『佐理の大弐』
登場人物
- 藤原佐理
- 気高い様子の男
単語
- あやしく:不思議に
- おどろく:目を覚ます
- 昼の装束:正式な束帯
- いとど :いよいよ
現代語訳
藤原佐理は敦敏の少将の子である。世間でも評判の能筆家である。大宰府での任期が終わり京に上られる時、伊予の国の手前にある港に宿泊した。その日はひどく荒れた天気で、海の状態も悪く、風が恐ろしく吹き荒れるなどしていた。
「少し天気が良くなってから港を出よう」ということにしていたが、また同じようにその日も天気が荒れていた。このようにして数日が経過したので、このような転機をたいそう不思議にお思いになって占いをなさると「神の祟りだ。」とだけ言った。しかし神の祟りを受けるようなこともしていない。どうしたものかと恐れなさりその時に次のような夢をご覧になったという。非常に気高い様子の男がいて、
「天気が荒れ、数日ここでお過ごしになっているのは私がそうするようにしたからなのです。全ての神社の社に額がかけられているのに私の所に限って額がない。それが不都合と思い、私も額をかけようと思いました。しかし、普通の筆跡で書かせるのは悪いことだと思われました。そこで能筆家であるあなたに書いていただこうと思い、この逗留中いつお書き願い申し上げようかと、引きとどめているのでございます。」
と仰るので、「あなたは誰でしょうか。」と返した。
すると「私はこの海岸におります翁であります。」と言う。
佐理は夢の中でもたいそうかしこまって引き受ける旨を申し上げようと思ったところ目をお覚ましになった。引き受けたことは言うまでもない。さて、伊予に向けて海を渡ると、荒れた日は少なく、天気はうららかであった。加えて追い風が吹いていて、飛んだかのように伊予の国にお着きになったのだった。そして何度も湯浴びをし、非常に潔斎を行い、身を清めたところで正式な束帯を身につけ、すぐに神の御前でお書きになる。神司などをお呼び出しになって一連の決まり事を行い、約束通り額を書いて奉納した。その後京に向けて足を進めたのだが、少しも怖く思うことが無くて末端の従者の船に至るまで無事に皆で京へお上りになった。
自分のすることを人間から褒め讃えられることでさえ愉快なことであるのに、まして神の御心にまで自分の行いを褒め讃えて欲しいと思うとは、いかに佐理がおごり高ぶっていることか。そしてこのことによって佐理はいよいよ日本屈指の能筆家として世間からの評判を獲得なさったのであった。佐理は六波羅蜜寺の額もお書きになったという。そのため、あの三島の社の額とこの寺の額は同じ筆跡である。
『中納言争い』
登場人物
- 九条殿 (藤原師輔)
- 御九郎君(藤原為光)
- 藤原斉信(為光の弟)
- 師輔 (為光の父)
単語
- わざと:わざわざ
- はかる:騙す
- 除目:任命式
- うつ伏す:うつむき
現代語訳
藤原師輔の九男である藤原為光は大臣の位に七年在位しており、法住寺の大臣と言われていた。彼は左衛門督である藤原誠信が人を恨んだままお亡くなりになったその様子を非常に驚き呆れたのだった。他人に官位の先を越され、つらい目に遭うことはよくあることでございますのに、お亡くなりになる運命であったのだろうか。これは藤原誠信が亡くなる原因となった中納言争いの話である。
同じ宰相であった弟である藤原斉信に比べ、藤原誠信は人柄、世間の評判は劣っていらしただろうと思われる人だった。中納言の座が空いた際、自分がその座に入ろうとしてわざわざ藤原斉信と対面なさり、
「この度の中納言の件、その座を望みなさるな。私が立候補申し上げます。」と仰った。
すると弟の斉信は
「どうして兄上より先に中納言の座を取りましょうか、いやない。ましてこのように仰るのであるから、立候補などあってはならない。」
と言い、このことを聞いた誠信は満足した様子で、その後、中納言の立候補をたいそう申し上げなさった。誠信は中納言の器には及ばないのだろうか、この様子をみた藤原道長は弟の斉信と話をした。
「お主は兄のように申し上げないのか。」
「左衛門督である兄が申し上げるので、私は。」
「あの左衛門督は中納言におなりになれないだろう。また、あなたがその座を避けるとなれば、他の人が中納言になるに違いないぞ。」
「兄が中納言になれないのならどうして他の人がその座にいようか。それなら私が中納言に。」
そうして、弟の斉信が中納言におなりになったのだった。兄の斉信は
「私に向かって『立候補などあるはずがない。』と言っていたのに、どうしてこのようなことに。私を騙したのだな。」と憤慨した。
いよいよ恨む気持ちを露わにして、任命式の日、朝から手を強く握り
「道長に私の昇進の道が阻まれてしまったぞ。」
と言っていた。食べ物も全く召し上がらないでうつむきなさっていたところ病にかかって、それから七日目にお亡くなりになったのだ。握った手の指はあまりにも強く、手の甲まで貫通して、指が出てきていたのだった。
解説
左衛門督は六位相当の官位であったと言われています。そして中納言は従三位であり、中納言の座に着けば破格の昇進となります。弟の斉信はその優しさから兄に中納言の座を譲ろうとしました。この優しい人柄が世間で評価されていたと窺えます。
対して兄の誠信は自身の能力を十分に理解していなかったため、自身が中納言の器でなかったと気付くことが出来ませんでした。そのため、道長と弟が共謀して騙したと思い込んだのです。もし、自分をもっと客観的に見ていたら、すんなり「中納言に及ばず」と現実を受け入れられたかもしれません。
誠信の人を疑ったり、思い込みが激しかったりという点を見ると、弟にとうてい及ばないことが分かります。その憎しみの深さと言ったら最終文にあるとおり、想像を絶するものであったのでしょう。
『弓争ひ』
登場人物
- 師殿 (藤原伊周)
- 中関白殿 (藤原道隆)
- 殿=関白殿(藤原道長)
単語
- 饗応:食事や酒でもてなすこと
- 無辺世界:仏教用語から転じて、見当はずれな場所や方向
かたへ:側に仕える者、仲間
現代語訳
藤原伊周が南院で人々を集めて弓の競い合いをされていた時、藤原道長がいらっしゃった。「思いがけないものに出会った、珍しい。」
藤原道隆は道長の姿に驚いて、道長をたいそう食事や酒でもてなした。
また、道隆は主催の伊周よりも身分が低い道長を先に矢を射るようお立てになったのだが、二人の行射が終わり結果を確認すると、身分の高い伊周の弓が道長に2本及ばなかったのだった。道隆や、彼らにお仕えする人々も
「勝負を2回ほど延長しましょう。」
と申し上げたので勝負を延長なさったのだが、このことが道長は穏やかでなく思われたようで、自ら「それでは、延長してください。」と仰ったのだった。
再び弓を射ようとした時、
「将来我が家系から天皇、皇后になる者が出るというなら、矢よ当たれ。」
と仰るも、当たったとはいえ中心ではなかった。
次に伊周が矢を射るのだが、たいそう臆したご様子でその手も震えていらっしゃったため、射た弓は的のあたりにさえ近づかず、見当はずれな方向へ飛んで行った。これを見た道長は顔色を青くした。
2周目になった。道長が射ようとした時、今度は「摂政、関白の地位に着くのなら、矢よ当たれ。」と仰った。すると矢は的が破れんばかりの勢いで飛んでいき、初めに射た場所と同じところに命中したのだった。
道長をもてなした時の雰囲気も冷めてしまい非常に気まずくなったのだった。主催の伊周の父である大臣は伊周に対し、「なに射ようとしている。射るな。射るな。」と制しされ、そのせいで完全に場が冷めてしまった。
そして道長は矢を戻してすぐに退出なさったのであった。
その頃、道長は左京大夫と呼ばれており、弓を上手に射るし、そしてたいそう好んでいらっしゃった。今日の一度で、この話通りの実力が見られるというわけではないが、道長のご様子や仰ったことのその趣旨から、側でお仕えする者は気が滅入ってしまったという。
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |