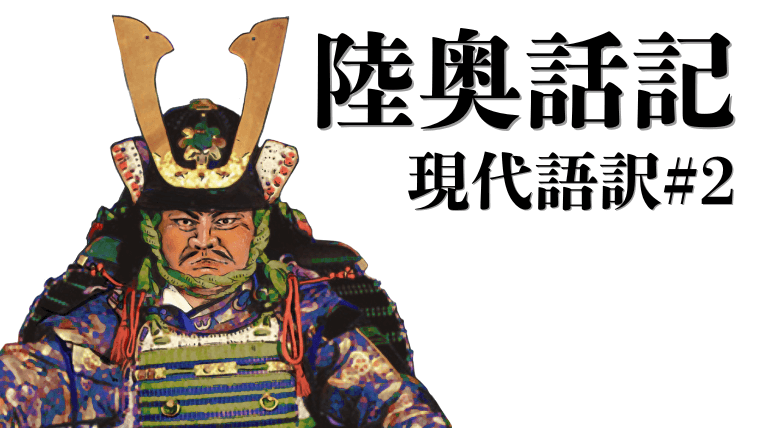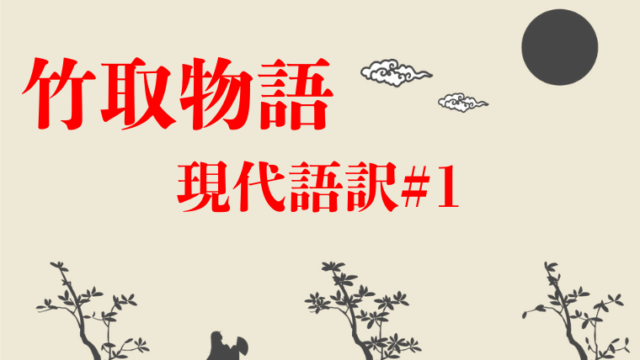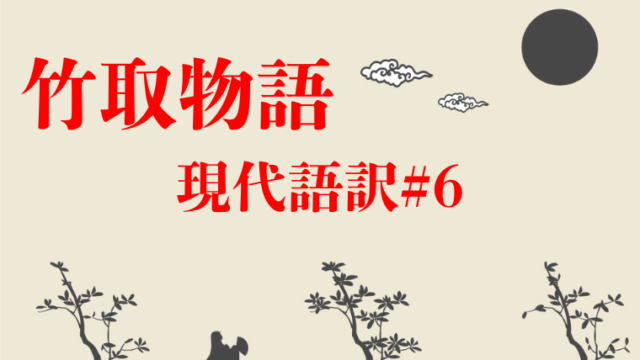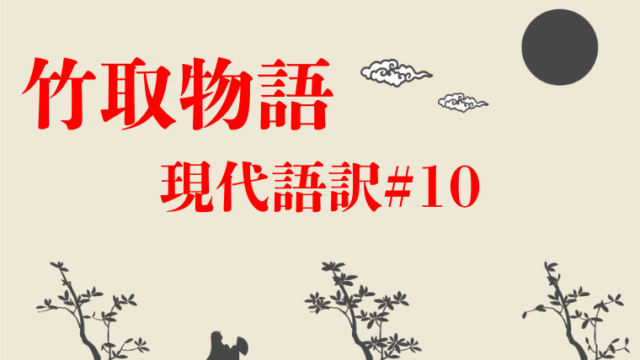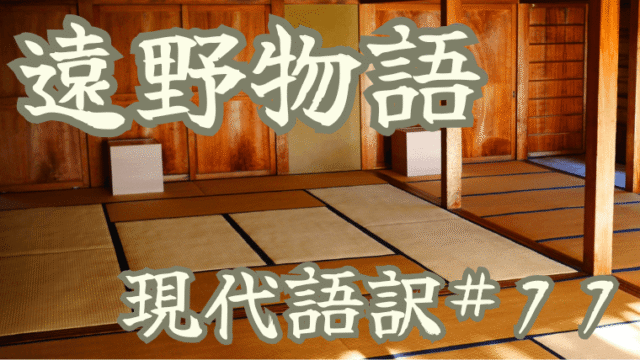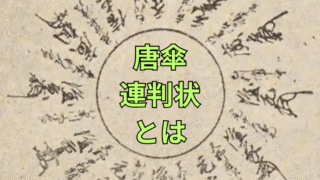現代語訳
源頼義の経任と頼時の死
頼義が陸奥国司の任期を終えたため、朝廷は新たな陸奥国司を任命したのだが、戦の知らせを聞いた新任の国司はこれを辞退し、任地に赴かなかった。このため、源頼義が再び任命されることとなり、頼時討伐を継続することとなった。しかし、このの騒乱によって国内は飢饉となり、十分な食料が供給できなかったため、大勢の兵が散り散りに去っていった。
再び合戦するべく策を巡らしいるうちに年月は経過し、天喜5年(1057)の秋9月、国府の頼義は朝廷の太政官に対し、安倍頼時討伐を進言する上申書を出した。その上申書にはこう記されていた。
『臣下、金為時と下毛野興重(しもつけののおきしげ)らは奥地の俘囚を懐柔し、官軍に味方させることに成功した。これにより艶屋(えんや)、仁土呂志(にとろし)、宇曾利(うそり)の3地域の蝦夷たちが、安倍富忠を首領として挙兵、金為時に従って進軍を開始した。しかし、これを知った安倍頼時は自ら出向いて、彼等に対して敵味方双方の利害を説明して説得を試みた。これによって頼時側に2000人ほど兵が靡いてしまった。富忠は伏兵を配置し、山岳地帯で彼らを攻撃した。激戦が始まって2日目、安倍頼時は流れ矢に当たり負傷、撤退先の鳥海(とりのうみ)柵で命を落とした。これで弱体化すると思われたが、頼時の残党はまだ降伏しなかった。そのため、我々は朝廷に対して官職や爵位を求めるとともに、諸国から徴兵して兵糧を調達し、残党を悉く誅伐することをここに提案する。朝廷から官符を賜り、兵糧を供給して軍兵を動員することを目指す。』
と。しかしながら、この案については朝廷の重臣の間で意見が一致せず、実行には至らなかった。
黄海の戦い
まだ論功行賞が始まっていないうちに、同年11月、頼義将軍は約1800の兵を率いて安倍貞任を討とうとした。対して貞任らは精鋭約4000人を率い、金為行が守る河崎柵を拠点として黄海(現岩手県一関市域)で頼義軍を迎え撃った。
風雪が非常に激しい天気で、頼義軍は行軍に困難を極めた。そして食糧が尽き人馬ともに疲れ果てた。一方の貞任軍は新たに手に入れた馬を駆り出し、疲弊していた頼義軍に襲いかかった。これは単に地元側と来訪側の土地に対する情報量が異なるだけでなく、兵力の多寡による差も大きかった。
官軍は黄海の戦いで敗北しましたが、それを補うかのように、猛者たちの武勇伝が以下に書き連ねられています。
黄海の戦い(それぞれの戦い:源義家)
頼義軍は大敗を喫し、数百人が戦死したが、頼義将軍の長男源義家は驚異的な勇敢さを発揮した。その騎射の腕前は神のようであった。義家は壁のようになった白刃の戦場を突き抜けて貞任軍を突破、大きな鏃の弓を放っては貞任軍の兵をひたすら射抜いた。その様子は雷が走り風が吹き荒れるかのようで、武神がこの世に降り立ったかのようであった。矢は雑に放っているわけではない。中った者は必ず死んだ。
貞任軍は逃げ走り、義家に立ち向かう者はいなかった。これによって陸奥の者らは彼を称えて「八幡太郎」と呼ぶようになったのである。このあだ名の意味するところは、漢の李広が飛将軍と呼ばれるのに同じである。
黄海の戦い(それぞれの戦い:藤原景通ら6騎)
頼義将軍の従者の中には、散り散りに逃げる者から戦死や負傷する者まで様々であった。最終的に残ったのはわずか6騎。長男源義家、修理少輔藤原景通、大宅光任、清原貞廣、藤原範季、藤原則明である。対して貞任軍は200騎余りを翼のように左右に展開し、包囲して攻撃を仕掛けた。
飛び交う矢はまるで雨のようであった。この時、頼義将軍の馬が流れ矢に当たって命を落とした。馬を得た藤原景通は頼義将軍のもとへ駆け、頼義将軍の窮地を救った。義家の馬もまた矢に中り死んだが、藤原則明が敵から馬を奪い、義家を助けた。
死地を脱するのは非常に困難な状況であったが、義家はひたすらに敵の指揮官を射殺し、また大宅光任ら数騎は決死の戦いを繰り広げた。そしてついに、貞任軍は前進することができなくなり、撤退したのであった。
黄海の戦い(それぞれの戦い:佐伯経範と臣下)
この時、頼義軍中に散位の佐伯経範という者がいた。経範は相模国の出身で、頼義将軍から厚遇されていた。別の戦場で戦っていた経範は、味方の敗北が決まり包囲が解けた時、将軍の行方が分からなかった。兵に将軍の行方を尋ねると、兵は答えた。
「頼義将軍は賊軍に囲まれております。従者はわずか数騎しかおりません。思うに、この状況で脱出するのは難しいでしょう。」
と。佐伯経範は言った。
「儂は将軍に仕えすでに30年。老いること齢60となった。将軍もまた70歳を迎えようとしておる。今、このような壊滅的な状況で、どうして将軍と命を共にしないことがあろうか。死して地の下まで付き従うのが、儂の本望だ。」
と。そして経範は引き返し、貞任軍の包囲の中へ飛び込んだ。経範に従った随兵は3騎。彼らは経範に言った。
「殿がすでに将軍と命を共にし、節義を尽くして死ぬとならば、我々がどうして一人だけ生き延びることができましょうか。たとえ陪臣(身分の低い臣下)であっても、節義を慕う心は身分に関係なく同じでございます。」
こうして彼らも一緒に貞任軍に突入した。戦はますます激しさを増し、彼らは貞任軍10人余りを討ち取った。劣勢の官軍、みな賊軍の前で倒れ、殺された者の屍は林のようであった。
黄海の戦い(それぞれの戦い:藤原景季)
藤原景季は景通の長男で、20歳ほどである。もともと口数の少ない性格で、騎射を得意としていた。合戦では、死を克服し普段通り陣中に帰ってきていた。貞任軍に飛び入っては兵団の首長を討ち取って帰ってくる。こういったことを七、八度繰り返していた。しかし、馬が倒れ、遂に景季は貞任軍に捕らわれてしまった。貞任軍は景季の武勇を惜しく思ったが、頼義将軍の親兵であることを憎み、その首を切り落としたのだった。
黄海の戦い(それぞれの戦い:藤原茂頼他)
散位の和気致輔(わけのむねすけ)や紀為清(きのためきよ)らは皆、命を顧みず、将軍のためにその命を捧げた。将軍のために死力を尽くした武士たちは皆、このような散位の人々であった。藤原茂頼(ふじわらのしげより)は将軍の腹心である。勇敢な男で善戦していた。
彼は軍が敗れて数日間、将軍の所在が分からず、周りの兵も
「すでに賊軍に討たれて命を落としたのでは」
と考えていた。藤原茂頼は悲しみ泣きながら言った。
「我は将軍の遺骨を探し出し、きちんと葬りたい。しかし今ここは戦火の激しい場所となっている。僧侶でなければ立ち入ることもできまい。髪を剃り、僧侶となって遺骸を拾うしかない。」
そうして茂頼はその場で出家し僧侶となり、戦場を目指して歩みを進めたのだった。だが道中、茂頼は将軍と会った。喜びと悲しみの感情を同時に覚えながら、将軍に付き従い帰還した。出家はあまりにも急な決断に思えたが、その忠義と節操は十分に感動を呼ぶものであった。
黄海の戦い(それぞれの戦い:平国妙)
また、散位の平国妙(たいらのくにたえ)は出羽国の出身である。勇敢な男で善戦していた。常に多勢を寡兵で打ち破っては一度の敗北もなかったため、人々は彼を「平不負」と呼んでいた(「平大夫(たいらのだいぶ)」という字に、「負けない者」という意味を込めたものである)。
大夫(だいぶ)を”大”負(だいぶ)と文字遊びします。さらにこれを、”大”負←→”不”負と逆の意味の単語で文字遊びします。これで、「負け知らず平国妙」という肩書の完成です。
頼義将軍は不負を呼び、先陣を任せた。この戦いの最中、馬が倒れて賊軍に捕らえられてしまったが、鬼切部の戦いでの敗北を機に貞任軍に属していた藤原経清が甥であったため、その縁故から命を助けられた。しかしこの行為は、武士として非常に恥なことであろう。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |