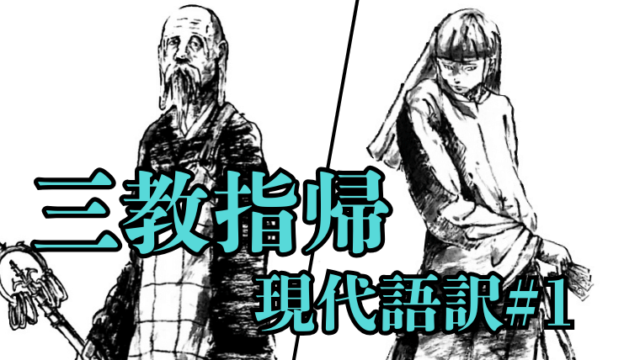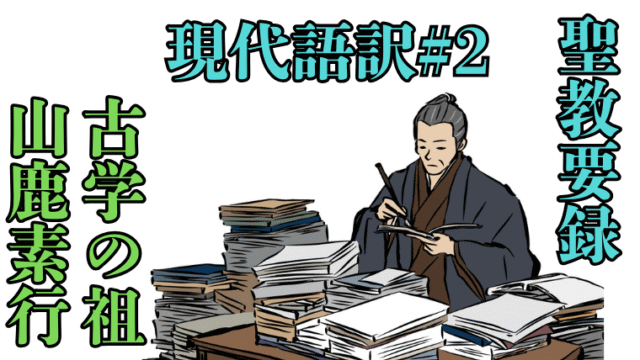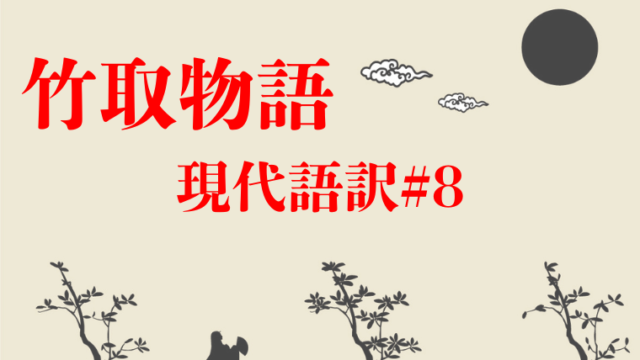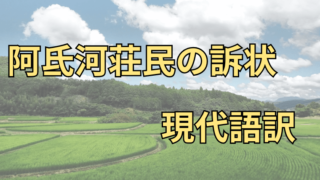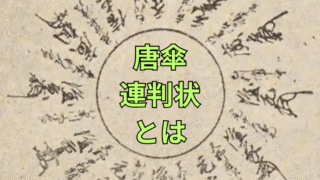現代語訳
安倍氏の台頭
奥六郡(岩手・紫波・稗向・和賀・江刺・胆沢)の俘囚長(=鎮守府長)に安倍頼良(よりよし)という者がいた。この者は安倍忠良の子である。
祖父である安倍忠頼は東夷の首長で、その威風は大いに広がり、村落はすべてこれに従っていた。忠頼は奥六郡を横行しては人民を脅して略奪を働いていた。こうして子孫は繁栄し勢力は拡大。次第に衣川(現岩手県南西部)以南にも進出するようになった。
身勝手な振る舞いは度を超え、安倍氏は税を納めず、また労役にも従事しない態度を朝廷に示していたのだが、代々驕り高ぶっては贅沢を極めたこの一族を誰一人として制することはできなかった。
鬼切部の戦い
永承六年(1051)、陸奥守であった藤原登任が数千の兵を率いて安倍頼良を攻めた。先鋒は秋田城介(出羽国の秋田城を拠点とした国司)の平重成で、登任は後詰めとして自ら兵を率いた。頼良は諸郡の俘囚をもってこれに抗戦、玉造郡の鬼切部において激戦となった。
その結果、登任の軍勢は敗北、大量の死者を出したのであった。官軍の敗北である。これを受けて朝廷は追討将軍を選ぶ議論を行い、全会一致で源頼義に任命することとなった。頼義は河内守源頼信の子である。頼義の性格は沈着で毅然、そして武略に富んでいたため、最も将軍にふさわしい器であった。
源頼義という人
長元(1028-1037)の頃、平忠常は坂東の奸雄として暴虐行為を働いていた。平忠常の乱(1028-1031)である。朝廷は幾度も追討使を送るも鎮圧に失敗、平忠常がついに降伏したのは、源頼信が追討使として派遣された時であった。これには嫡子の頼義も同行していた。一連の戦いによって、頼義の勇気と群を抜いた決断力、そして才気が世に知られるようになった。そのような頼義を慕い、下につく坂東の武士は少なくなかった。
頼義は若い頃、三条天皇の第一皇子、敦明親王(小一条院)の判官代(事務官)を務めていた。院は狩猟を好んでおり、よく野に出ていた。頼義にとっては、麋鹿(大鹿)、狐、兎などは常に格好の獲物であった。頼義はあえて弱い弓を使うのを好んでいたが、それでも、放った矢が獲物を逃すことはなかった。たとえ猛獣であっても頼義の矢に中れば必ず絶命するといったほどで、その射芸の巧みさは他者を大きく超えていた。腕前は述べた通りである。そんな頼義の騎射の技術に上野守平直方は感嘆し、密かに語り合ってはこう言った。
『我は不肖ながらも名将(桓武平氏)の子孫である。それが故に武芸を重んじている。これまで頼義卿ほど弓の巧みさを持つ者を見たことがない。ぜひとも、我が娘を貴方の箕箒(身分の低い妾)として仕えさせたい。』
と。こうして頼義は直方の娘を妻として迎え、三男二女をもうけたのであった。長男が義家、次男が義綱である。
義家は、2度目の東北内乱である後三年の役の中心人物で、この戦(前九年合戦)の主人公である源頼義の子です。
その後、判官代の功績により頼義は相模守に任ぜられた。武勇を好んだ頼義の名声を聞きつけては多くの民が頼義のもとに帰服した。頼義の威風は大いに振るわれ、頼義に対抗しようとする者たちは皆、奴僕のように従う他なかった。
また頼義は武士を愛し、施しを好む人物であったため、坂東以東に住まう、弓馬に優れた武士の大半は彼の門客となった。相模守の任を終えた後、頼義は上洛し、京で数年を経た今、朝廷の選抜に応じて征討将軍として重任を担うこととなったのである。
この重任のために頼義は陸奥守と鎮守府将軍を兼任、安倍頼良の討伐を命じられた。頼義の人柄と武勇は天下がよく知るところであり、頼義の任命は誰もが納得したのであった。
頼義の赴任
陸奥守として境(陸奥国のこと。陸奥国が蝦夷との境であることが由来)に赴任した直後、朝廷では上東門院藤原彰子の病気快癒祈願のために大赦が行われた(1052)。つまり安倍頼良(よりよし)は罪が赦されたわけである。これを聞いた安倍頼良は大いに喜び、頼義と同じ名前を避けるため『頼時』と改名、その後頼義に身を委ねるかたちで服属した。これにより、陸奥国内は無事平穏となったのである。頼義の統治は順調であった。そして国司としての任期を終える年(1056)、頼義は政務を行うため鎮守府胆沢城に入った。
阿久刀川事件(事件発生)
胆沢城に入城してから数十日間、頼時は身を低くして、謹んで頼義将軍に仕え、駿馬や金銀宝物など全てを将軍陣営に献上した。また、兵士を供出し、鎮守府から国府に帰る頼義の道中を護衛するよう手配もした。しかし、ある夜、阿久利川のほとりで、密かに報せが届いた。それは、権守こと藤原説貞の息子である光貞や元貞らの野営で、何者かが人馬を殺害したという報せであった。頼義将軍は藤原光貞を呼び出し、疑わしい者について尋ねた。光貞は答えて言った。
「以前、頼時様のご長男、貞任様が私の妹を妻に迎えたいとお望みになったことがあったのですが、我が一族の家格が低いことを理由にこれを拒否しました。断られたことを貞任様は『深く恥をかかされた』そうお考えになったと聞いております。故に、貞任様の仕業ではないでしょうか。他に我が一族に仇を持つ者はおりません。」
と。これを聞いた頼義将軍は激怒、貞任を召し出して罪を問いただそうと考えた。頼時は自分の子や甥たちに向かって言った。
「人はこの世界に生きる以上、誰もが家族や子供を持つものである。貞任が愚かであったとしても、父親というのは子への愛情を捨てることができない。貞任が一度でも誅罰を受けることになれば、どうして私はそれを忍ぶことができようか。故に、関所を閉じて頼義将軍の命は聞かないこととする。もし将軍が攻めてきたとしても、我が兵でそれを拒み、戦えばよい話である。将軍との交戦は憂うに及ばぬ。戦わず将軍のもとへ参じても、戦いに敗北しても、我々がともに死ぬ運命は避けられぬ。」
と。左右の者たちは皆こう言った。
「仰る通りです。泥ひとつで衣川の関を封じればよいのです。誰があえてそれを破ろうとするでしょうか。」
と。そこで頼時は道を閉ざし通行を遮断した。頼義将軍はこの行為にますます怒り、大軍を頼時に向けた。坂東の猛士たちが雲のように集まり、雨のように押し寄せ、歩兵と騎兵は数万に及び、補給物資や戦闘具が幾重にも積まれ、野を埋め尽くした。国内中が震え上がり、恐怖から、頼義軍を誰しもが歓待した。
阿久刀川事件(平永衡の誅殺)
この時、頼時の長女有加一乃末陪(ありかいちのまえ)の婿で散位(官位を持たない者)の藤原経清や、次女中加一乃末陪(なかのかいちのまえ)の婿である平永衡らは頼時に背き、それぞれ私兵を率いて将軍側についた。藤原経清や平永衡を含む将軍一行が衣川に近づいた時、ある者が頼義将軍に言った。
「平永衡は以前、前任の陸奥守、藤原登任の従者としてこの国に下向し、厚く恩恵を受けて一郡を領有していました。しかし、頼時の娘を娶ってからは登任に反意を抱き、合戦の際には頼時に加勢したのです。かつての主君であった登任に仕えなかったこの行為は不忠不義の行いです。今は表面上帰服しているように見えますが、内心では奸謀を企んでいるに違いありません。」
と。恐らく、裏で間者を用いて軍の動きや陰謀を調べさせ、報告させていたのだろう。また、平永衡が着用していた甲冑は他の兵とは異なっていた。銀の兜をかぶっていたのである。これは、合戦の時に敵兵が自分を狙わないようにするためだろう。古代中国、黄巾の乱や赤眉の乱のように、自他を区別するためが故か。
「早く永衡を斬り、頼時との内通の可能性を断つべきです。」
という意見に頼義将軍は
「尤もだ。」
と答え、行軍を再整備した。その後、永衡と、永衡の最も信頼している腹心の兵4人を召して、罪を問いただして斬り殺した。
阿久刀川事件(藤原経清の策略)
これによって、藤原経清一行は平永衡と同様に殺されることを恐れ、心穏やかでなくなった。そして、身近な客人に向かって密かに語った。
「前の車がひっくり返るのを見れば、それは後ろの車への戒めとなる(過去の失敗から学べという意)。古代中国、韓信や彭越が誅殺された時、黥布が恐れを感じたのと同じ状況だ。伊具十郎(平永衡)が誅殺された今、我々もいつ誅殺されるか分からない。どうすればよいか。」
客人は言った。
「殿が真心を示し、頼義将軍に誠実に仕えたいと思うのなら、それをやり遂げるべきですぞ。将軍は必ず最後まで殿を守ってくれます。と私は申し上げておりますが、実際、讒言が将軍の耳に入る前に反走して、安全な所に身を寄せる方が良いに越したことはありませぬ。将軍の御ために忠誠や功績を立てたとしても、いざ命を失った後では意味ありませぬ故。」
経清はこれを聞いて、
「その通りだ、それが良い。」
と納得した。そして経清は流言を立てて軍中で混乱を引き起こした。次のような噂である。
『敵の頼時が軽装の騎兵を別の道から進軍させて国府多賀城を攻め、頼義将軍の妻子を奪おうとしている。』
頼義将軍の家来は、家族が国府にいる者が多かったため、彼らは将軍に対し国府に戻るよう進言した。頼義将軍は家来たちの勧めを受け入れた。精鋭騎兵数千人を自ら率いて急ぎ国府へ帰還したのである。夕方であった。その間、配下の気仙郡司である金為時らが兵を派遣して頼時を攻撃した。頼時は僧侶の弟、良昭らを使ってこれに対抗した。
為時軍は一時的に優勢だったものの、後方支援がないことが原因で激戦の末に撤退。この状況を見て、藤原経清らは混乱する大軍の隙を突き、私兵約800人を率いて頼時のもとへ合流したのだった。
| 前の記事へ << | 続きを読む >> |