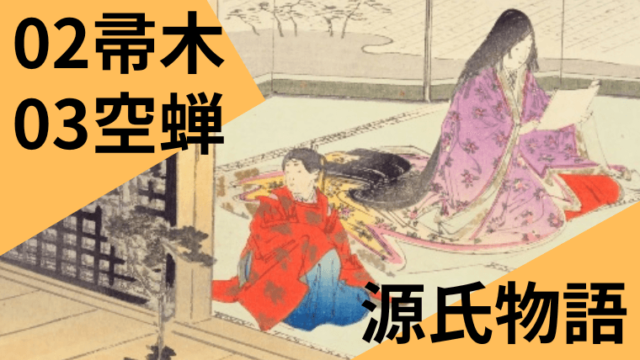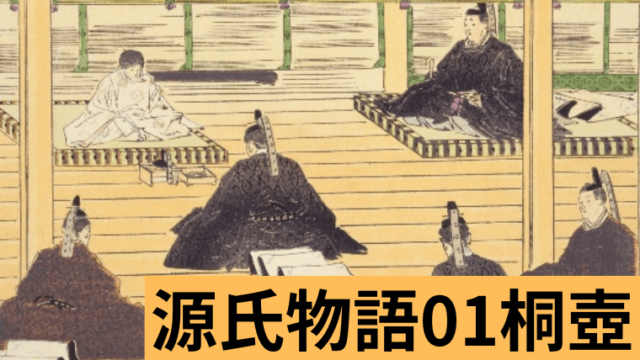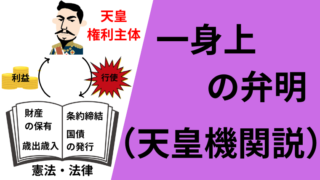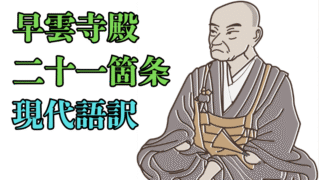現代語訳
| 一覧に戻る << | 続きを読む >> |
第十二 有王鬼界が島に渡つて俊寛に会ひ、俊寛死去せらるれば荼毘をして、その遺骨を頸にかけ、都へ帰り上り、方々修行してその後世を弔うた事。

右馬之允
それで、喜界ヶ島に残された俊寛はどうなったのだ?

喜一
そのことです。鬼界ヶ島へ流された3人の流人のうち、2人は召し還されて都へ上りましたが、俊寛は寂しい島に1人取り残され島守となって、その地で果てました。俊寛は幼い頃から不遇な境遇でしたが、そんな彼には、その時から召し使っていた童が1人おりました。名を有王(ありおう)と申します。
都にいた有王は
「鬼界ヶ島の流人たちが今日すでに入京したらしいぞ。」
と聞いたので、鳥羽まで出迎えに行ってみたのですが、自分の主人の姿は見えませんでした。
「どういうことか。」
と尋ねると、
「『俊寛はまだ罪が深い。』と清盛公が仰せになったらしく、島に残されたのだ。」
とのことで、有王の悲しみは言うまでもありませんでした。
それから有王は毎日六波羅の辺りを歩き回って様子を伺いましたが、俊寛の赦免の知らせは聞き出すことはできませんでした。そこで、こっそりと暮らしている俊寛の娘の所へ参り、
「俊寛様は都へ戻る絶好の機会にそれが叶いませんでした。故に、私は何とかしてあの島へ渡り、行方を尋ねようと考えております。文をお預けください。」
と申し上げました。
『泣きながら文を書いて持たせてくださいましたな、娘様よ。。。さて、都を出たいが、暇乞いをしても、まさか許されることはないだろうよ。』
と思い、有王は父にも母にも知らせないで、3月の末に都を出て、多くの波路を凌いで薩摩潟に下ったのです。薩摩から喜界ヶ島へ渡る湊では、喜界ヶ島に用がある人などいないが故に怪しまれ、人々は有王の着ていたものを剥ぎ取るなどしましたが、有王は少しも後悔することはなく、
『「娘様の文だけは絶対に人に見られまい」と文を元結の中に隠した。』
と、伝わっています。さて、商人の船に乗って、喜界ヶ島に渡ってみると、都でかすかに聞いていた話などは口にもできない(ほどひどい)所でありました。田もなく、畑もなく、村もなく、里もない。人は住んでいるものの、話す言葉も分からない。
『もしかしたら、このような人々の中に我が主人の行方を知っている者がいるかもしれない。尋ねてみよう。』
と思って、
「お尋ね申しあげたい。」
と声をかけると、
「何の用だ。」と答えが返ってきました。
「ここに、都から流されてきた法勝寺の執行というお坊の行方を知っている方はいますか。」
そう尋ねましたが、ただ首を振って
「知らぬな。」
と言うばかりでした。
『そもそも法勝寺や執行は有名なのだから、知っていれば何かしら答えるだろう。』
と思っていると、そのような人々の中にひとり、ふと思い出したように、
「そういえば、そのような方が3人ここにおられましたな。うち2人は昨年の秋に召し返されて都へ戻られたが、もう1人は残されておりました。あちこちを彷徨っておられたが、その後の行方は分かりませぬ。」
と語ってくれた。
何となく山の方に足を向けた有王は、はるか奥へと分け入っていき、峰に登ったり谷へ下ったりしたのですが、俊寛は見つけることはできませんでした。ただ白い雲が俊寛の跡を埋め隠すようで(和漢朗詠集の一節)、人が行き来するような道もはっきりしません。嵐が激しくて安眠できなかったので、夢の中でさえも俊寛の面影を見ることはできませんでした。
下巻「山遠雲埋行客跡 松寒風破旅人夢」です。
山ではとうとう俊寛を見つけることができなかったため、次は海辺に出て探してみたのですが、砂に足跡を残す鴎(かもめ)や、沖の白砂に群れる浜千鳥の他に、俊寛の行方を知る手がかりはありませんでした。
ある朝、磯の方から、陽炎(かげろう)のように痩せ衰えた者がよろよろと現れたのを目にしました。もとは法師であったと思われたのですが、髪は空へ昇るように伸び、無数の藻屑が絡みつき、荊(おどろ)を被ったように乱れに乱れていました。
継目(ついがめ。関節のこと)はあらわになり、皮膚はたるみ、身につけた布は絹か麻かも見分けがつかない。片手で荒海藻(あらめ)を拾って手にし、もう片手には漁師にもらった魚を持ち、なんとか歩こうとしてはいるが、足元がおぼつかない。そのような有様で、よろよろとこちらへ向かってきました。
「都でも多くの乞丐人(こつがいにん。乞食のこと)を見てきたが、このような有様の者はまだ見たことがない。まさか、餓鬼道から現世に出てきたのでは。」
と思うほどでしたが、その者も自分も次第に歩みを進め、近づいていきました。
もしかすると、このような人でも我が主の行方を知っているかもしれないと思い、
「お尋ね申し上げます。」
と声をかけると、
「何だ。」
とその者は答えました。
「都から流された俊寛という人の行方を知らぬか。」
と尋ねて顔を見た。数多く仕えている童の顔は覚えていないが、どうして俊寛の顔は忘れようか、
「この人こそ、探し求めていた。。。」
と声にできないや否や、手に持っていたものを投げ捨て、砂の上に倒れ伏したのでした。
「さてさて、お前は主人の行方を知っていたのだな。そうでなければここで出会うなど有り得ぬからな。」
そう言いながら俊寛は気を失って倒れ込みました。有王は膝の上に抱え、
「有王が参りました。遠く波路を越えて元気なお姿を拝見しようと喜界ヶ島までお尋ねしましたが、その甲斐もなく、このような辛い目に遭っているところを見ることになろうとは。」
と、泣きながら申し上げます。
しばらくして少し正気を取り戻したので起こすと、
「本当に、お前がここまで尋ねに来てくれたその決意は、近頃でいえば神妙なことだ。明けても暮れても都のことばかりが思い出されて、恋しい者たちの面影を夢に見ることもあった。幻の中に現れることもあった。特に、疲れ果ててからというのは、夢なのか現実なのかも区別できなくなった。だから、お前が来たことも、ただただ夢だと思ってしまう。もしこれが夢ならば、目が覚めた後、私はどうすればいいのだ。」
と、悲しそうにしました。
「これは現実でございます。私が現れたことよりも、このようなお姿で今まで生き延びられたことこそが夢かと思われるほど不思議でございます。」
「だからこそだ。昨年、少将(成経)や康頼に見捨てられて以後、頼るものもなかった我が心中を察してくれ。あの時身投げしようかとも思ったが、成経は『今一度、都からの便りを待たれよ。』などと慰めてくれた。何も出来ないというのに。私は愚かにも『もしかしたら』という希望を頼みにして生き長らえてきた。この島には人が食べる物が全く無いものだから、体力のあるうちは山に登って硫黄というものを掘って、九州から来る商人に会っては食べ物と交換などしていたものだ。しかし日に日に弱ってしまい、そのような仕事もできなくなってしまった。今はこのような長閑な日には磯に出てきては、網を引く人や釣り人に向かって手をすり腰をかがめて魚を頂き、引き潮の時には貝を拾い、荒海布を取って、磯の苔のような儚い命を繋いで今日まで生き長らえてきた。有王よ、これ以外、何に頼れば生きていけたと思う?ここで色々と話したいと思うが、まずは我が家へ。」
これを聞いた有王は、
『このような有様でも家を持てていたのか。』
と不思議に思いながらついて行くと、松の一群の中にある家に着きました。より竹(漂着した竹)を柱にして造られた家で、蘆(あし)で固定されてありました。また、桁や梁も渡されていました。上にも下にも松の葉がびっしりとかけてあったので、雨風が漏れてくるような様子はありませんでした。
俊寛は、昔は法勝寺という寺司でした。80ヶ所に及ぶ知行を管理し、また、棟門(切妻屋根の門)や平門(簡素な屋根の門)の中には4、500人ほどの使用人や一族を従えており、その者たちのために心を労りながら日々を過ごしていた人でした。そのような人が今、このような辛い境遇に置かれてるとは。ほんとうに、不思議なことでございます。
俊寛はその時、これが現実であると少しずつ思うようになり、
「それでだ。昨年、成経と康頼が都に帰るとなった時、事前に通達文といったものは渡されなかった。そして今回も同様に、お前が来るという知らせも何もなかった。どういうわけか、そうこう言われてないか?」
と問いかけると、有王は涙にむせびながら、うつむいてしばらくの間何も言いませんでした。そして有王は起き上がり、涙を抑えながらこう申し上げました。
「君(俊寛)が西八条に召し出された時、すぐに追っ手の役人がやって来て、家財から道具まで奪い取りました。その上身内の者たちも捕らえては謀反の次第を問い糺し、皆殺しにしたのです。北の方は幼いお子を隠し通すことができず、鞍馬の奥に身をお忍ばせになり、私は時々そこに通って、なるべく普段通りお世話しておりました。北の方は何に付けてもお嘆きになっておりましたが、それも愚かなことです。幼いお子たちは父である貴方をあまりにも恋焦がれておりましたので、参る度にお子たちから『有王よ、父上がいる鬼界ヶ島というところへ連れて行ってくれよ。』とせがまれました。ところが、過ぎし2月、お子たちはもがさ(天然痘)に罹り亡くなりました。北の方は夫といいお子たちといいひどく物思いに沈まれ、日に日に弱っていきました。そして3月2日、ついに北の方もお亡くなりになったのです。今は姫御前だけが奈良の叔母君のもとにございます。その文をここに持って参りました。」
そう言って文を取り出して俊寛に差し出しました。
有王の言葉のとおり、まさしく娘からの文でした。その奥書にはこう書かれていました。
『3人流されたうちの2人は都に召し還されたというのに、どうしてあなた様だけは未だにお戻りにならないのでしょうか。ああ、身分の高貴な者も卑しい者も関係なく、女の身ほど辛いものはありません。もし私が男子の身でございましたら、どのような島に住まわれていても訪ねて行くというのに。どうか、この有王をお供に、急いで都へお上りくださいませ。』
と。
「これを見よ。この子の文の書き様がなんと儚いことか。私を伴って急いで上洛してほしいと書かれている。この言葉こそが胸に刺さって恨めしい。思うままに体を動かせる状態でどうして3年もの春秋をこの島で送っていようか。もう上洛する体は私には残されていない。今年で12歳になると聞いているが、まだまだ幼子ではないか。私が代わりにとも思うが、このような儚い命となった今、人前に出たり宮仕えしたりして育てることができようものか。」
と嘆きました。親心というのは闇の中にあるわけではありませんが、子を思うと闇の中を彷徨うように思い迷ってしまうといいます(『後撰和歌集』引用)。そんな和歌の情景が俊寛に映ったのです。
『後撰和歌集』雑一 1102番 藤原兼輔
『人の親の心は闇にあらねども子を思ふ道にまどひぬるかな(親心というのは、闇の中にあるものでもないのに、子を思うことになると、闇の中を彷徨うように、思い迷ってしまうのです。)』
「この島へ流されてからというもの、暦もなければ月日の移ろいも感じられなかった。ただ自然に咲く花の落葉を見て春秋を知り、蝉の声を聞けば夏を、雪の積もるのを見れば冬を知るばかりであった。月と闇の入れ替わり(月の満ち欠け)で30日を数え、指を折って年月を数えてきた。今年6つになると思っていた幼子も、もう先立ってしまったのだな、まことに!西八条へ出た時、『童も共に行きます!』と慕ってきたこの子には、『すぐに帰ってくるぞ。』とすかして北の方のもとに留めたのだが、あのことが今のように思われるよ。あれが最後になると分かっていたなら、もうしばらく成長を見ていたかった!親となること、子となること、夫婦の縁を結ぶこと、いずれもこの世ひとつだけに許された契りじゃ。それなのにどうして、契りある大切な者たちが次々と先立ったというのに、今まで夢にも幻にも出てこないで知らせなかったのだ?このような身なりになっても人目を恥じず、なんとしても生き長らえようと思ってきたのは、もう一度彼らに会いたいと願ってきたからだ。姫のことは心苦しいが、皆が先立っても生きているのだから、歎きながらでも日々を過ごしていけよう。それにしても、このような有様になっても生き長らえて、私だけがまだ苦しみを重ねるのは、我ながら辛いことだよ。妻や子とこの嘆きを共にできないのだから。」
俊寛は自分の意思で食事を絶ち、ただひたすらに阿弥陀仏の名号を唱え続け、安らかな臨終の正念(こちら参照実語経)を祈りました。そして、有王が島に渡ってきて23日目、ついにあの粗末な庵の中でその生涯を終えられたのでした。享年37と伝えられております。
有王は、俊寛の虚しい亡骸に取りすがり、天を仰ぎ地に伏して泣き悲しみましたが、それも無駄でございます。心ゆくまで泣き続け、落ち着いた頃に
「君よ、後の世で必ずお仕え申し上げます。しかしこの世にはまだ姫御前が残されております。それに後世を弔い奉る人も他にはございませぬ故、今しばらくこの世で生きて供養申し上げます。」
そう言って、俊寛の庵を整えるのではなく切り壊しては、松の枯れ枝や蘆の枯れ葉を集めて庵を覆いました。火を点けて俊寛を藻塩の煙と成したのです。俊寛の荼毘(葬式の仏教語)を無事終えると、白骨を拾い首にかけ、再び商人の船を頼りに九州の地へ降りて上洛しました。そして俊寛の娘のいる所へ向かい、父の有様を初めから事細かに申し上げました。
「姫の書かれた手紙をご覧になって、ますます姫への思いが強くなっておりました。しかし、硯も紙もありませんでしたので、返信には及ばず、ただただ思いにかけて果てられました。そうなった今、どれだけ生々世々(しょうじょうせぜ。生まれ変わり死に変わりを繰り返して様々な世を渡ること)を繰り返そうとも、あの方のお声を聞くことも、お姿を拝見することも叶いませぬ。」
そう聞かされた姫御前は、伏して、声を抑えることなく泣き悲しみました。その後、姫御前は尼となって奈良の法華寺という寺で勤行をし、父母の後世を弔ったと伝わっています。
本当に哀れな話です。有王もまた、主君である俊寛僧都の遺骨を首にかけて高野に上って奥の院(空海の御廟)に納骨すると、蓮華谷で法師となり、諸国を修行しながら死ぬまで主君の後世を弔い続けたのです。このように人の嘆きや思いが積もる平家の終末期、いったい平家はどうなるのでしょうか?考えるだけでも恐ろしい。
(第十二。終。)
| 第十一に戻る << | 第十三を読む >> |