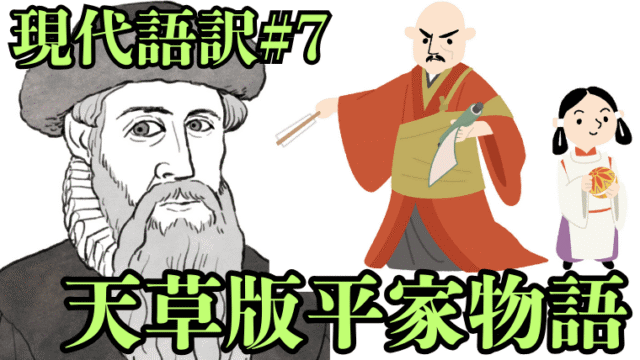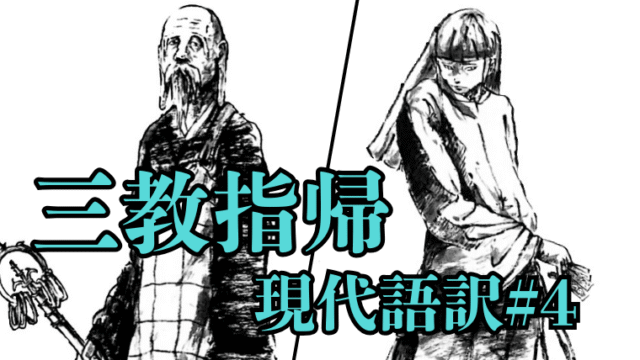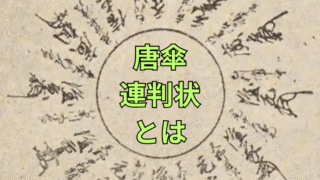天才の発現とその障害
青鞜社規則第一条には、「将来、女性の『天才』を発現させることを目的とする」という意味の条文が書いてある。 私たち女性は一人残らず潜める天才なのだ。天才の可能性を持っているのだ。可能性はやがて実際に存在する事実となるに違いない。ただ、今は精神集中が欠乏しているため、せっかくの人間の偉大な能力を引き出す手段が苦しい。能力ががいつまでも虚しく潜在したままで、ついに表に現れることなく生涯を終えるのは誠に遺憾である。
ニーチェ『ツァラトゥストラはかく語れり』の一節にはこう書いてある。
「女性の心情は、表面的で浅い水に浮かぶ軽薄で騒がしい泡のようなものだ。対して、男性の心情は深く、その水は地中の凹みを急速に流れる。」と。
女性は、人生の長くを家事に従事することに縛られていたが故に、精神の集中力を完全に鈍らせてしまったのだ。家事とは、注意の分配と不得要領によって成り立っている。天才を発現する手段が家事における集中であることは不適当であると私は思う。故に、私は家事における全ての細かい作業を嫌う。それだけ注意を分配せねばならない。
細かい生活は性格を多方面に向ける必要があり、結果性格を複雑に、そして難しくする。その多方面や複雑は、多くの場合、天才の発現と反比例の関係がある。
「誰しもが内に天才を潜在している」
ということに疑いを抱く人はまさかいるまい。今日の精神科学でさえこれを実証しているではないか。
天才の発現条件
例えば18世紀中ごろオーストリア、アントン・メスメル氏によって始まった催眠術は、彼の情熱と忍耐の結果、今日の学者たちの真剣な研究対象となっているのだ。宗教や哲学と全く接点を持たない人であっても、このことは多少なりとも理解していよう。
どれほどか弱い女性であっても、一度催眠状態に入ると、ある暗示を受けることで無から有を生んだり、死の中から生を生んだりといった、霊妙不可思議とも言うべき偉大な力を突然発揮することがあるのだ。無学で文字も読めない田舎の女性が外国語を話したり、詩や歌を作ったりすることも、私たちの目の前で何度も実験されている。火事や地震、戦争といった非常時において、誰しもが日常では思いつかないような働きを経験する。
学者は、『完全な催眠状態とは、全ての自発的活動の全てを停止させ、無念無想の精神状態になることである。』と言う。
そうであるならば、催眠状態とは、私の言う『潜める天才』が発現する状態と同じようだ。私は催眠術にかからないので遺憾ながら断言はできないが、少なくとも両者は類似した世界だとはいえる。
無念無想とはいったい何だろうか。祈祷の極致、精神集中の極致において到達して得られる事故忘却のことではないだろうか。無為(何も行わない、自然のままの状態)ではないか。恍惚(深い集中や喜びに満ちた状態)ではないか。虚無(何も存在しない、空っぽの状態)ではないか。真空(完全に空っぽで、何もない状態)ではないか。
実際、ここは真空である。真空であるが故に、ここは知恵という名の宝が無尽蔵にある大倉庫でもある。真空は全ての活力の源泉である。始まりも終わりもない、植物・動物・人類を経て永遠に伝えられるべき全ての能力の源なのである。ここには過去も未来もない。あるもの全てが現在。
自然との調和
ああ、『潜める天才』よ。我々の心の奥底、情熱の炎の中にある『自然』の知恵の卵よ。全知全能の『自然』の子供よ。
「フランスに我がロダンあり。」ロダンは現実に『潜める天才』を発現させた天才だ。かれは偉大な精神集中力を持っている。非常時の心を平常時の心として生きている。彼は精神生活のリズムと肉体生活のリズムを、瞬時に、そして自由に変えることができる人に違いない。だからこそ、彼は、インスピレーションを待ち続ける奴隷のような芸術家たちを笑ったのだ。彼は、その偉大な精神集中力に命じれば、いつでもインスピレーションを得ることができたのだ。彼は天才となる唯一の鍵を握っている人であった。そう言うべきだろう。
私は、朝昼晩の食事の時も、夕涼みの談笑の時も、常に非常時の心を持ちたいと願っていた。そんな私が、かつて『白樺』のロダン特集号を見て、多くの示唆を受けたわけだ。無知な私は、ロダンという名前さえ聞いたことが無かった。そして、記載されているロダンの特集から自分自身について多くのことを再認識した。
共鳴するものを強く感じた時、私はどれほど歓喜に堪えられなかったか!
それ以来、密室に一人座る夜を過ごした。小さな灯火が白く、次第に音が高くなり、嵐のように、しかしますます単調に、瞬きもせず燃える(精神集中力の高まり)。五羽の白鳩は、優しい赤い目も黒い目も同じ薄い膜に覆われて、止まり木の上でふっくらと膨れて安らかに眠る(五体の安定、心の平穏)。そうして私は大海の底で一人目覚めていった(深い意識=精神集中の中で新たな気づきを得る)。目覚めると私の筋肉は緊張し、全身に血潮がみなぎっている(新たな気づきの獲得による精神の高揚)。この時「フランスに我がロダンあり。」という思いがどこからともなく私の心に浮かんでくるのだ(ロダンの芸術に共鳴する瞬間)。そして私はいつの間にか彼と共に『自然』の音楽を――失われた高調の『自然』の音楽を奏でているのだった(ロダンの芸術と共に、性差などで失われた『自然(才能や知恵)』を自身の中に取り戻し、調和のとれた状態になった)。
雷鳥の天才の発現
私はかのクリムトの『接吻』を思い、思い出す。あらゆる情熱を一つに溶かすような強烈な接吻を。私の接吻を。接吻は正に全てを一つにまとめる行為である。魂よ、肉体よ。極限の緊張の先にある恍惚よ。安息よ。安息の美よ。接吻はこれら全てをもたらし、感激のあまり流した涙は黄金色に輝く。
日本アルプスの上で灼熱に燃えてくるくると回転する日没前の太陽よ(強烈な情熱)。それに対して孤峰の頂上に一人立つ私の静かな慟哭よ(強烈な孤独感)。
私は弱い。そして疲れた。何ものとも知れぬ、把握し難い恐怖と不安に、絶えず震える魂。頭の底が動揺している。銀線をへし折るような響きか、寝醒め時に襲ってくる黒い翼の死の強迫観念か。
けれど、けれど、一度自ら奮い立った時、『潜める天才』はまだ私を導いてくれる。『潜める天才』はまだ私を完全には見捨てない。そして、どこからともなく私の全身に力がみなぎってくる、私はただただ強い者となるのだ。
私の心は大きくなり、深くなり、平静になり、明るくなり、視野はその範囲を増した。全世界が一目で見える。あの重かった魂は軽く、軽く、私の肉体から抜け出して空にかかっているのだろうか。 それとも、実は重さのないものとなって気散してしまったのだろうか。私はもう、全く身も心も忘れ果て、言い表すことのできない統一と調和の感覚に酔ってしまったのだった。生も死も知らない統一感。あえて言えば、そこには永遠の生があり、強固な意志がある。
ナポレオンはあの険峻なアルプスを「何ともない土地だ!」と叫んだ。そう、どんな障害も克服できるのだ。私は真の自由、真の解放を感じている。私の心身は何の圧迫も、拘束も、恐怖も、不安も感じない。無意識のうちに右手が筆を持ち、何かを書き続ける。『潜める天才』が発現したのだ。 私は『潜める天才』を信じずにはいられない。混乱した内面がわずかに統一を保っているのは、ただただ『潜める天才』の存在があったからだ。
自由解放の意味
「「自由解放!!」」
女性の「自由解放」という声はずいぶん前から私たちの耳に響いている。しかし自由解放とは一体何なのか。私は、自由といい解放といい、それらの正しい意味が大きく誤解されているのではないかと思う。もちろん、単に女性解放問題といっても、その言葉には多くの問題が含まれていることだろう。
しかしだ。ただただ、女性を外界の圧迫や拘束から解放し、いわゆる高等教育を受けさせ、広く一般の職業に就かせ、参政権を与え、家庭という小さな世界から、親や夫という保護者の手から離れて、独立した生活をさせたからといって、どうしてそれが女性の自由解放といえるのか。
確かに、真の自由解放に達するためには良い境遇と機会かもしれない。しかし、それは手段であり、目的ではないのだ。理想ではないのだ。
とはいえ、私は女子高等教育が不必要だという意見にはもちろん反対である。「自然」から同じ本質を受けて生まれた男女に、一方は必要で、一方は不必要だとするのは、ある国ある時代においては一時的には許されるかもしれない。しかし、少し根本的に考えればこれほど不合理なことはないと分かろう。
私は、日本に唯一の私立女子大学(日本女子大学)があるだけという現状、男子の大学が女性に門戸を開かないという現状を悲しく思う。女性の知識の水準が男性と同じになったところで、それが何だ。そもそも知識を求めるのは、無知や無明の闇から脱して自己を解放するために他ならない。アメーバが周囲のものを取り込んで生きる糧にするように、人間も貪欲に知識を得る。しかし、一度目を拭いて見れば、殻(形だけの知識)ばかりなことに驚く。
そして、我々はその殻から脱したいと願うのだが、これに多くの苦闘を余儀なくされるわけだ。思想というのは私たちの真の知恵を暗くし、自然から遠ざける存在である。知識を弄んで生きる者は学者かもしれないが、到底知者とは言えない。むしろ、目前の事物の真実を見ることが最も困難な盲者に近い存在なのだ。
真の自然主義者と日本の自然主義者
釈迦は雪山に入り、六年間の修行の末に大悟(迷いから脱却し、悟りの境地に入ること)し、こう言った。
「なんてことだ。この世に存在する全ての生命が、仏性を有しているなんて。」と。
またこう言った。
「悟りを開いて、その視点から見ると、世界中にある全ての草木や国土も全て仏になるのだな。」と。
彼は初めて事物の真実を見抜き、自然の完全さに驚嘆したのだ。釈迦は真の現実家、真の自然主義者となった。空想家ではない。全自我を解放した者、大覚者となったのだ。 釈迦の教えにおいては、真の現実主義者は神秘主義者でなければならないこと、真の自然主義者は理想主義者でなければならないこととなっており、私たちはこれを理解している。ロダンも同じだ。彼は現実を徹底的に追求することで、現実と完全に一致する理想を見出した。
彼は「自然は常に完璧であり、彼女(自然)は一つの誤りも犯さない」と言った。
自らの意志で彼女に従い、従うことで彼女を自分のものとした彼は、自らを自然主義者と称している。しかし、日本において自然主義者と呼ばれる人たちは、現実そのものの中に理想を見出すまでには至っていない。精神集中力が欠けているからだ。
そのような彼らの心に、自然は決してその完全な姿を現さない。人間の深い瞑想の中でのみ見られる現実即理想の世界は、まだ、彼らの前には容易に開かれそうもない。彼らのどこに自由や解放があるのか。あの首輪、手枷、足枷はいつ外れるのか。彼らこそ、自縄自縛の徒であり、自らの奴隷状態に苦しむ哀れむべき人々ではないのか。 私は、無闇に男性を羨み、男性に倣って、彼らの歩んだ同じ道を少し遅れて歩もうとする女性を見るのが忍びないと思う。
真の自由と解放
女性たちよ、心の中に無駄なものを積み上げるよりも、何もない状態を充実させることで、自然がいかに完璧であるかを知りなさい。
では、私が望む真の自由と解放とは何だろうか。それは言うまでもなく、『潜める天才』や偉大な潜在能力を十二分に発揮することに他ならない。そのためには、自己の発展の妨げとなるもの全てをまず取り除かなければならない。 その妨げとは、外部からの圧力か。それとも知識不足か。確かにそれらも全く関係ないわけではない。しかし、主な原因はやはり自分自身なのだ。天才の所有者であり、天才が宿る宮である自分自身。『潜める天才』は自分自身を解放する時、現れる。
私たちは自分の内に潜むこの天才のために自分を犠牲にしなければならない。いわゆる『無我』にならなければならないのだ(無我とは自己拡大の極致である)。ただただ、私たちの『潜める天才』を信じることによって、そして天才に対する絶え間ない叫び声と渇望と全人格的な唯一の本能によって、祈りに熱中して精神を集中させて、自分を忘れる(無我に至る)以外に道はない。そしてこの道の極るところに、天才の玉座は高く輝くのだ。
女性として生まれたことへの喜び
私はすべての女性と共に、『潜める天才』を信じたい。ただ一つの可能性(『潜める天才』を信じること)を信じ、女性としてこの世に生まれてきたことを心から喜びたい。私たち女性の救い主は、私たちの内にある天才そのものなのだ。
もはや救いとは、寺院の仏や教会の神に求めるものではない。自らの努力によって、私たちの内にある自然の秘密(自然の本質や力)を明らかにするのだ。私たち女性はもはや天啓を待たない。自らが天啓となるのだ。私たち女性は奇跡を求め、遠い彼方の神秘に憧れない。自ら奇跡となり、神秘となるのだ。私たち女性は熱烈な祈りと精神集中を絶えず続けよう。そして徹底的に追求しよう。内に秘めた天才が現れる日まで。隠れた太陽が輝く日まで。その日、私たち女性は全世界を、全てのものを、自分のものとするのだ。その日、私たち女性は唯一無二の王者として、自然の核心に自立し(自然の本質と一体化すること)、反省の必要のない真の人(自己の行動や信念んに対して確固たる自信を持ち、後悔や迷いを持たない真正の人)となるのだ。
そして、孤独や寂しさがいかに楽しく、豊かであるかを知るだろう。もはや、女性は月ではない。その日、女性はやはり元始から太陽であることに気づくのだ。真正の人なのだ。私たちは今、日出る国の東の水晶の山の上に、眩しい黄金の大円宮殿を建てようとしている(純粋で完璧な自身という存在の上に、性差や固定概念に捕らわれず理想的な輝かしい未来や目標を立志しようとしている)。
女性たちよ、自身の肖像を描くときには、常に金色の円天井を選ぶことを忘れないで欲しい(自分が持つ『潜める天才』を最大限に認識し、それを誇りに思うべきである)。たとえ私が道半ばにして倒れたとしても、たとえ私が難破船の水夫として海底に沈んだとしても、それでもなお麻痺した両手を挙げて「女性たちよ、進め、進め」と最後の息で叫ぶだろう。今、私は感情が高ぶっている。目から涙が溢れている。溢れている。
結語
私はもう筆を置かなければならない。 しかし、なお一言、言いたい。
『「青鞜」の発刊は、女性の中の『潜める天才』、特に芸術を志す女性の中の『潜める天才』を発揮させる良い機会として、またそのための機関として多くの意味を持つものである。』と。
たとえ「青鞜」の発刊が一時的なものとなっても、発刊されるしばらくの間は、天才の発現を妨げる、女性たちの中にある塵・渣滓(さし)・籾殻といった不要なものを吐き出す役割を果たしてくれるだろう。そうなれば、「青鞜」の存在が僅かでも意義を持ったといえる。
私はまた思う。
『私たち女性が怠慢せずに努力を重ねた結果、「青鞜」が終わる日が来たとしても、私たちの目的は幾分か達成されているだろう。』と。
最後にもう一つ。青鞜社の社員は私と同じように、特に若い社員は一人残らず各自の『潜める天才』を発揮し、自分一人だけが持つ個性を尊重し、他人が犯すことのできない各自の天職を全うするため、ひたすら精神集中するような熱烈で、誠実で真面目で、純朴で、天真爛漫で、むしろ幼稚な女性であって欲しいと切望する。また、私はこれを信じて疑わない。青鞜社は、世間にある多くの女性団体に見られるような有名無実な腰掛け仕事ではない。
理想を現実にするには様々な手があるが、激しく熱望することこそが、理想を現実にする最も確実な、そして真の要因なのだ。
――完――
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |