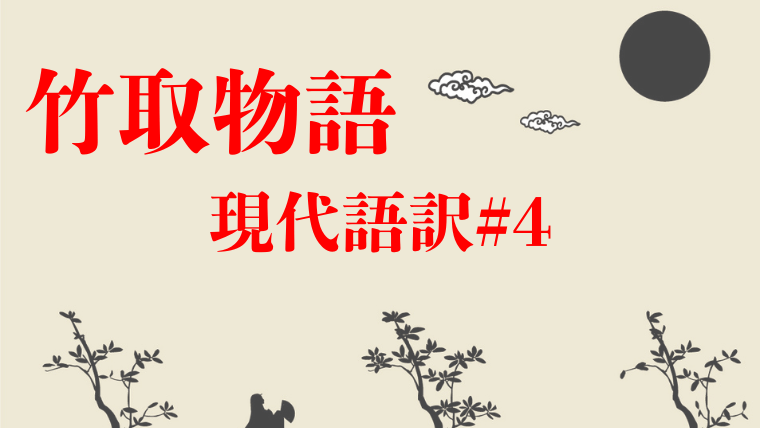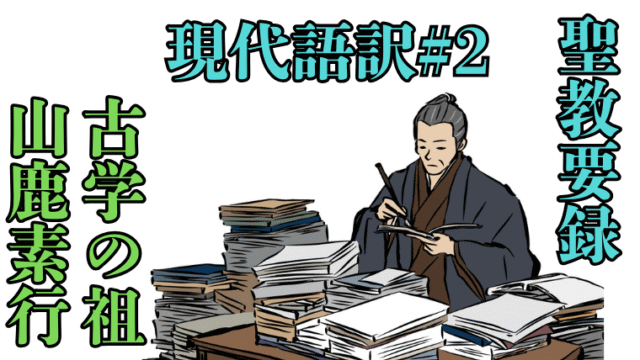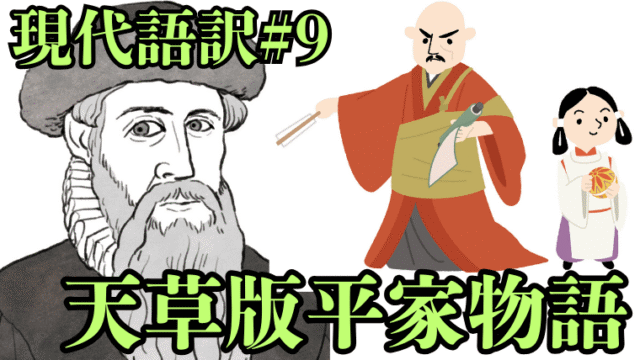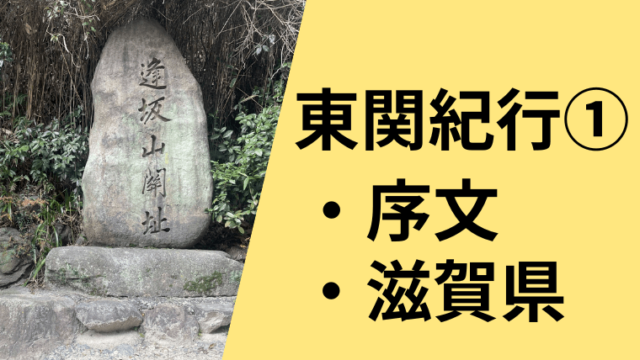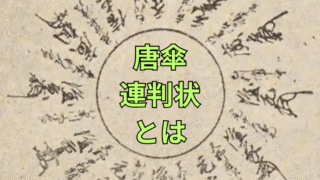一覧は下記サイトをご確認ください。
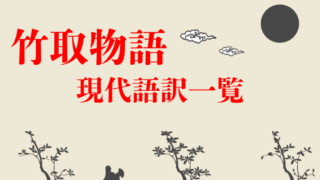
④二人目:車持皇子
車持皇子は、策謀家である。朝廷には、
「筑紫国まで湯浴びに行きます。」
と言って、暇を申し出た。対してかぐや姫の家には、
「玉の枝を取りに行ってきます。」
と使者に伝えさせた。下向にあたり、皇子に仕える人々は皆、難波まで送った。皇子は
「本当にお忍びなのだ。」
と仰っていたので、従者は多く連れていなかった。特に近くに仕える者に限定して出発した。他の人々は、出帆を見送ってから帰京した。京にはいない、と人々に印象付けるために、あえて見えるようにしたのである。そして、三日ほど経って、誰にも見つからずこっそりと、船でお帰りになったのであった。
前もって計画は、関わる者全てに仰せになっていたので、当時、最も優れていた一般職人(工匠)と役人職人(内匠)6人を呼び寄せて、簡単には近寄れないような家を造り、内部を三重に囲い、職人らをその中に入れると共に、皇子も同じ所に籠ったのであった。例えるならば、皇子の支配する十六の荘園を土台にして上に竈を作り、収入源の租をひたすら消費するかのように、玉の枝の制作に財産を費やした。
そしてそれは完成した。かぐや姫の言う通り、全く違わずに作ったのであった。そして賢く策を考え、難波に密かに持ち出した。
「船に乗って帰って来たぞ。」
と自分の屋敷に伝令を遣り、たいそうひどく苦しがっているふりをして船に居座った。迎えには多くの人が参上した。玉の枝は長櫃に入れて、物で覆って、かぐや姫のもとへ持参した。いつ耳にしたのだろうか。人々は
「車持皇子が、優曇華の花を持って上京なさったらしい。」
と大声で騒いだ。これを聞いたかぐや姫、
「私は、この皇子に負けるかもしれない。」
と、胸がつぶれる思いをした。こうしているうちに、門が叩かれた。
「車持皇子がいらっしゃいました。」
と告げられる。
「旅のお姿のままでございます。」
とも言うので、先に翁が会いに行った。皇子は、
「『命を捨てる覚悟で、あの玉の枝を持って参りました。』と言って、かぐや姫にお見せください。」
と言って翁に手渡した。翁はそれを持って入った。この珠の枝には、文が付けてあった。
いたづらに 身はなしつとも 玉の枝を
手をらでさらに 帰らざらまし
玉の枝が折れていたら、無駄死にしたとしても、帰って来なかったでしょう。無念の帰郷よりも玉の枝のほうが大切なのだから。
翁はこの歌も見て感嘆する訳でもなく、翁はかぐや姫のもとへ走りこんで言った。
「この皇子は、姫が申し上げた通りの蓬菜の玉の杖を、一箇所も怪しい所なく持って参りました。何をもって申し上げましょう。旅のお姿のまま、ご自宅へも寄らないで直接おいでになっています。早くこの皇子と結婚しなされ。」
と。かぐや姫は物も言わずに頬杖をついて、ひどく嘆かわしそうに物思いに耽った。皇子は、
「今さら、何も言うことはできないだろう。」
と言いながら、縁側に這い上がってきた。翁は、約束の通り持ってきたため、これも道理だと思った。
「姫。これは、この国で見られない玉の枝です。今度はどうしてお断り申せましょうか。それに、皇子は人柄も良い人でございます。」
などと言った。かぐや姫は言う。
「親の言うことに激しく嫌だと申すことは気の毒なものだな。」
と。かぐや姫は、手に入れ難い物を、思いもせずこのように持って来たことを疎ましく思った。翁は閨の中を整えるなどした。その後、翁は皇子に
「どのような所に、この木はございましたか。この世のものとは思えないほど麗しい、すばらしい物でございますれば。」
と申した。皇子は答えて言った。
「2年前の2月10日頃に、難波から船に乗って海に臨むも、行くべき方角も分からないらないと苦難に直面しました。しかし、『思うことすら成就できないでこの世に生きても、何の意味があろうか。』と思ったので、ただただ行先も定まらない風にまかせて船を進めました。『死んだらどうしようもない。生きている限り、こうやって航海ができるのだ。いつかは蓬菜山に出会うことができるかもしれないな。』そう思いながら波に従い海を漕ぎ、我が国を離れたところを航海しておりました。ある時は波が荒れ続けて海底に沈みそうになり、ある時は風に煽られ知らない国に吹き寄せられて、鬼のようなものが出て来ては我々は殺されそうになりました。ある時は来た方角も分からず行く先も分からず、海で遭難しそうになりました。ある時は食糧が尽きて、草の根を食い物としました。ある時は言い表せないほど不気味なものが現れて、我々に食いかかろうとしました。ある時は海の貝を取って命を繋ぎました。旅先で我々を助けてくれる人もいないというのに、そのような所で様々な病にも罹りました。行先すらも分からず、ただただ船の行くに任せて海に漂い、500日ほどかと思われた日の辰の時(午前8時頃)に、海の中遥か遠くに山が見えました。落ちないギリギリまで身を乗り出してそれを見ました。海の上に漂っている山は、たいへん大きく、高くて麗しい様子でした。『これだ。私の求める山に違いない。』しかし、そう思うも、本当にたどり着くとは、と思い、かえって恐ろしく感じました。山の周囲を漕ぎ巡らせて、二、三日ほど見て回ると天人の身なりの女が山の中から出て来て、銀の金椀を手に水を汲み歩いているのを見ました。船から降りて『この山の名は何と申すのか。』と問うと、女は『これは蓬莱の山です。』と答えた。これを聞いて、嬉しいこと限りありませんでした。女に『そう仰るあなたは誰ですか。』と問うと、『私の名前はホウカンルリといいます。』と言い、ふっと山の中に入っていきました。その山を見るに、全く登れそうにない。山の周囲を回ると、この世で見たことがない花木が立ち、金色、銀色、瑠璃色の水が山から流れ出ていました。また、そこには、色とりどりの宝玉でできた橋が渡してあり、あたりには、照り輝く木々が立っていました。そのような中、枝を折るのは憚られましたが、『ご要望に沿わない訳には。』と思い、この枝を折って持ってきたのでございます。あの山は限りなく興味深いものでした。この世のものに例えることができない世界でしたが、この枝を折ってから、いっそう、かぐや姫のことが気がかりになりました。船に乗ると追い風が吹いて、400日あまりで、帰ってくることができました。神仏への大願の力でしょうか。難波に到着し、昨日、都に帰って参りました。潮に濡れた衣でさえ脱ぎ替えずに、参上したのです。」
そう皇子は旅の経緯を語ってくれた。翁はこれ聞いて、感動して詠んだ。
呉竹の よゝのたけとり 野山にも
さやはわびしき ふしをのみ見し
代々の竹取も、野山でそうした辛いことに遭遇してきたのでしょうか。
これを皇子が聞いて、
「日頃辛い思いをしていましたが、その憑き物も今日落ちますよ。」
と言って返歌。
わが袂 けふかわければ わびしさの
ちくさのかずも 忘られぬべし
私の袂は海水でぬれていましたが、今日乾きました。辛い目に何度も何度も遭いましたが、それも忘れてしまうでしょう。
と仰ったのであった。こうしていたところ、皇子のもとへ、男6人が連ねて庭にやってきた。一人の男が、文挟みに文を挟んで申し上げた。
「内匠、漢部(あやべ)内麻呂が申し上げますこと、『玉の木を作り奉りましたこと、粉骨砕身し、1000日余りもの間尽力したことは、決して少なくない労力でした。それなのに、禄はまだ賜っておりません。禄をいただきたい。こちらで分配し、また家子(けご。弟子のこと)にも与えるつもりです。』とのことでございます。」
と言って、文挟みを捧げてきた。翁は、
「この工匠らが申しているのはどういうことか。」
と首をかしげてその場に居つくした。皇子は、思ってもいなかったことが起きた、と肝を冷やしていた。これを聞いたかぐや姫は、
「差し出されている手紙を取れ。」
と言って中を見た。手紙にはこう書かれていた。
『皇子の君は、千日余り身分の低い工匠らと同じ所に隠れ住み、工匠らに立派な玉の枝を作るよう命じられました。要望に応えましたところ、皇子は「官位でもやろうではないか。」と仰いました。このことについて最近、「御側室になるであろう、かぐや姫がお望みになったのだ。」とお聞きしましたので、宮中からかぐや姫の屋敷まで使いを送り、そこで賜ることを申し上げに来た次第でございます。』
かぐや姫は、日が暮れるにつれて物思いに沈んでいた気持も笑顔いっぱいに変わり、翁を呼び寄せて言った。
「本当に蓬莱山の木かと思ってしまいました。これらの振る舞いは全て、呆れるほどの嘘だったのです。はやく家に返してください。」
翁は
「確かに、わしも作り物だと聞いてしまいましたので、返すのはまことに容易でございます。」
と頷いた。かぐや姫の心は晴れ渡り、あの文に対して返歌した。
まことかと 聞きて見つれば ことの葉を
飾れる玉の 枝にぞありける
話を聞いて本当かと思いましたので見ておりましたが、言の葉で繕っただけの、偽の玉の枝でしたね。
そう言って、玉の枝も返したのであった。翁は、先程まで皇子を良くかたっていたが、さすがに気が悪くなったのか、居眠りをしていた。皇子は立ってもいられず座ってもいられずといった様子でいた。日が暮れてから、滑るように出ていった。その後、かぐや姫は愁いを訴えたあの工匠たちを呼んで座らせ、
「嬉しいことをしてくれた人たちだな。」
と言って、禄をたくさんお与えになったのであった。工匠たちはたいそう喜び、
「思った通りだったな。」
と言って帰っていった。帰り道、車持皇子が、血の流れるまで工匠らを痛めつけた。その上、工匠たちがかぐや姫から賜った褒美は車持皇子が全て取り上げ、彼らの手から捨てさせたので、工匠たちは逃げ失せたのであった。訴えは無意味なものとなってしまった。こうして、この皇子は
「これは一生の恥だ。これに過ぎる恥は後にも先にもないだろう。女を手に入れられなかっただけでなく、天下の人がこれを見て色々思うことを考えると、なんとも恥ずかしい。」
と仰って、たった一人で、深い山へと入っていったのであった。
宮司やそれに仕える人々が皆手分けして捜したが、お亡くなりにでもなったのだろうか、遂に見つけることはできなかった。皇子は、お供の人々から姿を隠し、以降長年姿を見せないのであった。このことから、魂が抜けたようにぼんやりすることを、「たまさかる」と言い始めたのである。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |