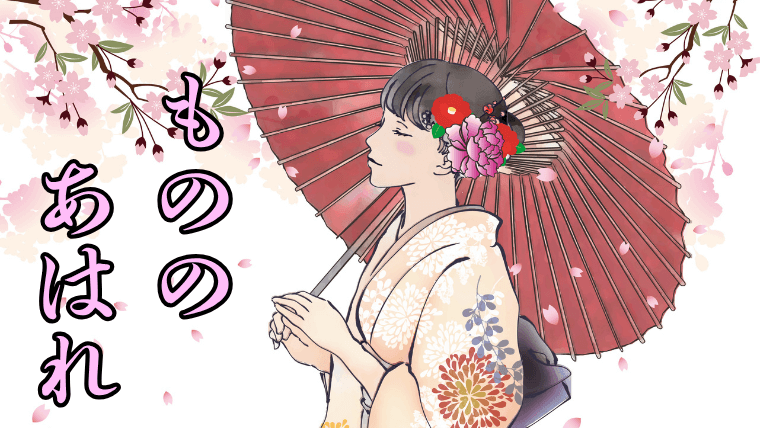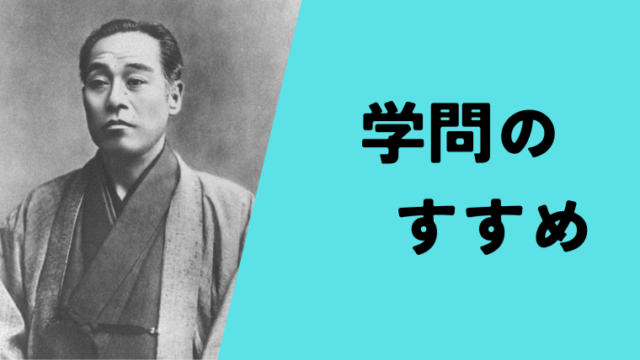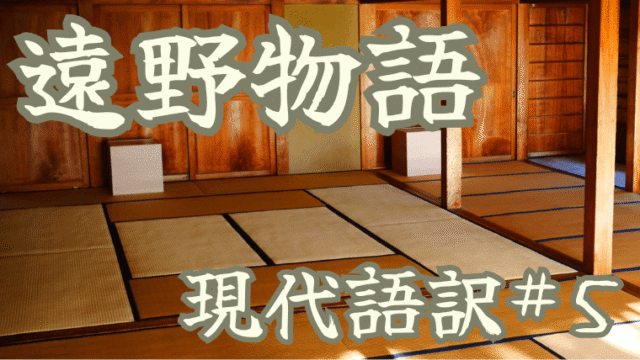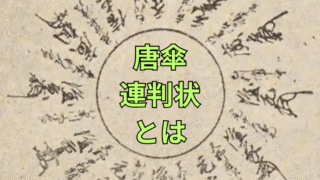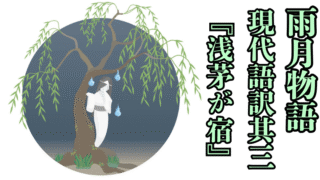解説
どんな本?
『源氏物語玉の小櫛(たまのこぐし)』は、江戸時代の国学者である本居宣長によって書かれた作品です。『源氏物語』の注釈書で全12巻構成となっています。完成は寛政10年(1798)頃。
作者:本居宣長
成立:寛政10年(1798年)
構成:全12巻
本居宣長がこの作品を著した背景には、「もののあはれ」という美学が根底になっています。『源氏物語』を「もののあはれを知る書」として高く評価し、『源氏物語』の作者である紫式部の感性が日本文学の理想であると判断しました。
江戸時代に入ってから幕府が国体管理のために儒学を推進、隆盛しましたが、これは中国の思想であり、日本の思想ではありませんでした。
蔑ろにされていた日本古来の思想を再評価しようとして生まれたのが国学で、主に神道的価値観の探求がなされました。本居宣長はその第一人者だったのです。
「玉の小櫛」の意味
玉も小櫛も美しいものの代表する単語です。
「玉」は『源氏物語』を指し、「小櫛」は小さい櫛のことで、多くの美しい女性が登場することと文学的にも美しい作品とをかけて、『美しい髪(物語)を、櫛で梳く(注釈)』という意味です。
宣長の『源氏物語』に対する敬愛の心とその洞察力が光るこの書は、古典文学を理解するために必要な文学的視点や思考力が読み取れる論文としても高く評価されています。
内容
「もののあはれ」に基づいた内容
『源氏物語玉の小櫛』の特徴は、単語の注釈や史実との関連性を解説するに留まらず、登場人物の心理や文章表現の美しさについて深く掘り下げている点といえます。注釈書としての機能と、「もののあはれ」に基づいた日本文学の美しさを解説する講義的機能を兼ね備えました。
具体的には、注釈書としては、現代(江戸時代)と平安時代の単語の意味の違いや、行間に込められた意味、言い回し表現などを丁寧に分析しました。
対して、「もののあはれ」的主張としては、行動や心情からその人物性を判断するのではなく、その時その時に生まれる登場人物の思いに共感するよう促しています。この「もののあはれ」が優れている作品が『源氏物語』なのです。
特に優れている点は文献比較でしょう。
第一巻で言及していますが、活版印刷の普及により多くの『源氏物語』が流通していた江戸時代、その代償として、多く異同や意味不明な解釈が混沌を極めていました。そこで本居宣長は多くの写本を比較検討し、最も精度の高い写本を定義、それに沿って各書の特徴や諸説を整理しました。これは、現代論文でも根幹部分にあたる要件整理にあたるもので、主張の根拠を明確に示したうえで論理立ててその可能性を立証する、実証的アプローチの先駆けとされています。
原因と結果が全てを言うジャンルの書籍でありながら、本居宣長の哲学的視点もみられるのが『源氏物語玉の小櫛』の特徴です。男女の色恋物語であることを前提に、人間の感情の普遍性や残酷性、「生」の儚さを描いた作品だと言っています。つまり、「もののあはれ」とは、ただ日本古来の文学を再評価するだけでなく、人間の感情の美しさを尊重した思想だったのです。
日本人が古来から持っていた美しい感性を本居宣長が再評価、理論的に言語化した「思想」のこと
現代語訳一覧
『源氏物語玉の小櫛』の現代語訳を一覧にしています。
巻一
すべて物語書の事
此源氏の物語の作りぬし
紫式部が事
つくれるゆゑよし
作れる時世
此物語の名の事
准拠
くさゞゝの事
注釈
引歌といふものゝ事
湖月抄の事
現代語訳
そのかみの こゝろたづねて みだれたる すぢどきわくる 玉のをぐし
すべての物語書の事
中むかしほど、物語といひて、一くさのふみあり、物がたりとは、今の世に、はなしというをにて、すなはち昔ばなし也、日本書紀に、談といふ字をぞ、ものがたりと訓たる、そを書に名づけて、作れることは、絵合の巻に、物語のいできはじめのおやなる、竹取の翁に、うつほのとしかげを合せてとあれば、此竹取やはじめなりけむ、その物語、たがいつの代につくれり●は、さだかにはしらねども、いたくふるき物とも見えず、延喜などよりは、こなたの物とぞ見えたる、そのほかかのたぐひなる、古ル物語ども、此源氏のよ。さきにも、かずゝゝ多く有しと聞けて、その名ども、あまたきこえたれど、後の世には、伝はらぬぞおほかンめる、
平安時代には、『物語』という一類の本がある。物語とは、当時の世での話、つまり今でいう昔話である。『日本書紀』では、「談」という文字を「ものがたり」と読んでいる。物語を本として最初に作ったのは、『源氏物語』「絵合」の巻に「物語の祖である『竹取』の翁や、『宇津保』の俊蔭に合せて」とあるから、『竹取物語』なのだろう。『竹取物語』は、誰がいつの時代に作ったのかは明確になっていないが、かといって、それほど古いものではなさそうで、延喜年間以降に作られたものだと思われる。その他、同類の古い物語が『源氏物語』が作られる以前から数々存在していると私は聞いているが、その名が後世に伝わってないものが多いようである。
又同じころ、それより後の物も、多くして、今の世にも、これかれと、あまたのこれり、栄花物語の、煙の後の巻に、物語合せとて、今あたらしく作りて、左右かたわきて、廿人合せなどせさせ給ひて、いとおかしかりけり、といへるを見れば、そのころも、おほく作りたりし也、
また、『源氏物語』と同じ時代、そして以降も多く物語が作られ、あれかこれかと多く残っている。『栄花物語』「煙の後」の巻には、「物語合せという遊びで、参加者が新しく物語を作り、それを左右に分けて、最終的に20人の作を合せたのは、非常に面白かった。」とあるため、『栄花物語』が作られた平安時代末期も物語は盛んに作られていたようである。
さてもろゝゝの物語のさま、おのおのすこしづゝかはりて、さまゞゝなれども、いづれも、昔のよに有し事を、かたるよしにて、あるはいささゝかかたち有し事を、よりどころにして、つくりかへてもかき、あるは其名をかくしもし、かへもしてかき、あるはみながら作りもし、又まれには、有しことを、そのまゝに書るも有て、やうゝゝなる中に、まづ多くはつくりたるもの也、さてそはいかなる趣なる物にて、何のためによむものぞというに、大かた物がたりは、世の中に有リとある、よき事あしき事、めづらしきことをかしきと、おもしろき事あはれなる事などのさまゞゝを、書あらはして、そのさまを、絵にもかきまじへなどして、つれゞゝなるほどの、もてあそびにし、又は心のむすぼゝれて、物おもはしきをりなどの、なぐさめにもし、世ノ中のあるやうをも心得て、ものゝあはれをもしるものなり、
さて、諸々の物語の作風は、各々少しずつ異なっていて様々であるが、様々とはいえ、いずれも、昔の世にあったことを語っているということは共通している。史実をもとに少し作り替えたり、実名を隠して別名で書いたり、もととなる物語とそっくりに書いたり、といった具合である。稀に、史実ありのままを書いた物語もある。このように様々ある物語なのだが、まず最初に言えるのは、基本的には多くが創作だということである。さて、それはどのような趣旨で、何を目的として読むのか。だいたいの物語は、世の中に存在する良い事や悪い事、珍しいこと、趣のあること、面白いこと、情緒を誘うことなどを様々なことを、書き表しては挿絵にして人に語るため、暇な時の手遊びにするため、心が荒んで物思いに沈んだ時の慰めにするため、といった趣旨で書かれる。そして、これらを読む目的は、世の中の実情を学びかつ物のあはれを知るためなのである。
かくていづれの物語も、だんしななからひの事を、むねとおほく書たるは、よゝの歌の集共にも、恋の歌の多きと、同じことわりにて、人の情のふかくかゝること、恋にまさるはなければ也、すべてこれらのこと、猶つぎゞゝに、くはしくはいふべし、
いずれの物語も、男女の仲についてのことを主題として書かれることが多い。それは、代々の歌集に恋の歌が多いのと同じ道理で、最も人情が深くあらわれるのが恋だからである。これらのこと全て、順に詳しく述べよう。
此源氏の物語の作りぬし
此物語は、紫式部がつくれりというは、世にあまねくしれることにて、はやくみづからの日記にも、そのおもむきに見えたれば、論なきを、それにつきても、くさゞゝの説あり、まづ宇治ノ大納言の物がたりに、源氏は、越前守為時これを作りて、こまかなる事どもを、女の式部にかゝせたり、といへること、花鳥余情にも引玉へり、されど此説用ふべからず、かの書にも、たしかに申さず、いづれかまことならむなど見えたり、又河海抄に、御堂殿、奥書を加へられて、老比丘筆をくはふるところ也、と書給へりと見ゆ、これ又ひがこと也、そのよしは、安藤ノ為章といふ人の、紫家七論といふ物に、くはしく弁へたるがごとし、
『源氏物語』が紫式部作であるということは、世に広く知られたことである。自らの日記『紫式部日記』にも『源氏物語』の趣がみられるため、議論するまでもない。しかし、作者が紫式部以外だとする説も色々ある。『宇治大納言物語』には「越前守である藤原為時が『源氏物語』を作り、細かい部分は娘である式部に書かせた。」とあるのだが、これを一条兼良が『花鳥余情』にて引用している。しかし、この説は信用できない。『花鳥余情』では、「確かにそうだ」と言い切っているわけではなく、「どれが真実なのだろうか」と書いているからである。また、四辻善成の『河海抄』には、「『源氏物語』は、紫式部が御堂関白殿(藤原道長)のもとへ持っていき、道長自身が加筆、奥付(証明印)を加えたものである。」とあるが、これも誤った説である。それは、安藤為章の『紫家七論』に詳しく述べられている通りである。
これらをおきても、くさゞゝの説ともあれど、みな後の人のつくりいへることゞものみ也、たゞ紫式部作れりといふほかは、みなうけがたし、又末の宇治十帖は、式部が作れるにあらず、といふ説あれど、ひがことなり、同じ人のつくれること、明らけし、又雲隠ノ巻は、名のみ有て、詞なきは、式部が心有ル事なるを、今の世に、其巻とて、別にあるは、後の人のしわさにて、見るにもたらぬ、つたなきものなり、又山路の露とて、夢浮橋ノ巻の末につづけたる物あり、そはかの雲隠といふものよりは、ふみことばなどまさりざまなれど、なほ後の人の作りたるにて、式部が筆には、似べくもあらず、いとこよなし、
これらの話を別にしても、様々な説があるが、全て後世の人が根拠のない論を作り、それを述べているだけである。紫式部作という以外の説は、いずれも受け入れがたい。また、『源氏物語』の終盤の宇治十帖は紫式部の作ではないという説もあるが、これも道理に合わない。宇治十帖も紫式部が作ったことは明らかである。また、「雲隠」の巻は「雲隠」という巻名だけがあり、本文が存在しない。これは式部に思うところがあってそうしたというのに、今の世になって「雲隠」巻と称する本文が別に存在しているのは、後世の人が作り上げた仕業であって、目も当てられない拙いものである。また、「山路の露」といって、最終巻「夢の浮橋」の巻末に続けたものが存在する。これは先に述べた贋作の「雲隠」巻よりは文章や言い回しなどは勝っているが、やはりこれも後世の人が作ったものであって、式部の筆遣いには全く及ばない。あからさまである。
紫式部が事
紫式部系図は、諸抄に見えたり、父為時が事、越後守とも、又越前守ともいへり、越後守なりしことは、後拾遺集八の巻、式部が兄の惟規が歌のはし書に見え、越後より越前守になりたし事は、続世継の九の巻に見えたり、然ればはじめ越後にて、後に越前になれりしなりけり、夫宣孝は、良門の五世の孫にて、勧修寺の家の先祖也、式部、上東門院に宮づかへせしは、論なし、鷹司殿の官女といへるは、よりどころありや、しらすわ、御堂殿の妾といへるは、みだりごとなるべし、さて式部といふ名は、実の名にはあらず、すべて女房に、式部少納言弁右近などいふたぐひ、みないはゆる呼名也、
紫式部の系図は、諸々の注釈書にみられる。父為時は、越後守とも、越前守ともいわれている。前者の越後守であったのは、『後拾遺和歌集』巻八の、式部の兄である惟規の歌のはしがきに見られる(※1)。越後守から越前守になったことは、『続世継(栄花物語)』巻九に見られる。つまり、最初に越後守、その後越前守になったといえる。式部の夫、宣孝は、藤原良門の五代目の子孫(良門-高藤-定方-朝頼-為輔-宣孝)で、勧修寺家の祖である。式部が上東門院彰子に宮仕えしていたのは言うまでもない。鷹司殿(彰子の母、倫子)の官女であったことは根拠となる説があるかどうか知らない。御堂関白こと藤原道長の妾というのは妄説である。さて、式部という名は、実名ではない。女房を、式部や少納言、弁、右近などといった類の名は、いわゆる呼び名である。
※1『後拾遺和歌集』巻八「別」
父のもとに越後にまかりけるに、逢坂のほどより源為善朝臣の許につかはしける
逢坂の 関うち越ゆる ほどもなく 今朝は都の 人ぞ恋しき
藤原惟規
こは初学のためにまづいふ也、此人、実の名は世につたはらず、すべて古へ名高かりし女房、おほくは実の名は見えず、撰集どもにも、よび名をしるされたり、さて式部といふに、紫和泉小式部などあるは、式部といふが、あまた有て、まぎるる故に、わかむため也、そは或は其姓、或は父また夫などの官位さ、母の名など、たよりにまかせてよはりしなり、清少納言江侍従などは、清原大江の姓也、和泉式部は、和泉守道貞が妻也、小式部は、和泉式部が子也、伊勢大輔は、伊勢ノ祭主輔親の女なり、大弐三位は、太宰ノ大弐成章の妻也、
これは初学の者のために言っておいた。紫式部の実名は世に伝わっていない。昔の名高い女房というのは多くが実名不明で、和歌集にも呼び名で名が記される。さて、式部には、紫式部、和泉式部、小式部というように式部といっても多くいる。ただ、これでは紛らわしいため、式部を区別するために紫や和泉がついて呼び名となっているのだが、この由来は彼女らの姓、父や夫の官位、母の名など、何かしらに依存している。清少納言、江侍従(ごうじじゅう)などは、それぞれ清原や大江の姓を、和泉式部は和泉守道貞の妻であることに由来し、以下、小式部は和泉式部の子、伊勢大輔は伊勢祭主輔親の娘、大弐三位は大弐成章の妻といった具合である。
さて紫式部も、もとは姓によりて、藤式部といへりしと也、そはとうしきぶともよむべし、江侍従も、ごうじゞうとよむべし、清少納言などの例なり、ふぢしきぶえのじゞうなどは、よむべきにあらず、男にても、江帥藤大納言在中将などのたぐひ、みなこゑによめり、さね又紫としもいへるよしは、河海抄に一説ニ云ク、もと藤式部といへるを、幽玄ならずとて、藤の花の色のゆかりに、紫の字にからためらるとあり、今思ふに、此説は、紫といふによりて、思ひよりて、おしはかりにいへるもの也、其姓をよぶに、なにの幽玄ならざることかあらむ、殊に藤は、みやびたるもじなるをや、又清輔ノ朝臣の袋冊子にいはく紫式部といふ名に、二説有リ、
さて、紫式部も最初は姓に由来し、藤式部と呼ばれていた。これは「トウシキブ」と読まれ、江侍従が「ゴウジジュウ」と読まれるのと同じ道理である。清少納言などもその例である。「フジシキブ」や「エノジジュウ」などと読むべきではない。男も同じである。江帥(ごうのそち)、藤大納言、在中将などの類は、全て音読みなのだ。さて、ではなぜ「ムラサキ」と訓読みなのか。それは、『河海抄』に一説がある。「もともと藤式部といっていたのだが、それでは音の響きに幽玄(美しさ)がないため、藤の花の色にちなんで、紫の字に改めたのである。」と。今思えば、この説は紫という色から連想して、紫に改称した理由を推測したに他ならない。ただの姓に、幽玄が感じられないとは何だ。特に藤の字なんて、雅な文字ではないか。また、清輔朝臣の著書『袋冊子』には紫式部という名について説が2つ述べられている。
一には、此物語に、若紫ノ巻を作れる、甚深なる故に、此名をえたり、一には、一条院の御乳母の子なり、しかうして上東門院に奉らしむとて、わがゆかりのもの也、はあはれとおぼしめせと申さしめ給うさふ故に、此名あり、武蔵野の義也とあり、此二つのうち、諸抄みな前の説にしたがひ玉へり、河海にも、一部のうち、紫ノ上の事を、すぐれてかきなしたる故に、藤式部を改めて、紫式部と号せられたりとあり、今思ふに、紫ノ上の事を、すぐれてかける故というは、さも有べし、若紫ノ巻を作れる、甚深なる故といふは、心得ず、いかでか若紫ノ巻のみ、殊に甚深なることあらむ、
ひとつは、「『源氏物語』「若紫」巻に非常に想いを込めたが故に、紫という名を得たのではないか」という説。ふたつは、「式部が一条院の乳母子であることに由来して、上東門院に宮仕えする時に、一条院より「式部は私に縁のある者なのだよ。良きように計らってくれ。」という思し召しによって、紫式部と改めた。これは、武蔵野の義だ(後に詳述あり)。という説。『河海抄』と『袋冊子』の両抄は、前者に従って展開されている。『河海抄』には「『源氏物語』では、紫の上のことを立派に書いているため、藤式部から紫式部に改称した。」とある。今思えば、紫の上のことを立派に書いているというのは尤もだと思うが、「若紫」巻に深く想いを込めているため、という因果関係は納得しかねる。どうして「若紫」巻のみが他の巻と違って思い入れが強いだろうか。
藤式部から紫式部に改称した詳しい時期は分かっていませんが、『源氏物語』完成以後であることははっきりしています。そのため、紫とは若紫にちなんで付けられたのではないか、という説が古来より展開されていました。
さて御乳母の子なりし故に、一条のみかどの、わがゆかりのもの也、とのたまひつる故といふも、さも有べきこと也、これは後の人のおしはかりとは聞えず、式部母は、常陸ノ介為信ノ女と、系図に見えたる、此人、一条ノ御乳母なりし事、物に見えたりや、考ふべし、ゆかりのものとは、御乳母兄弟のよし也、むさし野の義也とは、古今集ノ上に「むらさきの一もとゆゑにむさしのゝ草はみながらあはれとぞ見る、といへる歌の意にて、これより紫をゆかりといひならはせり、
さて、式部が乳母子であったので、一条院が「彼女は我にゆかりある者なのだよ。」と言うのは、十分あり得る話である。これは後世の人が推測して作り上げた妄説とは思えない。系図によると、式部の母(藤原為信女)は常陸介である藤原為信の娘である。この人は一条院の乳母であったことが何かしらの本にみられるか否か検証する必要がある。ゆかりとは2つの意味がかかっている。まずは式部と一条院が乳兄弟であるというゆかりで、ふたつめは武蔵野の義が、『古今和歌集』雑歌上に「むらさきの 一もとゆゑに むさしのゝ 草はみながら あはれとぞ見る」という歌の意味で、これから紫をゆかりと言い表した。
紫式部日記に、左衛門ノ督、【公任卿】あなかしこ此わたりにわかむらさきやさふらふと、うかゞひ玉ふ、源氏にゝるべき人見え給はぬに、かのうへは【紫ノ上】まいていかで物し給はむと聞ゐたりといへり、
『紫式部日記』に、『左衛門督(藤原公任)が
「恐縮ですが、この辺りに若紫(式部のこと。『源氏物語』に戯れて式部のことを若紫と言っている)はいらっしゃいますか。」
と伺ってきた。そこに光源氏に似ている人はいなかったので(=公任は不細工)、紫の上(式部のこと)は「どうお答えしましょう。」と聞き耳をたてていた。・・・』
とある。
此日記の文につけても、ゆかりの説、まさりておぼゆる也、其故は、ゆかりの説によるときは、紫といふ名、かの紫ノ上にはあづからぬことなるを、それとよそへてのたまへるぞ興なる、すべてたはふれ言は、あらぬことを、めづらかによそへていふこそ、興とはすなれ、もし紫ノ上の事を、すぐれてかけるによりての名ならむにはわたはふれて若紫とのたまへる、なにのめづらひげかあらむ、
『紫式部日記』のこの一文をみても、先のふたつの説のうち、後者の説が有力であると思われる。その理由は、紫式部の紫には、『源氏物語』の紫の上とは関係はないとはいえ、式部と紫の上とを関連付けることに趣が感じられるためだ。全ての冗談というのは、何も関係ない出来事や珍事を人の心と結び付けて言うから面白いのである。もし紫の上に特に心を寄せて書いていたとすれば、戯れとして公任が式部のことを「若紫」と呼んだことに、何の違和感もない。
つくれるゆゑよし
此物語、いかなるよしにて作れりといふこと、さだかにしりがたし、あるは上東門院にさふらふ時、大斎院より、めづらかなる物語やと、のぞませ玉へるをりに、作りて奉れりといふ説なと、うけがたき事、かの七論にも、くはしくわきまへたるがごとし、又西ノ宮殿に、をさなき時、なれ奉れりといへるは、時代もたがへり、あるは石山にこもりて、かけりといひ、大般若経の料紙にかけりなといへる、みな妄説也、
『源氏物語』がどのような理由で作られたのか、この点に関しては定かではない。式部が上東門院に仕えていた時、大斎院(村上天皇の子、選子)から「珍しい物語はないか?」と望まれたことをきっかけに作成したのではいかという説などが受け入れ難いことは、かの『紫家七論』に詳述されている通りである。また、幼少期に西宮殿(源高明)と慣れ親しんだというのも時代が相違している。石山寺に籠って執筆したとか、大般若経の写経に用いられる高級紙に書いたとかという説も全て妄説である。
行成卿清書といふも、此人名高き手かきなる故に、つくりていへるなるべし、又かの石山にこもれるをりしも、八月十五夜の月、湖にうつりて、心のすみわたりけるまゝに、物語の風情の、心にうかひければ、まづ須磨明石の巻を、かき始めける故に、須磨ノ巻に、こよひは十五夜なりけりと、おぼし出てと侍り、といへるなとも、いとゝゝうけられず、もしこよひは十五夜也とあるをもて、十五夜に書たる証とせば、初音の巻に、けふは子ノ日なりけりとあるなとをも、正月の子の日にかきたりとせんか、いともをさなきこと也、
藤原行成卿が清書したという説も、この人が能筆家であったことからでっち上げられた説であろう。また、石山寺に籠った説の根拠である、『8月15日の夜、月が湖に映り心が澄み渡っていくのを見て徐々に『源氏物語』の情景が心に浮かんできた。だから「須磨」巻と「明石」巻に「今宵は十五夜であると思い・・・」とあるのだ。』というのも全くもって受け入れられない。もし「今宵は十五夜なり。」とあるから十五夜から書き始めたというのが真実だと仮定すれば、「初音」巻にある「今日は子の日(元旦)なりけり。」というのは元旦に書いたからそうであるわけか?ひどく稚拙な主張である。
又今石山寺に、源氏ノ間といふ有て、式部が像、またその机硯なとゝてあるは、みなかの説によりて、事好むものゝつくれる也、又源氏ノ君を、西宮ノ大臣になすらへたるは、さることなれとも、紫ノ上を、式部みづからよそへてかけりなどいふは、いとをこ也、いかでさるおふけなきことをば、思ひよらむ、
また、現在、石山寺に源氏の間というのがあり、式部の像や机、硯などがあるのは、全てこのような妄説に便乗して物好きが作ったものである。さらに、光源氏を西宮大臣(源高明)になぞらえたのは言うまでもなく、式部自身を紫の上に投影して書いたなどという説に至っては、たいそう馬鹿げている。どうしてそのような身の程知らずのことが思いつくのだろうか。
作れる時世
此物語、寛弘のはじめにいできて、康和の末に流布すと、河海有て、諸抄それによられたり、今式部日記をもて考ふるに、寛弘の始めにいでくとあるは、さも有べし、これらの事、なほ七論に、こまかに考へて、出来たるは、いかにも長保の末、寛弘の始メなるべしといへり、然るに或人、栄花物語浦々の別れの巻に、かのひかる源氏も、かくや有けんと見奉るとあるは、長徳二年四月の事なれば、それよりさきに、はやく此物がたりは、世に流布せりと見ゆ、寛弘のはじめに作れりといふは、ひがこと也といへるは、中々にたがへり、
『河海抄』には、「『源氏物語』は、寛弘年間(1004-1012)のはじめに完成し、康和年間(1099-1104)の末に広まった。」と書いてあり、その他諸抄はこれによって書かれている。今、『紫式部日記』から考えてみても、寛弘のはじめに完成したとあるのは、尤もである。これらのことは、なおもかの『紫家七論』に詳述されており、その中では「確かに、完成は長保年間(999-1004)の末から寛弘年間のはじめであろう。」とある。しかし、ある人は「『栄花物語』「9浦々の別」巻に、「かの光源氏もかくや有けんと見奉る」とあるのだが、これは長徳二年(996)四月のことであるから、『源氏物語』はこれ以前に世に広まっていたのだ。だから寛弘年間のはじめに完成したと言うのは誤りである。」と主張した。かえって間違っている。
現代では、完成は寛弘五年(1008)とされています
栄花物語作れるが、長徳二年ならばこそ、さもいはめ、かの栄花は、寛弘より後に出来つれば、なてふとかあらむ、さて康和の末に流布すとあるは、いかゞ、日記のおもむき、式部がみやづかへして在しほど、はやく宮の内には、ひろまれるさまに見えたるをや、又殊に世にもてあそぶとは、俊成ノ卿定家ノ卿のころより也、といへる説も、いかが也、こは俊成ノ卿の、六百番ノ歌合の判の詞、又定家ノ卿の実美の詞なとのあるをもて、例のゆくりなく、おしはかりにいへるをなるべし、
『栄花物語』が作られたのは長徳二年であるならともかく、『栄花物語』は寛弘以後に作られた作品であるため論外である。さて「康和年間の末に広まった」とあるのは、どうか。『紫式部日記』を見ると、式部が宮仕えしていた時にはすでに『源氏物語』は宮中内で広まっていたことが分かるではないか。特に、「世にもてはやされだしたのは、藤原俊成卿や藤原定家卿の時代である。」という説も、どうかと思う。これは、俊成卿が藤原良経主催の歌合、六百番歌合にて判者を務めた時の「『源氏物語』が想起できない和歌は残念でならない。」という判詞や、定家卿が『源氏物語』賞美の詞を残したことが理由である。いつもの通り、思い付きの推測に基づいて述べられただけだろう。
『栄花物語』の完成は、最古でも1030年頃だとされています。
此物語の名の事
大かたもろゝゝの物語の名の例、おほくは其中に、主としていふ人の名をもてつけたり、此物がたりも、そのでうにて、光源氏ノ君の事を、むねとしてかける故に、源氏の物がたりとはいふ也、此君の名、光といふ事は、桐壺ノ巻に、なほにほはしさはたとへむかたなく、うつくしげなるを、世の人ひかる君ときこゆと見え、又ひかる君といふ名は、高麗人のめできこえて、つけ奉りけるとぞと見えたり、これを二説と見むは、わろかンめり、たゞ世の人の申す、ひかる君といふ名は、もとこまの人のつけ奉りたる也、といるなるべし、
だいたいの物語の題名は、その多くが作中の主人公名から名付けられている。『源氏物語』もそれで、光源氏のことを中心に書いているため、源氏の物語というわけである。この君の名を「光」というのは、「桐壺」巻に「やはり、源氏の姿かたちは何にも例えがたいほど美しいため、世の人は彼を『ひかる君』と呼んだ。」とあり、また「『ひかる君』という名は、高麗人が褒めて付けた名である。」とある。これを「説がふたつある」と捉えるのは良くないだろう。ただ単に、「世の人が言う『ひかる君』という名は、もともと高麗人が付けたものである。」と捉えるのが適切である。
かくて巻々に、此君のかたちをほめたる詞にも、多くひかるといへり、紅葉賀ノ巻に、かほのいろあひまさりて、つねよりもひかると見え給ふ、又同じひかりにてさし出玉へれば、葵ノ巻に、一ところの卿ひかりには、おしけたれためりなど、なほ多し、匂宮ノ巻のはじめに、此君のかくれ給ひし事をも、ひかりかくれ給ひにし後と書出せり、又薫ノ君をほむるには、多くかをりといふことをいへり、
各巻においても、光源氏の姿かたちを褒める時は多くが「ひかる」と表現されている。「紅葉賀」巻では「顔の色が誰よりも勝っていて、常に輝いている(光る)ように見える。」とか「(藤壺宮のお腹には源氏との子がいるため)源氏と同じ、輝かしい(光にて)お子がお生まれ名になったので、」とあったり、「葵」巻では「源氏ただ一人の光(御光)で、他にいる美しい者を押し消すようだった。」とあったり、この表現は多い。「匂宮」巻のはじめには、この君が亡くなったことを「お隠れ(光り隠れ給ひ)になった後、」と表現している。また、薫の君を褒める時には、多くに「かをり」という語を用いている。
さて源氏は、此君の姓也、桐壺ノ巻元服の時、源氏になし給へるを見えたり、物語の中に、ひかる源氏とつゞきたる詞は、帚木ノ巻のはじめ、若紫玉かづら紅梅竹川などの巻々にも見えたり、さて物語の名、光源氏の物語といふべし、たゞ源氏ノ物語とはいふべきにあらず、といふ人あれど、さしもあらず、はやく作りぬしの日記にも、たゞ源氏の物がたりといへるをや、
さて、源氏とは、この君の姓である。「桐壺」巻において、元服時に「源氏」姓が臣籍降下された。作中において光源氏と、「光と源氏」を姓名同時に用いた例は、「帚木」巻のはじめ、「若紫」巻、「玉鬢」巻、「紅梅」巻、「竹河」巻などにみられる。それで、この物語の題名は「光源氏の物語」というのだが、「ただただ光源氏だけの物語ではないだろう。」という人もいるが、そんなことはない。作者が自身の日記『紫式部日記』に「これは光源氏の物語である。」と書いているではないか。
准拠
此物語、諸抄といへるとあり、たとへば光源氏といへる人はなけれども、西宮ノ左大臣【高明公、】になそらへて書たり、といふたぐひ也、されど物がたりに書たる人々の事ども、みなことゞゝくなそらへて、あてたる事あるにはあらず、大かたはつくり事なる中に、いさゝかの事を、より所にして、そのさまをかへなどしてかけるとあり、又かならず一人を一人にあてゝ作れるにもあらず、源氏君一ところのうへにも、いにしへの人々のうへに有し事どもを、やまともろこしにもとめて、一事づゝとりたることもありて、すべて定まれるとはあらざる也、
諸抄には、この物語のもととなった事柄(準拠)について論述されている。例えば、「光源氏という人は現実には存在しなかったが、西宮左大臣こと源高明がもととなって書かれている。」といった具合である。しかしながら、物語に登場する人々に関して全部が全部現実の事象になぞらえて書かれているわけではない。物語という創作物の中に少しだけ改変した現実の出来事を書くといったことがある。また、必ずしも一人一人もととなる現実の人物をあてるようには作られない。源氏の君ひとりにしても、日本や中国に於て昔に生きた人々の身の上に起こったこと部分部分から取ってきている。なお、これには定まった手法はない。
おほかた此准挙といふ事は、たゞ作りぬしの心のうちにある事にて、必しも後にそれを、ことゞゝく考へあつべきにしもあらず、とてもかくても有べきなれども、昔よりさだめしあへる事なる故に、今もそのおもむきを、いさゝかいふ也、さてついでにいはむ、五条に、夕皃の君の跡、須磨ノ浦に、源氏ノ君の跡、長谷に、玉かづらの君の跡、などいひてあるたぐひは、みな事好めるものゝ、つくりものがたりぞといふことをだに、わきまへざるしわざ也、これらはむげにをさなき事なれば、人のまどふべきにもあらざめるを、かくいふは、たゞうひまなびのために、おどろかせるのみぞ、
大体の準拠というのは、ただただ作者の心の中に委ねられるということであって、必ずしも、後から全て辻褄が合うように考える必要はない。いずれにせよどうでもいいことだが、昔から議論されてきたことであったので、今、私の所感を云々と述べたまでである。さて、ついでに言うが、京の五条には夕顔の君の史跡が、須磨の浦に源氏の君の史跡が、長谷に玉かずらの君の史跡が、といった風に存在する類は全て、物好きが『源氏物語』が創作物であるということを弁えずにやったことである。これらは無垢の子どものいたずらに変わらないのだが、このように言及したのは、ただただ初学の人に注意を流すためである。
くさゞゝの事
よに此物語を、源氏六十帖といひて、そは天台の六十巻に擬ふといふ説、ひがこと也、此物語は、五十四帖こそあれ、六十帖はよしなきを、かの天台の書にしひて合せむとてさはいひなせるにこそあらめ、たとひ六十帖あらむにても、天台の書の事は、いと物どほし、又巻々の例、史記の本紀世家列伝によれりといふも、あたらぬこと也、すべてさやうの事は、後にあてゝいへば、似たるともあへるともあるものなれど、そはおのづからにこそあれ、
世ではこの物語を源氏六十帖という。これは天台六十巻を真似たという説があるが、これは誤りである。『源氏物語』は五十四帖なのだ。六十帖と言われもしないのに、かの天台六十巻に強引に合わせてこのような説を主張したのだろう。たとえ『源氏物語』が六十帖あったとしても、天台六十巻とは共通点がない。また、『源氏物語』の巻々は『史記』の「本記」「世家」「列伝」によるものだとする説も外れである。このようなことは全て、後からあてつけて言っただけであるので、似た点や合致する点があるというのは、それはそうだろうよ。
それにかたどれり、これによれりなどいふすぢは、大かたあたらぬこと也、竪横の並の事、さしも用なき事なれど、むかしよりさだあることなれば、一わたりこゝろえおくべし、物語の人々の系図は、たしかにおぼえおくべきことなり、其人々の系図をしらでは、まどはしきことおほく、又こまかなるこゝろばへの見えがたきもの也、然るに有リ来つる系図は、もれたることおほく、をりゝゝ誤リも有て、人のまどふことにて、後の抄どもに、或惟は改め考へなどもせられたれども、なほ全からず、これによりておもれ、いまあらたに、くはしくかむかへ定めて、新系図を作らまほしく、思ひわたれど、いとまなくて、いまだはたさず、人人の年齢、巻々の紀年の事、作り物語ながら、みな合せてかける物なれば、たゞさずは有べからず、
あれを模倣したとか、これをもとにしているとか、という主張は、だいたい間違いである。本の巻・並びの巻(巻同士の関係をもとに分類する分析方法)というのがあるが、これは役に立たないものである。しかし、昔から議論されていることであるので一通り心得ておくほうが良い。作中の人物の系図は、しっかり覚えておく項目である。この系図を知らないと理解できないことが多く出てきたり、細かい心情描写を捉えづらかったりといった事態に陥る。しかし、ありきたりの系図は漏れが多く、所々誤りもあるため、それを手にした人々を混乱させてしまう。私は後の抄録をもとに考えを改めなどはしているが、なお完全とはいえない。しかし、これら抄録によって、今新たに詳しく考え、新系図を作ろうと発起していたのだが、その暇が無くて未だやり遂げられていない。人物の年齢や巻々の年月は、作り物語とはいえ、一連の作品として書かれているものであるため、正さないわけにはいかないのである。
さればむかしよりさだ有て、後成恩寺殿のあらはし給へる、年立あり、然れどもすべて誤リおほくて、宇治の巻々にいたりては、ことにまがひたるひがこと多きを、諸抄に考へたゞされたれども、なほよろしからざる事どもある故に、おのれ又ことに考へをあらはして、くはしくわけまへつ、猶巻々の年月のついで、見やすからむために、図をも物して、たよりとしつ、本は、むかし河内本といふと、青表紙といふと、大かた二やう有しとぞ、其中に、定家ノ中納言の本なるをもて、ちかき諸抄なべて、よきあしきをいはず、ひたぶるに青表紙のかたをとられたるさまなるは、いかにぞや、いづれの本にまれ、よしあしきにつきてこそ、とりもすてもすべきわざなれ、かならずそのぬしによりて、さだむべきにはあらざるをや、
これに関しても昔から議論がなされており、後成恩寺殿(一条兼良)が書き表した年立があるが、これは全くもって誤りが多い。宇治十帖に至っては、とくに間違いが多い。諸抄をもとに考えて訂正したが、それでも良くない部分があるため、私は別の場所(巻三)に自身の考えを詳しく書き表した。また、巻々の年月の順番を分かりやすくするために図を作成し、理解の助けとした。『源氏物語』の原文は、古くは「河内本」と「青表紙本」という大きく分けて2通りあったという。青表紙本には、藤原定家による「藤原定家自筆本」というのがあり、最近の抄録は揃って、信憑性に関わらずひたすら青表紙本のほうを採用している。これはいかがなものか。いずれの本にせよ、その良し悪しによって取捨選択するべきである。藤原定家が名高い人物だからといって、作成者の名だけで良し悪しを判断してはなるまい。
かくて今の世にある本とも。摺たる写したる、あまたなるを、おのゝゝところゞゝゝに、すこしづゝの異有て、たがひによきことあしきことあるを、おのれあまたよみ合せて、これかれ異なるところゞゝゝ、中によきをとりて、しるしつる、そのくだり別におくに物しつ、すべて假字がきのふるき書ども、今の世につたはれる、いづれもゝゝゝゝ、写し誤れること、おちたることなどおほくして、よみときがたきふしおほかるに、此物語はしも、よゝの人々の、ことにふかくめでられて、ひろくもちひらるゝとの、こよなかりしけにや、あだし書どもにくらぶれば、写し誤は、いとすくなくなむ有ける、されどなほ、ひが写しと見ゆる所々も、たえてなきにはあらずかし、
今の世において『源氏物語』は、版本や写本など多く存在するが、それぞれ所々に違いがあり、互いに良い点悪い点がある。私は多くの本を読み比べ、あれこれ異なる部分を見出しては出来の良いほうを採用し、記してきた。このことは別の場所(巻四)に書き置いている。基本的に、代々世に伝わっている仮名書きの古い『源氏物語』はどれもこれも誤字や脱字が多く、読み解き難いと思うことが多い。この物語は世々の人々が特に称賛して広く読まれたため、誤字脱字が多いのだろうか。そのような本に比べれば、この度採用した本は写し間違いがとても少ない。それでもなお、誤写とみられる部分が全くないというわけではない。
注釈
ちうさくは、河海抄ぞ第一の物なる、それよりさきにも、これかれとあれども、ひろからずくはしからざるを、かの抄は、やまともろこし、儒仏のもろゝゝの書どもを、ひろく考へいだして、何事も、をさゝゝのこれるくまなく、解あきらめられたり、さては花鳥余情あり、河海の誤れるところをわきまへ、もれたる事どもを考へくはへなど、すべてたよりとなることいとおほし、此二つの抄は、かならず見ではかなはぬもの也、
注釈書は『河海抄』が最初である。それより以前にもあれこれと存在はしたが、分析の広がりもなければ詳しくもない内容となっている。対して『河海抄』は日本や中国、儒教や仏教の諸々の書のことまで広く考証を行っている。何事もほとんど謎を残さず解き明かしている。さて、他には『花鳥余情』がある。『河海抄』の誤りを修正し、漏れた部分を補い考察を加えるなど、書全体を通して頼りになることが非常に多い。この2つの抄録は必ず見るべきである。
但し誤リもいとおほく、語の注などには、殊にひがことのみおほくして、用ひがたし、其後哢花抄細流あり、河海花鳥の誤リをたゞし、かれこれと考へくはへられたり、さて又明星抄孟津抄眠江入楚万水一露湖月抄など、なほくさゞゝ、頭書や何やと多かり、皆さきゞゝの抄どもを引出て、さしもことなることなく、たゞすこしづゝかはれるのみ也、其中に、今世中にあまねく用ふるは、湖月抄也、げに此抄は、さきゞゝのもろゝゝの抄どもを、あまねくよきほどに、頭ラと傍ラとに引出、師説今按をもまじへ、すべて見るにたよりよきさまにぞ書キなしたる、
ただし、誤りも非常に多いのは事実である。語注などは特に誤りが多く、参考にし辛い。その後に作られた『哢花抄』や『細流抄』が、『河海抄』と『花鳥余情』の誤りを修正し、かれこれと考察を加えたものとなってある。さらには『明星抄』『孟津抄』『岷江入楚』『万水一露』『湖月抄』などもあり、その他頭書やら何やらも多く存在する。いずれも前に記した『河海抄』や『花鳥余情』などを引用し、たいしてこれらと異ならず、少しずつ変わった程度の作品となっている。これらの中でも、今の世において広く用いられているのは『湖月抄』である。前に記した諸々の抄録のよく出来ている部分を広く頭注や傍注として引用し、師説と自説とを交えた考察を行うといったもので、本当にこの抄録は、全体的に見ごたえのある良い書きぶりをしている。
さて又契沖ほうしの源注拾遺といふ物八巻あり、ことゞゝく注せるにはあらで、たゞ諸の抄にもれたる事、誤れる事どもを、こゝかしこ、わきまへ解たる物也、此人は、よにことなるさとり有し人なれば、めづらしきこと多し、すべてこの人のあらはせる書どもは、近き世のうきたる説をば、さらにとらで、何事も、古き書を証として、新に見明らめたることおほき也、又さきにもいへる、紫家七論といふものの一巻、これは注釈にはあらず、たゞ此物語の大むねを論じ、紫式部が才徳など、日記を引出て、くはしく考へ、昔よりの妄説どもをわきまへなど、さまかはりて、一ふしある物也、かならず見べし、
さて、契沖法師の『源注拾遺』という全八巻の抄録があるのだが、これは全てに注釈を施したものではなく、諸々の抄録からあちらこちらにあった埋もれてしまったことや誤っていることなどを、解き明かした書である。この契沖という人は並々ならぬ理解力を有していた人だったため、珍しい考察をしているものが多い。契沖の著書は全て、近年の浮説は決して引用せずに、何事も古い時代の書の記述を証とし、新たな発見をしている。また、前にも記した『紫家七論』という全一巻の書があるが、これは注釈書ではない。ただただ『源氏物語』の概要を論じ、紫式部の才徳などを『紫式部日記』を引用して詳しく考察し、昔から言われる妄説を論破するなどといった、一風変わった書である。必ず一目通すべし。
但しそのおほむね、たゞもろこし人の、書ども作れる例をのみ思ひて、物語といふ物の趣をおもはず、物のあはれをむねとかけることをば、いまだしらざるものにして、諷諭と見たるは、なほ儒者ごゝろにぞ有ける、又我師縣居ノ翁も、此物語の新釋といふ物あることは、はやくよりきけれど、いまだ其書をえ見ず、たゞその論考といふ一巻を見たり、その趣、大かた契沖為章がいへるにゝたり、新釋の例をも挙られたり、又熊澤了介とかいふ人の、外伝といふ物などもあれど、ひたぶる儒者ごゝろのしわざにて、ものがたりのためには、さらに用なし、
ただし、全体的な内容は、中国人の著作が最上であるという前提のもとで考えられたものとなっており、物語というものの趣を考慮していない。『源氏物語』が物のあはれを趣旨とした作品であることを安藤為章は知らないのである。『源氏物語』を情景と雰囲気だけで書かれた作品だとする主張がみられるのは、やはり儒学者脳である。また、我が師匠縣居の翁(賀茂真淵)も『源氏物語新訳』という注釈書を書いていたというのは昔から聞いていたが、未だに全巻見たことが無い。論考に関する一巻は見たのだが、この巻は全体的に、契沖や為章の主張と似ていたのに加え、新訳されていた箇所もあった。また、熊沢蕃山という人の『外伝』という書物があるが、見事なまでに儒学者脳で書かれていて、『源氏物語』と読む参考には全くならない。
これらをおきて、世にしられぬ物どもゝ、なほ有べき也、そもゝゝかくしるべのふみどもは、いとこゝらあれども、なほうはべの一わたりのことこそあれ、文章のこまやかなるこゝろばへ、作りぬしの、ふかく心をこめたるおもむきなど、くはしきくまぐままでは、いまだゆきたらはぬ事のみ多かめれば、たゞ注釈にのみすがりて、事の意の聞ゆるをよきにして、やむべきにはあらず、なほこまやかなるところを、おく深く尋ぬれば、えもいはぬあぢはひのあるふみぞかし、
これら以外にも、世に知られていない注釈書は、なおも存在するのだろう。そもそも、このように『源氏物語』の読み解きを助けてくれる書物はたくさんそこら中にあるけれども、なお内容の薄い論が全体を通して書いてあるならまだ良い。問題なのは、『源氏物語』の文の技巧による細かい心情描写や、作者が特に心を込めた風情などを詳しく網羅するまでに踏み込んだ内容を書くのは未だに多難であるからといって、ただただ注釈を頼って『源氏物語』の概要を知っていれば良いといったところで論考を止めることである。これは止めなくてはならない。そこから更に細かいところなど奥深くまで調べてみると、言葉では言い表すことのできないほど、味わい深い作品だと分かるのだ。
引歌といふものゝ事
物語の詞の中に、古き歌の、たゞ一句などを引出て、またくその一首の意をこめ、あるはその句のつゞきの詞の意をこめなどしたるを、引歌といひて、其歌は、大かた河海抄に引出されたり、まれにもれたるなど、花鳥にも出たり、其後々の抄どもに、しるされたるは、皆河海花鳥に出たるをとれる也、
物語の文中には、古い和歌ただ一句を引用したり、その一首に情景の意趣を込めたり、その句の続きの文章に意趣を込めたり、といった手法を引歌(ひきうた)という。引歌は基本的に『河海抄』に書き出されている。まれに漏れたものもあるが、それは『花鳥余情』にて補われている。その後登場した抄録に記されている引歌は全て、『河海抄』『花鳥余情』に既出のものをさらに取ってきている。
然るに河海抄に出されたる引歌、かなはぬも有リ、又詞のたがへることいと多く、あるは此歌とかの歌と、本末をとりまがへて引れたるなど、あるは又古歌にあらで、其意聞えぬえせ歌なども有リ、すべていとみだりなり、此事は、契沖もいへるごとく、たゞそらにうかべ玉へるが、たがへるなどを、そのまゝに、ゆくりなくしるされたるものとぞおぼゆる、然るを後の抄どもにも、その考へなく、たゞ河海のまゝにとられたる、それも又みだりなるわざなり、すべてその心して見べし、さて又河海其外の抄にも、引歌未勘としるされて、いかなる歌の詞ともしられぬも、をりゝゝあるは、猶よくかむかへて、引出まほしきわざなり、
『河海抄』にて記された引歌には誤っているものもあり、また和歌の文字が間違っていることが非常に多く、この和歌とあの和歌の上下を取り間違えて記していたり、古歌ではない意味の通らない和歌などもあったりと、全体的にひどく質が悪い。このことは契沖が指摘しているように、著者の四辻善成は、ただただ間違った和歌などを思い出して、そのまま筆の赴くままに書き記したのだろう。こうして後世の抄録などは、自分の考えも持たずに、ただ『河海抄』に記された和歌をそのまま引用しているのだ。なんとも目も当てられないザマである。引歌に関する書籍は、常にこのことを心に留めて読むべし。さて、『河海抄』やその他抄録には、「引歌未勘(引歌不明)」と記され、どのような和歌が取られているのか分かっていないものを時々見かける。なおよく考えて、その正体を引き出したいものである。
湖月抄の事
此物語、今の世、これかれあまたの本どもある中に、たよりよきまゝに、おほくは湖月抄を見る事也、それにつきて、こころうべき事どもあり、まづ此抄の本、おほかたはよろしき中に、をりゝゝあしき事、又詞のおちたるところなどあるは、今他本とよみくらべて、みなえり出て、奥にしるせがごとし、又此抄、すべて句読いとみだりにして、誤リおほく、中には句によりて、いたく語の意をも、誤ること多し、その心してよむべし、
『源氏物語』は今の世にあれこれと多くの本があるが、その中でも頼れるものはなく、結局多くの人は『湖月抄』を見ることとなる。これについて心得ておくべきことがある。まず、『湖月抄』は基本的に質の良い本だが、所々悪い部分や、言葉の落ちた所などがあるのだが、それに関しては他の本と読み比べて全て洗い出して後に記した。また、『湖月抄』は全体的に句読点が乱れていて、文体の誤りが多いだけでなく、中には句点の誤りによってまるっきり語意が変わっているといった誤りも非常に多い。このことには留意して読むべきである。
清濁も、わろきことおほし、假字づかひのことごとくたがへるは、後の世のおしなべたることなれば、わきていふべきにあらず、さていはゆる引歌の例に、一の点をかけたるに、引歌ならぬところおほし、引歌とは古き歌によりていへる詞にて、かならず其歌によらでは、きこえぬ所也、然るに此抄、河海花鳥などに、古歌を引たるをも、そのわきまへなく、引歌といふ物と、ひとつに心得て、かの点をかけたるところの多き也、
また、清音と濁音の使い方も悪い部分が多い。仮名遣いが悉く間違っているのは、後の世において発音が変化し続けていることが原因なので、私はこれに関しては言及しない。さて、引歌には、「一」の点を書いているのだが、それが引歌でないことが多い。引歌とは古い和歌に使われた言葉であるため、もとの和歌が分からなければ意味が通らない。つまり、『河海抄』や『花鳥余情』などには、古い歌を取ってきているものの、それが引歌か否かという区別はなされておらず、ただ引歌と共通する言葉が使われていたから、という理由でむやみに関係ない古い和歌を引歌にあてたのである。「一」の点が書かれているところがやけに多いのは、そう思ったからなのだろう。
又注の中に、河海抄花鳥余情などにある事を引るには、河また花と標すべきわざなるに、それをばおきて、後の抄に引たるかたによりて、哢あるは細なしとしるせる事つね也、されば、哢細なとゝて引たるには、河海花鳥の説おほしと心得べし、大かたこれらの事ども、今思ひ出るまゝに、一ツ二ツしるしぬ、なほもあらむは、なすらへても心得べき也、さておのれ今此小櫛を物するにも、世にあまねく見る本なるゆゑに、たよりよからむために、何事も、此湖月抄につきていふことおほし、巻々の、そのひらゝゝとしるすたぐひなり、
また、注釈の中で『河海抄』や『花鳥余情』などに記されている事柄を引用するなら、「河」とか「花」とか明記するべきであるのに、それを差し置いて、後世の抄録を引用している。「哢(『哢花抄』のこと)」や「細(『細流抄』のこと)」である。この二抄が『河海抄』と『花鳥余情』の誤りを修正し、かれこれと考察を加えたものであることは既に述べた通りで、言い換えれば、この二抄を引用としてはいるが、その実態は『河海抄』と『花鳥余情』に記されている説の引用が多いということを心得ておくべきである。これらのほとんどは、今私が思い出すままに記した一つや二つである。他にもあるが、今述べてきたことになぞらえて考えれば良い。さて、私が今この『源氏物語玉の小櫛』を著すのは、『源氏物語』が世間に多く詠まれている本であるからで、読解の助けにしてほしいと思ったからである。多くは『湖月抄』に即して述べた。『湖月抄』でいう、巻々のどこどこといった類の書き方である。
現代でも、年末に取り立てが来ることがあるのでしょうか。経験が無いので分かりませんが、そんな年末は避けたいものです。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |