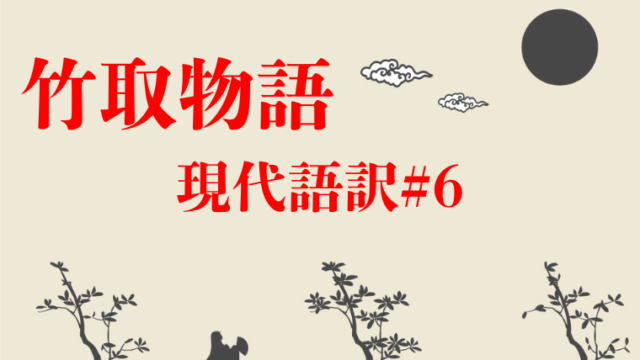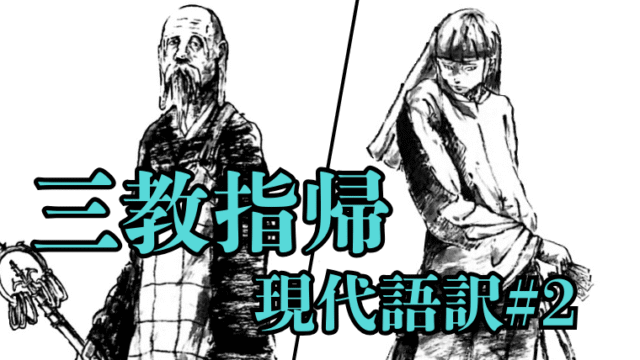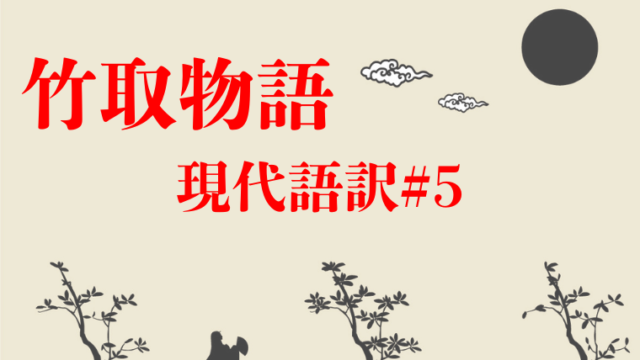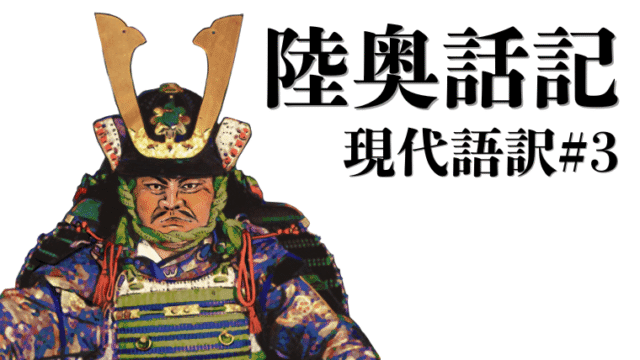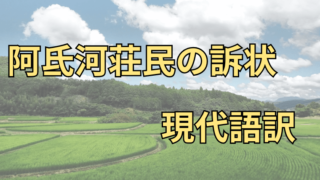51:色々の鳥
山にはさまざまな鳥が住んでいるが、その中で最も寂しい鳴き声の鳥はオット鳥である。夏の夜中に鳴く習性がある。沿岸部の村にある大槌から駄賃附(だちんづけ)の者などが峠を越え来た時、遥か遠くの谷底からその声が聞こえてくるという。
昔いた、ある豪農の娘の話である。この娘が、親しい仲のとある豪農の男の子と山に遊びに行った際、男の子がいなくなってしまった。夕暮、そして夜になるまで彼を探し歩いたが、見つけることができなかったので、ついに娘は「彼はこの鳥になってしまった。」と思った。
「オットーン、オットーン」という鳴き声は「夫」のことを言っているのだ。語尾がかすれるので、憐れな鳴き声である。
52:色々の鳥
馬追鳥(うまおいどり)は時鳥(ほととぎす)に似ている鳥だが、時鳥よりも少し大きく、羽の色は赤に茶を帯びており、肩には馬の綱のような縞模様がある。また、胸のあたりにクツゴコと呼ばれる馬の口に嵌める網の袋のような形がある。
ある豪農の家に使えていた奉公人が山へ馬を放しに行った時の話である。家に帰ろうとした時に馬が一頭不足していた。夜通し捜し歩いたが見つからず、ついにこの奉公人は馬追鳥となってしまった。「アーホー、アーホー」と鳴くのは、野にいる馬を追う時のこの地方特有の呼び声である。
年によっては、馬追鳥が里に来て鳴くことは飢饉の前兆であると言われている。もしこの鳴き声を聞きたいならば、生息している山奥にまで行くしかない。
53:色々の鳥
郭公(かっこう)と時鳥(ほととぎす)とは昔は人間の姉妹であった。郭公は姉である。
ある時、芋を掘って焼き、芋のまわりの堅い部分を自分が食い、中の軟かい部分を妹に与えていた。妹は「姉の食う部分は一層旨いのだろう。」と思い、庖丁で姉を殺した。
すると姉はたちまち鳥となり、「ガンコ。ガンコ。」と鳴いて飛び去っていったのだった。「ガンコ」とは方言で「堅いところ」という意味である。
妹はその鳴き声を聞いて「姉は良い部分だけを自分にくれていたのだ。」と思い、包丁で手にかけた悔恨に堪えなかった。そして妹も鳥となって「庖丁かけた」と鳴いたという。
遠野では、時鳥のことを「庖丁かけ」と呼ぶ。盛岡の辺りでは、時鳥は「どちゃへ飛んでた」と鳴くという。
※芋とは馬鈴薯のことである
54:神女
閉伊川(へいがわ)の流れには淵が多い。そのため、この川の恐ろさを由来にもつ伝説が少なくない。
小国川との落合に近いところに、川井(かわい)という村がある。その村の長者の奉公人の話である。
この奉公人が、ある淵の上に存在する山で樹を切ろうとしたところ、斧を水中に落してしまった。この斧が主人の物であったため淵に入って探しに行くと、川底まで行ったところで物音が聞えてきた。この音の正体を求めて進むと、岩の陰に家を見つけた。
奥の方には美しい娘が機を織っていた。彼の斧はそのハタシに立てかけてあった。「それをお返しいただきたい」と言うと女は振り返った。女の顔を見ると、なんと二、三年前に亡くなった我が主人の娘ではないか。
「斧はお返ししようと思います。ですので、私がこの場所にいることを誰にも言わないでください。礼として、あなたの身の上を良くし、奉公せずとも生活できるようにします。」と言った。
これの効果か否かは知らず。その後、奉公人は胴引(どうびき)などの博打に不思議と勝ち続けて金が貯まり、ほどなくして奉公を辞め、外に出ずとも富を持つ中ぐらいの農民になった。
この男はすぐに物忘れする性格であったため、この娘の言っていたことも覚えていなかった。ある日、同じ淵のほとりを過ぎて町へ行く時、ふとあの時の事を思い出して同伴していた者に、「以前このようなことがあった」と語った。『誰にも話すな。』という娘の条件を覚えていなかったのである。すぐにその噂は近郷に伝わり、その頃から男は富が再び傾きだしたという。そして、また昔の主人に奉公して歳月を過ごすこととなった。
家の主人は何を思ったのだろうか、その淵に何度となく熱湯を注ぎ入れるなどしたが、何の効もなかったとのことである。
※下閉伊郡川井村大字川井。「川井」はもちろん川合という意味であろう
55:河童
川には川童多く住んでおり、特に猿ヶ石川に多く生息している。
松崎村の川端家で、母娘二世代続けて川童の子を孕んだことがあった。生まれてきた子は容貌は極めて醜にくく恐ろしいものであったため、切り刻んで一升樽に入れて土の中に埋めていた。河童を産んだ妻の夫は新張村の何某といって、この者も川端の家に住んでいた。要するに、この夫婦は妻の家に住んでいるということである。夫は人に河童騒動の始終を語った。
ある日、川端家の者総出で畑仕事をしていた時のこと、夕方になったので帰ろうとした時、河童を産んだその娘(妻)が川辺にうずくまってにこにこと笑っていたのを見た。次の日は、畑仕事の昼休憩中に同じ光景を見た。というような日が続き、ついには村の何某という見知らぬ者が夜な夜な妻のところへ通っているという噂も出てきた。
その村の何某は、はじめは夫が浜の方へ仕事に行っている時間だけを窺っていたが、しばらくして、夫婦ともに寝ている夜にさえも来るようになった。「この見知らぬ者は川童だろう」という評判が徐々に高まったので、川端家がみなで集まって女を守るも効果はなかった。ついには夫の母も川端家へやって行きて女の側で寝るにまでなった。
ある日の深夜、娘の笑う声を聞いて、「さては来たな」と夫の母は思ったがなぜか身動きが取れない。こうして、人々は打つ手がなくなったのだった。
そして再び出産の時になった。河童の出産は極めて難産なのだが、ある者が「馬槽(うまぶね)に水を張り、その中で出産すれば安産になるだろう。」と言っていたので、試しにやってみることにした。
すると言った通りに上手くいき、生まれた子を見ると手には水掻きがあったのだった。また驚くことに、この娘の母も、かつて川童の子を産んだことがあるという。
このことを聞き、二代や三代どころの因縁ではないという者もいた。この母の家もまた豪農の家出身で、何の某という士族の家であった。村の議員をしたこともあったそうだ。
56:河童
上郷村の何某という者の家でも、川童のような物の子を生んだということがあった。
確な証拠はないけれども、身体が真っ赤で口が大きく、本当に醜い子であった。忌わしく思われたのでこの子を棄てようと思い立ち、道ちがえ(※)に持って行き、そこに置き捨てようとした。一間(約2m)ばかり離れたところでふと思い直し、
「これは惜しいものではないか。売って見せ物にすればきっと金になる。」
と思って連れて帰ろうとしたが、もうどこかへ隠れてしまい、見えなくなったという。
※「道ちがえ」とは道が二つに別かれるところ。すなわち追分である
57:河童
川岸の砂の上に川童の足跡が残っていることは決して珍しいことではない。雨の日の翌日などは特に見られる。猿の足と同じく親指は離れており、人間の手の形に似ている。長さは三寸(約10cm)に満たない。しかし、指先の形は、明らかに人の指には見えないという。
58:河童
小烏瀬川(こがらせがわ)の姥子淵(おばこふち)の辺りに、「新屋の家(うち)」という家がある。
ある日、淵へ馬を冷やしに行った。馬を引いてくれた子は他の場所へ遊びに行ったのだが、その間に、川童が淵から出てきて馬を水の中に引き込もうとした。しかし、馬の方が力が強かったため、かえって馬に引きずられて厩の前まで来たのだった。
河童は飼料を入れておく桶である馬槽(うまふね)に入って隠れた。家の者が、「河童が馬槽の中で伏しているな」と怪しんで、少し開けて見ると川童の手が出てきた。
村中の者が集まって、河童を殺すか許すかと評議したが、結局、「今後は村中の馬に悪戯をしない」という固い約束をさせて河童を解放したのだった。
現在、その川童は村を去り、相沢の滝の淵に住んでいるという。
※この話と似たような形式の話が全国に充満しており、また、川童が住んでいると言われている国には必ずこの話がある。なぜだろうか。
59:河童
他の土地では川童の顔は青いと言われているらしい、遠野では赤いと言われている。
佐々木君の曾祖母の幼かった頃の話である。友だちと庭で遊んでいたところ、三本だけ生えている胡桃の木の間から、真っ赤な顔をした男の子の顔が見えた。これは川童であったという。今もその胡桃の大木は存在している。そして、現在のこの家の屋敷の周囲はすべて胡桃の樹である。
60:狐
和野村の嘉兵衛爺(3・41・62に同じ)は雉子小屋に入って、雉子が来るのを待っていたのだが、その間、狐がやって来て雉子を追いまわすことがしばしばあった。
あまりにも狐が憎かったので狐を撃とうと思って銃口を向けると、狐はこちらの方を向いて何ともないような顔していた。さて、そのようなことも気にせずに引金を引いたのだが、なぜか不発に終わった。胸騒ぎがして銃を確認すると、いつのまにか、筒口から手元のところまでぎっしりと土が詰めてあったのだった。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |