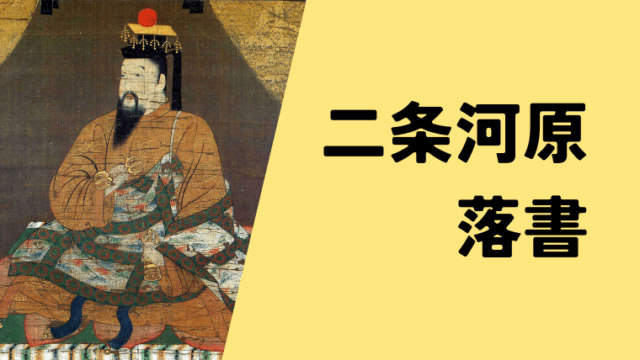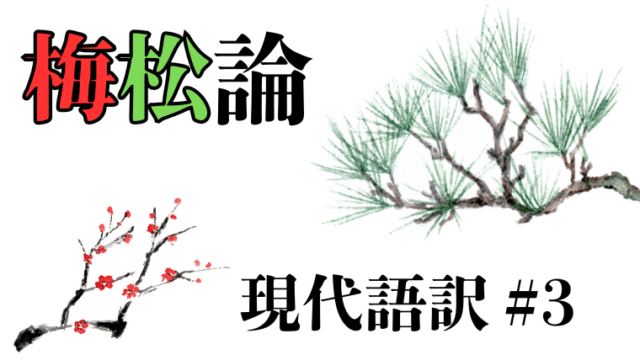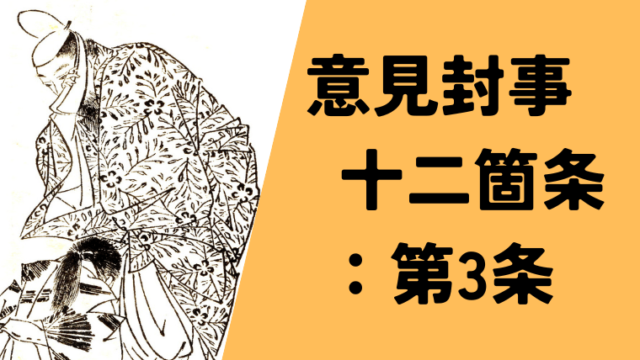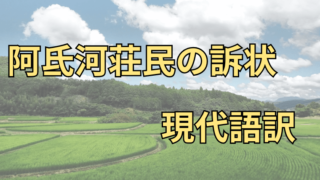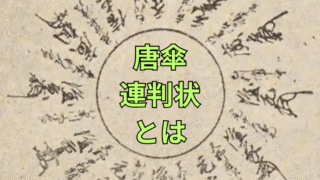現代語訳
建治元年乙亥 〇文永十二年四月二十五日改元
十月二十八日
高野山文書[又続宝集七十八]
阿テ河ノ上村百姓ラツゝシテ言上
一フセタノコト、リヤウケノヲカタエ、フセシツメラレテ候ヲ、ソノウエニチトウエカタエ、マタ四百文フセラレ候ヌ、マタソノウエニ、トシヘチニ一タンニ二百文ノフセレウヲセメトラルゝコトタヘガタク候、
一スナウノコト、イマゝデワ、百姓ユラツキ候ツレドモ、チトウトノキヤウヨリ、アラツカイニ、シモノクモンシ郎ヲクダシテ、カハウニセメ候エハ、タヘガタクシテ、セメトラレ候イヌ、
一ヲワタノコト、百姓トカウナシリ候ツレトモ、マコシ郎トノ、百姓ノイエニ、タシヨノヒトワ、カケニンカレコレ廿ヨ人ノツカイヲ、ツカイヲツケテ、カハウニセメラレ候ヘバ、タヘガタク候テ、セメトラレ候イヌ、
一ヲンサイモクノコト、アルイワチトウノキヤウシヤウ、アルイハチカフトマウシ、カクノコトクノ人フヲ、チトウノカタエセメツカワレ候ヘバ、ヲマヒマ候ワス候、ソノゝコリ、ワヅカニモレノコリテ候人フヲ、サイモクノヤマイタシエ、イテタテ候エハ、テウマウノアトノムキマケト候テ、ヲイモトシ候イヌ、ヲレラカコノムギマカヌモノナラバ、メ・コトモヲヲイコメ、ミゝヲキリ、ハナヲソキリ、カミヲキリテ、アマニナシテ、ナワホタシヲウチテ、サエナマント候ウテ、セメセンカウセラレ候アイダ、ヲンサイモクイヨイヨヲソナワリ候イヌ、ソノウエ百姓ノサイケイチウ、チトウトノエコホチトリ候イヌ、
一スナウコト、レウヲ、チトウトノカタヘセメラレ候ヘバ、セウゝゝハカリニマカリイデゝ候ヘバ、ヒクレ候イヌ、トモガラノイエニ、ヤトヲトテトマテ候ヘバ、チトウノトノヒトヒヤウクヲソロエテ、百姓ノトゞマリタルヤトエ、テマツヲサゝゲテ、十月ノ廿一日ヨナカハカリハヤク、百姓ノクヒヲキラントシ候コシテ候、百姓ソレニヲゝキニヲドロキサワキテ、十ハウヘニケチリ候テ、ワツカニイノチバカリワイキテ候、
一チトウノマコシ郎ドノ、廿ヨ人クソクシテ、百姓ノクサノイヲリニ、十月八日ヨリシテ、三日カアイタセメラレ候、マタ十月ノ十八日、二日アイタ、セメセンカウセラレ候、ソノアイダニ、クシウツカマリ候コト、二百センマデソナヘ候コト、タヘガタク候、ソノホカニ、五人三人ノツカイワ、ヒマ候ワス、カクノゴトキノクシウヲメシ候ガウエニ、百姓クリカキヲ、トノヒトヲ、ヲイノボセ、ヲイノボセトラセテ、モカキメシ候コト、モノアサナク候ナリ、
一コノ四人ノ百姓ヲ、コリヤウニエアントスベキゾト、コチヤ候ヘドモ、マスマスニ、チトウトノコカミヲカケラレ候ヘバ、コリヤウニエアンドセズ候、コレラコリヤウニアンドシテ候ワバ、百姓ミクシヲツカマツリ候トモ、イカゞ百姓ヨロコビ候ワン、
一チトウノチヤウセチノウマカイノコト、セムレイ候ヌコトニテ候ヘバ、百姓ラヲゝキナルナゲキ候、
一カクノゴトク、マコシ郎ドノ、百姓ノイヲリニ、モノゝクヒウクヲソロエテ、フミイリフミイリ、百姓ヲモリコメゝゝ、セタケラレ候ヘバ、イヨゝゝ百姓ウセ候ナンズル候、
一サメウシノワカミヤヨウトウト候テ、三貫文セニセメトラレ候コト、イマダセレイナキコトニテ候、
一十月廿五日ヨリ、チトウタラウマコシ郎上下卅五人、百姓ノモノトニシキヰ候テ、イロゝゝノモノヲ、セメトラザランナキヲワ、ナン十日モタツマシト候テ、一日ニクリヤ三トツゝシ候コト、タエクラウハカリモ候ズ、ソノウエニウマノカイマクサ、一日ニ一斗三升セメトリ候、ソノウエニ、マメアツキアワヒエヲトリカワルゝコトラタヘガタク候、
一コノウマノカイヲソクイルゝトテ、カマクワナベ巳上十五サラニムシチニトラレ候イヌ、
一ウスクマリタトナツケテ、タンヘチニ三百文ノゼニセメトラレ候コト、センレイナキコトニテ候アイダ、コトニ百姓スツナキコトニテ候、コノデウゝゝノヒレイニテセメラレ候アイダ、百姓トコロニアンドシタク候、
ケンチカン子ン十月廿八日 百姓ラカ上
題
阿氐河上村の百姓ら謹んで言上
1伏田について
一。伏田のことについてです。領家のお方に伏料を取られたというのに、その上地頭の方にまた四百文の伏料を取られました。また、更にその上に、年別に一段につき二百文の伏料を責め取られてしまうのは、耐えがたいことであります。
2年貢収納について
一。年貢収納のことについてです。今まで百姓らは納め先にお仕えしていましたが、地頭殿が京より下らせた新使いの下公文次郎が苛法もって我々を責めましたので、耐えられず、納めるはずだった年貢を責め取られてしまいました。
3繊維について
一。繊維の原虫カラムシ、綿のことについてです。百姓とが、孫次郎殿が百姓の家に他所の人、家人をかれこれ二十数人を行かせた。その者らの苛法をもって我々を責めましたので、耐えられず責め取られてしまいました。
4材木について
一。御材木のことについてです。地頭が人夫を、「夫役の京上夫として、或いは下向の連れ達に使う」と申し、このようなために地頭の方に責め使われています。そのため、暇がありません。責め使われず残った人夫ですら僅かであるのに、材木を切り出す際、「逃亡の跡にムギを撒け」と言って逃亡した者は追い戻されました。我々がこのムギを撒かないものならば、女子供を追い込み、耳を切り、鼻を削ぎ落し、髪を切って尼にして縄で縛って追い打ちをかけるのです。このような仕打ちに苛まれ、銭を責め取られているうちに御材木の切り出しがいよいよ遅れてしまいました。その上、百姓の在家一軒が、地頭殿によって壊され、取られてしまいました。
5年貢収納について2
年貢の収納のことです。地頭殿方に料を責め取られてしまいましたので、少々ばかりの人数で出頭したら日暮れになってしまいました。仲間の家に宿を取っていたのですが、地頭殿の家の者が兵具を揃えて、百姓の首を切ろうとそこへ松明を捧げてやって来たのです。十月二十一日の夜中に入った頃のことでした。百姓はそれに非常に驚き騒いで四散し、なんとか命を繋ぎ止め、こうして生きております。
6横行行為について
一。地頭の孫次郎殿が具足として二十人を用意し、百姓の草庵に来て十月八日から三日間の間責められました。また、十月十八日から二日間、銭を責め取られてしまいました。責め取られているその間生活に苦しんでいたのですが、二百銭まで用意するのは耐えられません。その他にも、五人、三人の孫次郎殿の使いがやって来るので暇がありません。このような苦しみ受けながらお仕えしているのだが、その上に百姓の採集した栗・柿は殿人によって追い上げられ取られてしまいました。もがきながらお仕えし、手元に残っている物は少なくなってしまいました。
7約束状について
一。「この四人の百姓を御領に安堵すべきである。」という書状があるのですが、ますます地頭殿が紙子という着物を課してくるので、四人を御領に安堵できません。彼らを御領に安堵してくれるのならば、百姓が雑税や夫役といった御公事を課せらてたとしても、ますます喜ぶことと思います。
8馬飼について
一。地頭が朝に行う馬飼いの仕事のことについてです。先例にない事でありますので、百姓らにとって大きな負担となり、嘆いております。
9横行行為について2
一。これまで述べた通り、孫次郎殿は物乃具・兵具を揃えて百姓の庵に何軒も踏み入り百姓を取り込めています。虐げられるため、いよいよ百姓は逃亡しようとしております。
10横行行為について3
一。「白毛である左女牛を若宮用の一頭に」と仰り、三貫文を責め取られてしまいました。未だ例のないことであります。
11横行行為について4
一。十月二十五日から、地頭の長男孫次郎が三十五人で上下の荘園の百姓の門戸にやってきて、色々なものを責め取っています。そうでない時は何十日も居座って台所で一日に三度食事をなさり、残らず食らい尽くすのです。その上、馬飼い用の馬草を一日に一斗三升責め取られたり、マメ、アズキ、アワ、ヒエを代わる代わる取られたりと堪えられません。
12横行行為について5
一。「うずくまり田」と名付けて、段別に三百文の銭を責め取られてしまいまいました。先例にない事であり、とりわけこの件は百姓になすすべはありません。
13横行行為について6
一。この馬飼いの遅く入れたからといって、鎌、鍬、鍋、以上十五はざらに質屋に取られてしまいました。
終わりに
これら条々に記したことは非例によって責め取られたものであり、百姓はただこの所で安堵して生活したいのです。
建治年間十月二十八日 百姓等ヶ上文
まとめ
いかがだったでしょうか。平安時代には受領や遙任といった悪質な国司がいましたが、それが地頭にとってかわったようなものとなってしまいました。歴史は繰り返すとよく分かります。
- 国司:朝廷が任命
- 地頭:幕府が任命
国司の権利が地頭に遷移した経緯についてはこちらで解説しています。是非ご覧ください。
https://toracha.com/zakki/kokushi-zito
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |