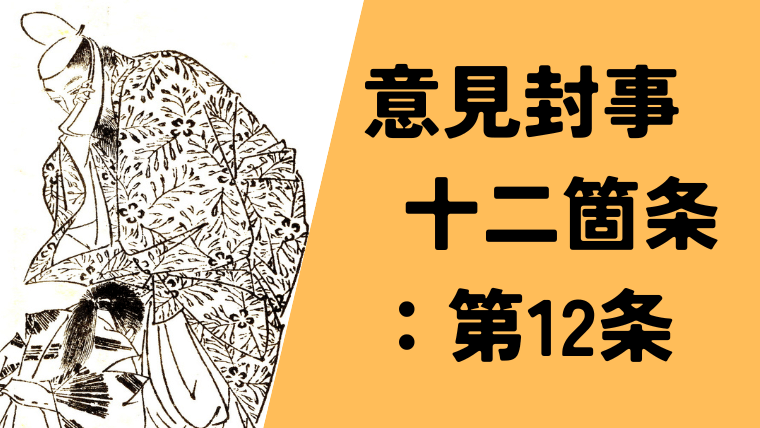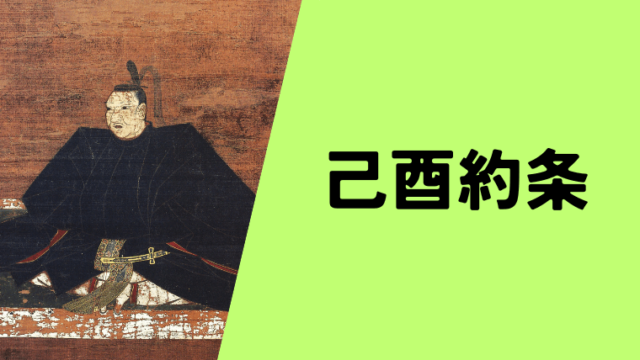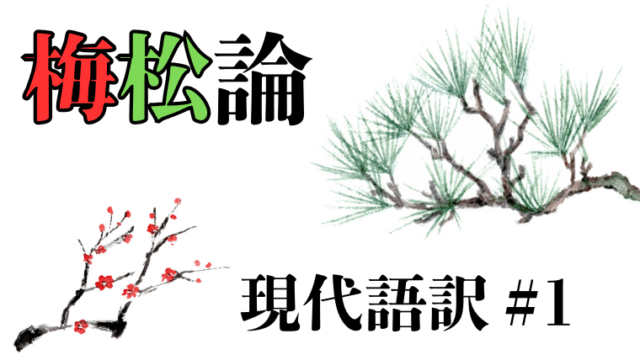プロフィール帳
その他条文の現代語訳一覧はこちらに掲載しています!
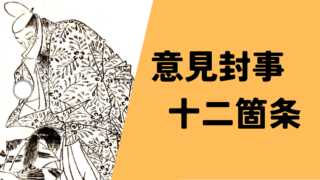
現代語訳
右臣伏見。山陽西海南海三道。舟船海行之程。自檉生泊至韓泊一日行。自韓泊至魚住泊一日行。自魚住泊至大輪田泊一日行。自大輪田泊至河尻一日行。此皆行基菩薩計程建置也。而今公家唯修造輪田泊。長廃魚住泊。由是公私舟船一日一夜之内兼行。自韓泊指輪田泊。至于冬月風急暗夜星稀。不知舳艫之前後。無弁浜岸之遠近。落帆棄檝。居愁漂没。由是毎年舟之蕩覆者。漸過百艘。人之没死者。非唯千人。昔者夏禹之仁。罪人猶泣。況此等百姓。皆赴王役乎。伏惟。聖念必応降哀矜者也。臣伏勘旧議。此泊天平年中所建立也。其後至于延暦之末。五十余年。人得其便。弘仁之代。風浪侵齧。石頽沙漂。天長年中。右大臣清原真人。奏議起請。遂以修復。承和之末。復已毀壊。至于貞観初。東大寺僧賢和。修菩薩行。起利他心。負石荷鍤尽力底功。単独之誠雖未畢其業。年紀之間。莫不蒙其利。賢和入滅稍及三十年。人民漂没不可勝計。官物損失亦累巨万。伏望。差諸司判官幹了有巧思者。令修造件泊。其料物充給播磨備前両国正税。冀也早降聖朝援手之仁。令脱天民為魚之歎。凡厥便宜具載去延喜元年所献意見之中。不更重陳。
播磨国の魚住泊の修復を重く要請します
瀬戸内海航海の現状
私が見た限り、山陽道、西海道、南海道の三道において船による移動は檉生(むろう)泊から韓(から)泊まで一日、韓泊から魚住泊まで一日、魚住泊から大輪田泊まで一日、大輪田泊から河尻泊まで一日の五日となっております。これはみな行基菩薩が建設したものであります。
しかし今、公家は大輪田泊のみを修造しており、魚住泊は長い期間廃れています。この理由は、現在、公私の船は韓泊から大輪田泊まで一日一夜のうちに航海可能となったためです。両泊の間に設置された魚住泊が利用されません。
冬の季節は風が強く、夜は星が稀であるため、舵取りの前後が分からず、沿岸部の遠近を調節ができません。その結果、帆は落ち、櫂は失い、哀愁の中船は沈み、死にゆくのです。このことによって毎年多くの船が水没し、その死者は1000人どころではありません。
昔、中国において夏を建国した禹は仁徳を備えており、罪人は仁徳の深さを感じ泣くほどでした。言うまでもなく夏国の百姓らは皆王の下す労働に従いました。思うに、聖王は哀憐の心を持って天より参られたのでしょう。
魚住泊の歴史
私は恐れ多いながら古い記録を見ました。魚住泊は天平年中(729-749)に造られたものだと分かりました。
行基は749年没とされているため、港の整備が晩年であったことが分かります。
その後延暦年中(782-806)の末期に至るまでの約50年間、人々は魚住泊を活発に利用していました。弘仁年中(810-824)になり、風や波が魚住泊を侵食し、石は崩れ、砂は水に飲まれました。次の天長年中(824-834)、右大臣であった清原夏野はこの現状を議題に上げ、遂に魚住泊は修復されました。
さらに次の承和年間(834-848)末期、再び魚住泊は荒廃しました。10年飛んで貞観年中(859-877)の初期、東大寺の僧賢和は菩薩行を修め、利他心により石を背負い、鋤を担ぎ、その力を尽くして人民に貢献しました。魚住泊の修造を行ったのです。賢和一人の誠実な行動でございます。港の整備はまだ完了していませんが、数年の間、その恩恵を受けていない人はいませんでした。
しかし現在、僧賢和が亡くなって約30年が経過しました。現状はすでに述べた通りで、人民は水死しており、枚挙にいとまがありません。官物の損失は非常に大きいです。
意見申し上げる
恐れながら希求します。多くの役人、判官、身体が強く賢い者、巧みな考えを持つ者に魚住泊を修造させるのです。その給料は播磨国、備前国の正税で賄います。願います。早急に天皇の御身に仁徳が降り、その仁徳が天皇の民らが魚となる悲しみから救うことを。
意見を列記するに良い機会となりました。過ぎ去りし延喜元年より献上したく考えていた意見を記載いたしました。重ねて述べることはありません。
(意見封事十二箇条 終)
摂津五泊
律令期の海路は、難波津を始点として、九州の大宰府はもとより、唐や新羅といった大陸国への海路が展開されていました。
その中でも特に、播磨までには5日かかるとされており、
(西)檉生(むろう)ー韓(から)ー魚住ー大輪田ー河尻ー難波津(東)
の順で、これを『摂津五泊(ごとまり)』といいます。
本文で、
現在、公私の船は韓泊から大輪田泊まで一日一夜のうちに航海可能となったためです。両泊の間に設置された魚住泊が利用されません。
とありました。
航海技術の発達か、別に航路を見つけたか、色を付けた間が半分の時間に短縮されたわけですね。
単語帳
| 舳艫 (じくろ) | 船頭と船尾 |
|---|---|
| 哀矜 (あいきょう) | 悲しみ哀れむこと |
| 菩薩行 | 施しを行う修行 |
| 鍤 (すき) | 鋤 |
| 不可勝計 | 枚挙にいとまがない |
| 判官 (はんがん) | 掾にあたる位。 |
| 幹了 | 身体が強く賢い者 |
| 巧思 (こうし) | 巧みな考えをすること |
| 第11条へ << | 一覧へ戻る >> |