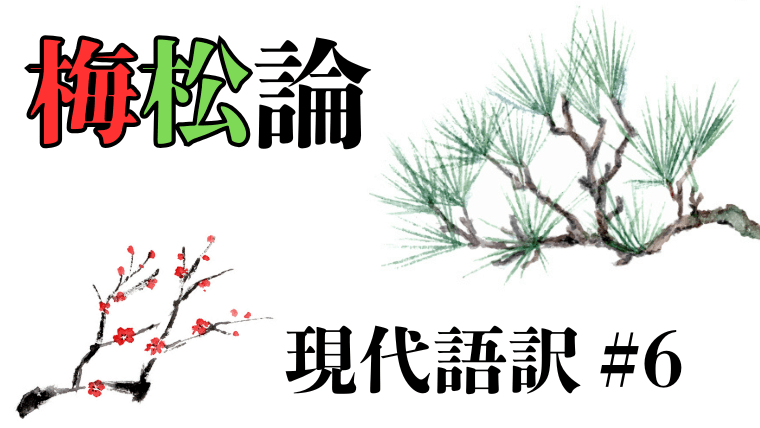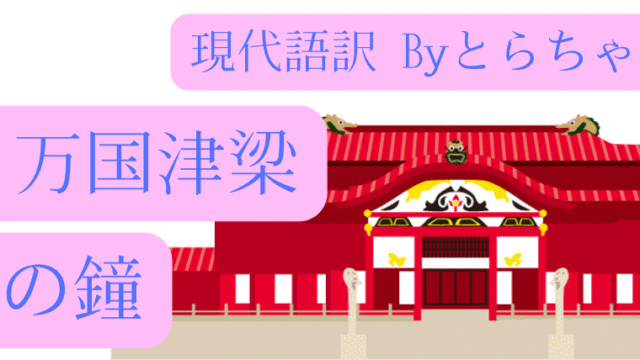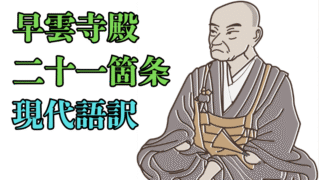23:手越河原の戦い
そこで尊氏はまず、上杉武庫禅門こと上杉憲房を新田義貞所領上野国の守護職に就け、新田義貞を牽制するようにした。上杉憲房はこれを承り、準備のために上野国に向かった。その間に京都から供奉した親類や代官の者共は急ぎ京都へ帰洛、逆に、足利に忠節を致そうとする者は京都から鎌倉へ下ってきた。東海道を上る者下る者、何となく美しい織物のようであった。
建武2年(1334)の秋と冬はもちろん穏やかではなかった。数万の官軍が関東に進軍していることを聞いた足利軍は足利直義は、高師直を大将として大軍を率いて東海道を発向させた。直義が師直の兄、高師泰に言う。
「まず三河国へ下り、矢作川を前線とせよ。承久の乱以降、我ら足利家の分国となっている。三河の軍勢をかき集め、新田軍に備えよ。決して渡河してはならんぞ。」
命令通り、高師泰は矢作川を前面として陣を敷いた。激突して3日が経過しても、決着はつかなかった。そこで高師泰は軍を3手に分けて上下の手を渡河させ、西の河岸で火花を散らした。中の手はまだ動かない。その時新田義貞の陣より長く義貞に仕えている堀口大炊介こと堀口貞満が馳せ参じ、武略を尽くして四方八方で暴れては高軍を討ち取っていった。新田軍の展開する西の陣へ渡河して合戦するのも難しい状況となり、不利となった高師直は徐々に後進した。遠江国の鷺坂、駿河国の今見村で戦線を維持するも新田軍を防ぎきれない状況であった。
建武2年(1334)12月2日、直義が20万の軍を率いて師泰と合流、12月5日、手越河原にて新田軍と激突した。『手越河原の戦い』である。人馬の足音は百や千の落雷のように、剣戟の音は電(いなびかり)のようであった。恐ろしいこと言うまでもない。正午に激突して数時間、討死した者、負傷した者は数知らず。そして20時頃、17回目の交戦において新田軍が夜襲に成功、直義軍は劣勢に立たされた。武家の多くはこの戦況を見て降参、新田軍に属してしまった。
降伏、謀反という決断をした武家を尊重する。決して裏切りでは無いのだ。名字を明かすのははばかれるため、ここでは記さない。
24:箱根・竹ノ下の戦い
敗北を喫した直義は箱根水呑峠に留まった。仁木頼章、細川顕氏、高師直、高師泰以下一騎当千の輩は1人残らず陣を敷いた。
所は変わって鎌倉。足利尊氏は先日の中院具光下向の際に帰洛する旨を伝えていたが、結果尊氏は京へ参上しなかった。尊氏にとっては本意で無かったため、このことを深く嘆いた。
天皇に親しく近くお仕えして勅命を受けては、「ありがたきお言葉」と言い、または「叡慮」と言い、どのような状況であっても天皇のお志を忘れずお仕えしていた。後醍醐天皇はこの私の思いなど知るまい、と尊氏は思ったのだった。
ひどく心を痛めた尊氏は政務を直義に任せ、細川頼春をはじめとする家臣3人を連れて密かに鎌倉の浄光明寺に蟄居した。その頃、直義が東海道での合戦に苦戦し、箱根山で窮地に立たされていることを尊氏は聞いたのである。そして尊氏は決断した。
「直義が死ねば私は生きていても仕方ない。助けたいが、これは勅命に反する行動である。このような所に籠っていてはますます我が心中は後醍醐天皇に伝わるまい。伝わるのは蟄居しているという事実だけだ。勝負運の神徳、八幡大菩薩の加護も受けられよう。既に後醍醐天皇は先鋒をこちらに向けられた。遠慮は要らぬ。」
名字が異なる3兄弟、小山朝政、結城朝光、長沼宗政の小山一族が惜しまれる。この3人は源頼朝が挙兵した治承の乱(1180)の際、前線に馳せ参じて頼朝に貢献した人物である。藤原秀郷の子孫、藤原政光が下野国小山に移った際に小山姓を名乗り始めた。3人はこの子孫である。小山氏の祖、藤原秀郷は平将門の乱こと天慶の乱(939)に乱の平定に貢献した人物で、これを機に鎮守府将軍の官職を得ている。その後子々孫々鎮守府将軍の地位を継承した。子孫には先に述べた小山一族や、鎌倉五代将軍藤原頼嗣がいる(根拠不明)。秀郷の武功を代々語り継がれるとは武家の誉れであろう。弓馬の道に精通した家であった。
これらの子孫が尊氏将軍から2000の兵を授かり、先鋒として建武2年12月8日、鎌倉を出立した。箱根水呑峠。人々が箱根に援軍を出すべきだと思っていたところに尊氏将軍が到着した。
「我々は水呑峠に向かう。敵は戦線を維持しており、優勢になることは無いだろう。」
そういうわけで尊氏軍は軍を発し、箱根山を越えて合戦することとした。敵が驚いているところを急襲する算段である。12月10日夜、竹ノ下。夜が開けるのを待ち、午前7時半頃、官軍の大将、新田義貞は箱根へ、一宮こと尊良親王、脇屋義助は「恋せば痩せぬべし。恋せずもありけり。」と詠み、竹の下へ向かうべく足柄平野南方の野に陣を敷いた。この歌は、足柄平野域で祀られている足柄明神が詠んだ歌である。
尊氏軍の先鋒は山を下りて野山に進軍し、坂本にて激突、尊氏軍が勝利した。その勢いで約30里押し込み、藍沢原を極限として尊良親王と脇屋義助は奮闘した。官軍側は数百人を討ち取られ、劣勢を強いられていたが、後醍醐天皇は長い功労のある小山自の幼い嫡男、常犬丸こと小山朝郷に武蔵国の太田庄を与えた。ここは由緒ある地だという。また、常陸国の関の郡を結城宗広に与えた。此度の合戦の下文は初めてである。これを見た輩共に、命を忘れて勇敢に戦おうと思わない者はいなかった。
「香餌の下必ず死魚有り」「重賞の處には勇士あり」という。前者は『三略』から生まれた故事、後者は1019年刀伊入寇の論功行賞において『小右記』を記した藤原実資の発言である。大きな報酬を前にすると、人々は命を懸けてでもそれを得ようとするのだ。
25:新田義貞の富士川渡河
さて、翌日12日、後退した官軍は駿河国佐野山に陣を敷いた。しかし、援軍として京から派遣された大友左近将監こと大友貞載の約300騎が官軍に加勢しないとの報せが入った。子細は分からないが尊氏軍に寝返ったことを意味する。矢合の最中に尊氏軍に加勢されたため、官軍はあっさり敗れて中将の二条為冬を初めとする大勢が討ち取られたのだった。こうして、箱根・竹ノ下の戦いは幕を閉じた。この二条為冬は足利尊氏の友人であった。その首をご覧になった尊氏将軍、愁傷の念が非常に深いものであったと伺える。
その日の夜は雨であった。尊氏軍は伊豆国府を見下ろせる山野に陣を敷いた。箱根に向かった新田義貞と接触した直義軍が見事勝利を収めたとの知らせが入り、敗走する新田軍と戦う算段である。尊氏軍の勢力は雲霞のごとく膨れ上がっていた。夜通し雨が降り続け、翌日13日も晴れる様子が無かったため、晴れを待たずに尊氏軍は伊豆国府に攻め入った。新田義貞の軍勢が箱根山水呑峠から陣を引いて夜通し落ち逃げ、三嶋神社を過ぎて東海道に出たところで激突、午前8時〜10時の2時間合戦した。鬨の声、矢叫び、えい声。仏教では大地が六通りに揺れるという。それに異ならなかった。この戦で畠山安房入道(詳細不明)が討死、新田義貞は残りわずかの軍勢を率いて富士川を渡河しようとしていた。
尊氏、直義軍は竹の下、佐野山、伊豆国府と三日の合戦に全勝し、府中、車返、浮島原、に陣取った。様々な家々が幕を張り、各々家紋の入った旗を立ち並べている。風に靡くその数幾千万であった。翌日14日。逗留の際に議論があった。これより尊氏、直義両大将は鎌倉に帰り関東を治めるか。はたまた、「関東の治国も大事だが、東海道におけるこの戦も重要である。むしろこの戦で挙兵するべきだ。」このような意見もでた。
そして翌日15日、東海道を攻め続けることを決め、浮島原を出た。時は12月の半ば。富士の麓にまで深雪が積もり、天山としての風格があった。いつの年の雪だろう。数日前の12月5日の手越河原の戦いにおいて官軍に属していた輩は、ここ富士川にて降参した。
昔で言えば、平東国の武士が西へ向かったのは三度あった。家追討宣旨による寿永3年(1184)の源範頼、源義経。承久三年(1221)承久の乱の北条泰時、北条時房。今年、建武元年(1334)の尊氏、直義。である。「上洛に何の疑いがあろうか」いずれの上洛も、自信の色が見られた。
さて、新田義貞。東海道であれば、山河の間にある足場の悪い難所で決戦するべきだ。そう考えて進軍していたところ、天龍川の橋を渡守が警護していた。この川は流れが早く深いため、橋がないと渡河は困難である。
「由々しき事態だ。誰か橋の警護を追い払っていただきたい。」渡守にそう言うと、渡守はこう語った。
「この乱によって我々は山林に逃げ隠れました。船は所々に置いております。そこに敗走してきた新田殿が到着しました。『河には浅いところは無い。敗軍とはいえ大軍。馬では渡河できない。とはいえ船を用意していると渡河が遅れる。味方は一人たりとも失う訳にはいかない。よし、急ぎ浮橋を作れ。渋ればお前たちを誅罰する。御成敗だ。』そして3日のうちに橋を作りました。新田殿は5日の夜に兵を渡らせて、皆渡ったと見たところ、最後にご自身が渡りました。『橋をすぐに切り落とせ。』そう兵共が下知しようとした時、新田殿は橋の中辺りで立腹されました。そして我々渡守を近くに召してこう仰せになりました。『せめて敗軍の我々だけでも渡る橋。いかにも切り落としたかろう。だがしかし、勝ちの勢いに乗っている東国の輩共は橋を再び掛けるのに時間を多く費やさない。船を焼き橋を切り落とすのは、敵が大勢で我々が小勢の戦で橋を背にして戦うことになった時である。これこそ手練のやる武略よ。敵がすぐに架けることのできる橋をわざわざ私が切り落とし、急に恐れをなして慌てふためいたのだ。と末代まで言われることが恥だと思うのも理由である。しっかり橋を警護せよ。』と言って、静かに橋を渡りました。そのため、足利軍を待っていたのです。橋はこの通り守り通しました。」
これを聞いた人は皆涙を流した。武家に生まれた者であれば誰もがそうあるべきなのだ。新田義貞は紛うことなき名将である、と思わない者はいなかったのである。
26:京都合戦
こうして東国八カ国(相模・武蔵・上総・下総・安房・常陸・上野・下野)、そして東海道各国の輩が足利将軍側についたのであった。美濃、近江に至る頃には、山野、村里に兵が充満し、それはそれは人や馬の立つ場所もないほどであった。その進軍を阻止せんと新田軍に従軍していた山法師、道場坊祐覚率いる延暦寺僧兵千人以上は近江伊岐代官の森に城を築き立て籠った。
「我々が戦線を支え、関東勢を近江に留める。敵の後詰を京都ではなくこちらに向けさせるのだ。」
足利軍はすぐに高師直を大将として大軍を寄越し、建武2年(1335)12月30日、僅か一夜でこの城を攻め落としたのだった。ここは東海道野路宿の西で琵琶湖の端である。そのため死を免れた者は皆船に乗って落ち延びたとか。攻め落として後、足利軍は軍を複数に分けた。
陣立ては、瀬田方面は総大将直義将軍、副将軍高師泰。淀方面は畠山高国、芋洗方面は吉見頼隆、宇治方面は尊氏将軍、である。
対する官軍。瀬田方面は千種忠顕、結城親光、名和長年が迎え撃った。
瀬田戦線は1月3日より合戦が始まったと聞いている。尊氏将軍は日原路を経て宇治へ。かつて元弘3年(1331)に起きた元弘の乱。北畠亜相禅門こと北畠顕家は後の後村上天皇である義良親王に仕え、出羽国、陸奥国の国守に務め、管領の地位にいた。その北畠顕家と義良親王が後醍醐天皇の要請を受けて出羽国、陸奥国の54郡の軍勢を率いて後詰として不破関を越えたとの報せが入ったのだ。官軍は宇治方面に大将として新田義貞を派遣、尊氏と激突した。宇治橋の合戦である。義貞は橋の中で二間(約4m)の距離を隔て櫓掻楯を構えて戦線を維持した。1月8日の夕、櫓下において結城氏の家臣、野木与一とその従者2人が一騎当千の武略を示し足利軍と戦った。新田義貞は感激のあまり腰に提げていた物を直に下賜するということをした。永遠に語り継がれる武功であった。戦線が膠着している間、宇治川を隔てて毎夜矢合いが行われていた。
その頃、細川定禅を大将として、赤松円心ら四国地方、中国地方の軍勢が足利軍として摂津国、河内国に馳せ参じた。尊氏の御教書を受け取った者は計り知れない。1月9日18時頃尊氏の陣へ報せが入った。
『我々中四国の軍勢は明日10日午前中に山崎の官軍を打ち破り狼煙を上げる。同時に京都へ攻めていただきたい。』と。
世が明けるのを待ち、細川定禅、赤松円心、中四国の国人らが山崎を、尊氏が宇治の城戸口を攻めた。予定通り中四国の軍勢は10日午後に山崎の官軍を打ち破って久我鳥羽に攻め入り、火を放った。官軍の皆が逃げ回った。その夜、後醍醐天皇は比叡山に逃れることとなり、内裏は焼亡したのであった。内裏焼亡は閑院焼亡の正元1年(1259)以来である。「これは一体」と驚き、そして悲しまない者はいなかった。同時に大臣や殿上人、以下結城親光、楠木正成、名和長年の屋敷も灰燼と化した。
なんと嘆かわしいことか。伝え聞いた話によると、中国の秦は滅亡の際、咸陽宮、阿房宮を焼き払われたという。他国のこととはいえ、この京の有様を見ると思い図られるものがある。寿永3年(1184)の平家都落ちもこのような感じだったのだろう。そう考えるとしみじみとした心持ちになる。
(梅松論上 終)
| 前に戻る << | 最初に戻る >> |