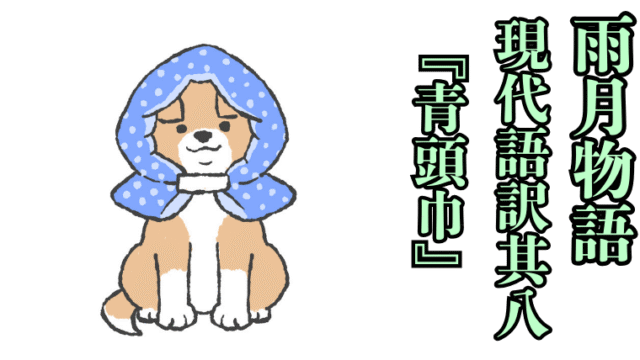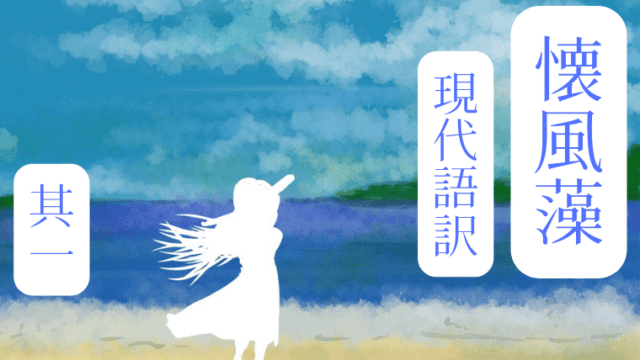一覧は下記サイトをご確認ください。

⑧帝の求婚
さて、かぐや姫の容姿が世にもたいそう優れていることを帝が耳にして、内侍、中臣房子に仰った。
「多くの人の身を滅ぼしてまで結婚しないというかぐや姫は、どのような女か。」
「その足で行って見て参れ。」
と。房子は承って、宮中を出た。家にやってきた房子を翁はかしこまって招き入れ、面会した。房子が嫗に言う。
「帝が『かぐや姫の容姿が優れていらっしゃると聞いた、よく見て参れ。』という旨の仰せ言を私に命じましたので、参りました。」
嫗は
「そうであれば、そのように申してきましょう。」
と言ってかぐや姫の部屋に入っていった。
「早く、あの御使いと対面なさいませ。」
「美しい容姿ではありません。どうしてお会いできましょうか。」
「そう酷くおっしゃいますな。帝の御使いをどうして粗略に扱えましょうか。」
「帝はご自身ではなく、その者をお召しになったのですから、畏れ多いとも思いません。」
かぐや姫は決して会いそうにない。嫗としては、かぐや姫は自分が産んだ子のようであるから親に従ってくれないかと強く言いたい気持ちであったが、かぐや姫が本当に気後れした様子で言うので、思うように責めることもできないでいた。嫗は内侍のもとへ戻って来て、
「残念ですが、この子は幼稚で頑固ですので、対面しないつもりです。」
と房子に申し上げると
「『必ず拝見してから参内せよ。』との仰せ言がありましたのに、拝見しないでどうして帰ることができましょう。この世に住む人で、国王の仰せ言を承らない人などいましょうか。道理の通らないことをおっしゃいますな。」
と臆した様子で言った。これを聞いて、なおさらかぐや姫が聞き入れるはずもない。かぐや姫は
「国王の仰せ言に背いたと仰るのなら、はやく私を殺してください。」
と言う。さて房子は宮中に帰参して、ことの経緯を奏上した。帝は
「多くの人を殺してきた者の心をお持ちなのだな。」
と仰って、かぐや姫に迫るのをお止めになったが、やはりかぐや姫のことを思い続けていたようで、
『この女の謀には負けぬぞ。』
とお思いになった。翁を呼び出して仰る。
「お主のところにいるかぐや姫を参内させよ。容姿が美しいと聞いたので使者を遣わしたが、甲斐なく会うことは叶わなかった。あんなに自分勝手な性格にしつけても良いものか?」
と。翁は畏まって御返事申し上げた。
「この娘は絶対に宮仕えしそうにない感じですから、もて余しております。とはいえ、屋敷に帰って仰せ言を伝えましょう。」
と奏上する。これをお聞きになった帝は仰った。
「お主が大切に育て上げたのであろう。どうして親の思う通りにならないのだ。もしこの女を宮仕えさせることができたのならば、お主に冠(五位以上の位)などを下賜しようではないか。」
翁は喜んで屋敷に帰り、かぐや姫に語った。
「このように帝が仰っているのだ。それでも仕え奉らないおつもりか。」
かぐや姫が答えて言う。
「そのような宮仕えはする気は全くありません。無理やり仕えさせようというのでしたら、消え失せましょう。御官位をいただけるように少しだけ宮仕えして、あとは死ぬだけです。」
と。
「してはなりません。得た官位も、我が子に見せないで何の意味がありましょう。それにしても、どうして頑なに宮仕えをなさらないのですか。死を選ぶほどの理由があるのですか。」
「それとも、あえて宮仕して、『やはりかぐや姫の言う、宮仕えすると人が死ぬという話は、嘘だったか。』という結末になるかどうかご覧になりますか。私は数多くの人の、いいかげんでない気持ちを無駄にしてきたのです。彼らは2年や3年もの間私に志を示しました。それなのに、昨日や今日志をお見せになった帝のお言葉に従うようでは、人に聞かれて恥ずかしいです。」
「天下のことはどうであれ、姫のお命に危険が及ぶことこそ、世にとって大きな問題なのです。やはり宮仕えするつもりは無いことを、申し上げて参ります。」
翁はそう言って、参上して申し上げた。
「仰せ言の畏れ多さにより、あの娘を宮仕えささようと説得を働きかけましたが、『宮仕えに出せば、その後死ぬつもりです。』と姫は申しております。そもそも、かぐや姫は造麻呂の手で産ませた子ではございません。昔、山で見つけた娘なのです。そのため、人となりが、世の人と似ないのでございます。」
と。帝は仰せになる。
「造麻呂の家は、山の麓に近い。狩りの行幸をして、その次いでに見よう。」
それに造麻呂(翁)が
「たいへん良いことです。かぐや姫が油断しております時に、不意に行幸してご覧下さい。」
と奏上すると、帝は急に日程を決めた。当日、帝は御狩にお出かけになり、かぐや姫の屋敷にお入りになった。部屋をご覧になると、光に満ちて清らかな様子で座っている人がいる。
『かぐや姫とはこの者だ。』
とお思いになった帝は、逃げて奥へ入ろうとするかぐや姫の袖を捕まえた。かぐや姫は顔をふさいでいたが、帝は部屋に入った最初によくご覧になっていたので、
『右に並ぶ者はいないほど美しい。』
とお思いになって、
「この手は緩めませんよ。」
と言って引き寄せようとした。かぐや姫は
「私がこの国で生まれていれば召し抱えても良かったでしょう。ですがそうでは無いのです。連れて行くのは非常に難しいと申し上げます。」
と奏上した。
「どうしてそのようなことがあろうか。やはり貴方は連れておいでになります。」
帝はそう言ってかぐや姫のいる所まで御興をお寄せになると、かぐや姫は突然、影になってしまった。帝は
『なんと虚しいことか。残念だ。』
『確かに、普通の人間ではなかったのだな。』
とお思いになって、
「それでは、お供としては連れて行かないこととします。だから元のお姿に戻られよ。それを見るだけで帰りましょう。」
と仰せになると、かぐや姫は元の姿に戻った。帝はそう言ったもののやはりかぐや姫の容姿を素晴らしく思ってしまい、その感情を抑えるのに苦しんだ。それと同時にこの美しい姿を見せてくれた造麻呂を賞賛した。そうして翁は、朝廷に仕える多くの役人の方々を盛大にもてなした。帝は、かぐや姫を屋敷に残したまま帰ることに満足できず残念に思ったが、やはり帝、宮中に魂を残した気持ちがして帰ったのであった。御輿にお乗りになった後、かぐや姫に和歌を送った。
かへるさの みゆき物うく おもほえて
そむきてとまる かぐや姫ゆゑ
帰りの行幸が辛く思われたので、振り向いては立ち止まった。かぐや姫が屋敷に留まるというから。
かぐや姫の返歌。
葎はふ 下にもとしは 経ぬる身の
なにかはたまの うてなをもみむ
むぐら(蔓草)が生い茂る翁の屋敷で長年過ごしてきた私が、どうして玉のような御殿を見ましょうか。
これをご覧になった帝は、ますます帰りたいと思う気持ちが上の空になる感覚を覚えた。立ち去り帰ろうという気持ちは全く思わなかったが、そうといっても夜道で夜を明かすわけにいかないので、宮中へ帰ったのであった。屋敷で働く人が誰かしらいるのを見ると、かぐや姫の傍に寄ることさえできそうになかった。
『他の人よりも清らかで美しいお方だ。』
と思っていた人とかぐや姫を比べても、かぐや姫の方がなお美しい。ほんとうに普通の人とは思えなかった。帝の御心にはかぐや姫のことだけがかかって、ただただ一人で日々を過ごした。帝は、屋敷の方へ向かう理由もないので翁と嫗の所には通わず、かぐや姫とは文を書いてやりとりした。かぐや姫はさすがに蔑ろにしないふうに文を送り、対して帝は情緒を誘う木や草に文を付けて、和歌を詠んで送っていた。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |