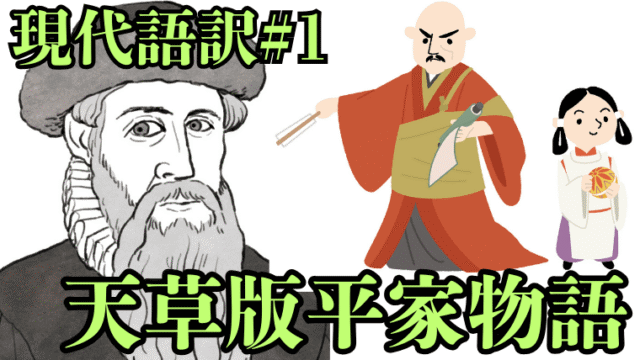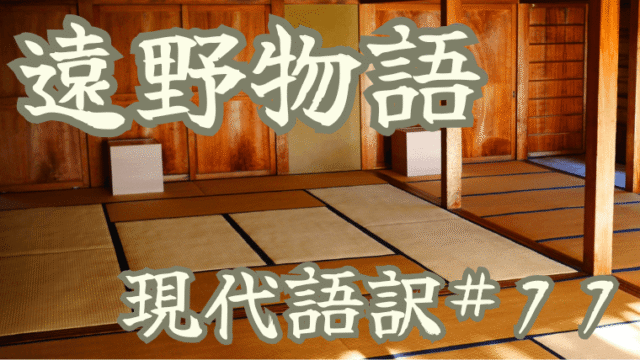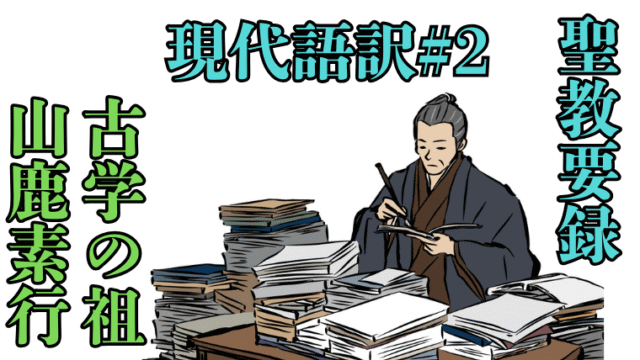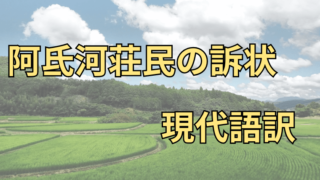庭訓往来について
『庭訓往来』の概要と現代語訳一覧は別にまとめていますので、こちらをご覧ください。

二月状現代語訳
(往信)弾正忠三善→大監物源
(返信)大監物源→弾正忠三善
03:二月二十三日状_往信
- 久しく会っていないことへの謝罪
- 歌会の誘い
- 歌や詩の名手も誘って欲しい
如山何日散意霧哉
併似隔胡越猶以千悔々々
抑醍醐雲林院花濃香芬々匂已盛也
嵯峨吉野山桜開落交条其梢繁難黙止者此節也
争徒然而送光陰哉
花下好士諸家狂仁如雲似霞
遠所之花者乗物僮僕難合期
先近隣之名花以歩行之儀思立事候
雖為左道之様以異躰之形
明後日御同心候者夲望也
連歌宗匠和謌達者一両輩可有御誘引
以其次詩連句之詠同所望候
破籠小竹筒等者自是可随身
硯懐紙等可被懐中欤如何
心底之趣難尽帋上併期参会之次
不具謹言
二月二十三日 弾正忠三善
謹上 大監物殿
最後にお会いしてから久しくなりまして、非常に残念であります。私はあなたと何日もお会いできず、気持ちが晴れません。古代中国、胡と越が遥か遠くに位置しているように、あなたとの距離が非常に遠く感じており、最後にお会いして以降一度もお会いしなかったことを非常に悔いています。
さて、醍醐寺や雲林院の花は濃香芬々として、既に見頃となっております。嵯峨や吉野山の桜は開花しているもの、散っているもの様々で、自然その梢は見頃に比べて葉が繁っている状況です。この機に及んで、何もしないでいるなどできません。どうして、徒に何もしないで月日を送る事ができましょうか、いや、できません。花を好む風流人や家柄による役職を忘れて風流に傾倒する狂人が集まる様は、霞が集まって雲になるのと同じです。
花を見に遠出する場合は、乗り物や従者などが必要ですが、なかなか皆の都合が合わず、予定を決めるのが難しいものとなっております。そこで私は、近隣の花の名所で、散策や詩歌の遊びをすることを思い立ちました。
本来あなたは乗り物に乗って移動するはずの身分であると心得ております。道に外れた行為ではあると存じておりますが、明日明後日、歩きでもよければ参加していただきたい。そうしていただければ本望です。
これに際して、連歌の師匠、和歌の達人、一人二人お誘い願いたい。それが決まった後、漢詩や聯句が詠める者を同じように一人二人お誘い願いたい。
破籠や小竹筒などは私が持参いたします。硯、懐紙などは、各々持参するべきでしょうか、どう思われますか。
私の思いは紙では書ききれません。不義かとお思いになるかもやしれませんが、ご参加、お待ちしております。不具謹言。
二月廿三日 弾正忠三善
謹上 大監物殿
04:二月二十三日状_返信
- 和歌以外の自信の無さを告白
- 参加は本望である
欲自是令申候之処遮而預恩問御同心之至多生之嘉会也
抑花底会事花鳥風月者好士之所学
詩哥管絃者嘉齢延年之方也
御勧進之躰相叶夲懐候者哉
後園庭前之花深山藂樹之桜
誠以開敷之㝡中也
若今明之際有暴風霖雨者無念事也
同者片時急度所令存也
和哥者雖仰人丸赤人之古風
未究長謌短歌旋頭混夲折句沓冠之風情
輪廻傍題打越落題之躰
詩連句者乍汲菅家江家之旧流
更忘序表賦題傍絶韻声質頗
如猿猴之似人同蛍火之猜灯
然而被召加人数一分者殆可招後日之恥辱
執筆発句賦物以下才覚未練
之間当座定可及赤面欤
聊可有用意由之事奉候
訖可致如形之稽古公私忩忙之間
不遑毛挙恐々謹言
二月二十三日 監物源
謹上 弾正忠殿 御返事
私から『花見に行きませんか。』とお誘いするところ、あなたの方からこの旨の手紙をいただきました。私の心はあなたのお心と同じです。
そもそも、花の下に集う会というのは色々と良い機会でもあるのです。花鳥風月は、風流を好む者にとって学ぶ機会でありますし、詩歌管弦は年が明け、歳を重ねたことを実感する良い機会であります。参加のお誘いは私の本来の願いに叶うものです。
近く、屋敷の庭先に咲いた花や、遠く、緑深く鬱蒼とした山に咲いた桜は誠に満開の時を迎えております。もし、近日暴風、長雨の天気となれば、この会は無念のこととなります。ですので、一時も早く開催したいものです。
和歌の道では、柿本人麻呂や山部赤人を仰ぐこととなっており、その手法を学びましたが、長歌や短歌、旋頭歌、混本歌、折句、沓冠といった道には、和歌では禁忌とされている輪廻、傍題、打越、落題といった手法があります。私はこれらをまだ習得しきれていません。
また、私は漢詩や聯句は野見宿禰を祖とする菅家、大江音人を祖とする江家が確立させた古い流派に倣いながらも、序、表、賦、題、傍絶、韻聲といった漢詩や聯句決まりを忘れています。
猿は人に似ていますが、人ではありません。蛍の光は本物の火ではありません。私は文芸の道に詳しくありませんので、参加した際には、風流人の真似事のような振る舞いをしてしまうでしょう。ですので、人数を一人加えられれば加えられるだけ、私は後日、恥を受けることとなってしまいます。
執筆、発句、賦物を書く生まれつきの才能もなく、無いなら無いで練習を積まなかった未熟者でございますので、参加すれば、赤面すること間違いありません。
とはいえ、あなたから『会の用意をしていただきたい。』との旨を承りましたので、仰せの通りにいたしましょう。もともと、会の参加は私の本望であります。
和歌や漢詩は、型に倣って稽古しておきます。公私ともに忙しいため、詳しく文を書く暇がありませんので、この辺で筆を擱きます。恐々謹言。
二月廿三日 監物源
謹上 弾正忠殿 御返事
| 正月状へ << | 三月状へ >> |