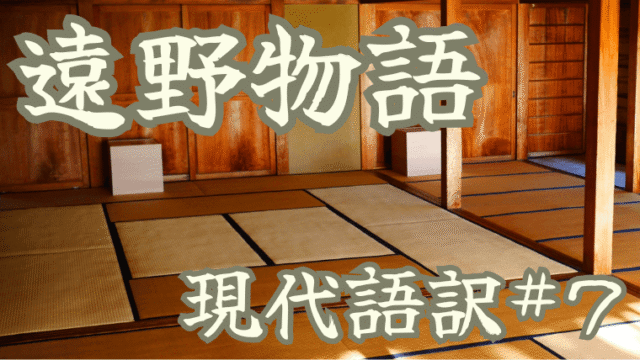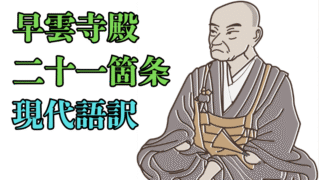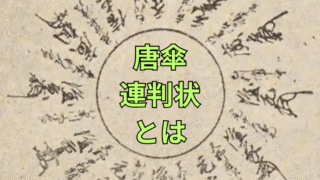菊池寛の経歴
作者の菊池寛はどのような経歴の人物なのでしょうか。文学界に名を馳せ、将棋にも通じ、人の上に立つリーダーシップ性を持つ、そんな天才でした。
- 生誕香川県高松市天神前に生まれる。江戸時代までは代々藩の儒学者の家系として位置付けられていた士族であったが、士族とは思えないほど貧しかったという。
- 大学時代(20代)大学は明治大学や京都大学などを転々とし、京都大学在籍中の28歳の時、芥川龍之介らと『新思潮』を刊行。同年の卒業後は『時事新報』の新聞記者として勤務した。
- 卒業後(30歳頃)『父帰る』は翌年の29歳の時に発表した作品で、31歳に発表した『忠直卿行状記』『無名作家の日記』が高い評価を受け、文壇的地位を確立した。この翌年に『恩讐の彼方に』を発表しており、若くして文才を発揮した天才児であったことが窺える。
- 政治参加(40歳頃)40歳時には社会民衆党の議員として立候補した経歴もある。
- 50代将棋にも長けており、57歳の時には五段を有していた。様々な協会、会社の長を勤めた経歴も数多く持つ。
その多才は多くの分野から認められていたことが窺えますね。
作品情報
登場人物
登場人物は全部で5人です。
| 父(宗太郎) | 年齢不詳。息子らが小さいときに行方をくらます |
|---|---|
| 母(おたか) | 51歳 |
| 長男(賢一郎) | 28歳 |
| 次男(新次郎) | 23歳 |
| 長女(おたね) | 20歳 |
舞台
明治40年ごろ(1907年ごろ)
現在の名古屋市熱田区
要約
南海道の海岸にある小都会。10月の初めごろ、六畳一間での話である。
仕事から帰ってきてくつろいでいる長男の賢一郎はおたねのことで母と会話していた。嫁入りが近いおたねの相手は金持ちなのだが、母は
「お金があっても人がろくでなしでは意味が無い」
と言い、あまり乗り気ではなかった。あったお金を道楽に浪費した、父宗太郎の振る舞い方が原因である。とはいえ、めでたい話であるから賢一郎は、お金は無くとも嫁入りくらいは出資してやりたかったのだが、母はそんな大金をはたく必要はないと言い、意見が割れるのであった。
重い空気を感じた賢一郎はまだ仕事から帰らない次男に話題を転じたが、それでも母は結婚話を続け、今度は賢一郎の相手探しのことを案じた。例にもれず父がいなくなった時の話付きで。そんな時、小学校勤務の次男新二郎が帰ってき、卓について奇妙な話を持ち出した。勤め先の校長がいなくなった父を見たというのだ。その校長は父と幼な友達であるため、
「見間違うことはない、話しかけることは叶わなかったが、間違いなく宗太郎であった。」
と話していたという。父がいなくなってからもう20年にもなっていたため、故郷に帰ってきたとしても、家に入るまでは敷居が高かろうと賢一郎は感じていた。夕飯の支度を母に促した賢一郎はやや真面目に校長が父に会ったことのことを新二郎に詳しく聞くと、逆に新二郎からかつての父の印象を聞かれた。新二郎は当時の記憶がほぼないのである。当時8歳であったとはいえ賢一郎はなにも覚えていなかった。
「お父さんはええ男やったと校長がよく話をしてました。」
「そう。昔女中から恋歌をそえた箸箱をもらった話とか。」
新二郎と母は父の話題で盛り上がり、楽しそうだった。
食事が始まり、新二郎は英語の検定の勉強を始めることを告白していた。お金のいらない宣教師のもとで学ぶらしい。
「父親の力を借りんでも一人前になれると証明せにゃな。俺は中学を出とらんから、無理な話だ。」
そう賢一郎が言うと、玄関からおたねが帰ってきた音がした。部屋に入って来るやいなや
「外で年寄りがこちらを見とる。」
と伝えてきた。この後、事件は起こる。
「御免!」と言ってその年寄りが入ってきたのだ。なんと父宗太郎だったのである。母は涙ぐみ、新二郎とおたねが順に挨拶した。そう、賢一郎を除いて。とはいえ警戒心は解かれたわけではなく、釣られ笑いも起きなかった。父はここ数年の活動報告をし、酒を要求したが、賢一郎は断った。
「俺の知ってる父親はとっくに死んだ。そのせいで幼いことから一家苦しんだのだ。父親は敵だ。」
賢一郎はそう言って、今日までの苦しかった日々を思い出しては吐き出した。そんな長男を見て新二郎は冷静に仲を取り合おうとするも、兄の怒りは治まらない。
「生みの親であっても、父としての権利を放棄したあなたには世話になっていない!」
この言葉で父はそれ以上言い返すこともなく、突然の来訪を詫びて元気なく家を出ようとした。そんな父の後ろ姿を見て、なお新二郎は父をうちに引き留めようと、兄との間に妥協案を見出そうとした。なにも賢一郎の言い分を否定しているわけではない。お前たちの父親は俺だという賢一郎の主張は、幼いころから一家の経済を支えてきた姿を見てきたから理解できるのだ。新二郎はどうすることもできず沈黙した。
「自分で養っていく才覚はある。」
そう言って宗太郎は家を出ようとし、最後に本心であろう、
「ただ家が恋しくなった・・・」
と、弱弱しい物言いで、ついに家を去ったのであった。
長い緊張が続いた。
「新!お父さんを呼び返してこい。」
「南の道はいない、兄さんも手伝ってください!」
「そんなことがあるか!」
二人は狂気の如く家を飛び出たのであった。
感想
明治・大正期の文学は新旧社会体制の対比として描かれている作品が多く存在します。全く異なるテーマの作品であってもシーンの一つとして「時代が変わった」と思わせるような描写があるのがこの時期の文学の特徴です。
戯曲『父帰る』では、一般に身近な「家庭」をテーマとしているため人気を博したのも一因と思われますが、この作品が評価されているのは社会の変化を絶妙に捉えているためではないかと私は感じました。
以下考察です。
考察
『父帰る』が評価されているのは2つの要因があるのではないかと考えました。
- 新旧社会体制の相違を捉えている点
- 「家庭」という身近なテーマを取り上げた点
新旧社会体制の相違を捉えている点
長男という立場の変化
長男というと、封建社会では家を継ぐ者として英才教育をはじめとし、次男三男よりも特別な扱いを受けることが普通でした。残された下の兄弟たちは家を離れて職を求めたり、他家に嫁いだりしていました。
『父帰る』の場合、長男の賢一郎は中学を出ていないことから高等文官の受験資格を失っています。対して弟は非常に優秀です。
賢一郎をみると長男という社会的上位者の立場がまるっきり変わっていることが分かります。幼少期は父が家を出た事が原因で非常に貧しい生活を送っており、賢一郎が父に代わって一家を支えていました。
分かりやすくすると、下のような構図になると考えます。
長男であっても、経済的に立場が弱い者は社会的身分も低い
↑↓
長男でなくとも、収入を得ることが出来る者が家庭の代表者的立場ととなる
現在は、弟のほうが稼ぎがあるので、弟が最も立場が上だということになりますが、幼少期から兄が一家を支えてきたことを考えると、兄が一家の代表者でしょう。また、そのような兄に対して恩を仇で返すようなことは弟はしません。
つまり、社会の変化、それに基づくバックグラウンドが、登場人物たち(特に父と長男)の感情の相違を、葛藤を生んでいると思います。
母と長男
常にお金に苦しまされた長男賢一郎。そんな彼と母とでも「妹の結婚相手」の話から価値観の違いがみられます。
妹の結婚相手はお金持ちであることが分かっており、このことから人に大事なものは何か意見を言い合う場面があります。
| 母 | 父の道楽趣味でお金に懲りた →人間性を重視 |
|---|---|
| 賢一郎 | 父の道楽趣味のせいで苦労した →経済力を重視 |
賢一郎は妹も苦労したから嫁入りの時でも無理してお金を積んであげたいと願いますが、母は少しで十分と言います。お金がなくて一家が苦労したことを賢一郎は悪かったと思っているのです。
この根本的な原因は父なので、自然父への憎しみにつながっています。
父と子
父が帰ってきてから、賢一郎はその道楽趣味のせいで一家が苦労したと激昂します。生みの親である父親は、血のつながりがあるとはいえ、この家庭では父親としての立場は無いと言い張るのです。これは「収入がある者が一家を支え、一家の代表者的立場」に該当します。
父は家庭を放棄した以上、一家の代表者ですらありません。しかし、帰ってきた父は自分を敬うような振る舞いをしました。その理由は以下の2つが考えられます。
- 「父」という家庭内での地位は如何なる理由があれ不動のものだと思っていたか
- 去り際の様子から、家庭内での接し方が分からず大きな態度で出てしまったか
どらも考えられます。個人的には、②のために①のように振舞ったのではないかと考えます。つまり、家庭内での接し方が分からず、父らしい威厳を見せるようにふるまったと思うのです。
「旧体制の認識が依然父の認識の中にあった」ということを踏まえて読み取りました。
そのような旧社会的な父と、新社会に振り回された長男とでは非常に深い確執が生まれるのは無理の無い話です。
「父と長男」の対立の次は「長男と次男」で意見が割れます。
| 長男(賢一郎) | 一家を不幸に陥れた極悪人として |
|---|---|
| 次男(新二郎) | あくまでも父として |
賢一郎は、帰る地を求めてきた父の詫びや次男の説得から葛藤します。
この年寄を、父として受け入れるか、私的な犯罪者と認定するか。当然、法的には裁けません。賢一郎の私情で、一家の現代表者として、父を裁こうとしているのです。
最後の場面
最後は父が家を去った後、二人が父を探しに行くのですが、この行動から、賢一郎は父を受け入れたのだと思います。
その後見つかったのか否か、わからないまま終わらせたのは物語に余韻を残すためでしょう。結末をあえて見せない手法かと思われました。
「家庭」という身近なテーマを取り上げた点
『父帰る』は戯曲で、一般人向けに作られた創作物になります。
最も身近なテーマはやはり「家庭」です。
この舞台設定が人気を博した理由であると思います。
まとめ
所見だと、何となくよく分からない作品という印象を受けるでしょう。私もそうでした。しかし、一か所一か所を細かく見ていくと、様々な構造に気づくことができたのです。歴史そして人間性への理解力が格段に上がり、むしろ非常に面白い作品だと気付かされましたね。これをすぐに高く評価した文人はすごいと思います。
父と子の対立や新旧社会制度の相違といった対比構造、それに加えて家族の人としての群像劇が加わったことで物語が複層的に広がっているため、高く評価されているか
『父帰る』は舞台設定が「家庭」であり、一般聴衆向けに作られたため、人気になったか
参考
小林和子2007『日本の作家100人 菊池寛-人と文学』 215-226頁 勉誠社
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |