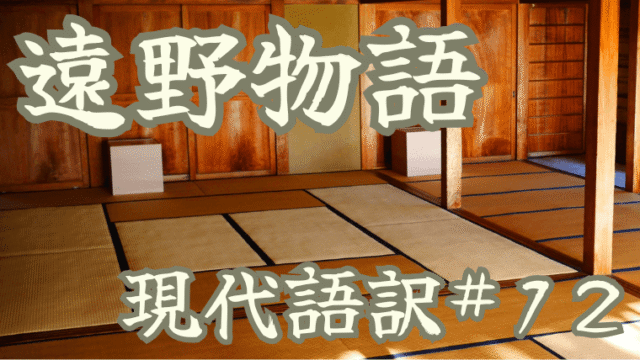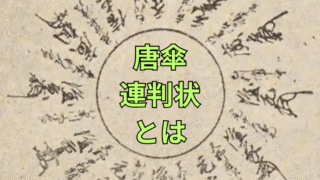現代語訳
| 最初に戻る << | 前に戻る << |
中将との出会い
ところで、この国の国司でいらっしゃる人の名前は山蔭の三位中将といいます。ちょうど姫君が人里を通過しているこの時、中将は縁行道をしていて、縁側にある四方の梢を眺めては、
「霞に包まれる遠い人里。卑しい家々にある蓬でできた蚊払い火の底の方で煙がくすぶっている。これが上空でたなびいている様がなんとも趣深い。こんな夕暮れ、恋人に見せたいものだな。」
と物思いに耽っていました。
この場を鉢かづきが通過します。中将は
「あれを呼んで来い。」
と命じ、若侍どもニ、三人が姫君のもとへやって来て、姫君はそのまま中将のもとへ連れていかれました。
「どこの浦のなんという者か。」
と中将が仰るので、姫君は
「私は交野のあたりに住んでいた者でございます。母に先立たれ、悲しみのあまりにこのような片端者となりました故、憐れんでくれる者もおりません。難波の浦だろうが何でも構まず、ただ足に任せて彷徨い歩いております。」
と答えました。
なんてかわいそうなことだ、とお思いになった中将は命じます。
「その頭の鉢を取ってやれ。」
者々が寄ってたかって鉢を取ろうとしますが、鉢はしっかりと頭に吸い付いて簡単には取れそうもありませんでした。これを見た人々は
「なんという化け物だ。」
と笑ったのでした。
中将はこれの様子をご覧になって、
「お前はこれからどこへ行くのか。」
と尋ねました。
「どこか特別行く先はありません。母と死別し、その挙句このような片端者にさえなってしまいましたので。私を見て憎いと思う人ばかりで、憐れんでくれる人などおりません。」
と返答したのでした。
中将はこれを聞いて
「不思議な者が私のもとにいても、それは良いものだ。」
と仰ったので、姫君は仰せのままに従い、屋敷に置かれることとなりました。
「お前ができることは何か。」
「突出したものはございません。琴、琵琶、和琴、笙(しょう)、篳篥(ひちりき)、『古今和歌集』、『万葉集』、『伊勢物語』、『法華経』八巻分と数々のお経を読みました、くらいでしょうか。その他にこれといった能はありません。」
「そうか、これといった能がないのなら、湯殿に従事してもらおう。」
まだ経験したことのない仕事でしたが、時勢ある人に従うことは世の習いです。こうして姫君は湯殿の火焚きを任されました。
屋敷での働き
夜が明けました。笑いながら姫君をなぶったり、憎んだりする人は多くいましたが、情けをかけてくれる人は一人もいませんでした。
その日の夜、「行水の時間だぞ、鉢かづき。」と、責め起こされました。まだ深夜0時、2時過ぎの日も昇ってない午前4時にです。
可哀そうに。地面につかないくらいのしなった竹が、雪の重さで倒れるような様子で寝ていた姫君。頼りないその身を起こして、働きます。
「つらいこの思いを柴の夕煙に乗せてどこかに飛ばしたいとしても、立ち昇った夕煙(姫君の良くない噂)が広がってまた苦しい思いをするのか。」
と物思いに耽りながら、
「行水のお湯が沸き終わりました。冷めないうちに早くお使いください。」
と衆に催促するのでした。日が暮れると、
「足の汚れを落とす。そのために湯を沸かせ、鉢かづき。」
と命令がきます。つらい身を起こし、乱れた柴を手繰り寄せながらこう詠みました。
苦しきは 折り焚く柴の 夕煙 憂き身と共に 立ちや消えまし
何が苦しいって、柴を折って焚くと夕煙が立つ(良くない噂が立つ)ことです。夕煙と一緒に、辛いこの身も消えてしまいたい。
前世にどのような悪行をすればこのような報いを受ける事になるのでしょう。
このような辛い世に生き、いつまでも死ねず生きながらえて、深く物思いに耽りながら寝る。
井出の里を思い、感情は駿河の富士山のように高揚し、袖は清美が関のように濡れる。
いつまでも生きながらえては辛さに耐えられず、涙を川のように流す。
涙川に乗ったとしても、その行く先(自分の行く末)もこれといって当てにならない。
「菊に乗った露がすぐ落ちて頼りないように、どうとでもなっていけよ、この身よ。」
と自分自身に心の中で語ったのでした。
松風の 空吹き払ふ 世に出でて さやけき月を いつか ながめん
松風が空にある雲を吹き払って曇りない晴れ晴れとした世の中に生まれて、澄んだ月をいつか眺めたいものだよ。
このように詠み、湯を沸かしたのでした。
御曹司との出会い
さて、この三位中将殿にはご子息が4人います。宰相殿御曹司という名の4番目の息子以外の3人は結婚してました。この宰相殿御曹司は非常に容姿に優れており、お姿は優美なもの。昔の人に例えると、光源氏大将か、あるいは在原業平か、といったところでしょうか。
春は花の下で夕暮れを待ち、散っていくことを悲しむ。夏は涼しい泉の底にある玉藻(藻の美称)を羨む。秋はまだ散っていない紅葉が、庭を敷き詰める散った紅葉を見て物思いに耽りながら月の前で夜を明かす。冬は蘆と蘆の間に張った氷の上で池の端で羽を閉じてオシドリが浮きながら寝ているのをみてさびしく思う。美しい色々を見せる四季すら及ばないご様子でした。
そんな御曹司はともに寝る相手もおらず、ひとり気ままに過ごしていました。そんな性格ですから、兄らも北の方(母)も同じ時に湯殿にお入りになる中、御曹司だけはお残りになって、夜遅くになってから、ひとり湯殿に入るのでした。
姫君は
「沸かした湯をそちらに移します。」
と言いました。その声が御曹司には優しく聞こえました。
「お行水にございます。」
そう言って差し出した姫君の手足が人並み以上美しく見えたので、御曹司はなんとも不思議な感覚を覚えました。
「おい、鉢かづきよ。誰もいないのだから何の差支えがあろうか。湯殿まで参れよ。」
これを聞いた姫君は昔のことを思い出して、
「人に湯殿のことは任せていたが、いざ自分で湯殿に行くとなると、どうしたらいいのだろうか。」
と思いました。
とはいえ、主人の命令ですので、どうしようもできません。姫君は湯殿へと参りました。
御曹司は姫君をご覧になって、思います。
「河内国は狭い。今まで多くの人を見てきたものの、これほどにもか弱く、非常に愛おしさを感じられ、美しい人には出会ったことが無い。いつぞやの花の都に上った時、御室の院(仁和寺)に花見をしにいったことがある。身分隔てなく人々が群がり、門前では市が開かれていた。そのような賑わいをみせていた場であっても、鉢かづきのような人は見なかった。いかにも。。。」
鉢かづきを見捨てるのが惜しく思ったのです。
「おい、鉢かづきよ。私はお前に思いをかけている。美しい紅ですら時を経れば色移りする(容姿の衰え)が、我々の仲は変わらないだろうよ。」
千年生きるという松に姫君との契りを懸け、百年生きるという亀は久しく結ばれたのです。姫君は軒端に咲く梅にずっと離れないでいる鶯のようにじっと、特にこれといった返事もしませんでした。
御曹司は重ねて言います。
「『古今和歌集』には(龍田川 紅葉乱れて 流るめり 渡らば錦 なかやたえなむ)という歌があるだろう。ここは龍田川ではないがね。乱れるクチナシ色(=口無し)の紅葉が君みたいだ。長寿の岩根(=言わね)の松とも言えようか、弾き(=気を引く)捨てられた琴は他に誰が弾こうか。もし君に文を重ねる相手がいるのであれば、逢瀬を遂げることなく虚しく消えてしまおう。君の為なら、かえって恨むようなことはしまい。どうだ、どうだ?」
警戒心の強い放し飼いの馬が人に慣れるように、いつか人は慣れるのでしょう。しかし姫君は気を強く持っていました。妹背の川(夫婦仲のたとえ)の中に入る(契りを交わす)ことが良いか悪いかも知らないから、何も申し上げることができなかったのです。
姫君は、御曹司の
「他に誰か弾き手がいるだろうか。」
という部分を恥ずかしく思ってしまいました。
「音を奏でる糸が全て切れてしまって、他に弾き手はおりません。私の普段の立ち振る舞いが悲しそうに見えるのは、虚しくも死別してしまった母のことを思ってなのです。それでいて、この身は消えずいつまでも命永らえています。私は、望んでもいないこの辛い世の中を、出家僧が身につける墨染めの衣のように恨めしく思い、嘆いております。」
こう申し上げると、御曹司は、全くもってその通りだ、とお思いになり、重ねてこう言いました。
「しかしまあ、有為転変の世の中に生まれてしまったのは虚しいことだよ。今の辛さが前世の報いとも知らないで、関係のない神や仏を恨んで日々を過ごしてしまう。お前は前世において、野の若木の枝を折っては(男女仲を壊す)愛し合った仲を離れさせて、人を嘆かせたことがあったのだろう。これほどの報いがあったから、今の世において母親に早く先立たれ、まだ幼い心なのに、物思いに沈みながら寝ては床を涙でいっぱいにしているのだ。そんな様子だよ。私はもう二十になるが、まだ妻を決めていない。自分一人だけの衣服を敷いてうたた寝するのも寂しく思うが、今日までこう過ごしていたのは、前世にお前との仲が深かったからだろうよ。めぐりめぐって今我々はここにいる。世の中には美しい人は大勢いるが、前世からの縁がない人には目もいかない。私がお前のことをこのように深く思うのは、前世からの縁があったからなのだよ。思いはじめてから今こうして逢うまでに交わしたお前の言葉を聞いていると末永く頼もしく思われる。鯨の寄る島(辺境の地)、虎が臥す野辺(荒野)、千尋の底(深い海底)、五道輪廻のあちらにある、六道四生のこちらにある、妹背の川の上流にある、涅槃の岸(死ぬこと)は変わってしまうとしても、お前との仲は変わるまい。」
と、深く契りに思いを込めました。姫君は御曹司の言葉に強く惹かれ、漕いでいる舟が港に入るような気持ちになりました。そして、思いもせず気持ちが御曹司に向かった姫君は、夜はここに寝て契りを交わしたのでした。しかし姫君は、粗削りの金属が瓦になるか金になるか分からないように、行く末がどうなるか分からないと不安を覚えます。
「自分の気持ちが誰にも知られないまま、どこへでも足に任せて行ってしまいたい」
と悲しみに暮れたのでした。これを見た御曹司。
「どうしたのですか、鉢かづき。何をそのようにお嘆きになっているのか。契りを交わした時から、微塵もあなたのことを疎かにしようなどとは思ってもいませんよ。日が暮れたら、すぐに尋ねましょう。」
と言いました。
それからというもの、御曹司は昼も折々姫君のもとへ通うようになり、ある日、
「私がいない間は、これで慰めてください。」
と、黄楊(つげ)製の枕と横笛を添え置いてくれました。この時の恥ずかしさというのは、どうしようもないほどでした。ふつうの人であれば、飛鳥川の渕瀬が定まらないように(人の心が変わりやすい)、心変わりしたでしょう。人は夜になればそうなるものなのです。しかし姫君はいまだ生きる甲斐を感じられなかったため、御曹司を心の頼みにしようと思いながらもできませんでした。このような状態で契りを交わしてしまった自分が恥ずかしく思われたのです。こう思ってはまた悲しみに暮れては涙を流すのでした。
御曹司はこの様子をご覧になって、
「鉢かづきの様子をものによくよく例えてみれば、楊梅や桃李の花の香りが漂いながら、雲の間から月が差し込んで、二月半ばの垂柳が風に乱れ舞っているといった風情だ。籬に咲くなでしこが僅かな露にも負けそうな、そんなか弱さで、恥ずかしそうに横を向いている姿が愛嬌があってかわいらしい。楊貴妃や、漢武帝の側室の李夫人もどうしてこれに勝ろうか。」
と、不思議にもそうお思いになりました。また、
「この鉢を取り除いて、美しい十五夜の月が誰でも見ることができるように、鉢かづきの姿も見れないものか。」
とお思いになったのでした。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |