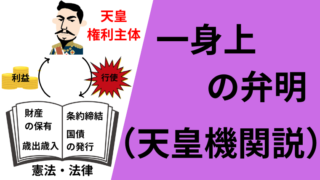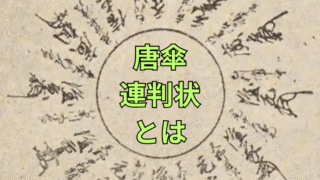現代語訳
| 最初に戻る << | 前に戻る << |
黄楊の枕と横笛
さて、御曹司は湯殿の傍らにある柴が積んである閨を出て、自分の住まいへと帰ります。道中、軒端に咲く梅をご覧になっては、
「通い終わって、鉢かづきはどれほど寂しく思っているだろう。今日の暮れもまた尋ねるが、住吉にある小さな松が千年後の寿命を待つよりも長い時間に感じられるよ。」
とお思いになります。
一方で姫君は、黄楊の枕と笛を置くところもないので、扱い辛くて困っていました。こうしているうちに、だんだんと夜が明けはじめました。夜明けを告げる鳥も夜明け空に横にたなびく雲も見られない時間に、
「行水の時間だぞ、鉢かづき。」
と責め立てられて、
「お湯が湧きました。どうぞ。」
と答えつつ、鬱陶しい柴を折っては焚き、こう詠みました。
苦しきは 折り焚く柴の 夕煙 恋しき方へ などなびくらん
折り焚く柴が夕煙となって飛んでいくことが心苦しい。よりにもよって、どうして恋しい人の方に向かってなびくのだ。
これを聞いた湯殿の奉行は、
「あの鉢かづきは頭こそ人とは異なるが、ものを言う声色、笑い方、手足の人並み以上の美しさは、昔から住んでおられる女房らよりもはるかに勝っているのではないか。親密になって鉢かづきと契りを交わしたい。あの頭は隠れていて顔全体がはっきりしない。口から下は見えるが、鼻から上は見えない。こんな片端者に心を懸ければ、仲間どもに笑われてしまおう。かえって恥ずかしいではないか。」
と思ったのでした。思いもよらないことが、ご尤もな話だったのです。
春の日は長いものですが、その日もだんだんと空が紅色に染まっていく時間になりました。夕暮れ時というのは、夕顔だけでなく、人の心も花咲く時間でもあるのです。御曹司は普段より華やかな衣装を着て、湯殿の傍らにある柴の臥所に佇んでいましたが、姫君は気づいていません。
「暮れになったら行くよ。」
予めそう伝えたのに、時間はすでに夜になろうとしていました。里の犬が人を咎めんと吠える時間です。見つけた姫君は、御曹司が来るまでの慰み物として貰った、黄楊の枕と横笛を持って詠みました。
君来んと 黄楊の枕や 笛竹の など節多き 契りなるらん
黄楊の枕はあなたの来訪を告げるものです。しかしまあ、どうして節の多い約束なのでしょう(短い時間の約束も守れない)。竹製の横笛がこれを感じさせます。
御曹司もとりあえず詠みます。
幾千代と 臥し添ひて見ん 呉竹の 契りは絶えじ 黄楊の枕に
黄楊の枕を頭にして、幾千万の年月も添い遂げてみせましょう。その呉竹(長い世を導く)の約束は絶えまい
こうして、姫君と御曹司は、比翼連理に、深い契りを交わされたのでした。
紙や布で包んだとしても色が漏れてしまう紅色のように、御曹司と姫君の関係は漏れてしまったのでしょうか。
「御曹司ともあろう方が鉢かづきのもとへ通いなさっている。なんとも呆れたことか。男が女のもとへ通うのは、身分の貴賤に関わらずなされる世の習いである。とはいえだ。御曹司が通われるのは良いとして、鉢かづきが御曹司に近づこうとしているのは認められない。」
と、姫君を憎まない人はいなかったのでした。
御曹司の愛
ある時のことです。御曹司がよそから客人の応対を夜更けまでしていました。夜更けになって通われたのですが、姫君は不安を感じて詠みました。
人待ちて 上の空のみ ながむれば 露けき袖に 月ぞ宿れる
御曹司が来るのを待つ今、気分は上の空です。上に広がる空を眺めると、涙で濡れた袖に月が映えているではありませんか。
これを聞いてますます姫君に思いを懸けるようになった御曹司。二人の仲はますます深くなり、そして御曹司が姫君を見捨てるような様子も見られませんでした。
二人の関係とはいえ、人というのは今も昔も変わらず、自分の身に関係のないことまでも口を出してしまいます。
「御曹司は世の中には鉢かづきの他に女は存在しないといった勢いで、このように振る舞われている。なんとも面白い人だな。」
と人々は笑うのでした。このことを耳にした御曹司の母上は、
「皆、間違ったことを申しているではないか。乳母に調べさせよ。」
と仰いました。その後、担当した乳母は
「これは本当のことです。」
と申し上げます。父母は呆れ、しばらく何も言えずに、しばらくしてから、
「おい、乳母よ。聞きなさい。とにかく、若(=御曹司)に諫言して、鉢かづきに近寄らないように計らいなさい。」
と命令したのでした。
乳母は御曹司の前に参上し、柔らかく諫言するべく、それなりのものを語り申し上げます。
「いかに若君様。真実ではないとは思いますが、湯殿の湯沸かしの鉢かづきのもとへ通われているという話をお母上より聞きました。『まさかそのようなことはないとは思うが、もし本当だとしたら、父上の耳に入らないうちに、鉢かづきを追い出すべきだ。』との仰せでございます。」
御曹司は返します。
「前々からこの時が来るのだろうと思っていたよ。鉢かづきと同じ樹の下で過ごし、同じ川の流れに乗って行く末を共にするのは、前世からの因縁によるものだと聞いている。はるか昔からそうだ。主人から罰を受け、深い海の底に沈んだ(主従関係が切れる)としても、仲睦まじい夫婦仲は切れるものではない。親から疑われ、たちまち無間地獄に堕ちたとしても、愛し合う夫婦仲であればそれの何が苦しいだろうか。父上の耳に入り、父上の手にかかったとしても、あの鉢かづきのためならば、命を捨てることすら微塵も惜しくはない。鉢かづきを見捨てようなど私は思ってもいない。母上の言葉に『はい。』と返事申し上げなかった結果、私と鉢かづきを追い出しなさるというのなら、どのような野の果て、山の奥に住むことになろうとも、想い人と共にいれるのなら、家を追い出されても全く悲しいとは思わない。」
そして、自分の部屋を出ては鉢かづきが過ごしている柴の積まれた戸にお入りになったのでした。
日頃は鉢かづきのもとに通っていたことを人目から包み隠していたのですが、乳母が参上してこう申し上げたこの時から、御曹司は人目を憚らず、朝から晩まで彼女のもとへ通い続けました。
兄らも、
「一族が住む場所に立ち入ることは許さない。」
と言って御曹司に圧力をかけましたが、それを辛く思うご様子もない。むしろ、さらに人目も憚らず、朝から夕まで鉢かづきのもとへと通ったのでした。
母上が言います。
「ともかくよ。あの鉢かづきは人に変化(へんげ)した化け物で、若を殺そうと思っているに違いない。どうしたら良い、冷泉。」
付き従い女房の冷泉は申し上げました。
「若君は、たいしたことでもないことにすら深く考えては恥ずかしがられる、といったように、普段から控えめなお方ですが、今回の件に関しては恥ずかしがっている様子が見られません。ですので、ご兄弟と嫁比べをなさってはいかがでしょうか。そうすれば、あの鉢かづきも恥ずかしくなってどこかへ勝手に行ってしまうことでしょう。」
なるほど。と思った母上は、
「いついつにご子息の嫁比べが開かれるらしい。」
と口々に触れ回りました。
御曹司は姫君のもとへ行っては涙を流して言いました。
「あの話をお聞きになってみてください。我々を追い出すために嫁比べをするということを言い出しては触れ回っています。どうしましょうか。」
「私のために、あなたの人生を狂わせてもよいのですか、私が、私が、どこかへ行ってしまいましょう。」
「あなたと離れてしまっては、一瞬でも生きていけまい。どこへでも、共に参りましょう。」
姫君はどうしたら良いのか分からず、涙を流したのでした。
嫁比べ1
さて、月日は流れ、0時を回って嫁比べの日になりました。御曹司と姫君は二人でどこへでも行ってしまおうといった表情で、憐れなものに見えます。
夜が明けたので、御曹司は履いたこともないわらじの紐を締めます。父母とともに過ごした住み慣れた家なので、さすがに名残惜しくお思いになった御曹司は落ちる涙に視界は曇り、家を出る前に、今一度父母に会いたいと思います。しかし、
「どこへ行くかも知らず家を後にすることは悲しいが、別れというもの一生に一度は必ずあるものだ。それが今なのだ。」
と振り切りました。
「私一人だけでもどこかへ行ってしまいましょう。あなたとは前世からの縁が深いのですから、またどこかでめぐり逢うことが出来るはずです。」
「なんとも恨めしいことを仰るのですね。どこへでもお供いたしますよ。」
君思ふ 心のうちは わきかへる 岩間の水に たぐへてもみよ
あなたを思う心がどれほどのものか、岩間から湧き出す水と比べてみてくださいよ。
出ていこうとしていた姫君は返します。
わが思ふ 心のうちも わきかへる 岩間の水を 見るにつけても
私があなたを思う心も、あの岩間の水のように湧きかえっています。
さらに姫君は続けます。
よしさらば 野辺の草とも なりてもせで 君を露とも ともに消えなん
よし、そうであるならば、私は野辺の草にならずに、あなたを露と思い、その露とともに消えてしまいましょう。
御曹司は返します。
道の辺の 萩の末葉の 露ほども 契りて知るぞ われもたまらん
我々の行く末は道端に咲く萩の葉に乗った露のようなものです。こうしてあなたと契りを結んだ今、私も参りましょう。
とお詠みになって、姫君と同じように家を出ようとしますが、さすがに名残惜しく感じた御曹司、悲しくお思いになっては体が固まってしまい、ただただ留めなく涙を流すのでした。
とはいえ、このまま留まっておくわけにもいきません。夜もだんだんと明けてきています。
二人して涙を流しながら急いで出ようとしたその時、被っていた鉢がカパッと二人の前に落ちたのでした。
御曹司は驚き、姫君の顔をつくづくと見ます。雲の間から姿を現した十五夜の月に異ないほど美しく、その髪、お姿は何にも例えることができないほど。
御曹司は嬉しく思います。落ちた鉢を持ち上げて見ると、二つの掛け子が付いており、中を見ると、黄金の玉・金の杯・銀の小さい手提げ・砂金で作られた三つの橘・銀で作られたケンポナシ(梨の一種)・十二単の小袖・紅の幾度も染め込んだ鮮やかな袴・数々の宝物、が入っていました。
姫君はこれを見て、
「母上が長谷(はせ)の観音様を信じ続けたことへのご利益だ。」
と思い、嬉しいも悲しいも、まずは涙が先です。
御曹司はこれを見て、
「あなたにこれほど素晴らしい果報があったとは、私は嬉しいよ。今はどこへも行かなくて良い。」
と言って、嫁比べの会場へと向かう準備をしました。
| 前に戻る << | 続きを読む >> |