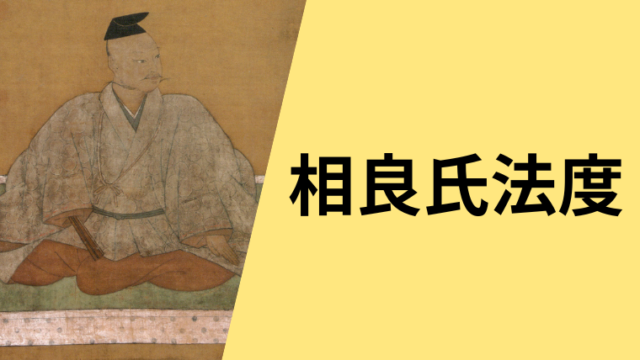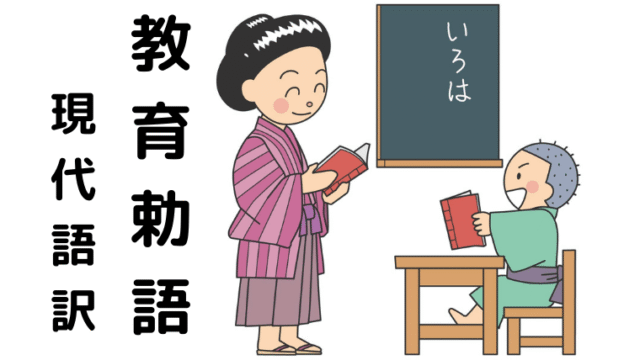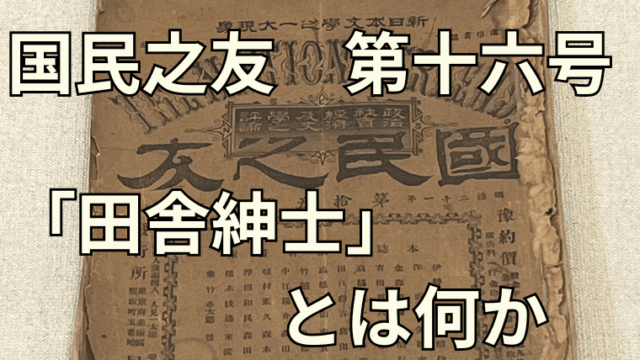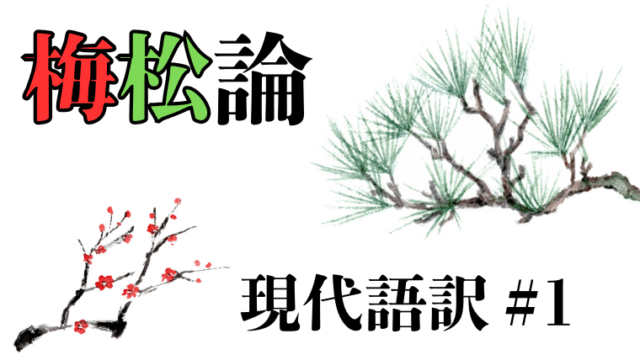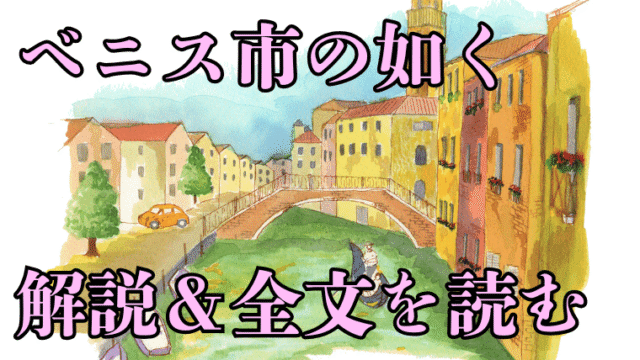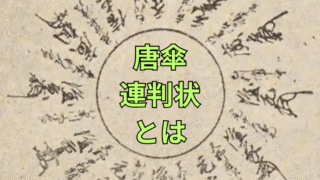解説
概要
1458年、琉球王国6代王の尚泰久によって鋳造された鐘で、かつては首里城正殿に掲げられていました。鐘には臨済宗の僧である溪隠安潜叟(けいいんあんせんそう)による銘文が刻まれており、その内容は、中国と日本の間に位置する琉球が、交易の架け橋として栄えたことを高らかに謳ったものとなっています。
後に説明しますが、尚泰久の時代は非常に政権が不安定な時期で、尚氏の滅亡期にあたります。それでもこの鐘を鋳造したのは、王権が不安定でも、先代が作り上げた琉球の外交理念と精神的支柱は不変である、琉球王国の繁栄は先代の尽力の賜物であると言いたかったためでしょう。また、後半には、王の長寿を願う文言もあることから、内乱の時代にこそ必要だった祈りの鐘でもあったとも言えるでしょう。
津梁の意味
「津」は港や渡し場を意味し、「梁」は橋を意味する単語で、仏教用語としては、迷いの世界から悟りの世界へ導く橋という意味で使われます。
内容を見ると、「蓬莱島」や「三宝(仏法僧)」、「四恩」、「須弥」など、仏教用語や、仏教的世界観を表す単語が多く見られます。
仏教で興隆した面と、日中の文化や経済の橋渡し役としての役割を担ってきた面の両方を表現するにピッタリな単語です。
尚氏について
尚氏が2つ?
尚氏は第一尚氏と第二尚氏に分かれます。ざっくり言うと、第一尚氏は琉球統一した一族、第二尚氏はクーデターで倒れた後に琉球国の王位を継承した一族です。第二尚氏は薩摩侵攻や明治維新を経験しました。
最後の国王、尚泰は1879年に沖縄県として日本編入される際に退位しました。琉球王国という独立国家が日本国に取り込まれたわけですから、このタイミングが最後なのは必然です。
今回は第一尚氏のみに絞って解説していきます。
第一尚氏
| 代 | 国王名 | 在位期間 | 備考 |
| 初代 | 尚思紹 | 1406-1421 | |
| 2代目 | 尚巴志 | 1422-1439 | 三山統一、琉球王国建国 |
| 3代目 | 尚忠 | 1439-1444 | |
| 4代目 | 尚思達 | 1444-1449 | |
| 5代目 | 尚金福 | 1449-1453 | |
| 6代目 | 尚泰久 | 1454-1460 | 志魯・布里の乱後に即位 |
| 7代目 | 尚徳 | 1461-1469 | 家臣金丸のクーデターにより王統終焉 |

第一尚氏は4世代で完結された王統です。琉球王国を統一した尚巴志は2代目で、「万国津梁の鐘」を鋳造した尚泰久は6代目になります。一代の在位期間が短く、近親間で譲位し合っている状況は、第一尚氏の政情が不安定であったことを表しています。
その尚泰久は志魯・布里の乱後に即位しましたが、この乱の勝者というわけではありません。乱の鎮火役として即位しました。
5代目尚金福の死後、その子の志魯と弟布里が王位を激しく争ったこの出来事を、志魯・布里の乱と言います。両者は首里城が全焼するほどの激戦を繰り広げましたが、志魯は戦死、布里も首里を追放されるという元も子もない結果となってしまいました。
上杉謙信の死後に起きた上杉景勝VS上杉景虎(北条三郎)の御館の乱のような、壬申の乱のような内乱でした。
そこで選ばれたのが、布里の弟である尚泰久だったのです。穴埋めのような王位継承を認める者は多くなく、その後わずか1代で第一尚氏は滅亡することとなってしまいました。
最後の王、尚徳は尚徳で手の付けられない人物で、非常に暴虐な性格であったといいます。賢聖であったならもう少し第一尚氏も存続できたかと思われますが、この性格によって家臣との対立が激化、最後は家臣金丸のクーデターによって第一尚氏は滅亡しました。
政情が不安定だった理由
王位交代が激しく、政権が不安定だったのは、第一尚氏の王権が非常に未熟であったためです。これは琉球統一時の策略が原因となっています。琉球統一のステップは次の章で解説しています。
簡単に説明すると以下のようになります。
尚巴志は北山、南山の王統は滅ぼしたが、按司(地方豪族)は安置した。これによって民の支持を獲得、統一に成功したが、按司の影響力は強いまま残り続けた。
中央集権を確立しない方針で琉球統一した尚巴志でしたが、彼の死後、按司が下剋上のチャンスを伺うという悪影響をもたらしました。これによって按司は王位継承戦に参戦したり、按司同士で対立したりと、国内の混乱を誘発、対する第一尚氏は、この内乱を鎮める力を持たないため、結果として不安定な王権が続きました。
琉球統一
琉球は、尚巴志によって統一される前、北山・中山・南山の三山に分かれていました。尚巴志は中山出身の按司(地方豪族)になります。

尚巴志のやり方は戦国大名の下向上に近しいものでした。まず、自身の出身の中山王を殺害し王位に就け、その後、北山と南山の王統を滅ぼすといったやり方です。暴君のような印象を受けますが、意外にも民からの支持は高かったようです。その理由は、あえて地方を基盤とする按司を残すことで、統治体制を緩和していたためだと言われています。これが後の王位争い激化のトリガーになったことは、尚巴志も思ってもいなかったことでしょう。
- 中山の掌握(1406)尚巴志はまず、当時の中山王であった武寧を滅ぼし、父尚思紹を中山王に即位させました。これが第一尚氏王統の始まりです。
- 北山の攻略(1416)北山は今帰仁城を拠点とする強国でしたが、尚巴志は中山の按司(地方豪族)と連合軍を結成、按司の護佐丸の策略によって北山内部に裏切りを誘発させました。これによって内部崩壊を起こした北山王攀安知は自害し、北山は陥落しました。
- 南山の攻略(1429)南山王他魯毎は暴君で民衆の支持を失っていました。尚巴志はこれを逆手に取り、南山の水源である嘉手志川と金箔の屏風を交換するという策略で王の信頼を失墜させ、そのまま南山を滅ぼしました。
- 琉球王国の建国(1429)1429年、ついに尚巴志は三山を統一し、首里を王都とする琉球王国を建国しました。首里城を築城し、明との朝貢貿易、日本との対等貿易を通じて国際的な地位を確立していきました。
ポイントは戦略的同盟と民心掌握でしょう。尚巴志は北山・南山の王統を滅ぼしても、按司を一掃するようなことはしませんでした。むしろ、彼らをうまく取り込みながら勢力を拡大していきました。
なぜそうしなかったのか。理由は2つあります。
- 基盤の貧弱さ 第一尚氏自身も下剋上によって成り上がった一族で、数代数十年といった基盤がありません。そのため、中央集権は不可能であったと最初から分かっていました。
- 安定統治を優先 按司は各地に根を張った有力者であり、その土地や民を支配していました。彼らを排除すれば混乱を招くだけでなく民からの反発を受け、反乱の要因になりかねません。そこで尚巴志は按司を懐柔し、協力関係を築くことで統治の安定を図りました。
基盤の重要性は歴史が証明しています。荘園を莫大に有していた藤原氏、知行国の拡大に成功した平家、関東武士の心を掌握した源氏等々です。現代でも、城下町があった市は発展していますが、そうでない地は発展が遅れているという現状もあります。
現在
現在は、ただの歴史的遺物としてアピールされているのではなく、沖縄の歴史的存在性、そして沖縄繁栄の象徴の偶像としてその存在感を放っています。2000年に開催された沖縄サミットの会場「万国津梁館」の名前の由来にもなっていたことはご存じでしょうか。この時2000円紙幣となった守礼門が目立ちすぎることになってしまいましたが、海外に対してはこの鐘の方が認知されていたといいます。
現物は沖縄県立博物館に所蔵されており、国の重要文化財に指定。公式サイト曰く、博物館では毎時0分と30分にその音を聴くことができるといいます。
時を超えて響く琉球の精神。行ってみたいものです。
現代語訳
琉球國者南海勝地而
鍾三韓之秀以大明為
輔車以日域為脣齒在
此二中間湧出之蓬萊
嶋也以舟楫為万國之
津梁異産至宝充滿十
方刹地灵人物遠扇和
夏之仁風故吾
王大世主[庚寅]慶生[尚泰久]茲
承宝位於高天育蒼生
於厚地為興隆三宝報
酬四恩新鋳巨鐘以就
本州中山國王殿前掛
着之定憲章于三代之
後戢文武于百王之前
下済三界群生上祝万
歳宝位辱命相國住持
溪隠安潜叟求銘々曰
須弥南畔 世界洪宏
吾王出現 済苦衆生
截流王象 吼月華鯨
泛溢四海 震梵音所
覚長夜夢 輸感天誠
堯風永扇 舜日益明
[戊寅]六月十九日[辛亥]
大工藤原國善
住相國溪隠叟誌之
琉球国は南海の国々の中でも地勢に優れた土地であり、新羅・百済・高句麗の三韓の秀でた技術や文化を集めて繁栄した。大国、明を車輪とし、日本を添え木とするような関係(欠けてはならない関係性)を築いてきた。琉球国はこの二国間に存在する蓬莱島だ。海洋国家として世界中の産物の渡し場となり、もたらされた宝(仏教)は国内に遍く充満した。琉球国に住まう地霊そして人々は、遠く海の果ての日本と明で隆盛している仁徳による教化を仰いだ。繫栄したが故に、我が王は庚寅の年に誕生した。尚泰久である。
庚寅は誤りでしょう。庚寅は1410年になりますが、尚泰久の生誕は1415年です。
尚泰久は天高く王位を受け、人民は豊潤な土地に住まう。三宝(仏法僧)を興んにし、四恩(父母の恩・衆生の恩・国王の恩・三宝の恩)に報いるため、新たに巨鐘を鋳造する。中山国の王殿の前にこれを掛ける。
琉球には北山、中山、南山の三国が存在しましたが、1429年に中山が琉球王国を統一しました。
琉球王国の在り方。それは、憲章は古代中国の三代(夏・殷・周)に倣うものを作り、文化芸術は遥か遠い昔から伝わるものを集め、継承するというものである。そのような王殿に掛けられたこの鐘の音は、下は三界(欲界・色界・無色界)にいる衆生を救い、上は永遠なる尚一族の王位を祝うだろう。恐れ多いながらも、相国寺(京都五山第二位)の住持(主僧のこと)、溪隠安潜叟(けいいんあんせんそう)に鐘銘の刻印を求めた。
銘に曰く、
『須弥の南畔(帝釈天や四天王が住む須弥山の南の州には人間が住んでいたとされる。)で世界は計り知れないほど広大なものとなった。そして出現した我が王は衆生を救い、衆生はその苦しみから救われた。地獄に落ちた衆生の過ちを断つ仏の道、月まで響く鐘の音は世界中に満ち溢れた。梵鐘の音が聞こえる所では、人々は長夜の夢(「煩悩にまみれた人の世は夢のように儚い。」の意。)から目を覚まし(=仏門への誘い)、天が感動するほどの真心が育まれる。そして、聖王、堯帝のもたらした政道は永く引き継がれ、聖王、舜帝のもたらした平和で穏やかな世の中はますます盛んとなろう。』
1458年(戊寅年)6月19日(辛亥の日)
刻銘、藤原國善。相国寺住持、溪隠叟、これを記す。
まとめ
琉球統一までの経緯と尚泰久がなぜ「万国津梁の鐘」を鋳造したか、それは国内情勢によるものだと考えても良いでしょう。銘文の内容からもそう読み取れます。
琉球王国の成立を知る人は多くないと思います。首里城や第二次世界大戦の遺構が目立ちますが、機会があれば、北山や南山の遺跡も巡ってみてはいかがでしょうか。
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |