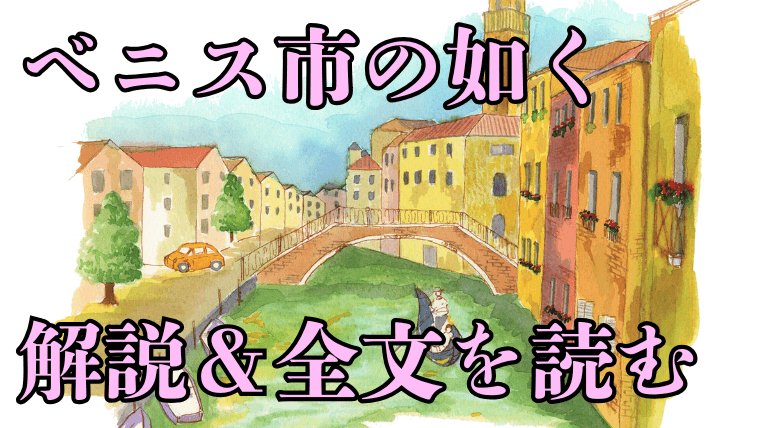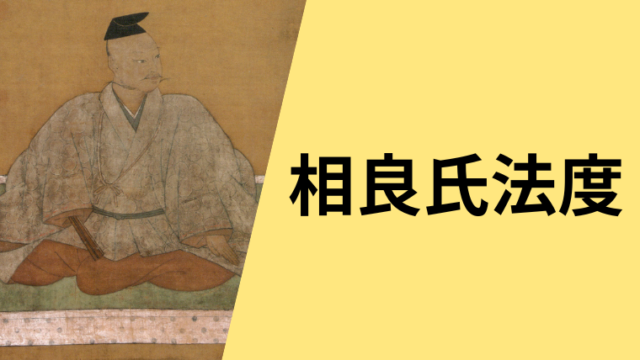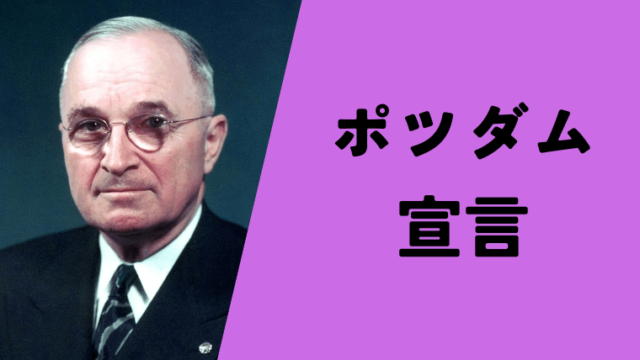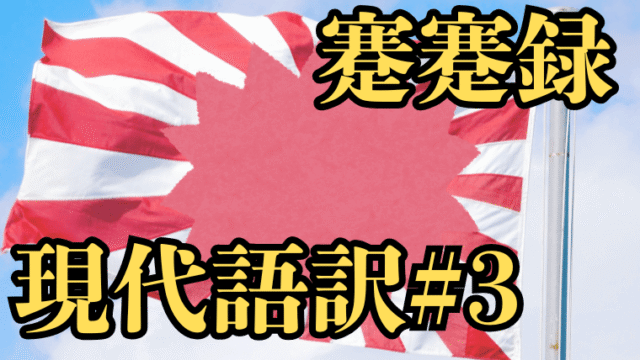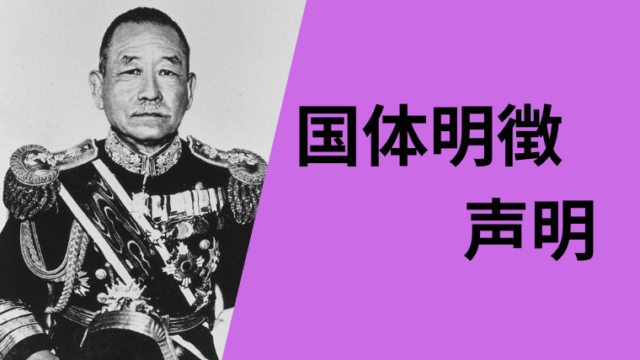プロフィール帳
解説
時代背景(日本)
この書簡が書かれたのは1561年。戦国時代真っ只中です。戦国時代といっても、数年違うだけで地図がガラリと変わる激動の時代ですので、この頃の日本がどのような状況だったか、軽く見ていきましょう。
桶狭間の戦い
織田信長が東海一の弓取りこと今川義元を討ち取った桶狭間の戦いが1560年(永禄3年)6月12日になります。この時すでにガスパル・ビレラは日本に来日していました。
キリシタン大名の登場
キリシタン大名で最も名のある人物は大友宗麟(1530-1587)でしょう。1550年頃に大友氏全盛期を築き上げた戦国大名で、フランシスコ・ザビエルとは1551年に接触しています。洗礼名はフランシスコ。改名したのは1578年で、晩年の話になります。
70年代は、大友宗麟に留まらず、有馬晴信や小西行長といったキリシタン大名が改名した時期で、キリスト教全盛期はまだ先の話です。
要するに、当時の堺はまだ信長上洛前で、六角氏や細川氏など畿内の大名が少数勢力で治めていた時期であったということです。
言い換えれば、経済開発を促した信長の楽市楽座令(1568)よりも前の段階から、商人による自治が堺では行われていたということなのです。
時代背景(世界)
キリスト教の布教活動とセットなのが植民地支配です。宗教によって人々の心を掴み、精神を無力化してその土地を攻略する、これが当時のヨーロッパ諸国の手法でした。世界に乗り出したことから、大航海時代とも言われます。
大航海時代の動向を見ていきましょう。
- 1492年スペインのコロンブスがアメリカ大陸に上陸。キリスト教改宗と武力制圧によって支配を進める
- 1494年トルデシリャス条約。スペインとポルトガルが世界を東西で分割して統治することを掲げた条約。スペインが南北アメリカ大陸、それ以外をポルトガルが支配する方針となった
- 1510年スペインがアステカ・インカ帝国(メキシコ、ペルー)を滅ぼす
- 1529年サラゴサ条約。トルデシリャス条約の境界変更。スペインの支配域がちょうど日本の堺あたりまで伸びる
- 1540年イエズス会設立。アジアやアメリカへ積極派遣を行う
- 1543年ポルトガルより鉄砲伝来。
- 1549年フランシスコ・ザビエルが日本に上陸
ザビエルやガスパル・ビレラは布教活動メインで来日したとされています。要するに、信仰心の厚いただの宣教師だったということです。結果的には、植民地支配が最終目的ではありましたが、彼らにその意図はなかったというのが現在の研究では言われています。
著者について
著者のガスパル・ビレラはポルトガル出身のイエズス会(カトリックの宣教団体)員です。自分の意思で日本に来たわけでなく、ポルトガルから派遣された宣教師で、宣教師なだけあって、キリスト教を日本で広めるために来日しました。
彼の前にはかの有名なフランシスコ・ザビエルが来日しており、ザビエルは山口大内氏や豊後大友氏からの庇護を受けました。
ガスパル・ビレラは、フランシスコ・ザビエルの後を継いだ宣教師として、幕府からも庇護を受けることとなります。最初に上陸したのは1556年。豊後に上陸し、ザビエルの時と同様、大友宗麟からの庇護を受け、その後、幕府への謁見と人口の多い町での布教を目的として堺入りを試みました。それが1561年のことで、堺ではなく京で布教活動を展開しましたが、2年後の1563年、仏教勢力による弾圧を受け、追放となりました。
別の書簡では豊後や博多での生活(戦乱に巻き込まれた苦難が多い)が記されています。
書簡から見て取れますが、ガスパル・ビレラは非常に学習意欲の高い人物であったことが分かります。日本語の習得に非常に熱心で、通訳無しで自力で教えを説くほどの語学力があり、また、日本人の習慣やライバル勢力となる仏教の歴史や現状なども的確に捉えていました。
しかし、プラスな話ばかりではありません。身内に向けての手紙のため、書簡には悪いことは書いていませんが、別の史料では、寺院や仏像の焼却・破壊行為を行ったことが記録されており、高圧的に仏教勢力と対立していました。
書簡の内容
日本の習俗についての記載が多いです。盂蘭盆会を始めとする祭りや、仏教に関する情報が事細かに記されています。特に、仏教宗派の経歴や仏教勢力の振る舞いの問題点を指摘した点は、現代の研究に大きなずれはなく、その調査能力の高さが評価されます。
布教活動の経過はリアルに描写されており、仏教勢力との対立だけでなく、プロテスタントとの関係性も読み取れるものとなっています。
その全容は、実際に読んでみてください[こちらをクリック!]
なぜ堺はベニス市のような町なのか
まずは該当の前後を読んでみましょう。
堺に着いて、我らの主は聖ルカの祭日である10月18日を楽しみにした。そうして、我らは聖ルカをこの町(堺)を守る聖人と仰いだ。この地において成すべきこと(布教)を我らの主は期待している。堺の町は非常に広大で大きな商人が多くいた。この町はイタリアのベニス(ベネツィア)のように執務官によって治められている。こので数日間休息をとり、その後我らの主が派遣した一行がいるヒエノヤマ(比叡山)へと出発することを決めた。
堺についての記述はたったこれだけで、さらに、ベニス市のようだといった根拠は、「堺が執務官によって治められている」という点だけになっています。
根拠が薄いように見えますが、この「堺が執務官によって治められている」という一文は、港町堺が非常に革新的な町であったことを示した歴史的史料になったのです。
16世紀の日本は戦国時代で、武士が統治を行う政治体制が常識となっていましたが、この堺は武士による支配ではなく、商人や町衆が自治を行っていた都市でした。その支配者層を会合衆と言います。彼等は、商人や町民の代表者たちで、彼らが堺の政治を担っていました。
この「会合衆」が、ガスパル・ビレラの言う執務官にあたります。
ベニスと比較したのは、ベニスは中世ヨーロッパでも有数の商業都市であり、海洋国家でもあったためです。商業都市というだけあって、武力統治とは異なり、元老院などで構成された執務官による共和制的な政治が敷かれていました。
また、地理的にもベニスと堺とは共通点がありました。それは、港湾都市であるということ。現代でも、水の都ベネツィアと呼ばれるほどで、中世の時点でもベニスは海運業で栄えていました。堺も同様、国際的港湾の役割を持ちながら、都の生命線として重要な位置づけにあったため、その地理的重要性と、武断政治から乖離した経済のオアシス的が共通点として十分満たされているのです。
「ベニス市の如く」の一文は、当時の堺の政治体制や経済的自立性、そして都市としての洗練さを高く評価した言葉だったのです。
では、当時の畿内の様子を、宣教師目線で見てみましょう。
現代語訳
1561年8月17日。堺発。神父(パードレ→訛ってバテレン)ガスパル・ヴィレラより、インドの神弟であるイルマン(パードレを補佐する職)等に贈る書簡
この書簡を送る目的
1559年、神父であったコスモ・デ・トーレス(かのザビエルと共に日本を訪れたイエズス会宣教師のひとり)の命により、我らイエス・キリスト(イエス→訛って耶蘇)の教えを布教できるか否か挑戦すべく京の都に向かう旨を、豊後にいるイルマンに連絡した。京の都に向かっているとはいえ、日本全国の宗教は多くが京と関わっており、上手く布教できるか、怪しいところである。この度、道中そしてその土地土地で起きたこと、並びに、我ら主デウスの行うこと(布教活動)を褒め給えることを目的として、耶蘇会員に通信することを約束する。
これにより、全ての幸福の源である我らの贖い主であるイエス・キリストを讚美し、また、主の光栄と名誉を喜べるイルマンに喜悦と慰安をもたらすこととなる。それだけでなく、祈祷の際、世界中に遠く散らばっているが故に語らうことが出来ない兄弟(宣教師)が何をしているのか想起しやすくなろう。
堺までの道程
1559年、私(ガスパル・ヴィレラ)はキリスト教布教のため、神弟ではないが神弟に等しい、ロレンソ了斎という日本人のイエズス会員と共に豊後を発った。ロレンソ了斎は日本のことについて精通しており、通訳で好き好きに語ってくれた。我々は京の都の方向に進む異教徒プロテスタントの船に乗り込んだが、悪魔(プロテスタント信者)らは、我が主イエス・キリストがこの航海で雌雄を決さん、と判断することを恐れ、多くの妨害を加えてきた。
一。ある日、丸一日風がなく、先に進めないことがあった。搭乗していたプロテスタントらは波凪に及んで、偶像(イエス・キリスト)に航海のために風をもたらし給え、と祈ろうとして寄付金を集めることとした。人々を順に回り、私のところに来て同じく寄付金を求めてきた。
「私は天地創造の真の神、創造神(旧約聖書『創世記』)を崇敬している。風は再び吹くと信じている。だからお前たちのしようとしていることに対して寄進はできないよ。」
と言うと、プロテスタントらは皆私に対して憤慨し、私が波凪の原因だと決めつけ船から追い出そうとした。私は、我らの主に行く末の一切を任せた。風は以降どうなったか。この時午後であったが、主が風をもたらしたのは翌朝であった。他の港を目指そうとし、第一の港を出て数レグアの距離進んだあたりで風向きが逆となり、結果四日間も船を進めることができなかった。この状況をみてプロテスタントらはいよいよ私が航海の障害だと信じ、口で体で我らに害を加えてきた。我らの主はこの行為を許さなかった。
第一の港に着き、天候の影響で10日間そこで逗留したが、この間我らは協議し、私を同行させないと決め、船頭にそのように要求。私は下船してこの港を出た。この港には乗れそうな船が一隻もない。そのため、先程の船に向かい、我らの主の愛により再び同行を認めて欲しいと交渉、主の許しにより人々の反対を押し切り船頭は再び私を乗船させてくれた。そして12レグア先の別の港まで同行したのであった。この港では、船が数隻あった。更に先へ進む我らのような者は皆ここで船を乗り換えることとなったが、同じく船に搭乗していた者が船々を尋ね、
「あの者らを船に乗せてはならない。中に天候を操る者がいる。もし乗せれば、あなた方の都合のいい天候は得られないぞ。」
そう説いていた。結果、皆我らを残して出港してしまったのだった。そうしていたところ、我らの主の許しにより旅客がいないということで別の船に乗せてもらうことになった。我等は少しも危険なく、自由な航海をすることができ、遂には我らを降ろした最初の船を追い越したまでである。この航海中、色々な船を見てきたが、海上を徘徊していた海賊に捕獲された船もあった。
ある港に着いた時、最初の船の同行者と遭ったが、彼らはしつこくもまた船々を尋ね、
「あの者らを堺の町に連れて行ってはならない。」
と説いていた。しかし、このような全ての妨害に屈せず、他の船が我らを乗せてくれた。
堺にて1(ベニス市の如く)
堺に着いて、我らの主は聖ルカの祭日である10月18日を楽しみにした。そうして、我らは聖ルカをこの町(堺)を守る聖人と仰いだ。この地において成すべきこと(布教)を我らの主は期待している。堺の町は非常に広大で大きな商人が多くいた。この町はイタリアのベニス(ベネツィア)のように執務官によって治められている。こので数日間休息をとり、その後我らの主が派遣した一行がいるヒエノヤマ(比叡山)へと出発することを決めた。
堺の話題は後で出てきます。彼等の目的は布教です。まずは、日本の宗教の大本山、比叡山を見て、日本の宗教の実態をその目で観察することにしました。
比叡山にて
堺の町を出発して数日後、都の手前6レグアにある比叡山に着いた。この山は非常に大きく、この山は近江国に所属している。山麓には非常に大きな湖がある。琵琶湖である。長さ約三十レグア、幅七レグアで、多くの川が流入することによってこの巨大な湖はできている。琵琶湖には多くの魚がおり、琵琶湖岸には大きな町がある。大津町である。比叡山はこの町に属している。山には多数の寺院があり、今ある分だけでも500を超えるという。昔は3300あったらしいが、この地は戦争が絶えなかったため戦禍に巻き込まれて破壊されたのだとか。
ここらの寺院に住むエセ教師は各宗派の坊主である。この世界には様々な人間がいるが、彼らはどの種の人間よりも傲慢だ。この山に住む人は多くが文学を好んでいるため、キリシタンに改宗した際平和な生活をおくるためには学問を盛んにすることが必要だろう。
比叡山に着いて我らの主の言葉を拝聴する者はいるか試した。しかし、ここに住むのは坊主である。故に、既に隠居した老学者、大泉坊乗慶という者、並びにその門弟数人が聞きに来た他は誰もいなかった。私は乗慶に
「万物の創造神はデウス1人である。」
と語ると、彼は理解が早いようで、
「日本の宗教とは反対の教えだが、お主の述べているところは大いに良い。」
とキリストの考えを認めてくれた。しかし、
「『他宗に靡くなど。』などと言って、坊主共が私を殺そうとするのが恐ろしいから受け入れられんな。」
と言った。我らは乗慶とその門弟に別れを告げ、京の都を目指した。
京にて
比叡山を出て少しして京都に着いた。季節は冬の初め。市内では我らを宿泊してくれる者がいなかったため、小さな貸家を見つけてそこを仮の宿とした。京都市は非常に広大であるが、昔話に聞いていたのとは違う。ある人が私に教えてくれたところによれば、この都市は長さ7レグア、幅3レグアあるという。京都は非常に高い山に囲まれ、山麓には至る所に広大な面積を誇る寺院が多数ある。
歴史の長い建築物で、多額の資産を保有していた。これら寺院及び市中は戦争がしばしば起り、その上火災が頻繁するため市中はかなり破壊されていた。住民は
「今思うと、過ぎ去った昔の栄華は夢のようなものだよ。」
と語った。この地は堺から遠く北方に位置しており、雪が多く降る。それなのに市には薪が少ない。戦争で消耗したとみえ、それ故に寒さに堪えた。また、食料品も欠乏しており、普段食べられる食料は、カブ、大根、ナス、チシャ(レタスのような野菜)、そして豆類である。
市は宗教の教え、そして文芸が非常に浸透、進歩しているといい、今もなお日本の諸宗派はこの京都、そして前述の比叡山から派生しているという。比叡山で出会った大泉坊乗慶はそのような権威のある地の中に住んでいたわけである。
京での布教活動
さて、京都市に着いて、先に述べた貸家を仮の宿とした後、我らは主に祈りを捧げた。主の教えを布教しようなどと思うこと度々であったが、まずはこの地の君主である足利義輝を訪問した(ルイス・フロイスの『大日本史』では、公方様と書かれている)。
結果、義輝公から允許状(布教の許可証)を貰うことに成功した。そうして、丸一日十字架を手に取って街路の中央に立ってはこの地に住まう者や通行者に主デウスの教えを説いた。集まった者は驚くほど多かった。ある者は目新しいことを聞くために、ある者は嘲笑するために。聴衆の質問に対して満足のいく返答をすれば、
『あの者は諸宗の教えを道理で論破することはできないようだぞ。』
と察したようで、市内にそう噂が流れると、私が説いた内容を知らない家は無いほどとなった。そして、ある者は
「悪魔の布教だ。」
と言い、ある者は
「坊主の教えの方が道理が通っている。」
と言った。坊主らは狂人のように市街を奔走し、人が集まる場所やその他で人々を煽動した。私が説いたデウスの教えを大いに罵倒し、更には『あの者は人肉を食う』とか『家には死人の骨がある』とかといった様々な虚偽の証言をしたのである。また坊主は、
「一般の民にはあの者は人間に見えるかもしれぬ。しかし私には見えるのだ。あの者は人間の肉を着た悪魔だと。」
などと言って、私が滞在していた市街に来ては住民を煽動しては、私を市街へ追放しようとしたのだ。極めつけには、私に宿を貸してくれた者に
「あの者を追い出さなければお前は人間でない。」
などと言った。そして
「直ぐに家を出てくれ。」
そう伝えられた。私はこの後どこに行けば良いか分からなかったため、私は坊主らの望みには速やかに応えられなかった。これをみて坊主は私を殺そうと剣を携えてやってきた。この国において、人に殺されそうになった者は切腹するという。あるいは、法官により殺されるという。日本はそのような慣習の国である。私は他人に殺されることが非常に不名誉なことだと思った。となれば、名誉のために自害するという話になるが、それだと、切腹しなければならない。 切腹は死の危険を冒す行為であった。
イルマン等よ、抜刀されたその立ち姿の下で感じたことを告白しよう。死について考えた。自ら死に臨むことは、決断から死に至るまでの間に大きな違いがある。私は、死がこれほどにまで近づいていたのを直に感じて少し恐怖を感じたが、
「私がこの場所にいること、つまり、日本の宗教と非常に関係が深い都において、異国のデウスの教えを説いていることが原因ではないか。」
と思い、他に相談するような人もいなかったので、我らの主、イエス・キリストに私の命の一切を委ねた。都での最初のキリシタン数人に対して、この家で洗礼を授けた。すると坊主の怒りに油を注いだようで、
「デウスの教えを布教することは中止せざるを得ない。」
と判断し、他の家に移った。
布教活動の成果
この家は壁が無く、寒気を防ぐものが何もなかった。時は1月。雪が非常に多い時期であったので、ここで多くの辛酸を舐めた。主は精霊を動かし、15人あるいは20人ずつその教に導いた。但し、その者の両親、友人そして隣人らは、
「キリスト教などに入る者は人ではない、下賤な者だ(身分の賤しい者は人でないと認識されていた)。」
と大いに軽蔑した。それ故に、彼らは隠れて生活した。都だけでなく、村落そして山間部からも多く来た。我が主の教えを聴いてはキリシタンとなる者が増加しはじめたのであった。私はこのような困難に直面した時、主の恩恵のおかげであまり恐れることはなかった。常に主ために命を捨てる覚悟であった。私の徳が足りないから布教が上手くいかないけれども、デウスが力を与えてくれたため坊主らに対抗する大きな勇気を得ることができた。こうして、坊主らの我々への妨害の熱は少しずつ冷めていったのである。
ただし、裏で行われていた扇動行為、流言、罵詈雑言はなおも止まらなかった。私を泊めてくれていた家の主人は酒を売っていたが故に、
「あいつらを家から追い出すまでは誰もお前の酒は買わない。」
と町ぐるみで口合わせをされていた。主人は我々に
「少しして家を去ってくれないか。」
と要求してきたが、我々には行く先が無い。そう懇願して家を出るまでに三か月の猶予を得、その間その家に留まった。寒気と精神的内辛さと病に苦しんだ。そんな中、我らの主は我々に大きな慰めをお与えになったのだ。多くの民がキリシタンになっていったのが目に見えて分かったのである。
夏が来て再び君主、足利殿を訪問し、この地に居住する許可を請うた。我等の悪言を流す者がいるなど多くの障害があったが、我らの主の許しにより、足利殿は我々に居住の許可を与えてくれた。ただの口約束ではなく、書面に起こして公布した。
『宣教師らに対し危害や妨害を加える者は死刑とする。』
といった内容であった。この許可を得て我々への迫害は止み、キリシタンの数は増加した。ついに会堂を一か所設ける必要があるほどとなり、このために一軒の大屋敷を姥柳町に購入した。これは、我らの主が都に置いた最初の会堂となった。この会堂が完成して以降、
「異教徒の教えを聴こう。」
と集まる者がますます多くなり、主を奉る者も多くなった。他にも、デウスの教えを
「善し。」
と認める者や、
「これは神聖な教えだ。」
と言う者がいたがが、悲しいかな、都で更に広く布教する勇気はなかった。布教活動がこのような状況なのを見て悪魔らは黙っていない。
この状況が一年続いた後、大きな迫害行為を起こし、坊主らは檀家や偶像を信仰する者(仏教徒)と協議し、この地を治めている三人の執政官に対して、可能な限りの賄賂を贈り、結果、執政官らは我々を追放することに決定した(領主及び執政官は松永久秀とその家臣らか)。
この地に留まる許可を与えてくれた君主はこのことを知らないようだった。そうして我らの主はこのような苦難に際し、主に仕える者、つまり我々をお守りなった。一人の良き異教の者が、この地の主足利殿に語りかけ、迫害行為を働く者が襲来する前の夜に使者を遣って、我々を市外の居城に我々を匿ってくれた。
「坊主らの怒りが鎮まるまでここで待ちなさい。」
と伝えてくれた。この使者が来た時、キリシタンらは我らが宿泊していた家に集まっては、議論した。
「異教の領主の言う通りである。迫害者が我々を京から追放すれば、勝利したと考え、デウスの教えの信用が損なわれてしまうかもしれない。だから追放されるより先に退去しよう。」
そう決まっては、彼らの多くが我々の移動に同伴し、4レグアの道を歩いては我らの友である者の城に入城した。私は3日4日ほどここに潜伏した後、このまま留まることは不可能であると考え、都に帰ってあるキリシタンの家に入った。キリシタンらはその後の経過や他のキリシタンが話すことを語ってくれた。我々の退去に市内は騒然となり、ある者は追放を不当と主張し、ある者はこっそりと我々のもとに来ては慰めたり力の限り援助したりしてくれた。彼らと協議して、我々宣教師がこの地に留まるか、それとも退去するか決定するため、4か月の猶予を請うことにした。そうして、我らの主の助けもあってこの要求は受け入れられた。君主足利殿は、我らの苦労や、出したはずの許可を坊主や執政官らが無視して引き続き迫害行為を働いていることを聞き、更に有力な書をお与えになった。
『何人たりとも宣教師らに害を加えてはならない。』
と。デウスはまた大柄の異教徒、つまり仏教徒数人を動かした。彼らは我々の味方となって援助してくれたのだ。これによって従来害を加えていた者も和らぎ、今は我々を庇護、援助するに至っている。つまり、悪魔が我々を追放しようとして起こしたことはかえってデウスの教え、そして我々の幸福となったのである。我々は益々堅固、そして安全の身となった。
イルマンらよ、私はこの地で悪魔に対して行う祭礼など多くを見てきた。兄等よ。これを聞いたら喜ぶだろうと思う。また、多くの道理に暗い者(キリシタン以外の者)らの騒ぎ楽しむ姿は、布教によって彼らの道理を明るくする可能性があるという希望を我々に与えてくれた。このような暗黒から彼らを救い出すことを造物主に祈るべきだと信じている。