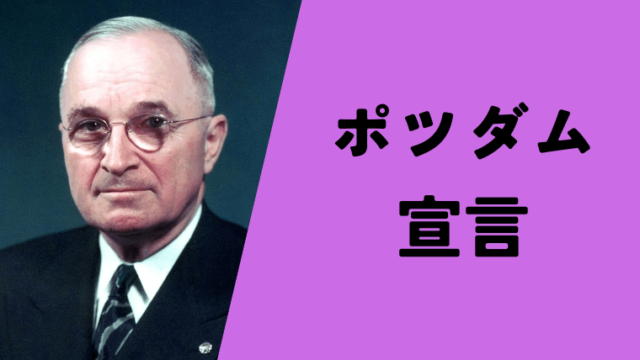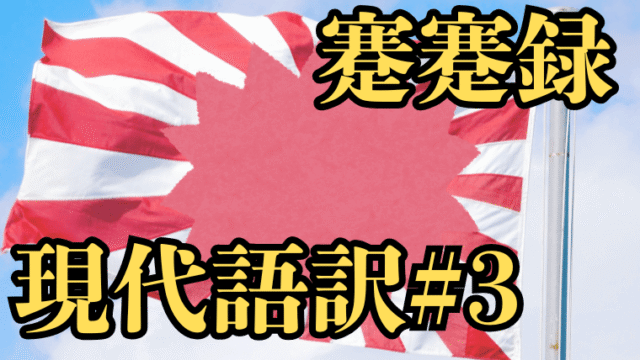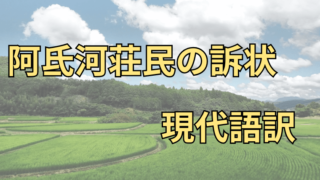現代語訳(続き)
祇園祭について
さて、8月には「祇園」と称する祭礼が人によって行われた。その方法は次に示す。まず、各町及役人に行うべき行事の一覧を配分し祭りの当日の朝、その行列を作る。
第一に、15またはそれ以上の、絹布やその他美麗な織物を被せた凱旋車が出てくる。この車には非常に高い柱を立て、車の中には太鼓や笛を持った多数の童子たちが乗り、その音頭に伴って歌ったり踊ったりする。車は30、40台で、各車には紋章を付けられる。その後ろを庶民や役人が槍や斧、薙刀といった武器を携えて行進する。薙刀というのは、刀身に色々と装飾が加えられた半槍で、それに短剣を嵌め入れた武器である。各車は役人や庶民が付き添う形で順を追って行進する。童子を乗せた車が通過した後、武装した人の車、その他絹布で覆われた歴史上の絵や美麗な絵が描かれた車が進み、この祭りの目的である偶像の殿堂に到る。こうして午前は終わり、午後は同じ偶像が乗せられた非常に大きな輿を持ち出す。これを多くの人がこれを担ぎ、この中に神がいるとして、
「中の像は動かしてはならない。」
といった宣伝を行い、庶民は大いなる信仰心をもってこれを崇拝する。この神輿に合わせて他の神輿も行進する。昔からこの偶像の愛妾の神輿も同伴させているという。銃の着弾距離ほどのところにも他の神輿があり、これは偶像の正妻である。正妻の神輿を担ぐ者は、夫の神輿と愛妾の神輿が一緒に進むのを確認すると、左右に走り回り、
『正妻の偶像が、夫と妾が共に行動しているのを見ては怒り狂っている。』
という様子を表現しようとした。庶民はこのように、正妻が大いに苦しめられる様子を見て、ある者は泣き、ある者は跪いて拝んでいた。そして神輿が全て揃い、偶像が安置される堂に到着すると、行列はここで終わる。他の祭礼は毎年8月14日午後から始まり、15日に行われるもので、「盆」と称される。これは祖先の霊魂を祭る行事である。人々は市街のあちこちに多くの火をともした燈籠を置く。燈籠は、それぞれが可能な限り美しく装飾を施されている。そして一晩中、人々は死者への信仰心のため、またはその場にあるものを見ようとして、街路を歩き回るのだ。
この日の午後、多くの人々が祖先の魂を迎えるために市外へ出て、迎える魂と出会える場所に到着し、魂と語り合った。また、米や果物を捧げたり、それができない者は熱湯を捧げたりする。彼らは、魂が来たことを喜び、長らく会えなかったことを話し、疲労を癒やすために座るよう勧め、
「一口食べなされ。」
などの、様々な親切な言葉を述べる。そして、持参した供え物を地面に並べ、一時間ほどその場に留まる。その間人々は、あたかも疲労を癒す魂が供え物を食べ終わるのを待つかのように振る舞う。これが終わると、人々は祖先の霊が向こうの世界にに戻るよう願い、その準備をするために帰宅する。そして家に帰ると、机を祭壇とし、その上に米やその他、祭りのある2日間分の食物を供える。
祭りが終わる日の午後、多くの人々が松明や灯明を携えて再び野山へ向かう。これは、祖先の霊が帰路に苦労しないように、道を明るく照らすためなのだという。霊に別れの挨拶をし、その後家に戻ると屋根の上に多くの石を投げる。霊は非常に小さく、また、雨に打たれると消失する存在だと信じられている。これを哀れむ気持ち故の行動だという。人々は祖先の霊の存在を固く信じており、この他にも似たような祭礼を行う習慣がある。そのため、我々キリシタンのような異なる説を述べたとしても、聞き入れてはくれないのだった。
「魂に食物を与えるのは何故だ?」
と尋ねると、
「魂らは非常に遠い天国(1億レグアの彼方)へ向かう旅路に3年を費やすのだ。途中で疲れても再び旅を続けられるよう、この援助が必要なのだよ。」
と言った。この祭りの間、坊主らは全ての墓をきれいに掃除することで、専ら権勢を振っていた。習わしとして、魂には多くの捧げ物をするのだが、どんなに貧しい者であっても、力の及ぶ限りそのようにする。これを行わない者は、隣人として認められないという。この習慣を見たイルマンたちは、憐れむべき国民が迷信に囚われていることを嘆いた。祈りの際、彼らに光明を授けてほしいと主に願った。
戦争の祭り
さて、他の祭りを挙げると、5月には戦争の祭りが行われる。これは、食事をとった後、希望者全員が武器を手に取り、背に偶像の絵を描いて野に出て二隊に分かれる。まず少年たちが投石し、次に弓と銃を用い、その後に槍、最後に剣を使って戦うという祭りである。この祭りでは、多くの人が負傷し、常に数人の死者が出る。死傷者が出ているが、この日は特別な許しがあるため、罰せられることはない。このようにして1日が終わる。日本の民は生まれつき戦を好んでいるため、遊戯すらも戦に関連している。彼らの名誉は戦にあるのだ。戦で最も多くの首級を得た者は、討ち取った者の身分に応じて最大の名誉を手にする。
キリスト教徒から見た仏教
僧院(僧の住居)は男女それぞれに存在するものの、肝心な点、すなわち我らが主イエス・キリストの信仰が欠けているため、徳と純潔を全くもって欠いている。時宗と称する仏教の一派では、男女が混住しており、全く区別がない。夜になると、全員で祈りを唱え、終わると、男は僧院の一部に、女は他方の一部に帰る。また、ある祭儀では勤行を終えた後、男女それぞれが一団となり歌を歌う。途中で男女共に踊り、歌を続ける。このような有り様なので、この僧院では堕胎や殺人といった犯罪が多く行われている。悪魔(徳と純潔を欠く原因となった超越的な何か)がこうした行為を目的として、このような制度を作り上げたのだと思われる。
これを読む最も愛する同士らよ、彼らがこのような盲目的な状態から救われるよう、私たちの主に祈ろうではないか。
悪魔はまた、偽りの奇跡をもって庶民を大いに惑わせている。都には雄大で壮麗な寺院が数多くあり、基本的に非常に高い山の上に建てられている。その位置故に、すぐにそれが寺院であることが分かる。悪魔はしばしばその姿を現すことで、人々から崇拝されている。都に近い非常に高い山には、昔は7000もの寺院があったが、今では500程にまで減っている。
その中に、非常に壮麗で多くの人々から崇敬されている寺院がひとつある。人々はそこを訪れては寄進を行っている。諸武将は戦に臨む際この寺院で祈願する。勝利した暁には金銭や礼拝堂を寄進することを誓い、その約束を果たそうと努める。一般の人々も危険や苦難に直面したり、何か望むことがあると、この寺院に祈り、助けを求る。悪魔はしばしば人々の夢に現れ、
「厚く信仰すれば救済しよう。」
と告げたり、
「信仰心が足りないから成就しないのだ。」
と告げたりする。もし願いが実現すれば、人々はそれが悪魔の力によるものだと考え、皆これを畏れ敬い、仕えるようになり、より信仰心を高めていく。悪魔に仕える者には報いがあり、怒りを買った場合には罰があると考えられている(これはおそらく石清水八幡宮のことだろう。石清水八幡宮は源氏の氏神であり、源氏は武神として広く尊敬されている。人々から信頼されて祈願されることが非常に多い場所である)。
空海(真言宗)について
また、コンポーダーシ(弘法大師=空海)と呼ばれる一人の僧も多くの人々を甚だ欺いているという。彼に関する伝承によると、弘法大師は悪魔の化身、つまり肉体を持った悪魔のような存在で、多くの罪悪を考え出し、人々に教えたという。また、この国において、中国から伝わった漢字と共に用いる仮名文字を発明したといわれている。また、多くの壮麗な寺院を建設した人物でもある。非常に高齢になった時、弘法大師は地下に穴を造らせ、その中に入った。
空海の高野山奥院御廟での入定説です。空海の原点ともいえる史料はこちら!
「この世に留まることを望みはしないが、死にはしない。私はここで休息を取るだけだ。1億年後に弥勒菩薩が現れる時、私は再びこの世に姿を見せるだろう。」
と語った。そして、その穴を覆わせ、そこに留まったのだった。それ以来、800年が経過した。庶民は、弘法大師の弟子である高野山の坊主を大いに崇敬している。弘法大師は今でも生きており、多くの人の前に現れていると信じられているためだ。魔除けのために弘法大師に祈る人や、閉じ込められている穴に参拝する人は日々数多くいる。他にも、弘法大師の教えに精通している3、4人の高位の僧は春夏秋冬の各季節に民衆の前に出てくるのだが、その時、庶民に大いに尊敬される。
一向宗について
そのうちの1人は、約370年前に死んだと伝えられており、一向宗と称する宗派の開祖、一向俊聖である(一向宗は浄土真宗の分派である。浄土真宗の開祖親鸞は、弘長2年11月28日、京都で没した。享年98。グレゴリオ暦換算すると、1263年1月9日である。今から299年前の話である)。
一向宗は信者が多く、庶民の多くがこの宗派を信仰している。本願寺浄土真宗は常に一人の僧を座主として立て、亡くなった前任者を継いで宗派の創立者の地位に就かせている。開祖親鸞は公然と多妻を成す他、多くの罪を犯していたが、人々はこれを罪とみなかった。この慣習は連綿と、歴代の座主に継がれている。人々の座主に対する崇敬は非常に深く、彼を見るだけで多くの人が涙を流し、自分たちの罪の赦しを求める。多くの人々が座主に対して、大量の金銭を献上しており、日本全体の富の大部分をこの坊主が保有している。
毎年甚だしいほどの盛大な祭りが催され、それに参加しようと人々が大勢集まるのだが、寺に入ろうとして門の前で待つ人々が、門が開かれると一斉に押し寄せるため、毎度、多数の死者を出している。この瞬間に死ぬことを幸福と考えて、わざと門の内側で倒れて群衆の圧力で死のうとする者がいるのだ。夜になると、坊主は説教を行い、それを聞いた多くの庶民が涙を流す。そして朝になると、鐘を鳴らして合図とし、その音で全員が堂内に入る。
法華宗について
約300年前に亡くなった日蓮と呼ばれる坊主は法華宗と呼ばれる別の教えを説いた。現在、この宗派の信徒は非常に多い。信者はこの坊主を聖人と崇めている(日蓮は、弘安5年(1282)10月13日、武蔵国池上で没した。享年61。グレゴリオ暦換算すると、1282年11月14日である。今から279年前のことである)。
堺という町の印象
最も愛するイルマンたちよ、以上に記したことは都で目にした多くの出来事の一部である。また、我が主の聖なる教えや、人々がキリスト教に帰依する様子についても記した。神父コスモ・デ・トーレスは、私が今滞在しているこの堺の町にやって来て、
「我らの主が開いて下さったキリスト教の門戸をさらに広げるように尽力せよ。」
と私に命じた。前に述べたように、この町は非常に経済活動が大規模でかつ潤っており、住民は物事の道理をよく理解している。私がこの地に到着してからというもの、異教徒の彼らはデウスの教えを聞くようになり、慈悲によってその教えを信仰し始めた。私はこの町で大きな収穫を得た。この書が、日本全土におけるキリスト教布教の助けになることを、我々の主に期待する。
この町は多くの住民が住み、裕福であり、また立地が良いため、常に平和であり、侵略されることがない。私たちがここに留まることを選んだのは、戦争が起きた場合はここに避難すれば安全であり、戦争が収まればここから出発することができるためである。この町に到着してから、私は多くの出来事を見てきた。見聞きした事実だけを述べて冗長は避けている。
堺にて2(行基を祀る祭り)
7月29日、町の住民は大明神と呼ばれる人物(=行基菩薩)のために開口神社で祭りを行った。この人物は、昔の天皇の臣下である。死後600年が経過したが、今でも聖人として崇敬され、今日において大きな堂が建設された。(『和泉名所図絵』によれば、開口神社はイザナギの御子である事勝国長狭命(サルタヒコ)を祀った神社で、境内には念仏寺がある。ここは聖武天皇の願いにより行基菩薩が建立したといわれている。既に述べたが、ここで言う「聖人」とは行基菩薩のことを指している。※開口神社と住吉神社とでの祭事を混同していると思われる。)
祭り当日の午後、昼食をとってから、長銃の射程距離を超えるほどの距離のある市街に出かけた。その市街では一端から他端までを梁を渡しており、桟敷のようなものを設置していた。通行を制限することで、そこから見物できるようにしたわけである。この準備が整うと、1レグア(約5~6km)の範囲から大勢の人々がここに集まってくる。さて視界の先、最初に登場するのは、馬に乗り手に剣を持った偶像である。その後ろには、弓箭を収めた箙(えびら)を携えた小姓が1人随行し、さらにその後ろには、手に鷹を持った者が馬に乗って随行していた。続いて、騎馬武者が多くやって来て、その後には、多くの徒歩の者が随行していた。この人々は様々な紋章を身につけ、そして全員が武器を携えていた。彼らは歌ったり踊ったりしながら、
「千歳楽(せんざいらく)、万歳楽(ばんざいらく)」
と唱えて行進していた。これは「千年の楽しみ、万年の喜び」という意味であり、行進する人々は驚くほどの喜びと楽しさをもってそれを唱えていた。それに混じる騎馬武者は互いに20、30人分の間隔を空けて進んでいるのだが、歩いているのは100人以上であった。祭りに参加したいと願い、集まった人々が非常に多い証である。馬が通り過ぎた後、白い衣を着た坊主(田楽法師であろう)が歌いながら行進する。その後ろに冠をかぶった騎馬武者が続き、この騎馬武者の傍らでは多くの女性(巫女であろう)が歌を歌いながら行進していた。さらにその後ろには、武装した兵士が、祭神の乗った神輿を迎えるために続く。この神輿は全て金で装飾されており、約20人が担ぎ、多くの人々がこれに付き従う。この人々は皆、歌を歌い、歌の最後には必ず
「千年の楽しみ、千万年の喜び」
という歌詞を繰り返し唱える。そしめ見物する人々は神輿を拝んでいた。祭神が堂に戻って祭りは終了した。
堺で布教する意義
最も愛するイルマンらよ。私は、この町で、右に記した以外にも、多くの魂が闇の中をさまよっている現実を目にしてきた。我らの主が、その慈悲によって、いつか彼らをこの闇から救い出してくださることを祈る。
既に述べたように、私は現在この町に滞在しており、既に4か月が経過した。クリスマスの時期に、もしデウスがお許しになれば、都にいるキリシタンたちと共に聖誕祭を祝うべく都へ向かう予定である。都を訪問し終えた後、翌年の3月には再び堺に戻り、ここでの活動を支えてくれる同士が到着するのを待つことになるだろう。
最も愛するイルマンらよ、我らの主デウスの愛を拠り所とし、このような聖なる使命に従事する準備を整えよ。なぜ私がそう訴えるのか。それは、まさに今が、この地にデウスの教えを根付かせ、そして広めるのにふさわしい時だと思うからだ。
この国の言語を理解するのはそれほど難しいことではない。私は未熟者ではあるが、既に日本語の大部分を理解できるようになった。少なくとも会話は十分に聞き取れる。また、この国には、日本語で書かれたデウスに関する書籍が既に多数あるため、それらを読み聞かせるだけでも、教えを聞きたいと望む人々を十分に満足させることができるだろう。必要なのは謙虚さと、主が許すまで、試練に耐え続ける忍耐である。主に仕えようと善意をもって努力する者に対しては、その慈悲によって布教に必要なものを与えてくださるだろう。
故に、最愛の同志よ、イルマンらよ、堺に来たまえ。兄らよ。もし堺に来てくれるなら、私はこの地で多くの活動を成し遂げることができるだろう。それを主に願う。この国にいる創造主から離れ彷徨う多くの魂のため、また主と違って遠く離れた地の兄弟と直接言葉を交わすことができない卑しい私や同士たちのため、祈りの時、主にこう祈ってほしい。
「我らの主よ、兄弟や私たち全員の心に働きかけたまえ。私たちがその聖なる御心を理解して行動できるように。」
と。
アーメン。
1561年8月17日、堺。
companhia(=イエズス会)に属する下僕であり、つまらない兄弟にすぎないガスパル・ヴィレラより。
まとめ
戦国時代の堺は、商業都市として栄えていた印象から、信長統治時代を思い浮かべる人も多いことでしょう。しかし、ベネツィアのようだと宣教師が感じたのは、信長統治よりも前の時代のことでした。より一層、堺の独立性が顕著にみられました。
ガスパル・ビレラは堺のみならず、京でも布教活動を行ったことにより、この書簡は当時の仏教勢力の実態を記録した史料ともなりました。中世の仏教勢力が現代でいう大規模な反社会的な暴力団集団であったことは度々言われますが、僧侶が暴力的に他宗を排斥しようとした記録を見るに、決して誇大報告でもないように思われます。
そんないち権門勢力が、まさか、数年後に信長によって延暦寺が焼き討ちされるとは思いもしないでしょう。
同時に、キリシタンも数十年後に追放されることになろうとは、思いもしなかったでしょう。
いつかは、ルイス・フロイスの『大日本史』も現代語訳してみたいものです。それでは。
| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |